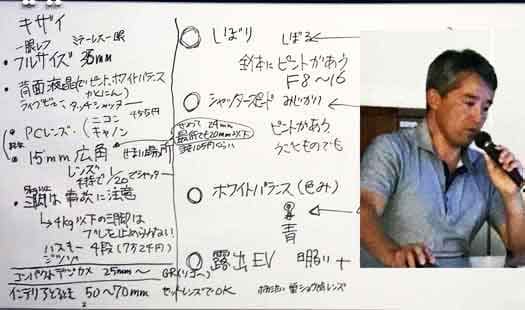北海道地震発生が9月6日。
その後しばらくはさすがに散歩などには行く心理ではなかったのですが、
先週くらいからややゆとりも出来て、
いつもの北海道神宮周辺緑地、自然公園内を早朝散策しています。
ことしの北海道はほとんど雨の夏だったのですが、
その上、関西を襲って関空に大きな被害をもたらせた台風がその後、
北海道にけっこうな被害をもたらせました。
北海道はそんなに台風も来ないし、地震も太平洋岸を除いて
そんなには多くない、という心理的なスキがあったことは事実でした。
気候温暖化の影響なのか、台風の凶暴化が進んでいます。
写真のように札幌周辺地域でも、こういう風で倒された自然木が多かった。
大雨とまでではないけれど、とにかく長い期間日照不足で雨がち。
そういう意味では樹木も地盤面が水分を含んで軟弱になっていて
そこに強風が吹いて、各所の森林で倒木被害が相次いだのです。
各所の森などにその痕跡を見ることができます。
この台風の後に、時間をほとんど置かずに地震が来たので、
ほぼ忘却してしまうところですが、
わたしの記憶ではこの札幌円山自然林でこんなに倒木が見られるのは初めて。
台風は風の被害が大きかったのですが、
しかしこの倒木メカニズムを考えてもやはりその前の
長雨が長期的に地盤面を軟弱化させたことで、
地震の被害を加速させたように感じられてなりません。
毎日少しずつ処理が進んでいるようですが、
まだまだ「立ち入り禁止」の案内が各所に見られています。
気候変動によって災害のレベルが一段スイッチが上がってくるように思われます。
ことし、というよりも、今後とも長期にわたってこういう
気候変動に伴うさまざまなキケンの高まりはあるのだろうと思います。
普段の暮らしレベルから、安全保障・危険の回避を
考えて行動していかなければなりませんね。