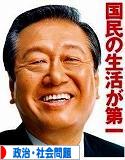afpbbnews さんが 2012/11/07 に公開
米大統領選で再選を決めた民主党のバラク・オバマ(Barack Obama)大統領が7日未明、地元イリノイ(Illinois)州シカゴ(Chicago)で支持者を前に勝利演説を行った。舞台には、ミシェル・オバマ(Michelle Obama)大統領夫人、娘のマリア(Malia Obama)さんとサーシャ(Sasha Obama)さんも登場した。(c)AFP
詳細記事はこちら
http://www.afpbb.com/article/politics/2911100/9798855
オバマ氏再選 基地問題の「前進」望む 沖縄にも人権、民主主義を
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-198975-storytopic-11.html
米大統領選は民主党の現職、オバマ氏が再選を決めた。共和党のロムニー氏との激戦を制しての勝利だ。だがそこに、「変化」という言葉に多くの米国民が共感し、世界が期待した、4年前の勝利の高揚感はない。国内「分断」をこれ以上拡大させたくないとの思いが、再選を選択した印象だ。
沖縄の米軍基地問題は選挙戦の争点にならなかった。しかし、米軍基地の過重負担に対する沖縄県民の我慢は限界に来ている。再選を受け、沖縄からは「基地問題の『前進』を」と強く望みたい。
「一つの米国」道半ば
今回の大統領選は長引く景気低迷の下で迎え、雇用問題や経済政策が最大の争点となり、内向きの選挙戦となった。「核兵器なき世界」など国際社会に向けた理念やメッセージも色あせた感がある。
激しい中傷合戦が象徴するように、「分断された米国」の姿を国内外に印象づけた選挙戦でもあった。人種差別や政党対立、貧富格差など、米社会が抱える問題を克服し「一つの米国」を目指したオバマ氏の取り組みは道半ばだ。オバマ氏は今後、景気回復を確実なものにし、国民の断絶をいかに修復するか、手腕が厳しく問われることになる。オバマ氏は貧困層に配慮し、中間層を重視する姿勢を見せた。「小さな政府」より、国民皆保険への医療保険改革など、政府の一定の関与を必要と見る政策が、米国で信任された意味は重い。貧富の格差を縮小し、中間層を充実させることは各国共通の課題とも言え、2期目の舵(かじ)取りを任されたオバマ氏の今後の政策には各国とも注目せざるを得ない。
オバマ氏はイラクから米兵を完全撤退させ、ブッシュ政権が始めたイラク戦争の終結を宣言した。アフガニスタンからも2014年末までの戦闘部隊撤退を目指すなど「変化」の一端も見て取れる。しかし、「核兵器なき世界」を提唱するなどして、09年に受賞したノーベル平和賞に見合う実績はまだ残していないと言わざるを得ない。それは、沖縄の米軍基地問題にも関わることだ。先の大戦後、沖縄を27年間も占領・統治したのは米国自身である。そして、日本復帰後40年を経ても沖縄は、その時代を引きずるかのように米軍基地が過重に残り、占領意識丸出しで県民の人権と尊厳を踏みにじるような米兵絡みの事件・事故が後を絶たないことは、オバマ氏も十分理解しているはずだ。
約束果たされないまま
米国が民主主義と人権尊重の価値を世界に築くリーダーを自負するのであれば、沖縄にもその価値を適用すべきだ。米大統領にはその責任がある。沖縄の基地問題の全てを「日本の国内問題」で片付けてはならない。米国も当事者であることを自覚すべきだ。
米有力紙のニューヨーク・タイムズ(電子版)は11月2日付の社説で、米海軍兵による集団女性暴行致傷事件や普天間飛行場への垂直離着陸輸送機MV22オスプレイ強行配備、県民の日米地位協定改定の訴えなどを挙げ「ワシントンは沖縄の正当な懸念にもっと敏感に反応すべきだ」と米政府の対応を批判した。その上で、沖縄の米軍駐留を減らし、速やかにグアムやハワイ、県外に移転すべきだと主張した。米有力紙の沖縄認識が、ここまで進んだことは歓迎したい。オバマ大統領もこうした訴えに耳を傾け、政策に反映させてほしい。
オバマ氏は今回の大統領選で、国民的人気が高いクリントン元大統領の支援を頼って行動を共にする場面が目立った。そのクリントン氏は2000年の沖縄サミット時に、沖縄での米軍の存在を減らすことを約束した。しかし、その約束は果たされないままだ。オバマ氏には2期目に、ぜひ沖縄県知事とじかに面談して、県民の声を聞いてもらいたい。大統領の理念と価値観で、沖縄の基地問題も着実に「前進」させてほしい。
☆ノダ政府も↑これくらいの事を自覚して米軍再編問題を再考すべきだ。でないとこの問題は、どこまで行っても平行線。絶対に交わることは無い。