世界遺産認定が確実化した富士山。
このところ急速に「入山料」論議がかまびすしくなってきた。
それを聞いて真っ先に思ったのは「昨年登っておいて良かった」。
ついでに言うと、登って山頂で見た景色は、使わなくなった小屋を重機が煙と音を立てて壊していたり小山に布団が何十と干されていたり、地上の生活感がふんぷんとしてて、「これが世界遺産?」という気がしないでもなかった。わたしが初登頂を成した日はまさに、世界遺産に適格かどうか調査するイコモスの担当者が富士山を訪れた日でもあった。
入山料導入の目的は主に2つ。1つは登山者数の抑制。世界遺産に登録されるとこれまでの経験から30%程度の観光客が増えると予想されるそうだ。京都大学・栗山浩一教授が7000円の徴収を課せばほぼ昨年並みの登山者数にとどまると試算している。
環境省によれば、昨夏の8合目付近の登山者数は31万8565人だそうで(わたしもその1人)、7000円(5合目以上に登る人が対象)を徴収すると約22億3000万円となる。
もう1つは、世界中から「汚い」と言われ、野口健さんもボランティアを結集しての清掃活動にあたっているとおり、富士山の環境保全が喫緊の課題となっている。登山者ではないだろうが樹海には廃タイヤや使用済み医療器具(注射針など)の不法投棄が行われたり、その量・中身とも善良なる市民がコツコツやっていたのではとても追いつかないほどだ。
したがって、いずれにしてもきれいにしようとおもえば相応の(しかも相当な額の)金がかかる。登山客が増えれば、当然マナーの悪い人たちも増えるので(自然なことです、残念だけど)よりいっそう費用もかさむ。
これを、入山料で賄おうというわけだ。
7000円、と試算した栗山教授も、仮に500円、1000円とした場合2%、4%減と抑制効果はないに等しいが、徴収総額としては1億6000万円、3億2000万円とそれなりの額となることから一定の意味があるとしている。
■わたしの意見
まず、なぜ世界遺産への申請ということになったのか。そもそも世界遺産とは何ぞや?というところから話すべきたと思う。世界遺産自体は、人類共有の財産とすべき貴重な「自然」や「文化」が、安易に失われないように(それは再び取り戻すことが困難なのだ)、とくに貴重なものについてはこれを第3者が審査・認定し、一定の(厳格な)保全基準を設ける。同時に世界に対してこれを告知し、人類全体で守っていく義務を負う。そんなことで概ね間違いないと思う。
趣旨はもちろん正しい。しかし、権威、権力が存在し、登録、認可という構造に取りこまれた途端、たいていはそこに利害が生じ、権益を求めて争いやいさかいがおこる。つまり金が絡んでこないわけにはいかない。世界遺産も例外ではない。とりわけ、多くの人が訪れやすい「文化遺産」では。
多くの人々(直接的な関係のある地元民、中でもとりわけ観光業や行政担当者)の期待は、どれだけ多くの人がやってきてくれてお金を落としていってくれるか、にある(もちろん、みんなの誇りでもあるこのすばらしい山に世界中の人が訪れてくれることへの喜びもあるにちがいないけど)。
今回の富士山の場合は「地元」が山梨・静岡2県であることで事情がさらにややこしい。これまでの取り組み方にも考え方にも富士山の受容の仕方にもちがいがあるからだ。入山料についての対応もまちまちになりドタバタしてしまった。
個人的には、富士山は世界遺産になる必要などなかったのではないかと思う。またその資格もないのではないか。自然遺産の基準がクリアできず文化遺産として登録した経緯にそれが表れている。
文化にもいろいろあって、ナイーブさが重要な場合とそうでない場合がある。対象と人間との関係が近いほどナイーブさが要求される。どんどん離れていってゼロに限りなく近いのが自然遺産ともいえる。
富士山の場合は、そういう意味ではひじょうに人間との距離が近い。わずか2か月で30万人以上が訪れ、都心の通勤電車を待つホームのごとく登山者が列をなし押し寄せる山で、どうナイーブさを維持しようがあるのか?
むりやり守るなどは不可能で、登山者の「善意や良心」に期待し、呼びかけ、うまく行ったり失敗したりを繰り返しながらやっていくしかないのではないか。
それは悪いことばかりじゃなくて、最大の利点は「自由」にある。本当に自分たちが守りたいものなら守れるはずなのだ。何十年後、何百年後、何千年後壊れてしまったならば、人間にとって、あるいは日本人にとって富士山はそこまでのものだったのだとあきらめるしかない。
世界遺産といったって、世界の監視の対象となっただけで、守るのは日本人であり地元の人々。ある意味代償として利益も得る。そこに矛盾はない。適正な仕事をし見合った報酬を得る。なんの問題もない。世界の遺産だなどと大手を振られてとやかく言われるだけにすぎない。果たして日本のような国が--金を出してるだけと時に言われもするが、この何十年世界中に支援を続けてきた国ではなかったか--守るべきものを自分たちで守ることができないわけがあるだろうか?
それを自ら望んで「世界で監視してほしい」と申し出るなんて、そこには別の意図があると考えるのが自然で、つまるところ、最大の目的は保全にではなく利益誘導にあるのは明らかなのである。表裏一体と言ってしまえばそれまでだけれど。
「自由」ということはすなわち「実力通り・実態通り」の姿がそこに反映される鏡にうつすことと同じだということにほかならない。他人がなんとかしてくれるわけでもないが、本気で思えば何とかなる可能性もあるということだ。
それ以上何を求めるのか?
さて、富士山に登るつもりのない人には入山料がいくらだろうが関係のないことだし、登りたい人にとっては安い方が良いに決まっている。強制されなくても呼びかければ寄付を申し出る人は(額はともかく)大勢いるだろう(これまでもいたにちがいない)。
毎日登っている人には7000円なら大変な負担になる。そうした登り方は金輪際あきらめるしかなさそうだ(ここでも自由が奪われる!)。
妥当な額といっても、誰にとって妥当なのか、まったくもって結論しようがないと言うしかない。はっきり言っておきたいのは、徴収されたお金が適正に目的のために使われるようにしてほしいということだ。復興予算みたいな話は勘弁願いたい。
富士山に「安全に」登るにはそれなりの装備や準備が必要だし、遠方から目指すなら旅費や宿泊費もばかにならない。さらに入山料が7000円も加わるなら、生活費に余裕もないけれど「一生に一度くらい富士山に登りたい」と思っていた人の何割かが、その夢もあきらめるきっかけにはなるかもしれない。
マラソン参加費の高額化と似た事情を感じる。
安全に走れるように整備してもらえればマラソン大会にいくつも出なくたって構わないのだ。同様に、ゴミは持ち帰るし、お金に余裕がある時は、求められるなら保全のための寄付をするのもOKだ。
自分の国の山や道だ。なんで自由に走ったり登ったりできないのだろうか。
このところ急速に「入山料」論議がかまびすしくなってきた。
それを聞いて真っ先に思ったのは「昨年登っておいて良かった」。
ついでに言うと、登って山頂で見た景色は、使わなくなった小屋を重機が煙と音を立てて壊していたり小山に布団が何十と干されていたり、地上の生活感がふんぷんとしてて、「これが世界遺産?」という気がしないでもなかった。わたしが初登頂を成した日はまさに、世界遺産に適格かどうか調査するイコモスの担当者が富士山を訪れた日でもあった。
入山料導入の目的は主に2つ。1つは登山者数の抑制。世界遺産に登録されるとこれまでの経験から30%程度の観光客が増えると予想されるそうだ。京都大学・栗山浩一教授が7000円の徴収を課せばほぼ昨年並みの登山者数にとどまると試算している。
環境省によれば、昨夏の8合目付近の登山者数は31万8565人だそうで(わたしもその1人)、7000円(5合目以上に登る人が対象)を徴収すると約22億3000万円となる。
もう1つは、世界中から「汚い」と言われ、野口健さんもボランティアを結集しての清掃活動にあたっているとおり、富士山の環境保全が喫緊の課題となっている。登山者ではないだろうが樹海には廃タイヤや使用済み医療器具(注射針など)の不法投棄が行われたり、その量・中身とも善良なる市民がコツコツやっていたのではとても追いつかないほどだ。
したがって、いずれにしてもきれいにしようとおもえば相応の(しかも相当な額の)金がかかる。登山客が増えれば、当然マナーの悪い人たちも増えるので(自然なことです、残念だけど)よりいっそう費用もかさむ。
これを、入山料で賄おうというわけだ。
7000円、と試算した栗山教授も、仮に500円、1000円とした場合2%、4%減と抑制効果はないに等しいが、徴収総額としては1億6000万円、3億2000万円とそれなりの額となることから一定の意味があるとしている。
■わたしの意見
まず、なぜ世界遺産への申請ということになったのか。そもそも世界遺産とは何ぞや?というところから話すべきたと思う。世界遺産自体は、人類共有の財産とすべき貴重な「自然」や「文化」が、安易に失われないように(それは再び取り戻すことが困難なのだ)、とくに貴重なものについてはこれを第3者が審査・認定し、一定の(厳格な)保全基準を設ける。同時に世界に対してこれを告知し、人類全体で守っていく義務を負う。そんなことで概ね間違いないと思う。
趣旨はもちろん正しい。しかし、権威、権力が存在し、登録、認可という構造に取りこまれた途端、たいていはそこに利害が生じ、権益を求めて争いやいさかいがおこる。つまり金が絡んでこないわけにはいかない。世界遺産も例外ではない。とりわけ、多くの人が訪れやすい「文化遺産」では。
多くの人々(直接的な関係のある地元民、中でもとりわけ観光業や行政担当者)の期待は、どれだけ多くの人がやってきてくれてお金を落としていってくれるか、にある(もちろん、みんなの誇りでもあるこのすばらしい山に世界中の人が訪れてくれることへの喜びもあるにちがいないけど)。
今回の富士山の場合は「地元」が山梨・静岡2県であることで事情がさらにややこしい。これまでの取り組み方にも考え方にも富士山の受容の仕方にもちがいがあるからだ。入山料についての対応もまちまちになりドタバタしてしまった。
個人的には、富士山は世界遺産になる必要などなかったのではないかと思う。またその資格もないのではないか。自然遺産の基準がクリアできず文化遺産として登録した経緯にそれが表れている。
文化にもいろいろあって、ナイーブさが重要な場合とそうでない場合がある。対象と人間との関係が近いほどナイーブさが要求される。どんどん離れていってゼロに限りなく近いのが自然遺産ともいえる。
富士山の場合は、そういう意味ではひじょうに人間との距離が近い。わずか2か月で30万人以上が訪れ、都心の通勤電車を待つホームのごとく登山者が列をなし押し寄せる山で、どうナイーブさを維持しようがあるのか?
むりやり守るなどは不可能で、登山者の「善意や良心」に期待し、呼びかけ、うまく行ったり失敗したりを繰り返しながらやっていくしかないのではないか。
それは悪いことばかりじゃなくて、最大の利点は「自由」にある。本当に自分たちが守りたいものなら守れるはずなのだ。何十年後、何百年後、何千年後壊れてしまったならば、人間にとって、あるいは日本人にとって富士山はそこまでのものだったのだとあきらめるしかない。
世界遺産といったって、世界の監視の対象となっただけで、守るのは日本人であり地元の人々。ある意味代償として利益も得る。そこに矛盾はない。適正な仕事をし見合った報酬を得る。なんの問題もない。世界の遺産だなどと大手を振られてとやかく言われるだけにすぎない。果たして日本のような国が--金を出してるだけと時に言われもするが、この何十年世界中に支援を続けてきた国ではなかったか--守るべきものを自分たちで守ることができないわけがあるだろうか?
それを自ら望んで「世界で監視してほしい」と申し出るなんて、そこには別の意図があると考えるのが自然で、つまるところ、最大の目的は保全にではなく利益誘導にあるのは明らかなのである。表裏一体と言ってしまえばそれまでだけれど。
「自由」ということはすなわち「実力通り・実態通り」の姿がそこに反映される鏡にうつすことと同じだということにほかならない。他人がなんとかしてくれるわけでもないが、本気で思えば何とかなる可能性もあるということだ。
それ以上何を求めるのか?
さて、富士山に登るつもりのない人には入山料がいくらだろうが関係のないことだし、登りたい人にとっては安い方が良いに決まっている。強制されなくても呼びかければ寄付を申し出る人は(額はともかく)大勢いるだろう(これまでもいたにちがいない)。
毎日登っている人には7000円なら大変な負担になる。そうした登り方は金輪際あきらめるしかなさそうだ(ここでも自由が奪われる!)。
 | まいにち富士山 (新潮新書) |
| 佐々木 茂良 | |
| 新潮社 |
 | 富士山に千回登りました (日経プレミアシリーズ) |
| 實川 欣伸 | |
| 日本経済新聞出版社 |
妥当な額といっても、誰にとって妥当なのか、まったくもって結論しようがないと言うしかない。はっきり言っておきたいのは、徴収されたお金が適正に目的のために使われるようにしてほしいということだ。復興予算みたいな話は勘弁願いたい。
富士山に「安全に」登るにはそれなりの装備や準備が必要だし、遠方から目指すなら旅費や宿泊費もばかにならない。さらに入山料が7000円も加わるなら、生活費に余裕もないけれど「一生に一度くらい富士山に登りたい」と思っていた人の何割かが、その夢もあきらめるきっかけにはなるかもしれない。
マラソン参加費の高額化と似た事情を感じる。
安全に走れるように整備してもらえればマラソン大会にいくつも出なくたって構わないのだ。同様に、ゴミは持ち帰るし、お金に余裕がある時は、求められるなら保全のための寄付をするのもOKだ。
自分の国の山や道だ。なんで自由に走ったり登ったりできないのだろうか。










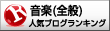






 須走口下山道入口までさらにお鉢を巡る
須走口下山道入口までさらにお鉢を巡る


























































