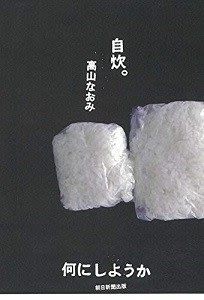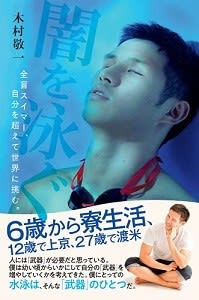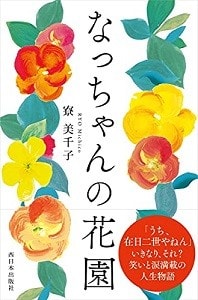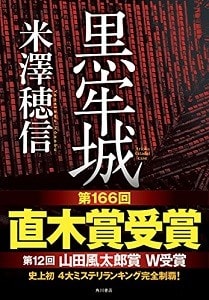
ブクログより
新聞の書評欄で見て、図書館にリクエスト。
待っている間に何と直木賞受賞が決定。
何というタイミング、と手に取りましたが私、戦国時代は苦手なんですよね。
誰それがどこどこを攻めた。誰それが誰それに謀反を起こした。などなど・・・登場人物多すぎるし、攻防により立場が簡単に変わるし、状況が目まぐるしすぎる、と思うのは私だけだと思いますが、ではなぜにこの本を?
作者のこれまでの作品が良かったのです。
帯にもある戦国×ミステリ これです。
時代は本能寺の変より4年前、信長に叛旗を翻し有岡城に立て籠もった荒木村重、そして土牢に幽閉されている織田方の黒田官兵衛。
あとはそれらを取り巻く人々。
舞台は変わらないし、時代もそれほど進まない、新しい人もあまり登場しない、そういう中で不可思議な事件が起こり、謎解きがなされるのです。
戦国ものながら大変わかりやすい、そしてやっぱりミステリーです。
それが史実に基づいて描かれているのですから、自然にのめり込んでいきます。
う~んますます目が離せない、米澤穂信さんでした。
直木賞受賞おめでとうございます。(2022/2/3)
第166回直木賞受賞作
黒牢城 / 米澤穂信

お雛様も終わり


山は早、花の時期となりました。