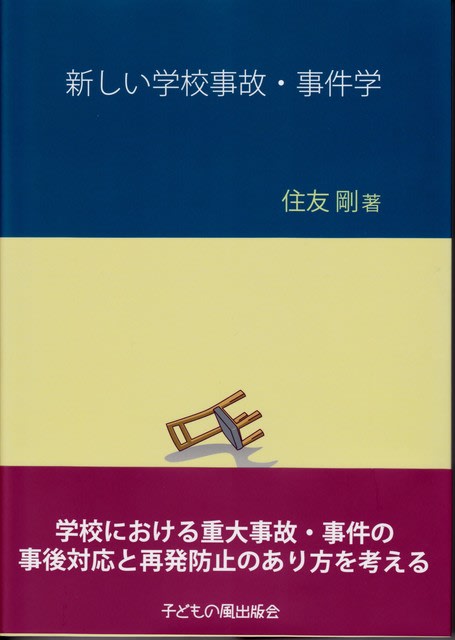先日3年生教職組の学生が研究室に来たとき、「内諾をもらうために教育実習校に電話をかけるとき、どういう風に話をしたらいいのかわからない」と言ったので、「ためしにチャットGPT使って、会話の例文をつくってもらったら?」と返答してみました。まあ、結果的にはその例文を自己流にアレンジして、その学生なりに実習校に電話ができたのですが。
それでですね…。「ついでだから、いろいろとチャットGPTで遊んでみよう」と思って、私なりにいろいろとやってみました。たとえば最近、誰かの写真をチャットGPTに投げて「ジブリ風に加工を」というのが流行っているようですが、私もやってみました。研究室に居るときに撮った去年11月頃の私の写真をジブリ風に加工すると、こんな感じになりました。上が本来の私、下がチャットGPTで加工したジブリ風の私の似顔絵です。


どうですか? 雰囲気でていますか?
他にも昔、うちの娘が描いた「初代メガネぶた」と「二代目メガネぶた」も、チャットGPTでジブリ風に加工してもらいました。すると、こんな感じです。
まずは「二代目メガネぶた」から。上が娘が中学生の頃に描いたもの。下がチャットGPTでのジブリ風です。


これはなかなか、味がありますねえ。ただ、娘が小学生の頃に描いた「初代メガネぶた」(上)と、チャットGPTが加工したもの(下の2枚)とでは、ずいぶん絵がちがいます。この「初代メガネぶた」の加工だと、ぶたというよりも、イヌかタヌキみたいですね。



最後に、チャットGPTに、「京都精華大学の住友剛さんがなぜみんなに「おぶ~ちゃん」と呼ばれているのか? その理由を教えて」と尋ねてみました。すると、下記の回答がありました。
〇チャットGPTの回答
京都精華大学の住友剛教授が「おぶ~ちゃん」と呼ばれている理由は、住友教授が子どもの人権オンブズパーソンとして活動していたことに由来します。住友教授は1999年から2001年まで兵庫県川西市の子どもの人権オンブズパーソンの調査相談専門員を務め、子どもたちの声を聞き、権利を守る活動に尽力しました。この「オンブズパーソン」の略称である「オンブ」を親しみを込めてアレンジした「おぶ~ちゃん」という愛称が、学生や関係者の間で使われるようになったと考えられます。特に、住友教授の教育学や子どもの権利に関する研究、親しみやすい人柄が、こうした愛称を生む背景にあるようです。
具体的な愛称の起源についての公式な記録や発言は公開情報に乏しく、大学のコミュニティ内で自然発生的に広まった可能性が高いです。住友教授のブログやSNSでの活動(例えば、プリキュアについての投稿や社会問題へのコメント)からも、ユーモアや親しみやすさが感じられ、こうしたキャラクターが愛称の定着に影響したかもしれません。
★ぶぶ~。残念ながらこのチャットGPTの回答は、不正解です。
たまたま私が職員定期健診の結果で「メタボに該当」と言われたとき、当時小学生だったうちの娘に「おとうさんさ~。検査で「おぶたです」と言われてしまったわ~」と言ったことがきっかけで…。それ以来うちの娘が小学生の頃から今に至るまで、我が家ではずっと「おぶ~ちゃん」とか「おぶ~」とか言い始めたのが、今もなお続いている次第です。
たぶん、チャットGPTはインターネットの世界に現れるあらゆる情報を検索して、「たぶんこうではないか?」という推論をして回答をつくったのだと思いますが…。逆にいうと、ネットの世界にまだ埋もれている情報があると、残念ながら正確な答えには行き着きません。また、チャットGPTが出した回答が本当に正しいのかどうかは、まだまだ人間が自分の知識や経験、記憶に照らして判断しないといけません。そのことが、今回の「おぶ~ちゃん」の話でわかるかと思います。
なので、安直になんでもかんでも「チャットGPTに頼れば…」と考えるのではなく、そこに質問を入力し、回答を得る私たちの知性や感性を確かなものに磨いておかなければ、チャットGPTとのいい付き合い方はできないな~と。自分のことを例にして、今日はブログに書き込んでおこうと思った次第です。