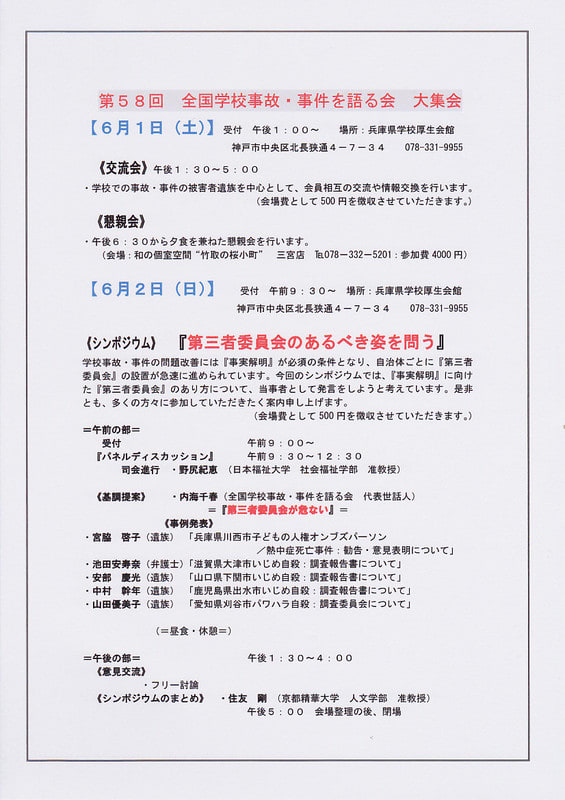この写真のとおり、子どもの自殺防止がテーマになっての講演会。
2012年12月14日に札幌市教委の調査委員会がだした子どもの自殺に関する報告書をもとにして、そこから何がわかるのか、何がわからないのか、そこがわからないような報告書になってしまった理由は何か、といったことをまとめて話しました。
これまでに見た教育行政の調査報告書のなかでは、かなり誠実に作業をしているという印象を受けたものの、この札幌市教委の報告書、「時系列的に経過を整理して書いていない」ために、「何が背景要因のなかで大事なポイントか?」が見えづらいという印象を抱きました。
また、調査委員会のメンバーのなかに当該中学校の校長や市教委の部長が入っていることで、どうしても、亡くなった子どもやその子どものいたクラスにたいして、当該中学校の教員がどう対処したのか、この学校がそもそもどのような課題を抱えた学校だったのかという点についての検討が弱いような印象も抱きました。
その結果、事実経過の検証作業から導き出される再発防止に向けての提言が、ごくありきたりな話で終わっているようにも思いました。
その一方で、スクールカウンセラー(SC)やスクールカウンセラーのスーパーバイザー(SCSV)が緊急支援としてかかわる形で、学校で子どもが亡くなったあとの対応(事後対応)がどのようにすすめられているのかも、この報告書からはよくわかりました。特に、子どもがいろんな葛藤を抱えながらも調査には積極的に協力していたこと、その子どもたちのケアに現場教職員が積極的にかかわることで、調査が生み出す子どもの心理的負担がかなり軽減されていたことが、報告書で触れられていました。でも、SCやSCSVは、子どもの心理的負担の部分をかなり強調する形で記録を残していたことも、報告書では紹介されています。これなどは、見ようによっては、報告書をまとめた調査委が暗に「これ以上、はれ物にさわらないで」と言っているようにも見えますね。
いずれにせよ、この報告書の内容、大津市の報告書などと比べて読むと、いろんなことが見えてきて、とてもよかったです。
ひとまず昨日、講演で話したことの要点のみ、お知らせします。