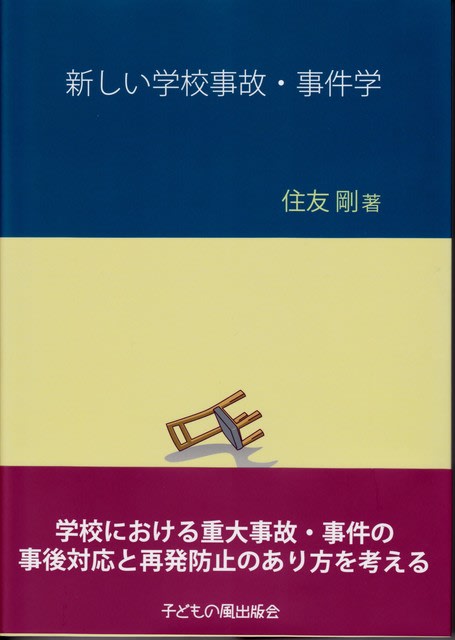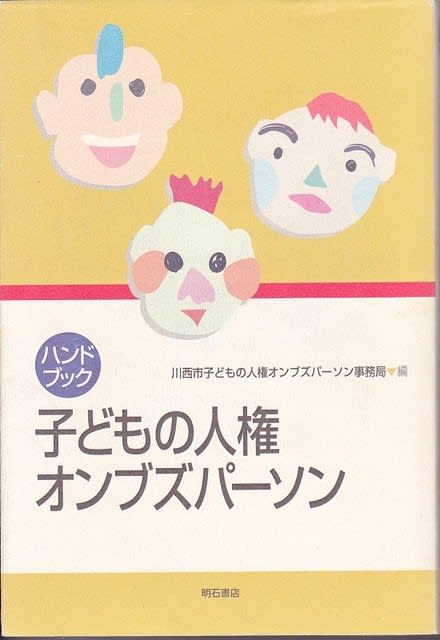この間、ずっとこのブログで論じてきましたが…。
神戸・須磨の小学校で起きた教員間いじめ問題がマスメディアで大きく取り上げられ、SNS上での反響なども含めて社会問題化しはじめてから、もうすぐ1か月になろうとしています。
そこで、この1か月間、この教員間いじめの問題に関して、私がくり返しこのブログで訴えてきたことを、あらためてここで整理し直しておきたいと思います。また、この教員間いじめの問題に先だって、今年(2019年)の春先には、いじめの重大事態の再調査報告書も出されました。そちらの問題にも関連することがいくつかありますので、ここで課題を整理しておきたいと思います。
ちなみに、ここで以下のとおり、教員間いじめ及び子ども間のいじめの重大事態に関する諸課題の整理を私なりにしますと…。およそ、今の学校事故・事件をめぐって何が問題なのかもわかってくるように思います。その整理の観点は、(1)~(3)のとおりになります。
また、以下のような課題の整理の仕方は、私が『新しい学校事故・事件学』(子どもの風出版会、2017年)を書いたからこそ「できる」ようになったのかもしれないな…と思って書いています。
(1)当該の事故・事件を起こすに至る経過と背景要因
そもそも、学校で子どもが亡くなったり、あるいは教職員間でいじめが起きたりするに至るまでに、いったい、何があったのか。また、そういう悲しい出来事に至る背景要因としては何が考えられるのか。この次元の問題があります。
たとえば垂水区の中学校で起きたいじめの重大事態(自死)のケースで言えば、お子さんが亡くなるに至るまでのいじめの経過や、そのいじめに対する学校側の対応の問題点などがここに該当します。また、神戸市の小中学生の学校生活が息苦しくなるような、そういう教育施策の諸問題(これは文科省レベル、神戸市レベルの両方がありますが)も、ここに含まれます。
あるいは、須磨の小学校の教員間いじめ問題でいえば、被害にあった教員と加害教員との間で何が起きたのか、そのときの教職員集団の雰囲気や管理職の対応がどのようなものであったのか、といった諸問題がここに該当します。また、このような教員間いじめが起きた背景にある神戸市の教育施策、さらには文科省の教育施策の問題も、ここに含まれます。
本来、起きてしまった悲しい出来事を調査・検証して、何らかの是正策を講じなければいけないのは、まずは(1)の次元の問題です。そのために、たとえば関係する教職員や子ども、保護者からのていねいな聴き取り、アンケートの実施などをふまえて事実経過を把握し、何が今回の問題で是正すべきポイントなのかを明らかにして、教育実践面や教育施策面の両方から今後の再発防止策を考えていく必要があります。
(2)当該の事故・事件が起きたあとの対応(事後対応)の経過とこれに関連する諸問題
次に、起きてしまった出来事そのものは悲しいと言わざるをえないのですが、でも、そのあとの学校や教育行政の事後対応のあり方次第では、その出来事をふまえた学校や教育行政の再生をはかっていくこともできます。ですが、この事後対応の時点で、たとえば亡くなった子どもの遺族と学校・教育行政との間などで、さまざまな問題が生じてきます。
先述の垂水区の中学校でおきたいじめの重大事態でいえば、再調査開始前に、事後対応の過程での市教委関係者によるメモ隠蔽の問題が明らかになりました。遺族側が「亡くなった我が子に何が起きたか、事実を知りたい」と思っていたのに、学校や教育行政側からこのような事後対応が行われると、当然、不信感を抱くことになります。
当然のことですが、このような事後対応のあり方そのものは、今後、是正していかなければなりません。ちなみに、学校や教育行政が行ってきた従来の事後対応のあり方を問い直すのが、前出の拙著『新しい学校事故・事件学』のテーマのひとつです。
また、須磨区の小学校で起きた教員間いじめの問題でいえば、たとえば被害にあった教員が苦情を訴えたときに管理職がどのような対応を行ってきたのか。また、市教委としてこのような教員間いじめの発生時にこれまで、どのような対応を行ってきたのか。こういう教員間の問題に関する事後対応のあり方も当然、問われてくると思います。そして、たとえば教職員間トラブル、あるいは教職員が仕事をする上での困難に関する相談・苦情申し立ての仕組みの不在などの課題があれば、この(2)の事後対応の課題に含めてもいいかもしれませんね。
なお、この(2)の事後対応に関する問題についても、私としては法的な観点だけでなく、教育学的・心理学的な観点からの調査・検証を行い、その結果をふまえた事後対応の問題点の是正、再発防止策の実施をはかっていく必要があると思います。また、そのためにも、やはり関係する教職員や保護者、子どもなどからの事情を聴く作業が必要になるでしょう。
そして、教員間いじめの問題でいえば加害教員と被害にあった教員、子どもどうしのいじめでいえばいじめていた子どもと被害にあった子ども、それぞれ双方への教育学的・心理学的な対応が、法的な対応に合わせて必要になるでしょう。また、周囲に居合わせた子どもや教職員へのケア・支援、学校再建に向けての取り組みも大事になると思います。
それこそ、たとえば今回の教員間いじめの問題でいえば、被害にあった教員の職場復帰に関する諸課題もここに含まれます。また、加害教員への懲戒処分及び処分後の「立ち直り」への諸課題についても、当然、ここに含まれます。周囲の教職員や当該の学校の子どもたちの受けた心身のダメージへの対応(=報道被害によるものを含む)も、ここに含まれるものと考えます。
ちなみに、川西市の子どもの人権オンブズパーソン制度は、いま、私が知る限り、あくまでも子どもの課題に限定されますが、この(1)(2)の両方の課題に適切に対応できる有効なシステムのように思います。もちろん、教職員間の紛争だと、その紛争自体は扱えず、あくまでも教職員間の紛争から派生的に生じたり、それにまきこまれたりする子どもの諸課題に限定されるわけですが。
(3)(1)(2)に対する社会的な反響とそれへの対応
(1)(2)は、どちらかといえば、その重大事故・事件が起きた学校に関係する人々(子ども・保護者・教職員)への対応ですが、(3)はたとえばマスメディアやSNSを通じて火が付いたかのようになっている世論への対応、さらには首長や市会議員などへの教育行政としての対応という課題です。なので「社会的な反響とそれへの対応」という風にまとめてみました。
たとえば垂水区の中学校でおきたいじめの重大事態で言えば、やはり再調査前のメモ隠蔽問題に対して、新聞やテレビなどで市教委に対する批判・非難の声が高まり、ツイッターなどのSNSでも市教委への批判等々が相次いだことと思います。当時、神戸市側は市長・市教委ともに、それら批判・非難への対応に追われていたことかと思います。また、このときも文科省から担当官が派遣され、市教委から事情を聴いて、何らかの「指導」を行って帰ったとの報道もあったかと思います。
また、その対応のなかでいじめの重大事態の再調査の実施を決めるとともに、なぜか、教職員不祥事と併せてメモ隠蔽問題を扱う別の会議体が設置され、市教委の「組織風土」改革なるものが提案されました。しかし、本当にあのとき、教職員不祥事とメモ隠蔽問題の両方をあわせて「組織風土」改革なるものを検討することが必要なことだったのかどうか。私は当時から疑問だったのですが、もしかしたら今回の教員間いじめ問題で何か、分限処分に関する条例改正を行う「伏線」をその頃からつくろうとしていたのかもしれません。
あるいはこのたびの須磨区の小学校での教員間いじめの問題でいえば、一部のマスメディアで激辛カレーを無理やり食べさせられている映像・画像が流れたことで、一気にSNSなどでこの問題に「火が付いた」状態になりました。その結果、たとえば市教委や当該の小学校、あるいは近隣の学校にまで苦情電話が殺到したり、映像を見た子どもたちのなかに心理的に動揺してしまう子どももでました。また、SNS上などでもりあがった「加害教員を早く処分しろ」「仕事を休んでいる加害教員に給料を払うな」という人々の声が、市長や一部市議たちを動かして、分限処分に関する条例改正にまで至ったのが、昨日の時点での状況です。
さらに、「市教委けしからん」「加害教員たち許せない」という声をひきうけるようなかたちで、神戸市長が市教委の「改革」と称して、首長部局に教委対応の担当課長を置いたり、教委側にも改革推進担当の課長を置くことを決めるなどの対応が行われました。そして神戸市教委の博物館や図書館、美術館などの担当部署を首長部局に移す提案のように、「いったい、この対応のどこが本件と関係するのか?」と思うような提案も、神戸市長側から行われるに至っています。まさに、このような神戸市長の動き方は、須磨区の小学校で起きた教員間いじめ問題という悲しい出来事にうまく乗りかかったような、そんな「惨事便乗型」の教育改革、あるいは「教育版のショック・ドクトリン」といえばいいでしょうか。
しかし、このように課題を整理していくとすぐに気付かれるかと思いますが・・・。
たとえば須磨区の小学校で起きた教員間いじめの問題でいえば、本来、神戸市長及び市教委の双方が互いに歩み寄って協力し、解決していかなければ課題は、(3)ではなくて、(1)と(2)の課題です。また、その(1)と(2)の課題についても、本来であれば「加害教員の処分」に関するコンプライアンス(法令順守)等々の法的対応だけでなく、教育学的・心理学的な調査・検証作業を実施すべきことです。その上で、子どもや保護者、地域住民、そして当該の学校に引き続き勤務する教職員の声を聴いて、かなり長期間にわたる学校への支援計画をつくり、「学校再生」の取り組みを着実に実施していくことが、なによりも必要不可欠なはずです。
にもかかわらず、この約1か月間、ひたすら(3)の課題への対応や、あるいは(1)(2)についての「法的対応」ばかりを優先的にやってきた…というのが、この間の神戸市側の動きのように思います。
そして、実は(3)の課題への対応や、(1)(2)の課題でも「法的対応」の課題ばかりを優先的に対応して、なんとなく「市長として、市教委として対応できている」という気分にさせられていくと…。
結果的に(1)(2)の課題のうち教育学的・心理学的なものが、当該の学校を含む神戸市内の学校にずっと残り続けることになります。また、それは別の見方をすると、神戸市や文科省のこれまでの教育施策の課題に「触れないことにする」のを可能とするわけです。これでは、ほとぼりが冷めたころに、また同様の重大事態が生じるのではないか…と、私などは危惧するわけですね。
私が昨日書いたブログのように、なぜ「公的良心の喚起者」としてのオンブズパーソンの例にならって、「ほんとうにこのままの対応でいいのか?」と、今月はじめから神戸の学校で起きていることについて言い続けているのかといえば、上記のような課題整理があってのことです。
昨日は残念ながら、あのような分限処分に関する条例改正案が可決してしまいましたが…。でも、引き続き上記の(1)(2)に関する課題への対応は残り続けています。なので、ここで1か月間の私からの情報発信の内容をいったん整理して、あらためて何が課題かを伝えておきたいと思い、今日のブログをまとめました。今後の神戸市内でのさまざまな取り組みの参考にしてください。