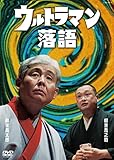補足:「大河への道」とは、立川志の輔師の創作落語です。郷土の偉人伊能忠敬をなんとか大河ドラマ化しようと奮闘する人々の話。志の輔師が佐原市(現・香取市)の伊能忠敬博物館を訪れた時の感銘をもとに2011年に初演。以来人気の演目として同時になかなかチケットの取れない高座として不動の地位にあります。映画化決定。5月ロードショー。
第一章・ドタキャンへの道はこちら
第二章・佐原への道はこちら
第三章・伊能忠敬への道はこちら
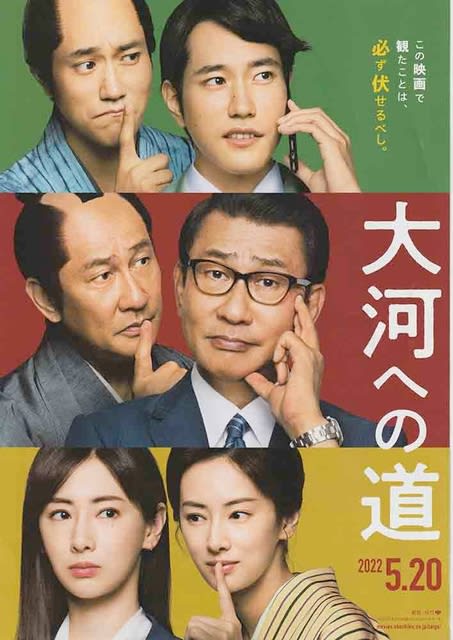
突然ですが、映画化です。
何が?って『大河への道』が、です。
豪華キャスト。
ネットをググっていたら発見しました。
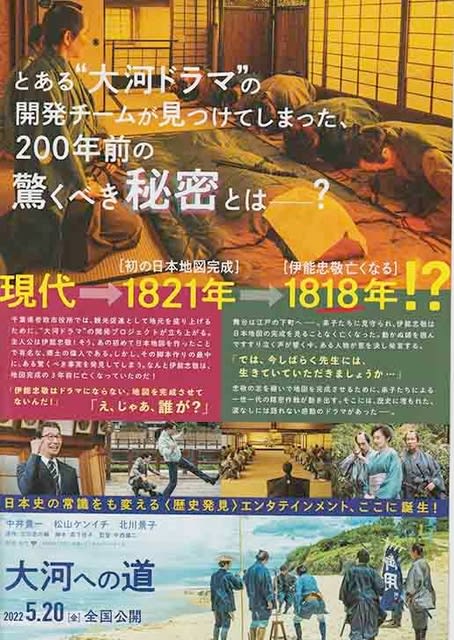
時は流れて2021年晩秋。
年号は平成から令和に変わって3年目の冬を迎えていました。
が、その時私はまだ『大河への道』を拝聴していません。
元号が変わった2019年に新型コロナウィルスが世界中を襲い
外出自粛、マスク着用、飲食店も映画館も劇場もすべて閉鎖
入学式からイベントまで全て中止。という異常事態に。
もちろん寄席なんてとんでもない。
そんな不自由な生活が2年も続くなんて思わなかった。
オリンピックまで一年延期の上、無観客開催。
その秋ようやくワクチン接種が一気に進み
やっと緊急事態宣言解除か?という2021年11月、突然のネットニュース。
映画化されるんだって!!
ああ、もう映画でいいじゃん!という思いと
いやいやいやいやいや、高座がいいの!!!
どこかで聞きたい!
どこかで!!という私の叫びはいったいどこに行くのでしょうか?
しかし、ここにも神様がいた!
翌2022年、新春志の輔らくご再開!
チケットは抽選だけど当たれば志の輔師に会える!
だけど再びの蔓延防止でまだ江戸に行くのは(コロナが)ちょっと怖い。
でももしかしたらここで『大河への道』がかかるかもしれない‥。
そして気がついた!ここで迷ってる場合ではない。
まずは抽選に参加せねばいかん!!あとのことはそれからじゃ!
ロー◯ケにアクセス、ポチッと、な。
当たるも八卦当たらぬも八卦。
で、当たりました。(あっさり)

もう絶対行くしかないじゃない。
そして、こんな時期にと恐縮しつつ
友人を誘ってみたら二つ返事でオッケー。
なんか新春早々縁起がいいかも!
思わず
「大河への道がかかったらいいなあ」
と呟いた私に友人曰く
「大河への道?演目にあるよ。」
え〜!!どうして知ってるの?あなたは神?もしかして神?!
「ちゃんとウェブサイトに書いてある。」どこまでも冷静な友よ。
あ、なんか書いてあったかも(汗)
私は例によって抽選応募にのみ全集中で
肝心の講演内容を見ていなかったのだけれど
(独演会なんかだと演目はその日決まりのことが多いので
ハナから考えていなかったの…)
でもパルコ劇場の場合はメインの出し物は決まっているのね。
というわけで
うわ〜い!!!3年越しのしゅうね… いや…思いが叶った!!!!
のであります。

公演は昼の部のみ。マスク着用、入場時体温測定、場内での飲食、
ホワイエでの軽食提供も物販もわずか。
ですが、正真正銘3年ぶりの生落語。
志の輔師オンリー、堪能しました。
誘った友人が大笑いしているのを横で聞いていられる幸せ、
会場が笑いに包まれる幸せ。
志の輔師のコロナ禍での葛藤が伝わる演出に同感できる幸せ。
ドローン映像も駆使した映像もリアルに
伊能忠敬の足跡を体感できる幸せ。
ひさしぶりに拝見する志の輔師の頭に
白いものが増えていることに感じ入る幸せ。
そして『大河への道』をたっぷり聞けた幸せ幸せな時間でございました。
終演後、感動の余韻を抱えたまま
渋谷のパルコの屋上で眺めた富士山最高だったのはいうまでもありません。

めでたし、めでたし。
第一章・ドタキャンへの道はこちら
第二章・佐原への道はこちら
第三章・伊能忠敬への道はこちら
さあ!今度は映画見に行くぞ!!
あ、佐原ツアもーリベンジせねば。
コロナ退散!!平和が第一!
落語は世界を救う!!…かもしれない。
というわけで、『大河への道、への道』最終章、これにて!
余談:志の輔らくごと同時開催中のポケモンセンターでのアルセウス発売記念に心奪われたのは内緒。


























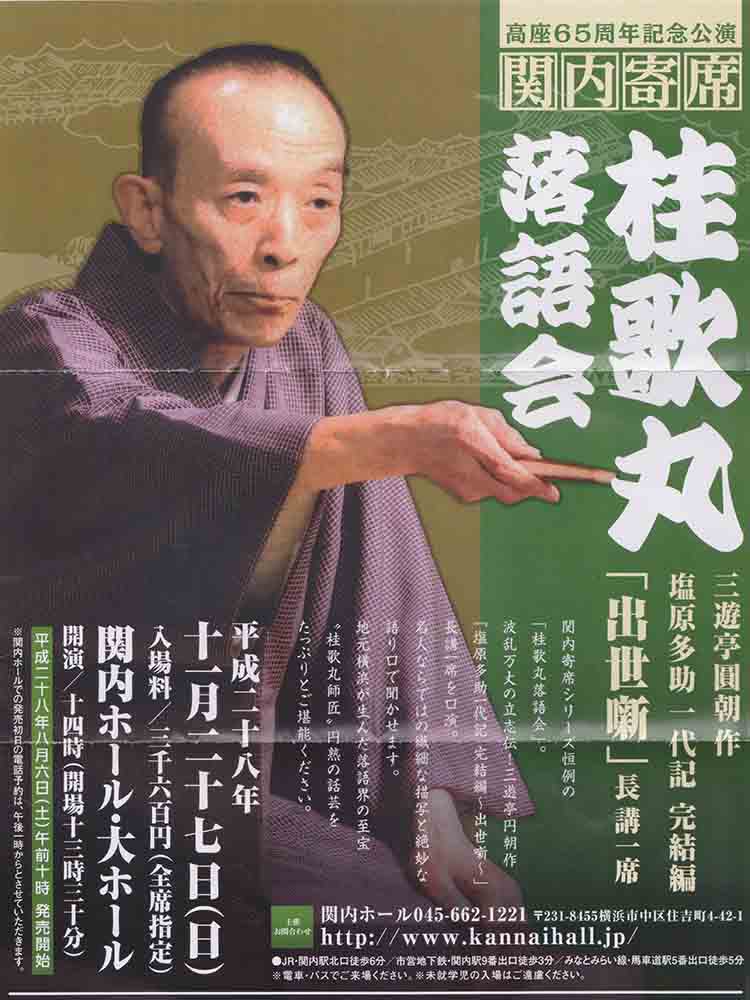
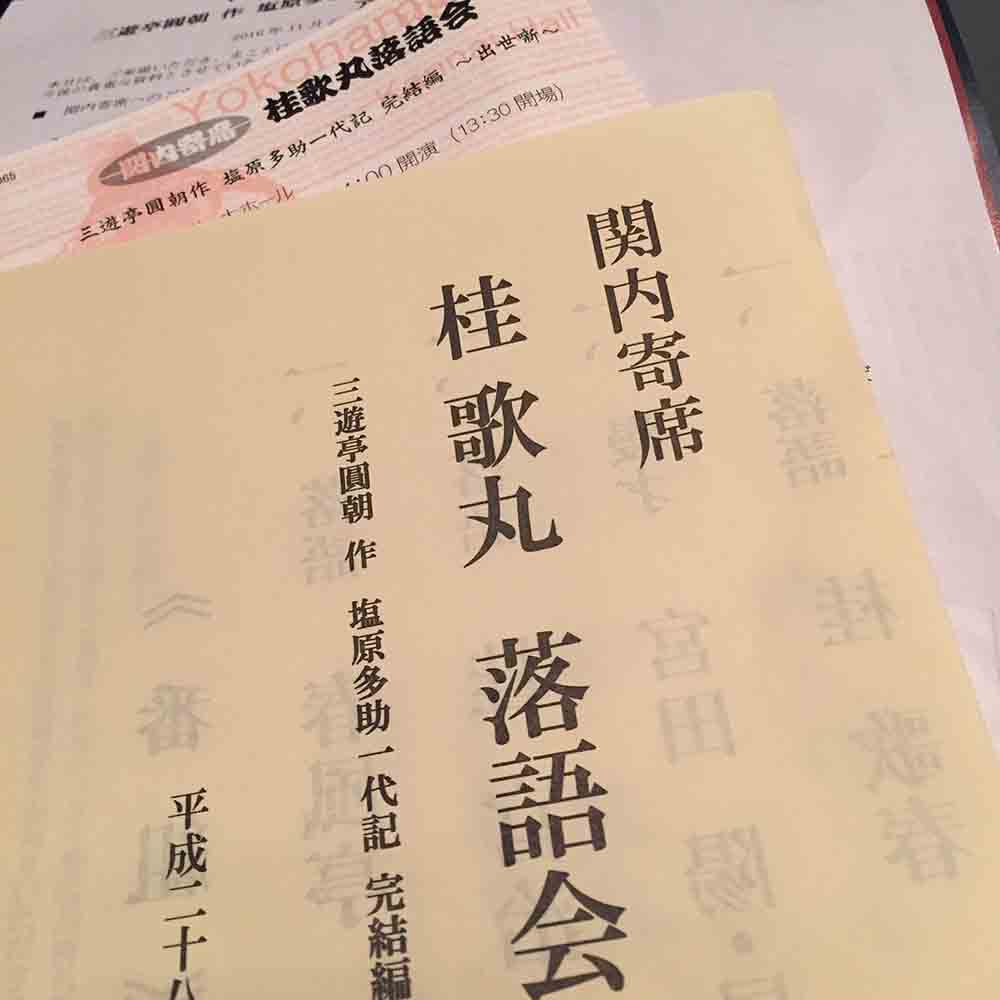
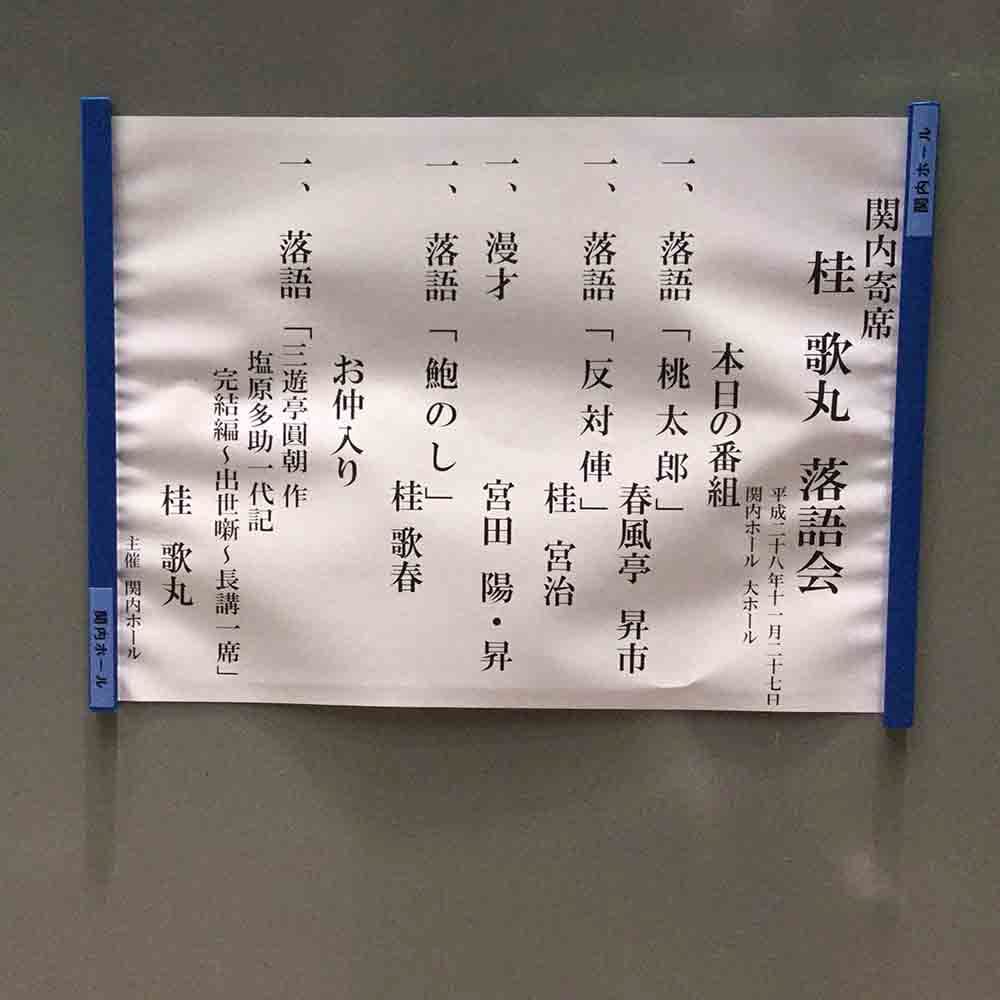



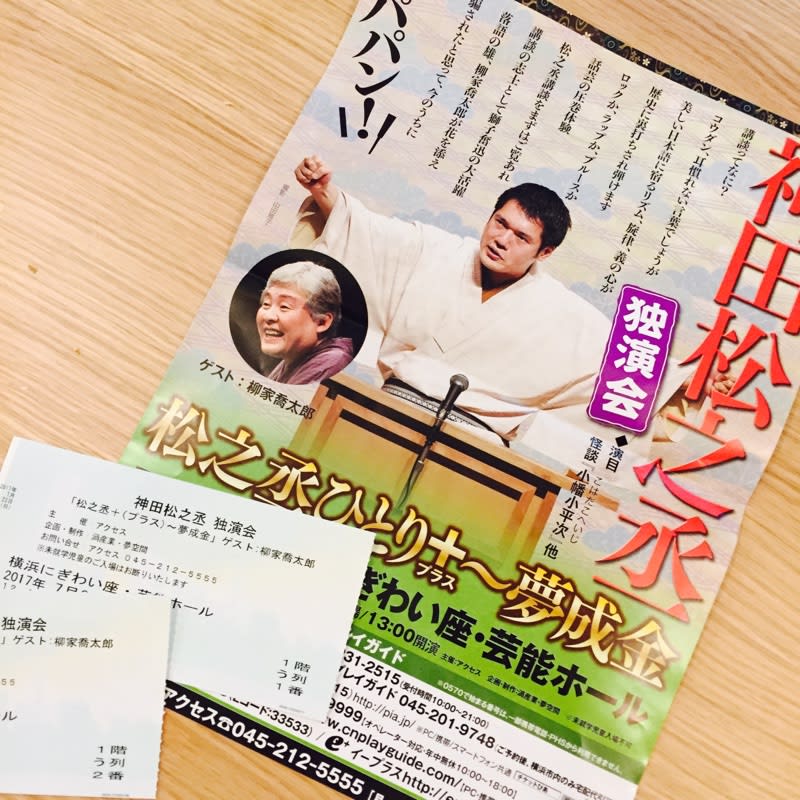 、
、