やって来ました、北の果て。

ここは網走番外地
かつてはここに送られたが最後、
過酷な自然環境と重労働から刑期を全うしても生きてシャバに出ることは難しいと言われた
最北の受刑地でした。
日本全国の犯罪受刑者から恐れられたという網走監獄は、現在博物館として残されています。

ただ単に最北の受刑地だったからではありません。
ここは北海道開拓史上、重要な役割を担った場所だったからでした。

正門から左て奥にある
教誨堂。


囚人たちによって建てらました。
現在はコンサートホールとしても一般に利用されているそうです。

中は綺麗になっていますが、個人的に一番身につまされてしまったのはこの教誨堂でした。
庁舎内部

監視所を中心に扇状に5本の廊下が広がっています。その両脇にずらりと監房が並んでいる作り。
雑居房連と、独居房連に分かれています。雑居房が廊下を見回る監視からは中の様子がよく見え、中の囚人は正面の監房の様子がわからないくの字型講師がはめ込まれています。
暖房は通路に設置されている石炭ストーブ。
講師壁にすることで、この暖房熱がそれぞれの監房に行き渡り仕組みです。
しかし夏はともかく冬は氷点下のこの網走で、果たして十分に暖がとれたかどうか定かではありません。
1)網走監獄はなぜ作られた?
極寒の地にそうまでして囚人を集めたのには理由がありました。
北海道開拓。
不凍港を求めて南下政策を進めるロシアに対して、北海道の軍備を固めることは時の明治政府にとっての急務でした。
肝いりで始められた北海道開拓でしたが、厳しい自然と北海道独特の泥炭地質によって困難を極めていました。
禄を失った士族や一角千金を夢見て志願した開拓団と屯田兵だけで人手をまかないきれず、十分な財源もない…
そこに目をつけられたのが急増する犯罪受刑者だったのです。
受刑者たちが携わったのは主に幹線道路建設。
建設は大型重機などはなく、ひたすら人海戦術。原野を開墾するところから始めなくてはなりませんでした。
まして受刑者は逃亡防止のため二人1組で鎖に繋がれての重労働でした。
作業中に事故や栄養失調、寒さで亡くなった囚人はその場に埋められ鎖が墓標がわりに目印として置かれたということです。
昭和30年に入ってこれらの遺骨が掘り起こされてきちんと埋葬されるまで、その墓標は延々と続いていたのでした。
野外作業小屋(レプリカ)

受刑者たちは大きな丸太を枕に並んで就寝。
起床時に看守が丸太の端を叩いて起こしました。
2)網走監獄の有名人
網走監獄には個性的な受刑者が二人いました。
ひとりは
五寸釘寅吉こと西川寅吉。
なぜか網走監獄名物のお土産にもなっています。

なぜかピーナッツ。

何度か収監されたのち、刑務所を脱走。逃走中に静岡県で警察に追われた際五寸釘差刺さった板を踏んでしまったもののそのまま十数キロを逃げたということから
五寸釘寅吉五寸釘寅吉の異名がついたと言われます。
何度か刑務所を転々としたあとにたどり着いた網走ではすでに伝説の人で、当人は模範囚だったとのこと。
高齢を理由に仮出所した後その波乱万丈な障害が当時の工業史によって面白おかしく語り伝えられたことから人気者に。
その後故郷三重で息子に引き取られて87歳でなくりました。(1941年)
もうひとりは
白鳥由栄
この人が事実上網走監獄最初で最後の脱獄囚。
昭和の脱走王とも言われています。
最初の犯罪では自首したものの刑務所での劣悪な待遇に抗議したことからさらに懲罰を受けたことがきっかけで脱走。1936年。
その後収監されるた秋田刑務所を脱走。1942年。
難攻不落と言われた網走監獄からも脱獄に成功。1944年。
しばらく消息を絶ちます。
その後、畑泥棒と間違われて暴行され相手を殺害。札幌刑務所に収監されます。死刑判決が出たことで、再び脱走。1947年。
よく年、東京の浅草で逮捕。
経緯は、その時たまたま声をかけた巡査にタバコをねだったところ、当時貴重品だったタバコを快く一本差し出されたことに感激。
巡査に白鳥はこう言ったと伝わっています。
「俺を捕まえて、あんたの手柄にしなさい。」1948年。
その後府中刑務所では模範囚として服役、1961年に仮釈放され1972年に死亡。
無縁仏になるはずの遺骨を引き取ったのは、仮出所時に親しく交流があった隣人宅のお嬢さんだったそうです。
3)網走監獄という集落
受刑者がいるということは、それを監視する役人もいるということで
こちらが今でいう官舎。


単身ではなく家族ごとの赴任。
生活は監獄ともに基本自給自足。
農地や牧場、農産物の加工場も含め網走監獄は単に受刑者の収監所というより一つの集落を形成するに至りました。
人が集まるところには物流が生まれ産業が発達します。
もちろん北海道の炭鉱や硫黄山での採掘作業にも受刑者が駆り出され、網走監獄の経費だけでなく網走の発展を支えました。
網走市は監獄と共存してきた街とも言われる所以です。
受刑者の作業が大きく変わるのは昭和27年以降。
受刑者の就労規定も改正されて、刑務作業に応じて時給が支払われるように。
それでも網走は監獄という負のイメージが嫌われて何度か監獄名の改称が願い出られています。
そのイメージを払拭するきっかけが
高倉健さん主演の映画、『網走番外地』シリーズの大ヒットでした。
地のはての受刑地は一躍観光名所になったのです。
昭和58(1983)年には刑務所改築に伴い、旧舎を移築復元した博物館として再出発することになり現在は網走観光のメインゲートになっているということでした。
ちなみにこの網走監獄舎は、昭和61(1986)年まで実際に使用されていました。
現在の網走刑務所はここから少し離れた場所にあります。
この橋の向こう、ね

もちろん現在は独居房がメイン。今収監されているのは再犯者や軽犯罪の受刑者がほとんど。
制限付きとはいえテレビも各房に設置。暖房も完備してるそうですよ。
____
以前の話は、
北海道でっかいどう(前書き)


































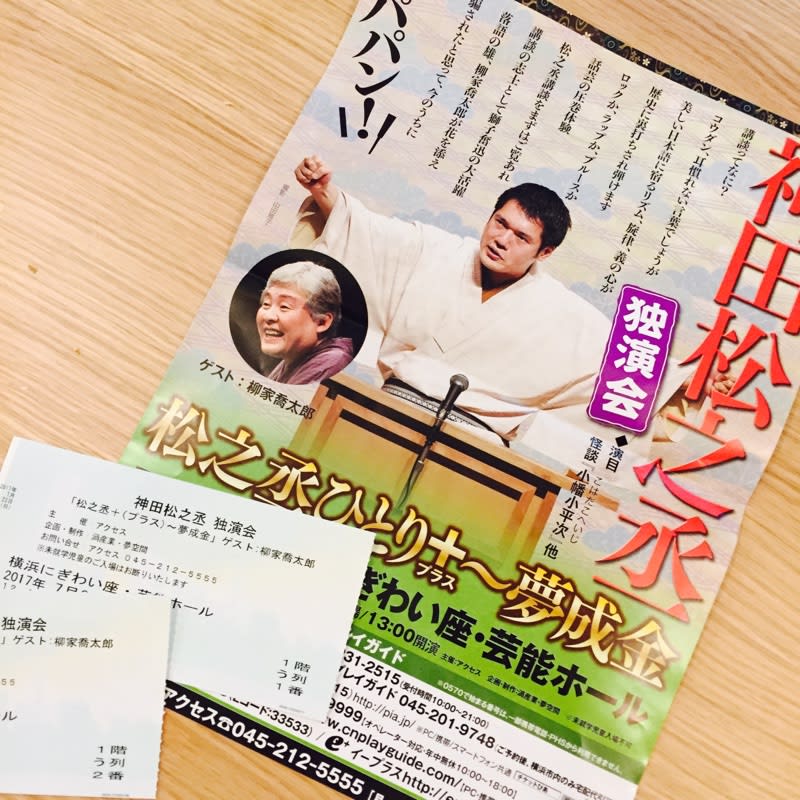 、
、




















