8月1日にアップされた東洋医学研究所のコラムです。ブログアップが遅くなってま~す
東洋医学研究所のコラムが更新されました

『経穴について その7』
東洋医学研究所グループ 井島鍼灸院(岐阜市) 院長 井島晴彦 先生
『経穴について その7』 研究所コラムはこちらをクリック!
経穴とは「ツボ」のことなのですが、身体にはたくさんの経穴があります。鍼灸師は治療に際し、古典文献や過去の先輩の経験などを参考にしながら患者の治療を行うわけです。古典文献に関しては、参考にすべきところはたくさんあるのですが、現代には適合しない部分、正しくない部分もたくさんあるわけです。文献が作成されてから多くの手が入っていたり、書き換えられている部分もあるわけですね。
そこを検証して、現代の鍼灸診療へ合うものを選別していくことも必要です。
私の師匠である、東洋医学研究所所長 黒野先生のご指導で、その経穴に関する調査を行っているのが井島先生です。また、古典文献を参考にすることは大事であるが、それを無批判に取り入れるのではなく、正しい部分と間違っている部分を検証していく必要があると、師匠は常々仰られ、言うだけでなく、古典の検証を科学的研究を踏まえて集積されています。
臨床を行いながら、このような感覚を持って、鍼灸の研究に、臨床に、後身の指導に尽力され、常に真実を探求されている人物(鍼灸師)は貴重であると思います。こんなこと愚弟が言うのもなんなのですが…
今回の井島先生のコラムは、経穴について、泌尿器疾患に関連する、中極、横骨、腰陽関、気海、水道という経穴に関して紹介してあります。
東洋医学研究所グループでは、黒野先生が長年の研究により導き出した13経穴を使用した生体制御療法を中心として治療を行い、さらにより効果的に患者の病態を改善すべく、様々な経穴を局所的治療として使用していきます。いろんな知識を得ることは臨床家にとって必要不可欠なことです。しかし、大切なのは軸となる治療方法があるということです。応用を利かすためには基礎がしっかりしていないと、知識を活かすことができないと言うことだろうと思いますね。
さて、今回のコラムで、「鍼灸が泌尿器疾患に使われるの
 」と思われた方も多いと思いますが、鍼灸治療は痛みやシビレなどの整形外科的疾患はもとより、もともと近代医学が入ってくる以前は鍼灸や漢方薬などが日本の医者が行う医術だったんですね。ということは現代医学でいう内科的疾患も治療していたんです。泌尿器疾患に関しても多く学会などで発表されているんです。
」と思われた方も多いと思いますが、鍼灸治療は痛みやシビレなどの整形外科的疾患はもとより、もともと近代医学が入ってくる以前は鍼灸や漢方薬などが日本の医者が行う医術だったんですね。ということは現代医学でいう内科的疾患も治療していたんです。泌尿器疾患に関しても多く学会などで発表されているんです。
泌尿器疾患でお困りの方は、一度、ご相談してみてくださいね。
あっ、鍼灸治療は魔法ではありませんので、効果が期待できない場合もございますからね。
さて、どうぞ東洋医学研究所コラムを生活の中で役立ててくださいませ

二葉鍼灸療院 田中良和

東洋医学研究所のコラムが更新されました


『経穴について その7』
東洋医学研究所グループ 井島鍼灸院(岐阜市) 院長 井島晴彦 先生
『経穴について その7』 研究所コラムはこちらをクリック!
経穴とは「ツボ」のことなのですが、身体にはたくさんの経穴があります。鍼灸師は治療に際し、古典文献や過去の先輩の経験などを参考にしながら患者の治療を行うわけです。古典文献に関しては、参考にすべきところはたくさんあるのですが、現代には適合しない部分、正しくない部分もたくさんあるわけです。文献が作成されてから多くの手が入っていたり、書き換えられている部分もあるわけですね。
そこを検証して、現代の鍼灸診療へ合うものを選別していくことも必要です。

私の師匠である、東洋医学研究所所長 黒野先生のご指導で、その経穴に関する調査を行っているのが井島先生です。また、古典文献を参考にすることは大事であるが、それを無批判に取り入れるのではなく、正しい部分と間違っている部分を検証していく必要があると、師匠は常々仰られ、言うだけでなく、古典の検証を科学的研究を踏まえて集積されています。
臨床を行いながら、このような感覚を持って、鍼灸の研究に、臨床に、後身の指導に尽力され、常に真実を探求されている人物(鍼灸師)は貴重であると思います。こんなこと愚弟が言うのもなんなのですが…

今回の井島先生のコラムは、経穴について、泌尿器疾患に関連する、中極、横骨、腰陽関、気海、水道という経穴に関して紹介してあります。
東洋医学研究所グループでは、黒野先生が長年の研究により導き出した13経穴を使用した生体制御療法を中心として治療を行い、さらにより効果的に患者の病態を改善すべく、様々な経穴を局所的治療として使用していきます。いろんな知識を得ることは臨床家にとって必要不可欠なことです。しかし、大切なのは軸となる治療方法があるということです。応用を利かすためには基礎がしっかりしていないと、知識を活かすことができないと言うことだろうと思いますね。
さて、今回のコラムで、「鍼灸が泌尿器疾患に使われるの

 」と思われた方も多いと思いますが、鍼灸治療は痛みやシビレなどの整形外科的疾患はもとより、もともと近代医学が入ってくる以前は鍼灸や漢方薬などが日本の医者が行う医術だったんですね。ということは現代医学でいう内科的疾患も治療していたんです。泌尿器疾患に関しても多く学会などで発表されているんです。
」と思われた方も多いと思いますが、鍼灸治療は痛みやシビレなどの整形外科的疾患はもとより、もともと近代医学が入ってくる以前は鍼灸や漢方薬などが日本の医者が行う医術だったんですね。ということは現代医学でいう内科的疾患も治療していたんです。泌尿器疾患に関しても多く学会などで発表されているんです。
泌尿器疾患でお困りの方は、一度、ご相談してみてくださいね。
あっ、鍼灸治療は魔法ではありませんので、効果が期待できない場合もございますからね。
さて、どうぞ東洋医学研究所コラムを生活の中で役立ててくださいませ


二葉鍼灸療院 田中良和











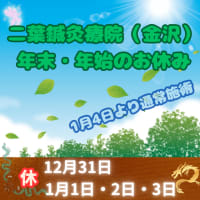
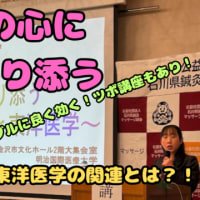







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます