12月の天気のいい朝…いつだったか 、久しぶりに朝の散歩をしてみました。空気も気持ち良く、その一日はとても冴えていた
、久しぶりに朝の散歩をしてみました。空気も気持ち良く、その一日はとても冴えていた のでは、と思うくらい気分が良かったです。
のでは、と思うくらい気分が良かったです。
そんな日は、いい仕事ができるんですよね。

朝何時だったかな~お月さまです
ということで、その頭が冴えていた理由を「セロトニン」という物質から考えてみました。
セロトニンとは、神経伝達物質の一つで、脳内ではドーパミンやノルアドレナリンとともに重要な働きを行うとともに、この二つの神経伝達物質の働きを調整する役目をもっています。セロトニン神経系は脳内に広く分布してます。また、その他の身体各部位にも広く分布しています。
セロトニンは、、小腸のクロム親和性細胞に約90%、血小板内に約8%、若干腎臓でも生産され、脳内には約2%存在します。抗がん剤などで、吐き気や嘔吐などの副作用が発症しますが、この小腸のクロム親和性細胞が抗がん剤により障害されることにより、セロトニンが分泌され、それが脳の嘔吐中枢を刺激し発症することが分かっています。
セロトニンの原料は、トリプトファンという必須アミノ酸で、肝臓に蓄えられたこの物質が脳の松果体というところに運ばれ生成されます。ここはメラトニンという睡眠に関るホルモンに関係するところでもあります。必須アミノ酸は身体の外から摂取(食事で)しなければなりません。豆類、赤身の魚、チーズ、バナナ、ケールなどに含まれます。昔ながらの和食を食べていれば不足することはありません。
セロトニンは、覚醒、睡眠、気分、情動、記憶、概日リズム、鎮痛、姿勢筋促通、自律神経調節などに働きます。早起きに関連するところでは、覚醒時の脳神経の状態を調整します。
セロトニン神経系は、太陽光を浴びる、歩行や自転車こぎなど一定のリズム運動。ガムを噛むなどの咀嚼運動、坐禅の深く長い呼吸、グルーミングなどによりセロトニンの分泌が賦活されます。逆に分泌を抑制するのは「慢性ストレス」です。
セロトニンの、少し難しい話をすると、脳の橋・大縫線核のセロトニン神経は、脊髄後角に投射して、内因性痛覚抑制系として働きます。痛みの軽減に働いているということです。慢性疼痛や原因不明の疼痛などは、ここら辺が治るポイントなのかもしれませんね。
延髄線維核群(淡蒼線維核・不確縫線核)のセロトニン神経は、脊髄前角の運動ニューロン(抗重力筋支配)や脊髄中間外側枝の交感神経節前ニューロンに影響を与えます。ということは抗重力筋ですから、姿勢の保持に影響し、深部筋肉の活動を促すということです。表面の筋肉の負担が軽くなるということでもあります。また、交感神経に作用して、起床時、血圧を上げ、心拍数を上昇させます。身体を目覚めさせる元の物質ということになります。
朝5時くらいが、自律神経の交感神経と副交感神経が入れ替わり、「よし今日も一日頑張るぞ!」モードに身体をもっていきます。早起きするということは、このセロトニンの分泌をさらに高めることになります。
ここまで、東邦大学医学部生理学 教授 有田秀穂 先生の研究を参考にさせて頂きました。
セロトニンが最重要ということではなく、身体は様々な物質が絶妙なバランスで調整しながら、自然の営みに合わせて、身体を常にベストな環境に整えようと働いています(生体恒常性維持機構)。セロトニンは、その一つの物質にすぎませんが、こんなに多くの働きを担っているのですね

治療院周辺を散歩。西の空にはお月さま

東の空は、夜明け間近
さて、私の日常を振り返り…
やることが多く、つい夜更かしをしてしまいがちです。このシーズンは妄念会でなく、忘年会の時期でもありますので、余計でしょうか… やはり、早起きの癖をつけるようにしたほうが、身体にも心にもいいようですね。
やはり、早起きの癖をつけるようにしたほうが、身体にも心にもいいようですね。
さて、さて、明日のクリスマスはさらに寒くなりそうですが、早起きしてみましょうかね

二葉鍼灸療院 田中良和
 、久しぶりに朝の散歩をしてみました。空気も気持ち良く、その一日はとても冴えていた
、久しぶりに朝の散歩をしてみました。空気も気持ち良く、その一日はとても冴えていた のでは、と思うくらい気分が良かったです。
のでは、と思うくらい気分が良かったです。
そんな日は、いい仕事ができるんですよね。


朝何時だったかな~お月さまです

ということで、その頭が冴えていた理由を「セロトニン」という物質から考えてみました。
セロトニンとは、神経伝達物質の一つで、脳内ではドーパミンやノルアドレナリンとともに重要な働きを行うとともに、この二つの神経伝達物質の働きを調整する役目をもっています。セロトニン神経系は脳内に広く分布してます。また、その他の身体各部位にも広く分布しています。
セロトニンは、、小腸のクロム親和性細胞に約90%、血小板内に約8%、若干腎臓でも生産され、脳内には約2%存在します。抗がん剤などで、吐き気や嘔吐などの副作用が発症しますが、この小腸のクロム親和性細胞が抗がん剤により障害されることにより、セロトニンが分泌され、それが脳の嘔吐中枢を刺激し発症することが分かっています。
セロトニンの原料は、トリプトファンという必須アミノ酸で、肝臓に蓄えられたこの物質が脳の松果体というところに運ばれ生成されます。ここはメラトニンという睡眠に関るホルモンに関係するところでもあります。必須アミノ酸は身体の外から摂取(食事で)しなければなりません。豆類、赤身の魚、チーズ、バナナ、ケールなどに含まれます。昔ながらの和食を食べていれば不足することはありません。
セロトニンは、覚醒、睡眠、気分、情動、記憶、概日リズム、鎮痛、姿勢筋促通、自律神経調節などに働きます。早起きに関連するところでは、覚醒時の脳神経の状態を調整します。
セロトニン神経系は、太陽光を浴びる、歩行や自転車こぎなど一定のリズム運動。ガムを噛むなどの咀嚼運動、坐禅の深く長い呼吸、グルーミングなどによりセロトニンの分泌が賦活されます。逆に分泌を抑制するのは「慢性ストレス」です。
セロトニンの、少し難しい話をすると、脳の橋・大縫線核のセロトニン神経は、脊髄後角に投射して、内因性痛覚抑制系として働きます。痛みの軽減に働いているということです。慢性疼痛や原因不明の疼痛などは、ここら辺が治るポイントなのかもしれませんね。
延髄線維核群(淡蒼線維核・不確縫線核)のセロトニン神経は、脊髄前角の運動ニューロン(抗重力筋支配)や脊髄中間外側枝の交感神経節前ニューロンに影響を与えます。ということは抗重力筋ですから、姿勢の保持に影響し、深部筋肉の活動を促すということです。表面の筋肉の負担が軽くなるということでもあります。また、交感神経に作用して、起床時、血圧を上げ、心拍数を上昇させます。身体を目覚めさせる元の物質ということになります。
朝5時くらいが、自律神経の交感神経と副交感神経が入れ替わり、「よし今日も一日頑張るぞ!」モードに身体をもっていきます。早起きするということは、このセロトニンの分泌をさらに高めることになります。
ここまで、東邦大学医学部生理学 教授 有田秀穂 先生の研究を参考にさせて頂きました。
セロトニンが最重要ということではなく、身体は様々な物質が絶妙なバランスで調整しながら、自然の営みに合わせて、身体を常にベストな環境に整えようと働いています(生体恒常性維持機構)。セロトニンは、その一つの物質にすぎませんが、こんなに多くの働きを担っているのですね


治療院周辺を散歩。西の空にはお月さま


東の空は、夜明け間近

さて、私の日常を振り返り…
やることが多く、つい夜更かしをしてしまいがちです。このシーズンは妄念会でなく、忘年会の時期でもありますので、余計でしょうか…
 やはり、早起きの癖をつけるようにしたほうが、身体にも心にもいいようですね。
やはり、早起きの癖をつけるようにしたほうが、身体にも心にもいいようですね。さて、さて、明日のクリスマスはさらに寒くなりそうですが、早起きしてみましょうかね


二葉鍼灸療院 田中良和













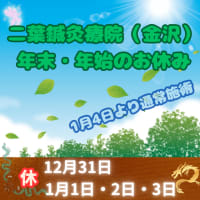
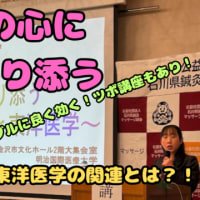










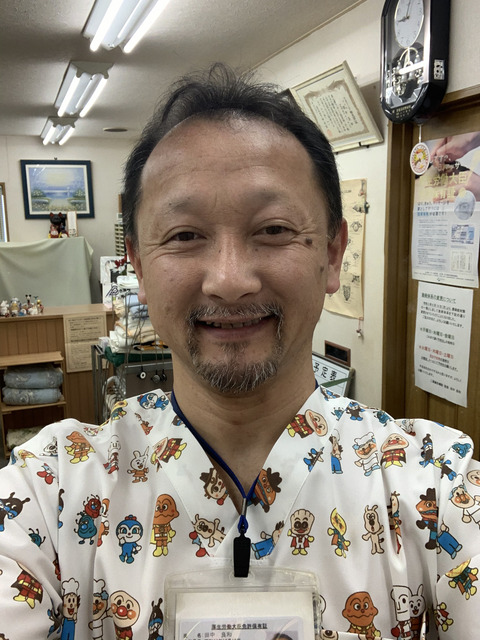

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます