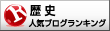「兄貴、そんな得体の知れないものを指で掬って大丈夫なんですかい」
岩徳が心配げな顔つきをしたが、端から見たら悪人面に磨きがかかっただけに見えた。岡っ引きには、悪の道に詳しい前科者がなることも多く、岡っ引きの全てが正義の味方という訳ではなかった。この岩徳は、本当の名前を徳三と言って、本職は神田鎌倉橋で楊枝の職人をしていたが、そのごつい風貌から、誰もが岩の徳三とか、岩徳と呼んでいた。
「無鉄砲なところは、わっちの生まれつきだ。それより、おめえさんに、兄貴なんて言われると鳥肌が立つ。なんか別の言い方はねえもんか?」
「佐々木様と同じように、旦那と呼ぶわけにもいかねえし、困ったな、こりゃ」
「つぶやきも岩徳の好きなように呼ばせてやりゃあいいじゃねえか」
同心の佐々木助次郎が笑った。
「兄貴、も困るが、そのつぶやきっていうのも、なんか嫌な感じでさぁ」
「少なくとも北のご番所ではおめぇの呼び名はそれで通ってるじゃねえか。いやだったらぶつぶつ言う癖を直すのが先決だ」
佐々木は明るく笑ってから、
「ところでおめえ、そんなものの臭いをかいでどうしようってんだ?」
と、不思議そうな顔をした。
岩徳が心配げな顔つきをしたが、端から見たら悪人面に磨きがかかっただけに見えた。岡っ引きには、悪の道に詳しい前科者がなることも多く、岡っ引きの全てが正義の味方という訳ではなかった。この岩徳は、本当の名前を徳三と言って、本職は神田鎌倉橋で楊枝の職人をしていたが、そのごつい風貌から、誰もが岩の徳三とか、岩徳と呼んでいた。
「無鉄砲なところは、わっちの生まれつきだ。それより、おめえさんに、兄貴なんて言われると鳥肌が立つ。なんか別の言い方はねえもんか?」
「佐々木様と同じように、旦那と呼ぶわけにもいかねえし、困ったな、こりゃ」
「つぶやきも岩徳の好きなように呼ばせてやりゃあいいじゃねえか」
同心の佐々木助次郎が笑った。
「兄貴、も困るが、そのつぶやきっていうのも、なんか嫌な感じでさぁ」
「少なくとも北のご番所ではおめぇの呼び名はそれで通ってるじゃねえか。いやだったらぶつぶつ言う癖を直すのが先決だ」
佐々木は明るく笑ってから、
「ところでおめえ、そんなものの臭いをかいでどうしようってんだ?」
と、不思議そうな顔をした。