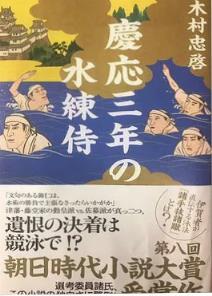先日、岡山県津山市に行った。
この地は洋学が盛んだった地で、宇田川玄随、宇田川玄真、宇田川榕按三代の所縁がある。
個人的には「舎密開宗」を表した宇田川榕按の名前は知っていたが、宇田川三代と言われるとよくわからない。
そこで調べてみました。
宇田川玄随(1755-1797) うだがわーげんずい
津山藩(現岡山県津山市)は、江戸城鍛冶橋門の内側に一万二千坪の拝領敷地を持っていたが、この江戸上屋敷で生まれたのが宇田川玄随である。
もとは漢方医で西洋医学を白い目で見ていたが杉田玄白らと付き合ううちに西洋医学の重要性に気づき、日本最初の西洋内科書『西説内科撰要』(全18巻)を刊行する。
蘭学者の大槻玄沢は、玄随の容姿を「色が白く体は小作り、顔付きは柔和で鼻は顔の釣り合いより大きく、眉は真っすぐ」と書いている。
また、性格については「常に控えめで、争いを好まない物静かな性格だったため、言葉や挙動が穏やかで婦人のようだった」とし、友人は玄随の号の東海を取って、東海婦人と呼んでいたそうです。

宇田川玄真(1770年 - 1835年)うだがわーげんしん
伊勢国(現三重県)の生まれ。
宇田川玄随の知己を得たのち、杉田玄白の養子となり、順風満帆のようにみえたが、養子になった直後から放蕩が始まる。
怒った玄白に離縁され、路頭に迷う暮らしに転落。
心を入れ替えた玄真は、「蘭日辞典」を編纂中の稲村三伯を助け、「ハルマ和解」を完成させる。
この努力が認められ、玄随の養子となる。
「西説内科撰要」を表し、蘭学者としての名声を得る。
その後、蕃書和解御用に命じられ、藩医のかたわら月に8回ほど幕府の仕事をした。
弟子には佐藤信淵、緒方洪庵、川本幸民、箕作阮甫といったそうそうたる顔ぶれがいる。

宇田川榕按(1798年 - 1846年) うだがわーようあん
大垣藩の藩医の息子として江戸にて生まれる。
14歳のとき、玄真の養子となる。
玄随が西洋医学の先駆けとして現れ、玄真が玄随の考えを継ぐ一方、翻訳業にも精を出したのに対し、榕按は植物学と化学に歴史的な足跡を残した人物である。
榕按は、日本で初めての植物学の植物学書である『理学入門植学啓原』(しょくがくけいげん)全3編を書く。
さらに『舎密開宗』(せいみかいそう)は日本の化学史に残る燦然たる実績である。
伊地智昭亘氏によると、榕按が作った言葉としては、
圧力、亜硫酸、塩酸、王水、温度、還元、気化、蟻酸、凝固、希硫酸、金属、金属塩、珪土、結晶、琥珀酸、酢酸、酸、酸化、酸性塩、試薬、煮沸、蓚酸、昇華、蒸気、蒸散、蒸留、親和、水鉛、吹管、青酸、成分、、装置、炭酸、中性塩、中和、潮解、尿酸、白金、物質、沸騰、分析、ほう酸、法則、飽和、溶解、容積、硫化、硫酸、流体、燐酸、るつぼ、濾過
などがあるとされる。
また19歳のとき『哥非乙説」という論文を書いて、コーヒーを紹介している。
珈琲という当て字を作ったのも榕按だとされている。

この地は洋学が盛んだった地で、宇田川玄随、宇田川玄真、宇田川榕按三代の所縁がある。
個人的には「舎密開宗」を表した宇田川榕按の名前は知っていたが、宇田川三代と言われるとよくわからない。
そこで調べてみました。
宇田川玄随(1755-1797) うだがわーげんずい
津山藩(現岡山県津山市)は、江戸城鍛冶橋門の内側に一万二千坪の拝領敷地を持っていたが、この江戸上屋敷で生まれたのが宇田川玄随である。
もとは漢方医で西洋医学を白い目で見ていたが杉田玄白らと付き合ううちに西洋医学の重要性に気づき、日本最初の西洋内科書『西説内科撰要』(全18巻)を刊行する。
蘭学者の大槻玄沢は、玄随の容姿を「色が白く体は小作り、顔付きは柔和で鼻は顔の釣り合いより大きく、眉は真っすぐ」と書いている。
また、性格については「常に控えめで、争いを好まない物静かな性格だったため、言葉や挙動が穏やかで婦人のようだった」とし、友人は玄随の号の東海を取って、東海婦人と呼んでいたそうです。

宇田川玄真(1770年 - 1835年)うだがわーげんしん
伊勢国(現三重県)の生まれ。
宇田川玄随の知己を得たのち、杉田玄白の養子となり、順風満帆のようにみえたが、養子になった直後から放蕩が始まる。
怒った玄白に離縁され、路頭に迷う暮らしに転落。
心を入れ替えた玄真は、「蘭日辞典」を編纂中の稲村三伯を助け、「ハルマ和解」を完成させる。
この努力が認められ、玄随の養子となる。
「西説内科撰要」を表し、蘭学者としての名声を得る。
その後、蕃書和解御用に命じられ、藩医のかたわら月に8回ほど幕府の仕事をした。
弟子には佐藤信淵、緒方洪庵、川本幸民、箕作阮甫といったそうそうたる顔ぶれがいる。

宇田川榕按(1798年 - 1846年) うだがわーようあん
大垣藩の藩医の息子として江戸にて生まれる。
14歳のとき、玄真の養子となる。
玄随が西洋医学の先駆けとして現れ、玄真が玄随の考えを継ぐ一方、翻訳業にも精を出したのに対し、榕按は植物学と化学に歴史的な足跡を残した人物である。
榕按は、日本で初めての植物学の植物学書である『理学入門植学啓原』(しょくがくけいげん)全3編を書く。
さらに『舎密開宗』(せいみかいそう)は日本の化学史に残る燦然たる実績である。
伊地智昭亘氏によると、榕按が作った言葉としては、
圧力、亜硫酸、塩酸、王水、温度、還元、気化、蟻酸、凝固、希硫酸、金属、金属塩、珪土、結晶、琥珀酸、酢酸、酸、酸化、酸性塩、試薬、煮沸、蓚酸、昇華、蒸気、蒸散、蒸留、親和、水鉛、吹管、青酸、成分、、装置、炭酸、中性塩、中和、潮解、尿酸、白金、物質、沸騰、分析、ほう酸、法則、飽和、溶解、容積、硫化、硫酸、流体、燐酸、るつぼ、濾過
などがあるとされる。
また19歳のとき『哥非乙説」という論文を書いて、コーヒーを紹介している。
珈琲という当て字を作ったのも榕按だとされている。