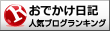雨が降るといえば、臆病に、
家に籠り窓を開ければ、素足に秋の深さが、
足袋をはき、履けば暑くてまた素足。
なんとも、いでたちに面倒な八王子の天気。
明日の予定にテレビの天気予報を
あちこちチャンネルを横目に、
チンチロリンで、決めようと・・。
2度降り、勝ったほうに明日の行き先を。
1度目が勝ったら秩父宝登山、2度目が勝ったら部屋の片づけ。
チンチロリン、
勝ったのは1回目の賽の目、4.5.6で.宝登山に、
買い出しに小走りした日曜日でした。
こんなんでは怒られる、
安中市板鼻の長傳寺。
1861年公武合体のため、
徳川14代将軍・家茂に嫁ぐ、和宮内親王が、
大行列をした中山道、板鼻宿。
上州の7つの宿場で一番賑わったところだという。
宿泊所から5分、和宮が立ち寄ったのは長傳寺。
開山1532年。
1596年現在の場所に移してから、3度の焼失の憂き目に会い、
庫裏は1847年から再建工事を始め、
1856年には彫物師が欄間を彫り始め、
荘厳な庫裏が完成したのは1868年。
1861年和宮が訪れた時、
欄間の彫刻の出来に、眼を光らせていたのが、
上州花輪彫刻の花形だった2代目石原常八・主信。
75歳の時。この2年後、
庫裏の完成を観ずに、77歳の生涯を閉じ、
長傳寺の彫刻が最後の作品となる。
彫物大工の多くの乳呑児は、
仕事が終わるころには、ここで元服し、引き上げた、と。
長傳寺、至る所に彼のまろやかな、鑿の跡が刻まれている。

👇中山道
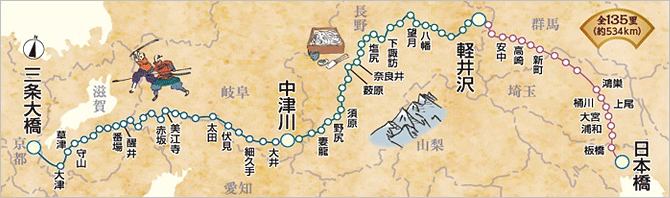





安政4丁巳年正月吉辰
大間正面極彩色欄間
三牧施主
勅使河原源右衛門好昌
彫工
当国勢多郡花輪在
石原常八主信 七十一歳作
金子文五郎宣信
👇
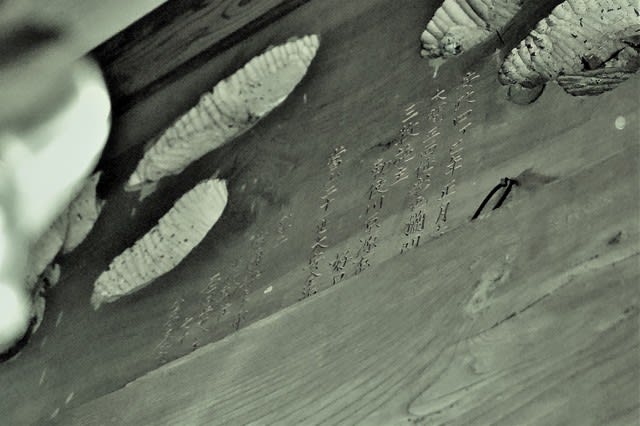



☝ 欄間総数14面
👇 須弥壇



この本堂に入って、彫刻を見ているときが、
いちばん、休まります。
長傳寺の大黒さん。判るような気がしました。


👇 幾度の火災に会って、焼失を免れた山門には、焼け焦げの跡が・・。


写真2018.10.9 安中市