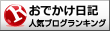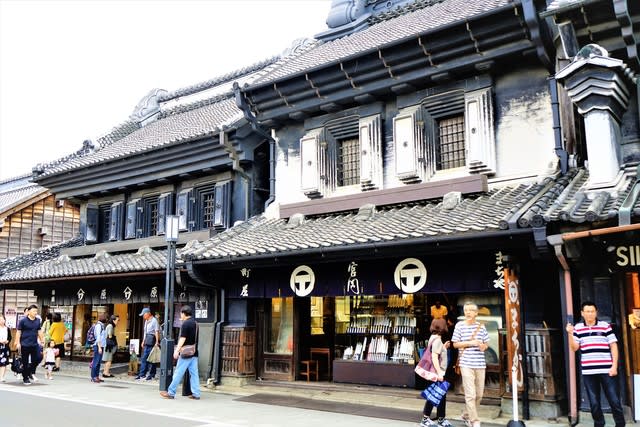☝ https://blogs.yahoo.co.jp/xpointx07からお借りしました。

黙して語らずに嬉しそうに一言、
ヤブカがすごかった。
家の合間、姉も手伝ってくれました。
10月9日、この日で彩色の仕事を終わらせた、
石原一喜さん。
大変だったのは、☝この模様だったと。
成した仕事に奥さんが、云います。
初めての仕事、「心配でした」と、笑顔。
資料の無い上での仕事、塗色の調べは雲をつかむよう!
多くを語ってくださったのが、
お母さん「よくここまで仕上げてくれました」と。
氏子総代が、ぽつり。
氏子の皆さんの、出し合ったお金、
市にも協力してもらいたかった・・・。
安中城の鎮守、熊野神社に459年を経て、
彩色を蘇らせた、塗師、石原一喜さんは、
素木の洗い出しは大切なことでした・・と。
目くるめく思い、
古葉の隙間の射す陽へ、
ふと・・・口角を緩めた姿、
仕事を成し終えた安堵に、
彩色に独自の観念、揺るがず決断した、
彼の姿勢。
高速の窓、安中の黒い山のシルエットに、
拝殿で手を合わせる塗師・石原さんの姿が、
浮かんだ、熊野神社での、出会いでした。


平成の塗師 石原一喜
名称 熊野神社
御祭神 大穴牟遅命、少名毘古那命、櫛御気野命
創建 永禄二年(1559年
所在地 群馬県安中市安中3-689
最寄駅 JR信越本線 安中駅
最寄IC 上信越自動車道 松井田妙義IC、富岡IC