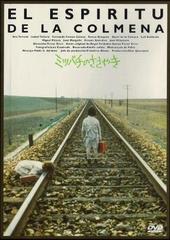
早稲田松竹で、ビクトル・エリセ監督の『ミツバチのささやき』と『エル・スール』が2本立てでやっていたので観てきた。
10年に1本程度しか作らない監督みたい。
その分、重厚で確かに素晴らしい映画だった。
wikipediaで見てみたら、
『1964年、兵役についたのち、溝口健二の『山椒大夫』を見て大きな感銘を受け、除隊後は映画一筋に生きる道を決意する。』
ってあって、驚いた。ミゾグチに影響を受けていたとは。
世界のミゾグチ。
巨匠とされる監督、溝口健二、小津安二郎、黒澤明・・・などなど。見るべき古典の映画は山積みだなぁ。
■『ミツバチのささやき』
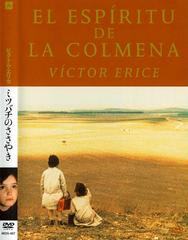
『ミツバチのささやき』の主人公である少女アナは、自我が未分化で、とても危うく揺れ動いている、そんな幼い時期。
時に現実、空想、妄想、嘘・・・の区別が分からなくなる。
その間でゆらめく「自分」という存在に、とても危うく、脆いものを感じる。
そんな未分化な時期に、人の裏切り、人の死、人との約束、人との出会い・・・・・
色んな概念と初めて出会うのだろう。
そして、そういう初めての概念との出会いで、「自分」というものは作られていく。
この映画、そんな誰もが経たはずの未分化で危うい時期を、素晴らしく巧みな映像で表現している。
映像も素晴らしく美しかった。
叙情的で詩的な世界が広がる。
まさに、映画ではないと表現できない世界。
冗長な説明がなく淡々と進むのがよいと思った。
あまり個人的に好きでない映画は、出演者が「映画解説」のようにストーリーを説明しすぎてしまうから、観ていて興ざめしちゃうのです。
ビクトル・エリセ監督の映画は、基本的に観る側の自由な解釈にゆだねられてどんどん進んでいくので、それが自分の好みにとてもあっていた。(もちろん、それはともすれば「自己満足で意味不明な映画」になる危険性もあるので、監督の絶妙なバランス感覚に任されている。)
小さい女の子も演技が上手く、物語にどんどん引きこまれてしまう。
あと、客観的/超越的な視点から撮っているような映像が時に挟み込まれているので、そういう視点の転換がなんとも美しいのだと思った。
■『エル・スール』
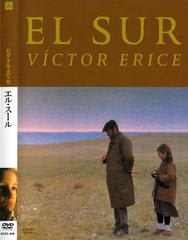
この映画は、スペイン内戦時代の政治的な複雑な背景を持つ映画なんだと思う。
でも、映画の中では複雑なことはほのかに匂わせるだけで前面に押し出してこない。見終わった後に「そうだったんだのかもな」と回想させるだけに留めている。
そして、登場してくる子供も、もちろんそんなに難しく複雑な事情は分からないだろし、そういう子供のイノセントな視点で、映画はどんどん進んでいく。
複雑な時代背景の中では、人々も複雑な背景をもっていて、その上で、人々は淡々と生活している。
でも、その時代が根っこに持つ「複雑さ」が、人間の「わからなさ」をどんどん際立たせていく。
主人公のエストレリャは、子供のときに自分の父親の「わからなさ」に初めて気づく。
自分の肉親である父親が、一番近い存在である父親がとてつもなく大きな「わからなさ」を抱えている人であることに、ある時気づく。
そして、今まで気づいてなかった自分に気づき、そんな自分自体にも驚く。
「わからない」ものを「わかる」ために、子供特有の「わからない」意味不明な行動をとることもある。
色々な手段を駆使して、なんとか「わからなさ」を「わかろう」としてみる。
ただ、結局実の父親は、なんだか「わからない」。
「わからない」ものは「わからない」まま、謎は謎のまま残る。
僕らのように映画を観ている側も、娘エストレリャからと同じ目線になり、「わからない」父アグスティンをなんとか「わかろう」と思い、そういう目線の高さにドンドン引っ張り込まれていくのです。
映画の背景に、当時の時代の暗く憂鬱な気分が強い影を落としている。
内戦や戦争で国中をかき乱されたせいなのか、スペイン人が根っこに抱える暗さ、哀しみ、やるせなさ・・・・。
そんな得も言われぬ感情が、映画から伝わってくる。
最後も、すごく余韻が残る。
夕陽と共に川のシーン。
そこは音とともにとても衝撃な場面のはずだけど、映画の中では「まるで何もなかったかのように」あっという間に、その場面は過ぎ去っていく。
■圧倒的な日常の流れ
ふと思う。
日常、その中で得る膨大な記憶。
日々はとても膨大な情報にあふれているけれど、日々は圧倒的な速さで、つむじ風のように通り過ぎていく。
誰もが、いろんな衝撃的な出来事に出会うことがある。
誰にも言えないような重い体験を抱えながら、そんなことを感じもさせずに日常を淡々と生きている(ように見える)人が、実は大勢いるのだろう。
映画を観ていて、そんな「かなしさ」のようなものを感じた。
「楽しさ」のような「光」ではなく、「かなしさ」のような「影」の体験。
日常はあっという間に、水の流れのようにどんどん流れていくものだ。
「光」も「影」も、衝撃的な出来事は人を固定化しようとするけれど、時間の針はそこで止まろうとするのだけど、それに対して圧倒的な日常はどんどんと流れて行く。
自分は止まろうとも、自分の足元を支える日常はどんどん流れ、変化していく。
そんな圧倒的な日常の流れがあるおかげで、誰かの止まってしまった時計の針も、いづれ勝手に動き始めるものなのかもしれない。
ありふれた日常がつくる圧倒的で超越的な時間の流れ。
その流れは、僕らが固定化しようとするいろんなものも液状化してドロドロ溶かして、日々更新されていくのだろう。
そうして、日々を生きているのだろう。
■「わからない」ことを抱えて
「わからない」ことに出会うと、「わかりたい」と思う。
でも、「わからない」ものは「わからない」ままに過ぎ去っていくことが圧倒的に多い。
無理やりに「わかった」気になったことは、ただの錯覚や思い込みであったり、自分に嘘をついているだけのことが多い。
「わかる」ことよりも、膨大な「わからない」ことを抱えながら、僕らは何食わぬ顔で、日常を生きている。
だからこそ、時に出会う「わかる」瞬間は、僕らの中に稲妻のように電流を走らせ、その人の深い場所を豊かにしてくれるのだろう。
圧倒的な「わからなさ」こそが、結果として日常に無限の彩りを与えている。
映画内容とは少しズレルかもしれないけど、映画『エルスール』に底流として流れ続けている、父親の「わからなさ」から、ふと頭に浮かんだ。(頭に浮かぶのは数秒なのに、文字にするとこんなにも量が必要となる!)
・・・・・・・・・
「ビクトル・エリセ DVD-BOX - 挑戦/ミツバチのささやき/エル・スール」もあるみたいだけど、普通のところではきっと貸出はしてない。
早稲田松竹でも11/13までであっという間に終わっちゃう。
やっぱり早稲田松竹は2本立てだしお得。
大学生時代に時々ここに見にきていたの思い出す。
ビバ、高田馬場。
このビクトル・エリセ監督は、映画好きにファンが多いコアな監督だからだろうけど、土曜は満員御礼で驚いた。(ちょうど早稲田祭もやってたからかもしれないけど。)
一気に2本見るのは疲れるものではありますが、早稲田松竹はイイ映画が多いし、安いし、最高デスね。
(期せずして、我ながら最近映画の投稿が多いなぁ。)
10年に1本程度しか作らない監督みたい。
その分、重厚で確かに素晴らしい映画だった。
wikipediaで見てみたら、
『1964年、兵役についたのち、溝口健二の『山椒大夫』を見て大きな感銘を受け、除隊後は映画一筋に生きる道を決意する。』
ってあって、驚いた。ミゾグチに影響を受けていたとは。
世界のミゾグチ。
巨匠とされる監督、溝口健二、小津安二郎、黒澤明・・・などなど。見るべき古典の映画は山積みだなぁ。
■『ミツバチのささやき』
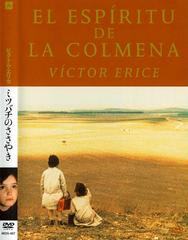
『ミツバチのささやき』の主人公である少女アナは、自我が未分化で、とても危うく揺れ動いている、そんな幼い時期。
時に現実、空想、妄想、嘘・・・の区別が分からなくなる。
その間でゆらめく「自分」という存在に、とても危うく、脆いものを感じる。
そんな未分化な時期に、人の裏切り、人の死、人との約束、人との出会い・・・・・
色んな概念と初めて出会うのだろう。
そして、そういう初めての概念との出会いで、「自分」というものは作られていく。
この映画、そんな誰もが経たはずの未分化で危うい時期を、素晴らしく巧みな映像で表現している。
映像も素晴らしく美しかった。
叙情的で詩的な世界が広がる。
まさに、映画ではないと表現できない世界。
冗長な説明がなく淡々と進むのがよいと思った。
あまり個人的に好きでない映画は、出演者が「映画解説」のようにストーリーを説明しすぎてしまうから、観ていて興ざめしちゃうのです。
ビクトル・エリセ監督の映画は、基本的に観る側の自由な解釈にゆだねられてどんどん進んでいくので、それが自分の好みにとてもあっていた。(もちろん、それはともすれば「自己満足で意味不明な映画」になる危険性もあるので、監督の絶妙なバランス感覚に任されている。)
小さい女の子も演技が上手く、物語にどんどん引きこまれてしまう。
あと、客観的/超越的な視点から撮っているような映像が時に挟み込まれているので、そういう視点の転換がなんとも美しいのだと思った。
■『エル・スール』
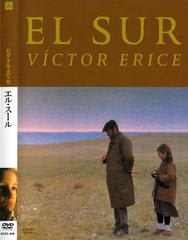
この映画は、スペイン内戦時代の政治的な複雑な背景を持つ映画なんだと思う。
でも、映画の中では複雑なことはほのかに匂わせるだけで前面に押し出してこない。見終わった後に「そうだったんだのかもな」と回想させるだけに留めている。
そして、登場してくる子供も、もちろんそんなに難しく複雑な事情は分からないだろし、そういう子供のイノセントな視点で、映画はどんどん進んでいく。
複雑な時代背景の中では、人々も複雑な背景をもっていて、その上で、人々は淡々と生活している。
でも、その時代が根っこに持つ「複雑さ」が、人間の「わからなさ」をどんどん際立たせていく。
主人公のエストレリャは、子供のときに自分の父親の「わからなさ」に初めて気づく。
自分の肉親である父親が、一番近い存在である父親がとてつもなく大きな「わからなさ」を抱えている人であることに、ある時気づく。
そして、今まで気づいてなかった自分に気づき、そんな自分自体にも驚く。
「わからない」ものを「わかる」ために、子供特有の「わからない」意味不明な行動をとることもある。
色々な手段を駆使して、なんとか「わからなさ」を「わかろう」としてみる。
ただ、結局実の父親は、なんだか「わからない」。
「わからない」ものは「わからない」まま、謎は謎のまま残る。
僕らのように映画を観ている側も、娘エストレリャからと同じ目線になり、「わからない」父アグスティンをなんとか「わかろう」と思い、そういう目線の高さにドンドン引っ張り込まれていくのです。
映画の背景に、当時の時代の暗く憂鬱な気分が強い影を落としている。
内戦や戦争で国中をかき乱されたせいなのか、スペイン人が根っこに抱える暗さ、哀しみ、やるせなさ・・・・。
そんな得も言われぬ感情が、映画から伝わってくる。
最後も、すごく余韻が残る。
夕陽と共に川のシーン。
そこは音とともにとても衝撃な場面のはずだけど、映画の中では「まるで何もなかったかのように」あっという間に、その場面は過ぎ去っていく。
■圧倒的な日常の流れ
ふと思う。
日常、その中で得る膨大な記憶。
日々はとても膨大な情報にあふれているけれど、日々は圧倒的な速さで、つむじ風のように通り過ぎていく。
誰もが、いろんな衝撃的な出来事に出会うことがある。
誰にも言えないような重い体験を抱えながら、そんなことを感じもさせずに日常を淡々と生きている(ように見える)人が、実は大勢いるのだろう。
映画を観ていて、そんな「かなしさ」のようなものを感じた。
「楽しさ」のような「光」ではなく、「かなしさ」のような「影」の体験。
日常はあっという間に、水の流れのようにどんどん流れていくものだ。
「光」も「影」も、衝撃的な出来事は人を固定化しようとするけれど、時間の針はそこで止まろうとするのだけど、それに対して圧倒的な日常はどんどんと流れて行く。
自分は止まろうとも、自分の足元を支える日常はどんどん流れ、変化していく。
そんな圧倒的な日常の流れがあるおかげで、誰かの止まってしまった時計の針も、いづれ勝手に動き始めるものなのかもしれない。
ありふれた日常がつくる圧倒的で超越的な時間の流れ。
その流れは、僕らが固定化しようとするいろんなものも液状化してドロドロ溶かして、日々更新されていくのだろう。
そうして、日々を生きているのだろう。
■「わからない」ことを抱えて
「わからない」ことに出会うと、「わかりたい」と思う。
でも、「わからない」ものは「わからない」ままに過ぎ去っていくことが圧倒的に多い。
無理やりに「わかった」気になったことは、ただの錯覚や思い込みであったり、自分に嘘をついているだけのことが多い。
「わかる」ことよりも、膨大な「わからない」ことを抱えながら、僕らは何食わぬ顔で、日常を生きている。
だからこそ、時に出会う「わかる」瞬間は、僕らの中に稲妻のように電流を走らせ、その人の深い場所を豊かにしてくれるのだろう。
圧倒的な「わからなさ」こそが、結果として日常に無限の彩りを与えている。
映画内容とは少しズレルかもしれないけど、映画『エルスール』に底流として流れ続けている、父親の「わからなさ」から、ふと頭に浮かんだ。(頭に浮かぶのは数秒なのに、文字にするとこんなにも量が必要となる!)
・・・・・・・・・
「ビクトル・エリセ DVD-BOX - 挑戦/ミツバチのささやき/エル・スール」もあるみたいだけど、普通のところではきっと貸出はしてない。
早稲田松竹でも11/13までであっという間に終わっちゃう。
やっぱり早稲田松竹は2本立てだしお得。
大学生時代に時々ここに見にきていたの思い出す。
ビバ、高田馬場。
このビクトル・エリセ監督は、映画好きにファンが多いコアな監督だからだろうけど、土曜は満員御礼で驚いた。(ちょうど早稲田祭もやってたからかもしれないけど。)
一気に2本見るのは疲れるものではありますが、早稲田松竹はイイ映画が多いし、安いし、最高デスね。
(期せずして、我ながら最近映画の投稿が多いなぁ。)










私も早稲田松竹にはお世話になっています。
エリセの二本立ても松竹で観て、その日にDVDボックスを注文してしまいました!彼の映画は時間の使い方や色の質感が大好きです。
同監督の「マルメロの陽光」もおすすめです。
スペインの画家が庭のマルメロの木を季節をまたいで描いていくのを、それと同じ時間をかけてじっくりフィルムにおとしていく映画です。こういうムービーがあっていいんだな、と静かに感激してしまいました。
「エルスール」の元となったのは、エリセの当時の妻のアデライダ・ガルシア=モラレスの中編小説で、これはまた映画とすこし語り口が違って、少女の独白のスタイルをとったミステリアスな物語でよかったです。とっても「印象的」でした。これもおすすめです!
ちなみに私のエル・スール(南)は九州熊本です。父が熊本出身ですから笑。
このブログでは、はじめましてですね。
早稲田松竹、いいですよね。
早稲田松竹を見に行くときは、いつも時間ぎりぎりで走りこんで見てますが、あのこじんまりした規模の大きさが、ローカルな映画館っぽくてなんともいい感じ。
2本立てだと、2本見ないと損な気がしますけど、さすがに土日とかじゃないと連続してみるのは難しくて。
早稲田松竹では、12月には溝口健二、年末には、フランソワ・トリュフォー監督の映画もありますよね。時間あれば行きたいなー。
ところで、エリセ監督の二本立て。早稲田松竹に来られてたんですね。やはりセンサーがある人は集うのですね。早稲田松竹は、人気ある映画、土日行くとほんと満員になっちゃいますし。
それと、エリセ監督のDVDボックス!買ったんですね!うらやましいな。ぼくもケチらずに買おうかなぁ。財産というか、宝になりますよね。食べ物なんて消えてなくなるけど、DVDボックスはそこに残る(当たり前)。
映画監督だと、テオ・アンゲロプロス全集のDVD-BOXとか(村上春樹も好きだって言ってたし)、アンドレイ・タルコフスキー(惑星ソラリス、サクリファイス、ノスタルジア・・・)、カネフスキー(動くな、死ね、甦れ!、ひとりで生きる。 タルコフスキー、カネフスキーの二人はなんだか名前が似ている。)・・・・・
話題としては聞くものの、その辺のレンタルビデオ屋に置いてないのが多くて。(渋谷のツタヤみたいな巨大なところにはあるのかな) 見て見たいのはいっぱいあるんです。
でも、自分の部屋が、本で底が抜けるんじゃないかとヒヤヒヤしてるもので、DVDもCDも少しセーブしてます。
本よりは軽いですけど。まあ、せっかく稼いだお金はそういうのに使おうとは常々思ってはいるのですが。
あと、全然違うので思い出したのですが、このDVDボックスも2年くらい迷ってる商品。笑
「日本 その心とかたち」 加藤周一 [DVDボックス] 定価41790円!
映画館に行くたびにブースがあって売ってある、日本の国宝美術シリーズのDVDも、いつも心ひかれるし。
あ、脱線しました。
>>>>>>>>>>
彼の映画は時間の使い方や色の質感が大好きです。
>>>>>>>>>>
ぼくもそういうところが好きですね。
あのくすんだ色とか、なんとも言えませんよね。時間を感じさせる色って、なかなか難しいものです。
監督の世界観というか、センスというか、そういうものと波長が合うかどうかって大きいですよね。
ほんとにすごい人は、どんな人を包み込む多層の波長を持っているのでしょうし。
「マルメロの陽光」、観た事ないです。
あらすじ聞くと、不思議な映画ですね。やはり、「時間」っていうのは彼エリセ監督の映画の中で大事な要素なのでしょう。
たしかに、ぼくらは映画を見るとき、ほんの2時間くらいで終わっちゃいますが、それまでに膨大なフィルムから抽出しているわけで、そしてフィルムに入っていない色んな構想や思索の段階があるわけで。
巨大な時間の中の、あるささやかな2時間が映画。
そういう作業をしている人間にとって、「時間」っていうのは切っても切り離せない根源的なテーマなのでしょう。
それこそ、「マルメロの陽光」も早稲田松竹でやってくれないかなぁ。
「エルスール」の元となった小説の件。
これ、店頭で売ってありましたね。
というか、その本を友人から借りたのに、そのままになってる気が!
早く読んで返さないとー。思い出しました。ありがとうございます。
ちょうどいいタイミングなので、本のほうも読んでみます。
ところで、お父様は九州熊本なのですね。同郷っていうのはうれしい。
熊本、いいとこですよ。食事も水も野菜もうまい。自然もありますし、川と緑が多い、洗練されたとてもいい場所です。是非遊びに行ってみてください。
そう言われて思い出しましたが、僕が学生時代に習っていたフラメンコの教室が、まさしく<エル・スール>でした!なんか聞いたことある名前だと思ったんですよねー。
野村眞里子先生、お元気かなぁ。
DVDボックスは高いですね…。私もAmazonのカートに入れっぱなしにして日々拝んでいます笑。でもエリセだけは買ってしまいました。
加藤周一「日本その心とかたち」、知りませんでした。かなり充実した内容みたいですね。文化財に対する惹かれ方や情熱が素敵だとおもえる批評家さんに出会えたなら、お金をはたいても追いかけたいものですが、やっぱり高いですね…いろいろ高いです笑。
フラメンコ習われていたんですね!すごい!わたしはロマのおばちゃんが躍るような元祖の土着的な力強さと、バレエやコンテンポラリーダンスの要素がうまく融合したあたりのフラメンコが大好きです。
エリセの確か映画学校の同期だったカルロス・サウラという監督は、フラメンコを非常に魅力的に撮るひとで、一時ほんとうに心酔しました。稽古場の写真撮影に興味をもったのも彼の影響が大きいです。機会があればぜひチェックしてみてください!!
九州へは大学1年の春休みにバックパック旅行しました。青春18きっぷで22時間かけて門司についたので、「とんでもなく遠くに来てしまった!もう帰れない」と思ったことを覚えています笑。おじいちゃんに「いえでしたとー?」なんて聞かれたりして。ほんとうにいいところですね、人も自然も。
たしかに、早稲田松竹は意外に同じ日に見てる可能性あります。あそこ意外に小さいですし。
僕は大学時代にときどき行ってたんで、10年前くらいですが、当時はもっとくだらない映画多かった気が。
何も得るものも、失うものもない、単なる時間つぶしのような映画が多かったような。まあ、単に自分が映画に対して感受性が開かれてなかっただけかも、とも思います。
加藤周一「日本その心とかたち」、すごい面白そうじゃありませんか?
この本のバージョンもなかなか素晴らしくて、よく大学生協の本屋で立ち読みして、(もう結構読んでしまいましたが)いづれ買おうと思いつつ。
あと、お金の件もさることながら、東京一人暮らしだと部屋に限界があるので、そういう空間の物理的問題であきらめることも多い。とか言いつつ、古本屋に行くと、かならず最低一冊は何かを握りしめますが。
フラメンコ習ってたのです。いまでもときどき再開したいと思いますよ。あのカスタネット打つのがあまり上達しなかった気が。足のステップとか全体的な振り付けはすぐ覚えれるんですけど。フラメンコはリズムが独特なので、それが体にしみこむのに時間がかかった気が。
カルロス・サウラのフラメンコ映画の「イベリア」とか、DVDでかって持ってますよ。アントニオ・カナーレス出てるんですよね。彼の踊りも生で見に来ました。学生時代には値段が高くて、そのことくらいしか覚えてません。笑
僕も、そういう大きい舞台で見るフラメンコより、スペインに旅行した時に見た、その辺のBarとかで地元のおじさんおばさんとかが歌って踊りだすフラメンコ(日本の盆踊り?)に感動したのです。あの生活に密着した踊りに感銘を受けて、習いはじめました。
おじいちゃんに「いえでしたとー?」っていう方言は、なんとなく懐かしかです。郷愁誘われます。
『・・・したと?』っていう疑問形は、熊本ではかなり多用しますので。僕もいまだに熊本弁が抜け切れてないうえに、標準語と混ざってしまっているので、東京でも熊本でも現地の人に違和感を感じられてしまいます。異邦人です。
フラメンコはステップが難しそうですね。わたしはサウラの「サロメ」を観て電気が走りました。
大学の二外もスペイン語で、文法は忘れても(笑)スペインにはどうも惹かれてしまいます。わたしも旅行で5日くらい滞在できたんですが、マドリーのカフェでおばあちゃんと相席したり、深夜こわごわ映画を観に行ったり、バルをはしごしたりして、ほんとうに良かったです。
フラメンコは、ぴょんぴょん跳ねるバレエとちがって大地に大地に向かう踊りですよね。いちどお話ししたあるダンサーは阿波踊りもできちゃう方でしたが、「腰の落とし方が似てるのよ」とおっしゃるのを聞いて、なるほどと思いました。生活や土着の祭事にかかわるような舞は、そういうものなのかも。
はあ、ごめんなさい、どこで終わりにしたらいいか分かりませんね笑。興味深くブログ拝読しています。「ゴクゴク」という感じです。あたまを柔らかくしながらしっかり勉強になります。
親戚とかって、包み隠さず思ったことをそのまま言うからつらいと同時に貴重な存在ですよね。笑
悪意もないし、あっはっはで笑って終われる雰囲気があって。本音と建て前と言いますけど、やはりこのバランスは、人とどの程度の関係かで全然変わってくるもので。
ただ、個人的には、【真・善・美】に関してだけは、僕は建前を言いたくないと思っていて、人の講演や舞台などを見に行ったときに何の感動もないと、「とても良かったよー」ってお世辞が言えないので、困ることがあります。そういうとき、たいてい沈黙してますが。笑
確かに、言われて気づきましたが、フラメンコは下につながる感じですね。ステップもどんどんと足を地球にたたきつけて、深く沈んでいく感じ。フワフワと空には向かいません。音自体も、地響きのようにその場を振動させ、その人自体も振動させる感じ。
「土地と切れていない」ということが大事なのかもと思いました。悪く言えばローカルで局地的なものになりうるのでしょうが、よく言えばその土地の記憶や時間と結びついているので、切れていないだけに、その土地に住んでいる人を「つなげる」効果がある気がします(これはつい最近ブログに書いたトピック)。
フラメンコは、何か日本の土地と切れていないつながっている実感を感じさせてくれるのかもしれませんね。しかも、あの踊りは流浪のジプシーなどが踊っていたもので、その根底にはつよい「かなしみ」が流れているような、そんな溢れんばかりの感情を受け取るのです。
なんか、フラメンコ論になってきました。笑
最近は生フラメンコを見てないから、みたいなー。新宿の伊勢丹会館6階のエル フラメンコとかで、ご飯食べながらフラメンコ見れるのをやってるんですよね(学生のときは値段高めだと感じてましたけど)。昔自分も踊ってた時はよく見に行ってました。
フラメンコの踊りの体の動かし方は、今やっているフリークライミングにもなんとなく応用が効いてるような気もしてます。