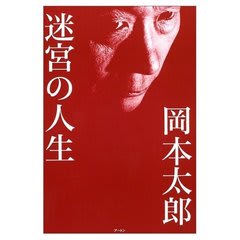
■自分の源流・芯・核・軸・根
岡本太郎がかなり好きだ。
自分が精神的に辛かったりした時期に、なんとなく自分の組成を考えてみたことがあった。
組成のコア部分には、「自分はどんなモノ・感覚を大切にしているのか。何が好きなのか」がある。
■岡本太郎 手塚治虫
家族以外で、自分の源流、芯、核、軸、根っこ・・・に近いところにある人を考えてみた。
強烈な磁場を感じた人。強烈な「出会い」をした人。
そうして考えていたら、自分の核のすぐ近くには岡本太郎と手塚治虫がいるのが分かった。
挫折や失敗は人を成長させるというが、それは自分の核や組成物質を考え直すきっかけだからなのだと思う。
別に、彼らになりたいとか、彼らの真似をして生きていきたい、とかではなく。
ある種の光。敬意と憧れのまなざしで見る北極星のような定点の存在。
勿論、他にも無数の色々な人に影響を受けた。今後も影響を受けるだろう。
別に著名人でなくても影響を受ける人は無数にいる。
そういう無限の出会いの繰り返しの果てに、結果として偶然に自分というのは作り上がると思う。
■信頼できる大人としての岡本太郎
岡本太郎の最初の印象は『芸術は爆発だ!』と目の玉をひんむいて睨んでいる印象がある。
変な人だ、と思ったと同時に、正直で、生身で、丸裸で、それでいて何かを僕らに必死で伝えようとしている人だとも思った。そのことは伝わった。本気の人だ、と。
自分が子供だったとき、「大人」や「言葉」をあまり信じていなかった。
なぜなら「大人」は世間体を重視して嘘ばっかりついているように思えたし、「言葉」も真実のコトバよりも嘘のコトバばかりが氾濫していたように思えたから。
だからこそ「大人」と「言葉」が結びついた「大人の言葉」は、相当に胡散臭いものだと思っていた。(今でもある程度は思っている)
言語世界よりも、自然とか、風景とか、絵とか、造形とか、踊りとか、態度とか、眼差しとか、思いとか・・・そういう非言語的な世界から感じとることを重視していた。
そんな中で、岡本太郎は無条件に信頼できる人だった。
岡本太郎のまっすぐで純粋な曇りない姿勢。揺るぎない高次元の存在。岡本太郎の発言や態度や生き様には、嘘や欺瞞がないと思った。
■「迷宮の人生」より
岡本太郎の「迷宮の人生」から、印象的だった言葉をご紹介します。
もし岡本太郎の言葉から興味を持ったら、是非絵の世界も感じてもらいたい。
画集では「歓喜」という本が自分は好きです。
「人生、即、迷宮」という哲学。
これは人間論でもあり、生命論でもあり、宇宙論のようにも読める。
-------------------------------
岡本太郎「迷宮の人生」より
-------------------------------
P7
なぜわれわれは「迷宮」というテーマに惹かれるのか。
それはまさにわれわれが現実に、迷宮のなかに生き、耐えて、さまざまな壁にぶつかりながら、さまよっているからだ。
事実、人生、運命について見通せるものは何もない。
瞬間瞬間、進む道に疑問を不安を抱き、夢と現実がぶつかりあっている。
強烈に生きようと決意すればするほど、迷宮は渦を巻くのだ。
それは日常の痛切な実感ではないか。
迷宮の中で期待と絶望にふり回されるのは、人間だけだ。
動物は本能的に迷路を潜り抜けてしまうが、人間は意識によって、たとえ何でもないところでも出口を失い、迷う。
夢と絶望、それはいくつもいくつも重なりあって、瞬間瞬間にひらけ、また閉じ込められる。
解決したと思ったとたんに新しい混迷のなかに閉ざされる。
矛盾のなかを、手さぐりで進んでいる。
まさしくそれが人生だ。
-------------------------------
-------------------------------
P13
迷宮のなかでは不思議な時間・空間が迫り、動揺する。
そこに恐怖感、絶望感、希望がからみあう。
時空の無限のひろがり。
それはまた、強烈な幻想だからこそ、暗くそして明るい。
この動と静。相反し対立する渦。
まさにラビリンスは人間生活の運命そのものだ。
-------------------------------
-------------------------------
P14
迷宮は常に静と動のなかに振動している。
それは人間の心の動揺からである。
確かにラビリンスは不動であり、静止しているかのようだが、また無限に転動しているのである。
静動一体、時空の矛盾したからみあい
-そこに無限にひらく夢と恐怖。
迷宮・即・人間の運命。
-------------------------------
-------------------------------
P84
自分の心のうちにある迷宮のなかを、熱情をもって彷徨ってゆけばよいのだ。
嬉しさと不安感をまじえながら夢幻の世界を創造し、ひらいてゆく。
-------------------------------
-------------------------------
P96
ケルトの「組紐文」も「縄文」にひどく似ている。
無限にからみあい、回転してゆく。
私はかつて、『美の呪力』でこのように書いた。

**************
『組紐文は(キリスト的とは)まさに正反対の世界観だ。
中心というものがない。無限にのび、くぐり抜けてひろがる。
世界を流動の相で捉える人々の造形だ。
たった一人、一つのものが中心だとか力を持つなどという、こだわった権力意志ではない。
自分たちを超えた運命がいつでもすれ違いながら流れて行く。
それがどこに行くか、はじまりもなければ終わりもない。
とすれば、あらゆるポイントがはじまりであり終わりである。
だからどんな部分も、絶対感をもって宇宙に対する。価値でもなければ無価値でもない。
無限に時空のなかに、みえてゆくエネルギーであり、意志だ。』
**************
これがラビリンスだと私は直感する。
それは運命感であり、宇宙観なのである。
無条件で人間の夢をひらいた軌跡だから、そこには始まり、終わり、決められた形というものではなく、
始まりは終わり、終わりは始まり、無限だ。
つまり永遠の循環。
縄文やケルトの組紐文を見てそこに私が迷宮を幻想するのは、
形が、いわゆる迷宮のイメージに似ているというのではなくて、
そこに表出される世界観、運命観が迷宮のなかに生きているからだ。
そして私は自分の運命がそのまま、そこに反映して、命がそこにからみあうような、自分と一体の思いがする。
キリキリ回っている、くぐり抜けくぐり抜けしていく線、そのいきかたそのもの。
-------------------------------
-------------------------------
P103
迷宮の出口を出るということは、つまりは人生を退いてしまうのだ。
それは死ぬことではない。
死でもなく、生でもない、真の生命感を失った無意味の存在になってしまうことだ。
死と生がからみあっているところに生命の情感、迷宮の神秘があるのだ。
人間はみな、それぞれラビリンスを創造しているのだ。
数十億の人間がこの世にいるならば、数十億のラビリンスがある。
-------------------------------
-------------------------------
P111
(岡本敏子さんの後書き)
岡本敏子「迷宮をゆく太郎」
『太郎さんは、ふだんは快活でやんちゃで、ユーモア好きの、陽性の人だったし、
スパッと筋を通して論理的でもある。およそ迷宮らしくない人だった。
深刻そうな、重苦しい気配は嫌いなのだ。
だがその裏側に、もう一つの極に、デリケートで神経質、くちゃくちゃした、とことんこだわる性癖が隠れていた。
くねくねと執拗にくねって、無限に渦巻いてゆくケルト文様のような、ひだの深い情熱、混沌がひそんでいる。
迷宮に住む怪物にふさわしい人だった。』
-------------------------------
P123
『岡本太郎が好きで勇気をもらっている人たちは、
「岡本太郎」という個性が最初から天性のものとしてあったように思っているようだ。
そしてその強さに憧れたり、とてもあんな風にはなれないと悩んだりしている。
私はそういう人に言いたい。
「岡本太郎は、最初から岡本太郎だった訳ではないのよ。彼は岡本太郎になったの。」
自分で決意して、覚悟を決めて、そうなり、それを貫いたのだ。
転生強い人とか、聡明な人、才能のある人、そんなのは何でもない。
そういうものはいつでもぐらぐらするし、破れる。
才能のある人は才能によってつまずくし、聡明な人は自分の馬鹿に気がつかない。
だが岡本太郎は最初から、まったく捨て身、自分を投げ出したところから出発した。
だから彼は恐れない。
強くてこんなことをやっていたのなら、ただの豪傑だ。おめでたい愚者だ。
だが彼はそうではない。
痛がりやで、繊細極まる神経の持ち主で、しかもいろんなことが見えてしまうたちだ。
それがこれを貫きとおしたということが凄い。
だから力なのだ。人に迫るのだ。』
-------------------------------
興味が湧いた人は、青山の表参道の裏道にある彼の旧アトリエ「岡本太郎記念館」や、小田急線の向ヶ丘遊園が最寄り駅の「川崎市岡本太郎美術館」に足を運んでみてくださいね。
そのときは、僕も誘ってください。
岡本敏子さんの発言が素晴らしいですね。
「岡本太郎は、最初から岡本太郎だった訳ではないのよ。
彼は岡本太郎になったの。」
岡本太郎がかなり好きだ。
自分が精神的に辛かったりした時期に、なんとなく自分の組成を考えてみたことがあった。
組成のコア部分には、「自分はどんなモノ・感覚を大切にしているのか。何が好きなのか」がある。
■岡本太郎 手塚治虫
家族以外で、自分の源流、芯、核、軸、根っこ・・・に近いところにある人を考えてみた。
強烈な磁場を感じた人。強烈な「出会い」をした人。
そうして考えていたら、自分の核のすぐ近くには岡本太郎と手塚治虫がいるのが分かった。
挫折や失敗は人を成長させるというが、それは自分の核や組成物質を考え直すきっかけだからなのだと思う。
別に、彼らになりたいとか、彼らの真似をして生きていきたい、とかではなく。
ある種の光。敬意と憧れのまなざしで見る北極星のような定点の存在。
勿論、他にも無数の色々な人に影響を受けた。今後も影響を受けるだろう。
別に著名人でなくても影響を受ける人は無数にいる。
そういう無限の出会いの繰り返しの果てに、結果として偶然に自分というのは作り上がると思う。
■信頼できる大人としての岡本太郎
岡本太郎の最初の印象は『芸術は爆発だ!』と目の玉をひんむいて睨んでいる印象がある。
変な人だ、と思ったと同時に、正直で、生身で、丸裸で、それでいて何かを僕らに必死で伝えようとしている人だとも思った。そのことは伝わった。本気の人だ、と。
自分が子供だったとき、「大人」や「言葉」をあまり信じていなかった。
なぜなら「大人」は世間体を重視して嘘ばっかりついているように思えたし、「言葉」も真実のコトバよりも嘘のコトバばかりが氾濫していたように思えたから。
だからこそ「大人」と「言葉」が結びついた「大人の言葉」は、相当に胡散臭いものだと思っていた。(今でもある程度は思っている)
言語世界よりも、自然とか、風景とか、絵とか、造形とか、踊りとか、態度とか、眼差しとか、思いとか・・・そういう非言語的な世界から感じとることを重視していた。
そんな中で、岡本太郎は無条件に信頼できる人だった。
岡本太郎のまっすぐで純粋な曇りない姿勢。揺るぎない高次元の存在。岡本太郎の発言や態度や生き様には、嘘や欺瞞がないと思った。
■「迷宮の人生」より
岡本太郎の「迷宮の人生」から、印象的だった言葉をご紹介します。
もし岡本太郎の言葉から興味を持ったら、是非絵の世界も感じてもらいたい。
画集では「歓喜」という本が自分は好きです。
「人生、即、迷宮」という哲学。
これは人間論でもあり、生命論でもあり、宇宙論のようにも読める。
-------------------------------
岡本太郎「迷宮の人生」より
-------------------------------
P7
なぜわれわれは「迷宮」というテーマに惹かれるのか。
それはまさにわれわれが現実に、迷宮のなかに生き、耐えて、さまざまな壁にぶつかりながら、さまよっているからだ。
事実、人生、運命について見通せるものは何もない。
瞬間瞬間、進む道に疑問を不安を抱き、夢と現実がぶつかりあっている。
強烈に生きようと決意すればするほど、迷宮は渦を巻くのだ。
それは日常の痛切な実感ではないか。
迷宮の中で期待と絶望にふり回されるのは、人間だけだ。
動物は本能的に迷路を潜り抜けてしまうが、人間は意識によって、たとえ何でもないところでも出口を失い、迷う。
夢と絶望、それはいくつもいくつも重なりあって、瞬間瞬間にひらけ、また閉じ込められる。
解決したと思ったとたんに新しい混迷のなかに閉ざされる。
矛盾のなかを、手さぐりで進んでいる。
まさしくそれが人生だ。
-------------------------------
-------------------------------
P13
迷宮のなかでは不思議な時間・空間が迫り、動揺する。
そこに恐怖感、絶望感、希望がからみあう。
時空の無限のひろがり。
それはまた、強烈な幻想だからこそ、暗くそして明るい。
この動と静。相反し対立する渦。
まさにラビリンスは人間生活の運命そのものだ。
-------------------------------
-------------------------------
P14
迷宮は常に静と動のなかに振動している。
それは人間の心の動揺からである。
確かにラビリンスは不動であり、静止しているかのようだが、また無限に転動しているのである。
静動一体、時空の矛盾したからみあい
-そこに無限にひらく夢と恐怖。
迷宮・即・人間の運命。
-------------------------------
-------------------------------
P84
自分の心のうちにある迷宮のなかを、熱情をもって彷徨ってゆけばよいのだ。
嬉しさと不安感をまじえながら夢幻の世界を創造し、ひらいてゆく。
-------------------------------
-------------------------------
P96
ケルトの「組紐文」も「縄文」にひどく似ている。
無限にからみあい、回転してゆく。
私はかつて、『美の呪力』でこのように書いた。

**************
『組紐文は(キリスト的とは)まさに正反対の世界観だ。
中心というものがない。無限にのび、くぐり抜けてひろがる。
世界を流動の相で捉える人々の造形だ。
たった一人、一つのものが中心だとか力を持つなどという、こだわった権力意志ではない。
自分たちを超えた運命がいつでもすれ違いながら流れて行く。
それがどこに行くか、はじまりもなければ終わりもない。
とすれば、あらゆるポイントがはじまりであり終わりである。
だからどんな部分も、絶対感をもって宇宙に対する。価値でもなければ無価値でもない。
無限に時空のなかに、みえてゆくエネルギーであり、意志だ。』
**************
これがラビリンスだと私は直感する。
それは運命感であり、宇宙観なのである。
無条件で人間の夢をひらいた軌跡だから、そこには始まり、終わり、決められた形というものではなく、
始まりは終わり、終わりは始まり、無限だ。
つまり永遠の循環。
縄文やケルトの組紐文を見てそこに私が迷宮を幻想するのは、
形が、いわゆる迷宮のイメージに似ているというのではなくて、
そこに表出される世界観、運命観が迷宮のなかに生きているからだ。
そして私は自分の運命がそのまま、そこに反映して、命がそこにからみあうような、自分と一体の思いがする。
キリキリ回っている、くぐり抜けくぐり抜けしていく線、そのいきかたそのもの。
-------------------------------
-------------------------------
P103
迷宮の出口を出るということは、つまりは人生を退いてしまうのだ。
それは死ぬことではない。
死でもなく、生でもない、真の生命感を失った無意味の存在になってしまうことだ。
死と生がからみあっているところに生命の情感、迷宮の神秘があるのだ。
人間はみな、それぞれラビリンスを創造しているのだ。
数十億の人間がこの世にいるならば、数十億のラビリンスがある。
-------------------------------
-------------------------------
P111
(岡本敏子さんの後書き)
岡本敏子「迷宮をゆく太郎」
『太郎さんは、ふだんは快活でやんちゃで、ユーモア好きの、陽性の人だったし、
スパッと筋を通して論理的でもある。およそ迷宮らしくない人だった。
深刻そうな、重苦しい気配は嫌いなのだ。
だがその裏側に、もう一つの極に、デリケートで神経質、くちゃくちゃした、とことんこだわる性癖が隠れていた。
くねくねと執拗にくねって、無限に渦巻いてゆくケルト文様のような、ひだの深い情熱、混沌がひそんでいる。
迷宮に住む怪物にふさわしい人だった。』
-------------------------------
P123
『岡本太郎が好きで勇気をもらっている人たちは、
「岡本太郎」という個性が最初から天性のものとしてあったように思っているようだ。
そしてその強さに憧れたり、とてもあんな風にはなれないと悩んだりしている。
私はそういう人に言いたい。
「岡本太郎は、最初から岡本太郎だった訳ではないのよ。彼は岡本太郎になったの。」
自分で決意して、覚悟を決めて、そうなり、それを貫いたのだ。
転生強い人とか、聡明な人、才能のある人、そんなのは何でもない。
そういうものはいつでもぐらぐらするし、破れる。
才能のある人は才能によってつまずくし、聡明な人は自分の馬鹿に気がつかない。
だが岡本太郎は最初から、まったく捨て身、自分を投げ出したところから出発した。
だから彼は恐れない。
強くてこんなことをやっていたのなら、ただの豪傑だ。おめでたい愚者だ。
だが彼はそうではない。
痛がりやで、繊細極まる神経の持ち主で、しかもいろんなことが見えてしまうたちだ。
それがこれを貫きとおしたということが凄い。
だから力なのだ。人に迫るのだ。』
-------------------------------
興味が湧いた人は、青山の表参道の裏道にある彼の旧アトリエ「岡本太郎記念館」や、小田急線の向ヶ丘遊園が最寄り駅の「川崎市岡本太郎美術館」に足を運んでみてくださいね。
そのときは、僕も誘ってください。
岡本敏子さんの発言が素晴らしいですね。
「岡本太郎は、最初から岡本太郎だった訳ではないのよ。
彼は岡本太郎になったの。」










いなばさんの岡本推薦度は、
ホント、手を変え品を変えのもので、
これは、やっぱり、すごいんだなと。
(松っちゃんの尼崎時代のトークじゃないけど、繰り返しは本物ですよね。)
グラスの下に顔があったっていいじゃないか!…に肯定されたって話はグッと来た!
ちょうど、新聞読み返してて、
前に、自分の影響受けた人をよく思い出してみればってので、関連した話が。
茂木は、未来が不確実な今、どう生きるのが大切かの問いに、
そうした不確実性を楽しいと捉えることが大切。脳は本来、楽観的だと言います。
そして、そのためには、「根拠のない自信を持て」と。
しかし、それはなかなかむつかしい。
そのために、「安全基地」が必要。
幼い子であれば、母親の膝なんだろうけど、大人になったら、それはムリなので
(笑)、
大人は、「自分の中に揺るぎなく立つ原理/原則」がベースとなり得る。そんなものないという人がいるかもしれないが、内面は掘ってみれば必ず見つかるはずだと。自分の過去を振り返る作業=自分の過去は育てられると結んでいます。
…この辺の話は面白いですよね。
いなばさんの中では、岡本太郎が間違いなく、〈原理〉として血肉化しているんだろう。迷ったり不安になったときにも、岡本先生ならどう見るだろうか?という形で常に参照できるような存在になっている。…たしかに、ぼくにも何人かそうした〈原理〉とでも言うような人がいる気がします。
これ、この前会ったとき少し話した内容なんだけど、
自分も若かりし日って、まあ天の邪鬼で、わがままで、でも自分が何者でもないからしょうもない人間で、でもなんとなく学校の授業も全然面白くなくて、学校早退したり遅刻したりしながら、なんかいろんなとこブラブラしながら無為に時間を過ごしていたものです。
ああいう時間って、今見返すと「悩む」とか「考える」とかの時期だったんだろうけど、当時はそんなことすら知らなかったから、もう無為にダラダラ時間過ごしてたような気がするんですよね。
でも、そういう果てしなくダラダラした時間って実はかなり大事だったと思う。
悩むとか、考えるとか、そういう言語化された前のもっとモヤモヤした状態なんだと思う。
今は変に知恵がついてきたから、「今俺は悩んでいる」とか変に客観的に分かるんだろうけど。
そういうモヤモヤした青春の時期に、岡本太郎をテレビCMで見て、「グラスの底に顔があってもいいじゃないか!」ってギロっと睨みながら叫んでいる岡本太郎を見て、なんかその時の自分は救われたんです。
なんと言えばいいか難しいんだけど、若かりし未分化でダメでしょうもない自分を全肯定してくれたような気がしたのですね。「そのままでいいじゃない!」っていう感じで。
岡本太郎とはそういう思い出があります。それを最近思い出したんで、Is氏と会ったときに話したのです。意外に、自分の過去の思い出の扉をあけていくと、綺麗に引き出しに入ってましたね。なんかすっかり忘却してた気がしたんだけど、実は海馬の記憶野の中に大切に大切に収納してあったような感じ(笑
その時から少し時間をあけて、彼の著作や画集を見て、更に魂を掴まれたんです。そこも結構タイムラグあった気もします。
・・・・・・・・
Is氏が引用している、茂木さんの「内面は掘ってみれば必ず見つかるはずだと。自分の過去を振り返る作業=自分の過去は育てられる」っていうのはわしの実感と同じだー。
内なる宇宙である自分と、外なる宇宙である世界があるんだから、二つの宇宙を自由に行き来すればいいと思うんです。境界とか狭間って、色々本質が隠れているなぁと思うんだけど、それは、内なる宇宙と外なる宇宙の境界そのものが、「私」という概念なんだからだと思う。
なんか、かなり哲学的になってきたけど(笑
やっぱ窮地に陥ったとき、岡本太郎とか手塚治虫とかと無意識に対話しているような気がするんだよね。彼ならどうするだろう、彼なら何に涙を流したりするだろう、何を犠牲にするだろうとかね。
想像力を使って、死者の声に耳を傾けることって結構大事だと思うんですよ。そうすると、色んな死者(祖父母とかもそうだけど)に自分が守られているような気がしてくるから不思議です。その辺が、生命の本質的な謎や迷宮の核心部なのかなぁ。