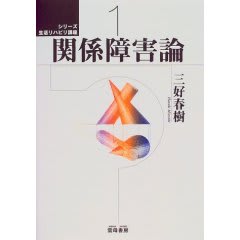『関係障害論』 三好春樹著 雲母書房
これは、老人介護についての本です。
三好さんの本は、89年に『生活リハビリとはなにか』を読んで以来のファンで、
ほとんどすべての本を読んでいます。
「老人」介護の本でありながら、私の頭の中では、
ほとんどすべて「子ども」との付き合いとして理解できる本でした。
なかでも、この「関係障害論」は、
私がまとめたいと思っている
「授業という生活」の意味を考えるのに、
一番役立っている一冊です。
三好さんは、「なぜ老人が縛られなければならないのか」
というのが最初の問題意識だと言います。
「なぜ、縛るのか。
たとえば、食事をしないから、鼻からチューブを入れて流動食を流し込む。
そうすると、老人は痛いわけです。
違和感がありますから、それを引き抜きます。
・・・すると手足を縛る、ということになる。」
また「オムツをしていて、オムツを引っ張りだして不潔行為をするから縛る」。
そういう理屈に対し、三好さんは、
「なぜ手足を縛る前に、
何か他に方法があるのではないかということを
発想していけないのか」と考えます。
それは、私にとっては、
「なぜ子どもを分ける前に、
何か他に方法はあるのではないかということを
発想していけないのか」と聞こえるのです。
「言うことを聞かないから」「ダメということをしてしまうから」と、
ベッドに縛り付けるのと、みんなと違う場所に囲われるのとは、
発想としては同じだろうと思うのです。
しかも、縛ることを、
「抑制」という「医療・看護の言葉」でごまかしているのも、
「個別のニーズにあった指導」等という
「学校の言葉」でごまかすのと同じ。
そこでは、「関係」という目に見えないものを、
どう見て、評価して、作り出していくか、
という大事なものが欠けているせいではないか、というのです。
久しぶりに読み返して、やっぱり面白いので、
「授業という生活」と、「こだわりの溶ける時間」の原稿を考えるために、
少しゆっくり、この本を紹介したいと思います。(つづく)