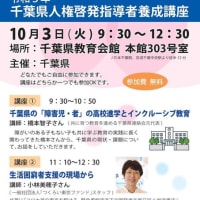ふつう学級の介助を考えるためのメモ (005)
《怖れから自由になる介助》
思いやりの心をもって「介助」をしてあげればいい、という人もいる。
だけど、私にはそれが「優しい管理」や「遅れを招く環境」にみえる。
子どもが、自分のできないことを、「優しく、おもいやり」をもってされるしかないとき、
それは、主体に土足であがることになっていないか。
「介助行為」に思いやりの心を添える、のではなく、「介助」される子どもとの「対話」と「相互行為」に、「手をかす行為」や「知恵をかす行為」を添えること。
介助「される」ことで「脅かされない」「能動」を残す行為。
介助「される」状態のなかで、なお子どもが「主体」として参加している状況を見落とさないこと。
子どもが「怖れなくていい」関係作りが前提にあることは当然として、学校の中の介助は、一対一で行うものではない。介助行為をいつも目にしている大勢の子どもたちがいる。
だから、「介助」という「強制力の行使」が、周りの子どもにとっても「少しも怖れなくていいもの」と感じられるものでなければならない。
「怖れなくていい」関係作り。
相互行為として「手をかし、手を添える」こと。
それを伝えるためには、介助行為の技術や工夫以上に、それを見ている子どもたちと相互理解するための、創意工夫が大切になる。
学校の中の介助とは、それを含めてのこと。
最新の画像もっと見る
最近の「手をかすように知恵をかすこと」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- ようこそ就園・就学相談会へ(494)
- 就学相談・いろはカルタ(60)
- 手をかすように知恵をかすこと(29)
- 0点でも高校へ(393)
- 手をかりるように知恵をかりること(60)
- 8才の子ども(161)
- 普通学級の介助の専門性(54)
- 医療的ケアと普通学級(90)
- ホームN通信(103)
- 石川憲彦(36)
- 特別支援教育からの転校・転籍(48)
- 分けられること(67)
- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)
- 膨大な量の観察学習(32)
- ≪通級≫を考えるために(15)
- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)
- この子がさびしくないように(86)
- こだわりの溶ける時間(58)
- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)
- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)
- 感情の流れをともに生きる(15)
- 自分を支える自分(15)
- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)
- 受けとめられ体験について(29)
- 関係の自立(28)
- 星になったhide(25)
- トム・キッドウッド(8)
- Halの冒険(56)
- 金曜日は「ものがたり」♪(15)
- 定員内入学拒否という差別(97)
- Niiといっしょ(23)
- フルインクル(45)
- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)
- ワニペディア(14)
- 新しい能力(28)
- みっけ(6)
- ワニなつ(351)
- 本のノート(59)
バックナンバー
人気記事