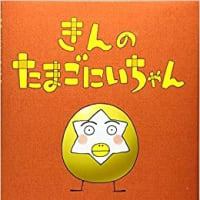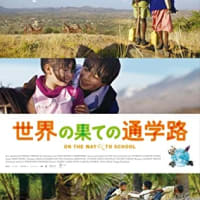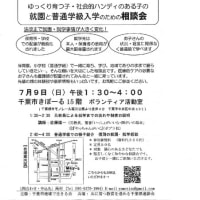《4つの問い》
「その問い」は、本当は4通りある。
《健常児と障害児》×《普通学級と支援学級》。
その組み合わせは、次の4通りになる。
A「健常児に、どうして普通学級なのか?」
B「健常児に、どうして支援学級なのか?」
C「障害児に、どうして普通学級なのか?」
D「障害児に、どうして支援学級なのか?」
こう書いてみて、改めて気づく。
使われる「問い」は、Cだけだ。
Cの問いだけが、いかにも「自然」な問いかけのように使われているけれど、他の問いは聞かない。
問う人は、その理由を考えたことがあるだろうか?
支援学級の子に、D「どうして支援学級なのか?」と問わないのは、「答え」を聞くことに意味がないからだろう。
「本当は、みんなと一緒がいい」と、子どもが答えても現実は変わらない。
だから、問わない。
万が一、変えようとすれば、その時にはCの問いが立ちはだかる。
「障害児なのに、どうして普通学級なの?」
それは、「問い」ではない。
□
ところで、AとBの問いを、聞いたことのある人がいるだろうか?
私は、一度も聞いたことがない。
なぜか?
A=普通学級に健常児がいるのは当然で、自然なこと。
B=支援学級に、健常児は一人も「いない」から。(※)
あまりに当然で、自然なことを、大人は問わない。
□
Cだけが問われ続けてきたのはなぜか?
それは「問い」ではなく、「私の経験ではあり得ない」という「意思表示」に過ぎなかったのだ。
だから、私が40年かけて集めた「宝物の山」は、ひとつも届かない。
子どもたちの声と言葉とまなざしと表情の「答」のすべてが、私にとっては人生で一番の宝物。
でも「問う人」たちには、ただのざれごと。
問いがあって、「答」があるのではなかった。
答えは最初から、私たち自身の生き方と子どもとのつながりのなかにあった。
そのつながりと生き方に疑問を投げかけるために、その問いは生まれる。
疑問を投げかける形での否定。
それは、すべての子どもの意思と主体感覚を否定するものでしかない。
疑問は、あなたの人生の中に生じたもの。
疑問は、あなたの生き方の過程で、生じたもの。
疑問は、あなたの人とのつながり方に、生じたもの。
あなたの人生の疑問を、どうしてこの子たちが答えてあげなくてはいけないのか。
それは、この子たちの役割でもなければ、私の仕事でもない。
だから、私の中から「その問い」は消えた。
その問いを生む社会とは、別の社会の感覚を、残りの人生で生きたい。
この子たちを、守るために必要なだけしっかりと、ただし捕まえられていると感じさせないくらいゆるく、ひとりの子どもの身体感覚と主体感覚が育つことを願いながら。
(※1)
本当は、支援学級に《健常児はいない》とはいえない。
特殊教育の時代には非科学的な心理判定による間違いがあったし、そもそも「性格異常児」とか「普通学級不適応」と言われてしまえば《健常児》とはみなされない。
まさに8才の私がそうだった。
今は「特別な支援が必要な子」にはすべて特別支援教育が行われる、などと言われ、その辺はよけいあいまいだ。なので、この話はまた別の機会に。
最新の画像もっと見る
最近の「誰かのまなざしを通して人をみること」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- ようこそ就園・就学相談会へ(517)
- 就学相談・いろはカルタ(60)
- 手をかすように知恵をかすこと(29)
- 0点でも高校へ(402)
- 手をかりるように知恵をかりること(60)
- 8才の子ども(162)
- 普通学級の介助の専門性(54)
- 医療的ケアと普通学級(92)
- ホームN通信(103)
- 石川憲彦(36)
- 特別支援教育からの転校・転籍(48)
- 分けられること(68)
- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)
- 膨大な量の観察学習(32)
- ≪通級≫を考えるために(15)
- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)
- この子がさびしくないように(86)
- こだわりの溶ける時間(58)
- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)
- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)
- 感情の流れをともに生きる(15)
- 自分を支える自分(15)
- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)
- 受けとめられ体験について(29)
- 関係の自立(28)
- 星になったhide(25)
- トム・キッドウッド(8)
- Halの冒険(56)
- 金曜日は「ものがたり」♪(15)
- 定員内入学拒否という差別(99)
- Niiといっしょ(23)
- フルインクル(45)
- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)
- ワニペディア(14)
- 新しい能力(28)
- みっけ(6)
- ワニなつ(351)
- 本のノート(59)
バックナンバー
人気記事