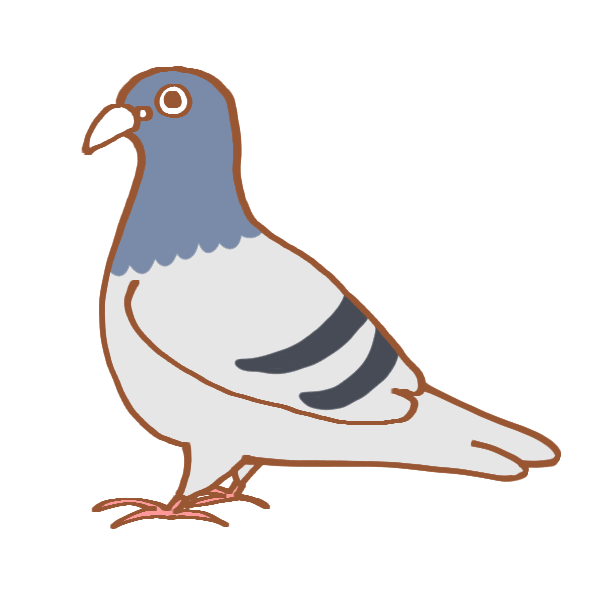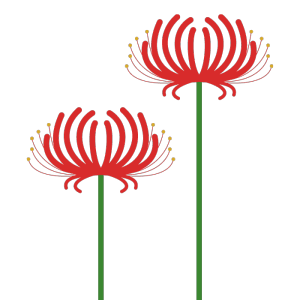令和元年9月14日(土)
名 月 : 芋名月、今日の月

陰暦8月15日の月
仲秋の満月を愛でる行事は中国から伝わって来た
ものである。 それ以前から月は暦として生活に
密着していた。
十五夜も農耕上の重要な折り目の行事であった。
芋や豆を供えるのは農耕との拘わりを示すもの
であり、8月15日(陰暦)の月は「芋名月」、
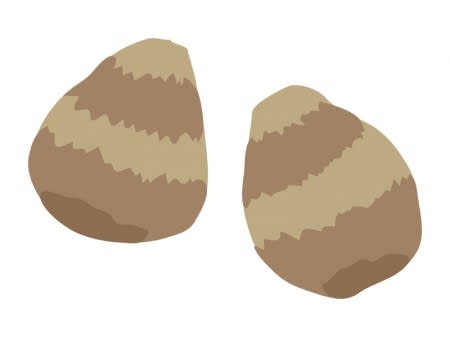
9月13日(陰暦)の後の月は「豆名月」と呼ぶ。
月は古来、崇拝の対象であったが、仏教伝来と
共に信仰上の意味を深めるようになった。
「かぐや姫」の物語も、月の神秘性、宗教性を
反映するものといえる。
十三夜の月見は中国にはなく、我国独自のもので
両夜の月を祀る事が風習となった。
名月や池を巡りて夜もすがら 松尾芭蕉
俳句には古典から現代まで、重要な季語の一つ
となっている。
また、「徒然草」には8月15日、9月13日
には「婁宿(ろうしゅく)なり、この宿清明
なる故に、月を弄ぶに良夜とし」とある。
良夜は本来は深夜或いは月の良い夜を表し、
特に十五夜をいう。
昨夜(9月13日)は「仲秋の名月」

月見団子

カミさんが、里芋と月見だんごを買ってくる。
曇天の一日で、夕方になっても雲がびっしり、
6時30分頃、少しずつ雲が切れはじめて
月が覗く、、、
7時過ぎ、「お父さん、月が見えるヨ、、、」
暫し眺め、芋の煮転がしを食べビールを一杯、

また雲が覆い、、時折、月が見え隠れ、、、、

朝刊に、岐阜城にかかる名月の写真、、

やはり雲がかかり、これはこれで名月か、、、
今日の1句(俳人の名句)
十五夜の雲のあそびてかぎりなし 後藤 夜半
名 月 : 芋名月、今日の月

陰暦8月15日の月
仲秋の満月を愛でる行事は中国から伝わって来た
ものである。 それ以前から月は暦として生活に
密着していた。
十五夜も農耕上の重要な折り目の行事であった。
芋や豆を供えるのは農耕との拘わりを示すもの
であり、8月15日(陰暦)の月は「芋名月」、
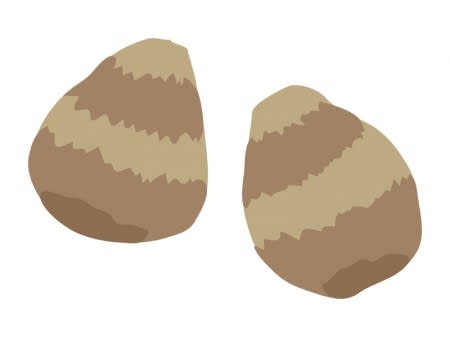
9月13日(陰暦)の後の月は「豆名月」と呼ぶ。
月は古来、崇拝の対象であったが、仏教伝来と
共に信仰上の意味を深めるようになった。
「かぐや姫」の物語も、月の神秘性、宗教性を
反映するものといえる。
十三夜の月見は中国にはなく、我国独自のもので
両夜の月を祀る事が風習となった。
名月や池を巡りて夜もすがら 松尾芭蕉
俳句には古典から現代まで、重要な季語の一つ
となっている。
また、「徒然草」には8月15日、9月13日
には「婁宿(ろうしゅく)なり、この宿清明
なる故に、月を弄ぶに良夜とし」とある。
良夜は本来は深夜或いは月の良い夜を表し、
特に十五夜をいう。
昨夜(9月13日)は「仲秋の名月」

月見団子

カミさんが、里芋と月見だんごを買ってくる。
曇天の一日で、夕方になっても雲がびっしり、
6時30分頃、少しずつ雲が切れはじめて
月が覗く、、、
7時過ぎ、「お父さん、月が見えるヨ、、、」
暫し眺め、芋の煮転がしを食べビールを一杯、

また雲が覆い、、時折、月が見え隠れ、、、、

朝刊に、岐阜城にかかる名月の写真、、

やはり雲がかかり、これはこれで名月か、、、
今日の1句(俳人の名句)
十五夜の雲のあそびてかぎりなし 後藤 夜半