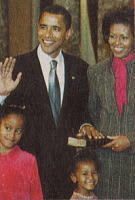慶応4年1月23日(1868年2月16日)、大久保利通が大阪遷都を建議した。
アメリカの東インド艦隊司令官のマシュー・ペリーは、嘉永6年6月3日(1853年7月8日)、4隻の黒船を率いて来日し、浦賀へ入港して日本に対して開国を要求。翌嘉永7年1月16日(1854年2月13日)には旗艦サスケハナ号など7隻の艦隊を率いて江戸湾(現在の横浜市金沢区の沖)に迫り条約締結を求め、3月3日(3月31日)には日米和親条約を調印し外交関係を結んだ。(詳しくは黒船来航参照)。
1868年、日本は、このようなペリーの強引な砲艦外交によって資本主義世界に取り込まれ、幕藩的割拠体制(徳川幕藩体制参照)に支えられた日本を否定し、「御一新(大政奉還と廃藩置県。明治維新参照)」による民族国民国家の創出をめざすことになる。
この「御一新」は、軍事・経済的に優越している欧米に対抗する民族結集の場を、万世一系の皇統をいただく皇国であるという物語を共有することで実現され、この物語は列強の植民地になるのではないかという状況下、日本列島の住民を天皇を中心とする民族精神に結集せしめ、他国と異なる選民との意識に呪縛された日本国民を生み育てることになった。薩長討幕派を主力とする維新政府は、「王政復古」「万機親裁(天皇が日常的に万機を親裁する体制。天皇親裁参照)」を、かかげ、天皇が国家の根軸であり、権力の主体であることを説き、万邦(あらゆる国。万国)に対峙(たいじ)しうる独立国日本の基盤をかためていくことになったという。(朝日クロニクル「週刊20世紀」045)。
新政府の中心は、薩長両藩をはじめとする討幕派の下級藩士層だったが、宮廷勢力、公議政体派(公議政体論参照)の力も根強かった。
そのため、維新政権樹立に中心的な役割を果たした薩摩藩士、大久保利通は、宮廷勢力を天皇から切り離し、天皇親政(君主【国王・皇帝・天皇など】自身が政治を行うこと、またはその政治形態【君主制の一形式】のこと)を実現するため、慶応4年1月23日(1868年2月16日)、大阪への遷都を建議した(日付等は以下参考に記載の“怒濤の幕末維新-攘夷・開国から民撰議院設立建白書提出へ-特別展-衆議院憲政記念館-“による)。
大久保が建白した「大坂遷都建白書」には「主上ノ在ス所ヲ雲上トイヒ、公家方ヲ雲上人ト唱ヘ、龍顔(天皇の顔。玉顔ともいう。天皇に対する最高敬語。龍は皇帝の象徴。)ハ拝シ難キモノト思ヒ、玉体ハ寸地ヲ踏玉ハサルモノト余リニ推尊奉リテ自ラ分外ニ尊大貴ナルモノ、様ニ思食(おぼしめ)サセラレ、終ニ上下隔絶・・・」・・とあるように、かって、例のない厳しい朝廷弾劾の書であったようだ。(週刊朝日百科「日本の歴史」)。
天皇は、単に今までのように公家のための天皇ではなく、人民のための天皇という絶対君主の姿でなければならない。そのような天皇を核心として、万邦対峙を実現し、わが国を欧米列強に伍(ご)していく強国にしようというのである。そのためには、天皇が京都の「玉簾(ぎょくれん)」の中に閉じこもらずに、国民の前に姿を現すべきだと大久保は考えていたのだ。
しかし、 この遷都計画に対して、急激な変化を恐れる公家や保守的な大名たちが抵抗。遷都計画は二転三転し、結局、大坂遷都論は縮小されて大坂行幸に形を変え、慶応4年3月21日(1868年4月13日)には大坂に向かって総勢1655人の行列が出発した。そして、大久保は、東本願寺難波御堂(現在の難波別院【通称、南御堂】で、天皇に謁見したという(以下参考に記載の“NHK:その時歴史が動いた第133回「幕末ニッポン・幻の遷都計画」”)。
兎に角、明治天皇はついに京都御所の奥深くから民衆の前に現れたのであった。
前島密は、慶応4年(1868年)に大久保利通の大阪遷都論を読んで、これに対し、江戸が遷都地にふさわしいという理由を全6か条あげて建言、その内容は、全体として首都はどういうものであるべきか、都市景観の問題や将来の交通の問題、日本全体の中での位置関係、運輸・港湾の便なども考慮した非常にまとまったものだそうで、大久保もこれに納得したようだ。慶応4年5月11日(1968年6月30日)、新政府は江戸府を設置し、同年年7月17日(9月3日)に江戸が東亰(後に東京)と改称されると、江戸府も東京府と改称された。そして、明治元年9月20日(1868年11月4日)総勢3300人の行列が東京に向かって出発した。これが、日本史上初の東京行幸(東幸)であり、1869年に明治天皇が皇居(旧の江戸城)に入ると、東京は近代日本の事実上の首都となった(東京を首都とする法的根拠はないとする意見もある。東京奠都を参照)。
こうして、大久保の大阪遷都構想は紆余曲折を経て、最終的には東京遷都という形で実現。これが、日本を近代国家へと転換する大きな一歩となったといわれている。
しかし、大坂遷都は実行されなかったがせめて御所(皇居)だけでも大坂に移転していたら日本の歴史は相当変わっていただろうね~。
(画像は、明治元(1868)年11月(旧暦10月)明治天皇は京都から東京に東幸。写真は、東京都立中央図書館特別文庫室蔵。アサヒクロニクル「週刊20世紀」掲載分より)
参考:
1868年 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/1868%E5%B9%B4
1868年[ザ・20世紀]
http://www001.upp.so-net.ne.jp/fukushi/year/1868.html
明治維新 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%B6%AD%E6%96%B0
砲艦外交 – Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B2%E8%89%A6%E5%A4%96%E4%BA%A4
怒濤の幕末維新-攘夷・開国から民撰議院設立建白書提出へ-特別展-衆議院憲政記念館-
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/kensei/kensei-tokubetsu.htm
「万機親裁体制の成立 ―明治天皇はいつから近代の天皇となったのか―」
http://www.hmn.bun.kyoto-u.ac.jp/sympo02-01/02.html
最高敬語 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98%E6%95%AC%E8%AA%9E
近衛忠房 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E8%A1%9B%E5%BF%A0%E6%88%BF
大久保利通の大阪遷都論
http://373news.com/_bunka/jikokushi/91.php
NHK:その時歴史が動いた第133回「幕末ニッポン・幻の遷都計画」~江戸か大坂か?大久保利通の大改革~
http://www.nhk.or.jp/sonotoki/2003_05.html#01
[PDF] 江藤新平の明治維新
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/9494/1/42103_12.pdf
公議政体論 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%AD%B0%E6%94%BF%E4%BD%93%E8%AB%96
東京行幸 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E8%A1%8C%E5%B9%B8
明治天皇はいつから近代の天皇となったのか
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/works/seouluniv.htm
東京奠都(てんと)までの流れ、紛糾する新政府内部》 2008.04.03更新
〈大久保利通による大阪遷都論〉
http://www.photo-make.co.jp/hm_2/ma_19_a.htm
アメリカの東インド艦隊司令官のマシュー・ペリーは、嘉永6年6月3日(1853年7月8日)、4隻の黒船を率いて来日し、浦賀へ入港して日本に対して開国を要求。翌嘉永7年1月16日(1854年2月13日)には旗艦サスケハナ号など7隻の艦隊を率いて江戸湾(現在の横浜市金沢区の沖)に迫り条約締結を求め、3月3日(3月31日)には日米和親条約を調印し外交関係を結んだ。(詳しくは黒船来航参照)。
1868年、日本は、このようなペリーの強引な砲艦外交によって資本主義世界に取り込まれ、幕藩的割拠体制(徳川幕藩体制参照)に支えられた日本を否定し、「御一新(大政奉還と廃藩置県。明治維新参照)」による民族国民国家の創出をめざすことになる。
この「御一新」は、軍事・経済的に優越している欧米に対抗する民族結集の場を、万世一系の皇統をいただく皇国であるという物語を共有することで実現され、この物語は列強の植民地になるのではないかという状況下、日本列島の住民を天皇を中心とする民族精神に結集せしめ、他国と異なる選民との意識に呪縛された日本国民を生み育てることになった。薩長討幕派を主力とする維新政府は、「王政復古」「万機親裁(天皇が日常的に万機を親裁する体制。天皇親裁参照)」を、かかげ、天皇が国家の根軸であり、権力の主体であることを説き、万邦(あらゆる国。万国)に対峙(たいじ)しうる独立国日本の基盤をかためていくことになったという。(朝日クロニクル「週刊20世紀」045)。
新政府の中心は、薩長両藩をはじめとする討幕派の下級藩士層だったが、宮廷勢力、公議政体派(公議政体論参照)の力も根強かった。
そのため、維新政権樹立に中心的な役割を果たした薩摩藩士、大久保利通は、宮廷勢力を天皇から切り離し、天皇親政(君主【国王・皇帝・天皇など】自身が政治を行うこと、またはその政治形態【君主制の一形式】のこと)を実現するため、慶応4年1月23日(1868年2月16日)、大阪への遷都を建議した(日付等は以下参考に記載の“怒濤の幕末維新-攘夷・開国から民撰議院設立建白書提出へ-特別展-衆議院憲政記念館-“による)。
大久保が建白した「大坂遷都建白書」には「主上ノ在ス所ヲ雲上トイヒ、公家方ヲ雲上人ト唱ヘ、龍顔(天皇の顔。玉顔ともいう。天皇に対する最高敬語。龍は皇帝の象徴。)ハ拝シ難キモノト思ヒ、玉体ハ寸地ヲ踏玉ハサルモノト余リニ推尊奉リテ自ラ分外ニ尊大貴ナルモノ、様ニ思食(おぼしめ)サセラレ、終ニ上下隔絶・・・」・・とあるように、かって、例のない厳しい朝廷弾劾の書であったようだ。(週刊朝日百科「日本の歴史」)。
天皇は、単に今までのように公家のための天皇ではなく、人民のための天皇という絶対君主の姿でなければならない。そのような天皇を核心として、万邦対峙を実現し、わが国を欧米列強に伍(ご)していく強国にしようというのである。そのためには、天皇が京都の「玉簾(ぎょくれん)」の中に閉じこもらずに、国民の前に姿を現すべきだと大久保は考えていたのだ。
しかし、 この遷都計画に対して、急激な変化を恐れる公家や保守的な大名たちが抵抗。遷都計画は二転三転し、結局、大坂遷都論は縮小されて大坂行幸に形を変え、慶応4年3月21日(1868年4月13日)には大坂に向かって総勢1655人の行列が出発した。そして、大久保は、東本願寺難波御堂(現在の難波別院【通称、南御堂】で、天皇に謁見したという(以下参考に記載の“NHK:その時歴史が動いた第133回「幕末ニッポン・幻の遷都計画」”)。
兎に角、明治天皇はついに京都御所の奥深くから民衆の前に現れたのであった。
前島密は、慶応4年(1868年)に大久保利通の大阪遷都論を読んで、これに対し、江戸が遷都地にふさわしいという理由を全6か条あげて建言、その内容は、全体として首都はどういうものであるべきか、都市景観の問題や将来の交通の問題、日本全体の中での位置関係、運輸・港湾の便なども考慮した非常にまとまったものだそうで、大久保もこれに納得したようだ。慶応4年5月11日(1968年6月30日)、新政府は江戸府を設置し、同年年7月17日(9月3日)に江戸が東亰(後に東京)と改称されると、江戸府も東京府と改称された。そして、明治元年9月20日(1868年11月4日)総勢3300人の行列が東京に向かって出発した。これが、日本史上初の東京行幸(東幸)であり、1869年に明治天皇が皇居(旧の江戸城)に入ると、東京は近代日本の事実上の首都となった(東京を首都とする法的根拠はないとする意見もある。東京奠都を参照)。
こうして、大久保の大阪遷都構想は紆余曲折を経て、最終的には東京遷都という形で実現。これが、日本を近代国家へと転換する大きな一歩となったといわれている。
しかし、大坂遷都は実行されなかったがせめて御所(皇居)だけでも大坂に移転していたら日本の歴史は相当変わっていただろうね~。
(画像は、明治元(1868)年11月(旧暦10月)明治天皇は京都から東京に東幸。写真は、東京都立中央図書館特別文庫室蔵。アサヒクロニクル「週刊20世紀」掲載分より)
参考:
1868年 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/1868%E5%B9%B4
1868年[ザ・20世紀]
http://www001.upp.so-net.ne.jp/fukushi/year/1868.html
明治維新 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%B6%AD%E6%96%B0
砲艦外交 – Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B2%E8%89%A6%E5%A4%96%E4%BA%A4
怒濤の幕末維新-攘夷・開国から民撰議院設立建白書提出へ-特別展-衆議院憲政記念館-
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/kensei/kensei-tokubetsu.htm
「万機親裁体制の成立 ―明治天皇はいつから近代の天皇となったのか―」
http://www.hmn.bun.kyoto-u.ac.jp/sympo02-01/02.html
最高敬語 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98%E6%95%AC%E8%AA%9E
近衛忠房 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E8%A1%9B%E5%BF%A0%E6%88%BF
大久保利通の大阪遷都論
http://373news.com/_bunka/jikokushi/91.php
NHK:その時歴史が動いた第133回「幕末ニッポン・幻の遷都計画」~江戸か大坂か?大久保利通の大改革~
http://www.nhk.or.jp/sonotoki/2003_05.html#01
[PDF] 江藤新平の明治維新
http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/9494/1/42103_12.pdf
公議政体論 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%AD%B0%E6%94%BF%E4%BD%93%E8%AB%96
東京行幸 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E8%A1%8C%E5%B9%B8
明治天皇はいつから近代の天皇となったのか
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/works/seouluniv.htm
東京奠都(てんと)までの流れ、紛糾する新政府内部》 2008.04.03更新
〈大久保利通による大阪遷都論〉
http://www.photo-make.co.jp/hm_2/ma_19_a.htm