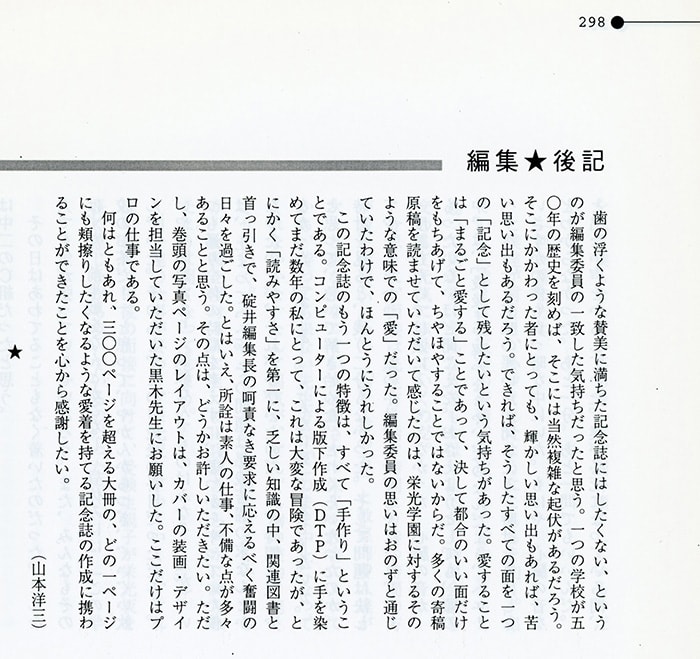95 怒りをかう日々、あるいはリアリティのありか

2016.8.29
このところ立て続けに人の怒りをかっている。それも共通して「リアリティ」のありかについてのぼくのいい加減な発言に原因があるらしい。昔から人を怒らせるような失礼千万な発言ばかりして周囲に多大なる迷惑をかけてきたぼくであるが、こんなに高級なテーマで怒りをかうなどということは、実に珍しいことで、それだけでもありがたいと思わなければならない。ぼくのような自己中の人間は、人に怒られでもしなければ成長しない。
そのひとつが、『シン・ゴジラ』のことで、もともと特撮ものをほとんど見たこともなければ、『エヴァンゲリオン』も名前だけは知っているものの、見たことがないから監督の庵野さんのこともまったく知らないぼくが、『シン・ゴジラ』を見て、よせばいいのに批評家ぶって、〈ここには「死者」がでてこないことによって、妙な「リアリティの希薄さ』が生じている〉なんてことを、フェイスブックに書き込んだものだから、「ゴジラ」をこよなく愛する友人から、何をわけわかんないこと言ってんだ! って感じで、もろに怒られてしまった。
まあいくらトンチンカンなぼくとても、映画の画面に「死体」が出てこないからリアリティがない、なんてことを思っているわけではなくて、ぼくが感じた「妙な『リアリティの希薄さ』」は、あの3月11日に、テレビで生の映像として見ていた津波、逃げ惑う車、流される家、その映像の持っていた「質感」とどこか符合するということだったのだ。津波だけではない、その後の、津波被害の惨状、原発への海水の放水などの映像、さらに遡れば9.11のあの映像までもが重なるのだが、そのどれもが、極めて「リアル」なはずなのに、「どこか映画みたい」という感想をもたらさないではいられない「妙な『リアリティの希薄さ』」があったように思うのだ。
それをそこまで書かないで中途半端で終わってしまったのがよくなかったのかもしれない。でもそうやって怒られてみると、そもそもリアリティって何なのだろうかというこのところずっと思っている問題がちっとも解決していないことに気づくのだった。現実があまりにひどいと、リアリティを失うものなのだろうか。そこで失われたリアリティとは何なのだろうか。そもそもリアリティとは何なのだろうか。そんなことを、ひっきりなしに考えつづけた。
そんな折も折、映画好きの集まるBARに出かける機会があって、ほとんど初対面の人たちと映画について言いたい放題話すという珍しい体験をした。相手が見ず知らずの人であることをいいことに、ぼくはほとんどタガが外れて、恥も外聞もない「旅の恥はかき捨て」状態になった。『シン・ゴジラ』のことも話題にはなったが論争にはならず、話はやがて小津安二郎へ移った。
ぼくは小津は大好きだが、昔から最後の作品『秋刀魚の味』だけはどうしても素直にいいと言えない。
この映画に登場する東野英治郎扮する元教師の描き方に耐えられない思いを見るたびにするからだ。出世した教え子たちが、先生を招いて宴会をするのだが、食卓に出た「ハモ」を先生は名前は知ってはいるが食べたことがないのだと言い、「これがハモですかあ〜」と言って感激して食べる。先生がへべれけになって帰ることになり、飲み残した「ダルマ」のボトルをお土産にもらって一人の教え子に付き添われて帰った後(ダルマをあんまり先生がおいしそうに飲むから、教え子が酒が残っているボトルを土産として持たせるわけだが、それを喜ぶ先生がまた惨めにぼくには思えるのだ)、残った教え子が「アイツ、ハモを食べたことがないんだ。」と微妙な笑みを浮かべて言う。何度見てもこのシーンに、傷つく。嫌だなあと思う。残酷な描き方だなあと思う。このシーンを見たがために、ぼくは長いこと教え子たちと飲むことをなるべく避けてきたと言っても大げさじゃないような気がするくらいだ。小津の映画は暖かいというけれど、この映画にはどこか底知れない「残酷な目」が感じられる。小津の底知れない「暗さ」「孤独」がある、というふうに感じてきたのだ。
というようなことをしゃべったら、昭和20年生まれのBARのマスターの怒りをかった。もっとも、お互い飲んでいるし、目は笑っていたから、どこまで本気が分からないが、そんなことはないんだ、そんな批判は間違っているといって、まくしたてる。「孤独があるだあ、何言ってやがる、そんなこと言ったら、小津の映画はどことったって孤独だよ、人間が孤独なんて当たり前のことじゃねえか。そんなこといってオレを説得できると思ってんのか。そんなレベルで小津の批判なんかするな!」ってすごむ。
すると、マスターに加勢する人が出てきて、「『あいつハモ食ったことないんだぜ』っていうセリフはねえ、先生を馬鹿にしてるわけじゃないよ。ああいう言い方で親しみを表しているんじゃないか。それが今時の映画やドラマの歯の浮くようなセリフと根本的に違うところ。そこが小津さんの素晴らしいところなんだ。なんでそんなことも分かんないんだっ!」 と詰め寄る。
何しろこの人たちは、どうやら映画については趣味を超える知識と体験のあるほとんど映画のプロといってもいい人たちのようで、ちょっと映画が好きっていうレベルのぼくみたいな半端なヤツが太刀打ちできる相手ではないと判断したけれども、どうせ乗りかかった舟だ、ここはいっちょういけるとこまで行ってみようと、「窮鼠猫を噛む」状態で反撃してみた。
それはそうかもしれないけど、ぼくがそう感じるんだからしょうがないでしょ。ぼくは42年間教師をやってきて、こういう惨めさをずいぶん味わってきたし、最近では明治の文学史を知れば知るほど、どれだけ「教師」という職業が、「尊敬に値しない」ものとして人々に認識されてきたかってことが嫌というほどわかるんですよ。いくら小津の映画だからといって、そういうことを感じちゃいけないってことはないでしょ! 映画を見て、何をどう感じようとそんなこと見る者の勝手でしょ! って言い返した。
結局、酔っ払いの言い合いだから何の結論もないままに、話は終わってしまったが、ここでも、「リアリティ」の問題があったのではないかと思うのだ。映画の一部にほの見える「小津のどうしようもない絶望的な孤独感」があったとして、そこに「リアリティ」を感じ、そこにざらっとした感触を感じ、自分の感情に重ね合わせて、「ああ、嫌な感じだなあ。」と思うのは、決して小津への批判ではない。「曲がりくねった共感」なのかもしれない。
うまく言えないけれど、「リアリティ」を感じるというのは、自分の感情に直接触れたと感じるということではないのだろうか。そういう意味では、あの教え子の言葉に、ぼくはまさしく「リアリティ」を感じてきたのだし、それがたとえ「嫌な感じだなあ」という非共感的感情を伴うものだとしても、だからこそ、あの映画は、ぼくの「感情に直接触れたと感じる」ところのある映画なのだとも言えるわけだ。「好きだ」とは言えないかもしれないが、「リアリティ」のある映画としていつまでの心に残っているだとも。
あるいはこうも思う。そこまで人間を残酷に見つめた果てに、そんな感情を超えた人間の真実が描かれる、その「真実」こそが小津映画の「リアリティ」なのかもしれないと。そしてこうも思う。ぼくの「リアリティ」の理解は、すごく感情に偏っているのではないか、ちっとも社会的な「現実」が視野に入っていないんじゃないか、と。
そんなことを、映画を見る目の成長を夢見てウジウジと考える日々である。