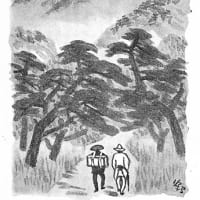詩歌の森へ (8) 丸山薫『汽車に乗って』

2018.5.27
汽車に乗って
汽車に乗って
あいるらんどのような田舎へ行こう
ひとびとが祭の日傘をくるくるまわし
日が照りながら雨のふる
あいるらんどのような田舎へゆこう
車窓(まど)に映った自分の額を道づれにして
湖水をわたり 隧道(とんねる)をくぐり
珍しい少女や牛の歩いている
あいるらんどのような田舎へゆこう
高校生の頃、堀辰雄の小説によって、突然文学に目覚めたぼくは、詩のほうも、もっぱら「四季派」のものに親しんだ。三好達治、丸山薫、、立原道造、津村信夫などをずいぶん読んだような気がする。やがて、そうした関係から、萩原朔太郎や室生犀星を知ることになるのだが、何しろ、にわか文学青年の身には、丸山薫の分かりやすい詩が格好の詩への入口だったわけだ。
この詩とどこで出会ったか、今では記憶にないが、今読むと、なんだかとても懐かしいと同時に、そうか、これは朔太郎の影響下に出来たんだなということがよく分かる。つまり、朔太郎の『旅上』だ。
旅上
ふらんすへ行きたしと思へども
ふらんすはあまりに遠し
せめては新しき背広をきて
きままなる旅にいでてみん。
汽車が山道をゆくとき
みづいろの窓によりかかりて
われひとりうれしきことをおもはむ
五月の朝のしののめ
うら若草のもえいづる心まかせに。
文語と口語の違いはあるが「あいるらんど」のひらがな書きは、「ふらんす」からヒントを得たのだろうし、汽車に乗って、窓によりかかって外を見るという構成もまったく同じだ。「本歌取り」といっていいだろう。
この詩では、「あいるらんど」というひらがな書きと、その音の響きが、この詩のすべてと言ってもいい。「ふらんす」以上のインパクトがある。「るら」というラ行の二文字のつながりが生む、なんともいえない甘ったるい感じ。これが「アイルランド」とカタカナ書きにするとふっと消えてしまう。
この音が生み出す甘ったるい感じが、風景の中に、シロップのように溶け込んでいき、詩全体に夢みるような童話的なイメージを醸成する。
朔太郎の場合は、汽車から見える風景に具体性はなく、もっぱら「夢みる自分」が中心だが、薫の場合は、「祭りの日傘」「湖水」「隧道」「珍しい少女や牛」と具体的なイメージを重ねている。そしてそれゆえに、読者も、「あいるらんどのような田舎」を汽車に乗って旅している気分に浸ることができるわけである。
そうした意味で、いつ読んでも気持ちのいい、心温まる詩だと言えるだろう。
しかしながら、ひとつ困った問題がある。この丸山薫の詩によって作り出された「あいるらんど」という国のイメージが、現実と甚だしく異なっているということだ。この詩によってイメージされる「牧歌的」な「あいるらんど」は、現実の「アイルランド」が経てきた過酷な歴史を日本人が認識する妨げになってきたような気がするのだ。
丸山薫がこの詩を書いたとき、アイルランドに行った経験はなかった。このイメージを彼がどこから得たのか分からないが、あくまで想像上の「あいるらんど」であることは間違いない。しかし、読者は、へえ〜、「アイルランド」ってこういうのどかな国なんだあ、と思ってしまう可能性は非常に大きいだろう。現に、ぼくなども、ずいぶん長いこと、「アイルランド」についてのイメージはこうした「のどかな田舎」だった。
こうした誤解というのは、けっこうあるはずで、最近、やたら外国人が日本にやってきて、ワンダフルとか、クールとかって言ってるらしいのも、誤解としか思えない。誤解でも何でも、外貨が稼げるならいいのかもしれないが、なんか、釈然としないのも事実である。