ドラマ『夏目漱石の妻』が終わった。最終話 「たたかう夫婦」
大げさに言えば息を殺して見入った、それくらい面白かった。
いやあ、私が鏡子夫人だったらやってられない。即刻家出してしまう。そんなご夫婦の像。
漱石夫妻がたたかっているなら、その夫婦を演じていた尾野真千子さん長谷川博己長谷川さんも役者同士たたかっていて。
ドラマがより厚みを増していた。
全4話観終わった後、がぜん漱石周辺人たちのことが知りたくなった。興味津々野次馬根性丸出し。
まず最初に読んだのが、夫妻の長男の純一さんの長男、夫妻にとっては孫夏目房之介さんのエッセイ集。
『漱石の孫』 
NHKのテレビ番組「漱石の孫、ロンドンに行く」という企画に便乗して、ロンドンの漱石が下宿していた部屋を訪ねる。
漱石と号した僕の祖父が、ちょうど百年前に、ロンドンのこの部屋で文学を相手に苦闘した。
その元下宿部屋に、今僕はいる。
けれど、僕は漱石に会ったこともない。長男だった父・純一が9歳のとき、漱石は他界している。
思いのほか小さなその部屋に入ると、突然不思議な感情がわきあがった。
その不思議な感情を解き明かそうと多方面から迫っていく。期待に反して漱石の人となりのことはほぼ出てこない。あとがきに
『漱石の孫』という本なのだから、漱石という文豪の存在によって被った迷惑や肉親の話だけをつなげて書いても書けそうなものだ。
が、途中でマンガ論の解説が入り、やや歴史背景の話しに深入りし、心理分析の真似事までしている。
もっとシンプルに、ただ文豪漱石と僕について書けなかったものか。
とある。読み手としては「そのとおり」と言わざるを得ない。うーん野次馬根性を満たすには他の本がなものかと。
次に手に取った本がこれ。
漱石の妻鏡子さんが晩年、孫の半藤末利子さんに
「いろんな男の人を見てきたけど、あたしゃお父様(漱石)が一番いいねぇ」
と目を細めておっしゃったという末利子さん自身の一文を読み、このドラマはそれを書けば良いのだと思いました。
というドラマの脚本家池端俊策さんの一文に惹かれて。
半藤末利子さん『漱石の長襦袢』 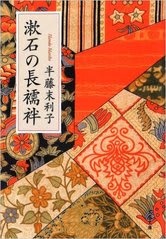
私の母(筆子)は、鏡子が度外れて豪胆であったからあの漱石と暮らしていけたのだ、と
「お祖母ちゃまが普通の女の人だったらそうそうと逃げ出すか、気が変になるか、自らの命を絶っていたことでしょうよ」
といつも鏡子を庇っていた。
ああやはり。ドラマ観て思ったことはその通りなんだと。漱石夫妻の長女の感慨は重い。
初めてご夫婦(夫は半藤一利さん)でエステに行ったときのことを、
なんで毎朝顔を洗うか洗わないかの夫の方が美肌なのか。
生まれつき面の皮の熱い男には適わないということかしら。なんて書くくらい歯に衣着せず、ときに辛口毒舌末利子さん。
漱石のお弟子さんに対してもなかなか辛辣な批評。
そして祖母鏡子さんのことも身内といえど客観的な目で、でもそこはそれ身内だからこその愛あふれる感情も率直に。
手の込んだ料理は表に食べにいくか、表から取るというのが鏡子流である。
「今晩のすき焼きは美味しかった」と漱石がほめようものなら毎晩でもすき焼きを出し続ける奥さんである。
こんなおばあ様だから美味しいものが大好きなおじい様もさぞや閉口したのではないか、と。
母筆子は「私はああはなりたくない」いう思いが知らぬ目に植え付けられていったようである、なかなか冷静な目で見ている。
「修善寺の大患」と言われている漱石大喀血のときの様子を一部始終見ていたお部屋係さんの話が伝わっていて、
その老舗旅館の大女将は
「修善寺では鏡子奥様は素晴らしい御立派な女性と語り継がれておりまして悪口を言うものは
一人もおりません。なぜ悪妻と呼ばれていらっしゃるのか私どもにはわかりません」
と末利子さんに話してくれて、面映ゆくもあったが私は心持よかったとの感想を述べている。
漱石も「お前には本当に世話になった」と回復後心から深謝した。とあるから、漱石だってまんざらなじゃないのね。(えらそうか)
巻末に母筆子さんの『夏目漱石の「猫」の娘』(松岡筆子)が掲載されている。
私の中に蘇る父の記憶は、愛情と重なって投影されることは少ないのです。
妹たちとは別の、何か近寄りがたい、恐ろしい父の像なのです。
そうした想い出が、骨がらみとなって、一生離れずじまいとなったとでも申しましょうか
とにかくこれはこの上ない不幸、いいえ不孝なことでございます。
修善寺の大患以降、漱石は穏やかで優しくなったという。
弟たちと相撲をとっていて 漱石は不利になると助けを呼ぶ、妹たち二人は駆け付ける、4対1の大ずもう。
それはそれは滑稽な姿になるのが再々だそうだが。
それでも。
筆子さんと恒子さんの二人だけは、只笑って見物しているだけで、決してこの取っ組み合いにまざる気にはならなかったと。
いかに幼少時、父である漱石に理不尽で暴力的な扱いを受けたことかが想像できて痛ましい。
それでもやはり親子、最後にこう結んでいる。
父にもっと生きていて欲しかった、そして生きている間に、父との距離を、もっと狭めたかったという想いは、
年を重ねるたびに、強くなっていくようでございます。
1966(昭和41年)3月
こうなったら、後は鏡子夫人の著作を読まねば、と意気込んでいる次第。















