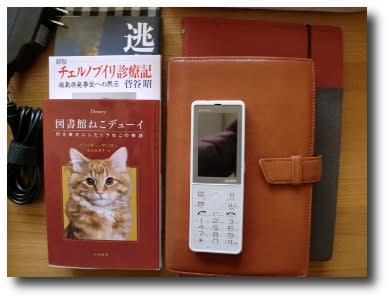1988年1月の寒い朝、米国アイオワ州のスペンサーという小さな町にある公立図書館のブックポストに、小さな子猫が入っていて、今にも凍死しそうな状態で発見されます。新任一年目を過ぎた図書館長であった著者は、子猫をなんとか助けることができましたが、問題は図書館で子猫を飼うことを理事会が認めるかどうかでした。町の条例には、公共施設で猫を飼ってはならないという規則がないことを確認し、猫が図書館利用に資するという論旨で理事会に諮り、許可を取り付けます。このあたりの大胆で緻密な動きは、いかにもアメリカの行動的な女性のタイプだなと感じます。
そういうわけで、町の小さな公立図書館で飼われることになった子猫は、図書の十進分類法の生みの親の名前にちなんで、デューイ・リードモア・ブックスと名づけられ、図書館のアイドルとなっていきます。それは、たとえばこんなふうでした。
同時に、図書館ねこデューイと強く結ばれたこの女性館長の人生も、少しずつ明らかにされていきます。それは、次々と不幸に見舞われながらも、それを乗り越えてきた年月でした。そして、後半の18年を支えてきたのが図書館の仕事であり、デューイの存在だったようです。本書中のあちこちに見られる記述、たとえば:
このような記述は、著者の人間観察の深さを感じさせます。でも、国際的に有名になった図書館ねこが老いてしまったとき、辛い決断が待っているのでした。
○
ハヤカワ文庫、ヴィッキー・マイロン著『図書館ねこデューイ~町を幸せにしたトラねこの物語』(羽田詩津子訳)です。思わず引き込まれる、読み応えのある一冊でした。
そういうわけで、町の小さな公立図書館で飼われることになった子猫は、図書の十進分類法の生みの親の名前にちなんで、デューイ・リードモア・ブックスと名づけられ、図書館のアイドルとなっていきます。それは、たとえばこんなふうでした。
ある年配の男性は毎朝同じ時刻にやってきて、同じ大きな居心地のいい椅子にすわって新聞を読んだ。奥さんは最近亡くなり、一人暮らしだときいていた。わたしは彼が猫好きだとは思っていなかったが、デューイが初めてひざに登った瞬間から、満面に笑みを浮かべた。彼は新聞を読むときにもはや一人ではなくなったのだ。「ここで暮らして幸せかい、デューイ?」老人は毎朝たずねては、新しい友人をなでてやった。デューイは目を閉じて、たいてい眠りこんだ。
同時に、図書館ねこデューイと強く結ばれたこの女性館長の人生も、少しずつ明らかにされていきます。それは、次々と不幸に見舞われながらも、それを乗り越えてきた年月でした。そして、後半の18年を支えてきたのが図書館の仕事であり、デューイの存在だったようです。本書中のあちこちに見られる記述、たとえば:
デューイは驚くようなことをするせいで特別だったのではなく、彼自身が驚くべき存在だったから特別だったのだ。彼は一見ごくありふれた人間を連想させた。知り合うまでは、人ごみで目立たない存在。仕事をさぼったり、文句をいったり、分不相応なものを求めたりしない人間。彼らはすばらしいサービスを提供することを信条としている、有能な司書や車のセールスマンやウェイトレスだ。仕事に対して情熱があるので、仕事以上の働きをする人々。彼らは人生でどういうことをなすべきかを知っていて、それをきわめて上手にこなす。(中略)あるいは店員。銀行の窓口係。自動車修理工。母親。世の中は個性的で目立ち、金持ちで利己主義の人間に目を向けがちで、ありふれたことをきわめてちゃんとこなしている人々には気づかないものだ。
このような記述は、著者の人間観察の深さを感じさせます。でも、国際的に有名になった図書館ねこが老いてしまったとき、辛い決断が待っているのでした。
○
ハヤカワ文庫、ヴィッキー・マイロン著『図書館ねこデューイ~町を幸せにしたトラねこの物語』(羽田詩津子訳)です。思わず引き込まれる、読み応えのある一冊でした。