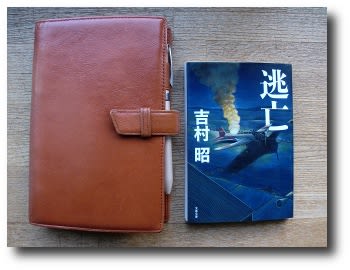吉村昭著『逃亡』を読みました。文春文庫(新装版)です。
本作品の主人公、望月幸司郎は、福島の農村の次男坊で、霞ヶ浦の海軍航空隊で整備兵として地味な生活を送っています。ある日、兄の紹介で慰問に来た女性の招きで、川崎の自宅を訪問、楽しい時間を過ごしますが、帰りの上野駅では、土浦を通過する常磐線の終列車がすでに発車した後でした。翌朝の始発まで待っていては、過酷な制裁を受けなければなりません。水兵服を着て狼狽する彼を見て、ソフト帽をかぶった四十歳くらいの男が声をかけてきます。男の貨物トラックに乗せてくれるというのです。上野から土浦まで、手賀沼のふちを迂回するように走りながら、航空隊の見学はできるのかとたずねられ、幸司郎は「できる」と答えます。無事に隊に戻れた昭和18年の晩秋、ある日曜日の午後に、トラックに乗せてくれた男が面会に来ます。そして、航空隊を見学させてくれたお礼に、翌週の日曜に、ご馳走すると言います。知り合いもない幸司郎は、山田と名乗る男に親近感と信頼を覚え、男の知人が経営する繊維会社が製造し海軍に売り込む参考とするため、数日だけ落下傘を借用したいという頼みを、つい承諾してしまいます。
持ち出した落下傘を、約束どおり返してもらったものの、元の場所に戻す機会をうかがっているうちに、落下傘一個の不足が発覚、捜索が始まってしまいます。一つのボタンの掛け違いが別の不都合を生むように、落下傘の不足を埋め合わせるために、男に指示されたのは、九七式艦上攻撃機を燃やしてしまうというものでした。
○
名を変え、姿を変え、苦しい逃亡生活が始まります。しかし、生活はしていかなければなりません。逃げ込む場所は、軍属という名の、実態はタコ部屋というところで、残酷な監督が逃亡者に制裁を加える、過酷な労働の日々でした。しかし、それでも軍法会議と銃殺刑におびえる軍隊生活よりはましだったのでしょうか。敗戦の玉音放送を聞き、占領軍に保護を願い出ます。そして、さらに五年間、諜報工作員として占領軍に使われます。
プロローグの奇妙な電話は、戦後も心休まることのなかった望月幸司郎の日々をより効果的に表すべく工夫された、作家による小説的な想定なのだろうと思います。古くは高野長英や、昭和の脱獄囚など、逃亡記を得意とする作家の、この分野の代表作と言ってよいでしょう。
本作品の主人公、望月幸司郎は、福島の農村の次男坊で、霞ヶ浦の海軍航空隊で整備兵として地味な生活を送っています。ある日、兄の紹介で慰問に来た女性の招きで、川崎の自宅を訪問、楽しい時間を過ごしますが、帰りの上野駅では、土浦を通過する常磐線の終列車がすでに発車した後でした。翌朝の始発まで待っていては、過酷な制裁を受けなければなりません。水兵服を着て狼狽する彼を見て、ソフト帽をかぶった四十歳くらいの男が声をかけてきます。男の貨物トラックに乗せてくれるというのです。上野から土浦まで、手賀沼のふちを迂回するように走りながら、航空隊の見学はできるのかとたずねられ、幸司郎は「できる」と答えます。無事に隊に戻れた昭和18年の晩秋、ある日曜日の午後に、トラックに乗せてくれた男が面会に来ます。そして、航空隊を見学させてくれたお礼に、翌週の日曜に、ご馳走すると言います。知り合いもない幸司郎は、山田と名乗る男に親近感と信頼を覚え、男の知人が経営する繊維会社が製造し海軍に売り込む参考とするため、数日だけ落下傘を借用したいという頼みを、つい承諾してしまいます。
持ち出した落下傘を、約束どおり返してもらったものの、元の場所に戻す機会をうかがっているうちに、落下傘一個の不足が発覚、捜索が始まってしまいます。一つのボタンの掛け違いが別の不都合を生むように、落下傘の不足を埋め合わせるために、男に指示されたのは、九七式艦上攻撃機を燃やしてしまうというものでした。
○
名を変え、姿を変え、苦しい逃亡生活が始まります。しかし、生活はしていかなければなりません。逃げ込む場所は、軍属という名の、実態はタコ部屋というところで、残酷な監督が逃亡者に制裁を加える、過酷な労働の日々でした。しかし、それでも軍法会議と銃殺刑におびえる軍隊生活よりはましだったのでしょうか。敗戦の玉音放送を聞き、占領軍に保護を願い出ます。そして、さらに五年間、諜報工作員として占領軍に使われます。
プロローグの奇妙な電話は、戦後も心休まることのなかった望月幸司郎の日々をより効果的に表すべく工夫された、作家による小説的な想定なのだろうと思います。古くは高野長英や、昭和の脱獄囚など、逃亡記を得意とする作家の、この分野の代表作と言ってよいでしょう。