津々堂さんのブログ「津々堂のたわごと日録」に江戸前期の熊本藩士・山崎半彌が著した「歳序雑話」に書かれた祇園社(現在の北岡神社)の「祇園会(ぎおんえ)」のことが紹介されていた。かつてこの祭は旧暦6月14日に行われていた。今年の暦に変換すると7月31日に当たるらしい。
この「歳序雑話」については以前僕もブログに取り上げたことがあるが、祇園社の下を流れる坪井川には遊舟が浮かべられ、舟上では酒食とともに音曲を楽しむ風景が描かれている。その中で気になったのが「倡瞽ハ淫楽ノ器ヲ鳴シ、淫風ノ歌ヲ謳ウ」という一節。これは「盲人の音楽家がみだらな楽器を演奏し、みだらな歌を唄う」という意味に解釈できるが、「みだらな音楽:淫楽」という表現が気になった。山崎半彌という藩士は陽明学にも明るかった識者と伝えられるので、江戸前期の儒者熊沢蕃山の著書「集義和書」(1676年頃)を読んでいたと考えられる。その「集義和書」の中に「天下の人心、正楽なき時は、必ず淫楽(インガク)をこるものなり」という一節がある。ここでいう「正楽」とは雅楽や武家の式楽である「謡曲」などを指し、「淫楽」とはいわゆる民俗楽を指したものらしい。山崎はこの「淫楽」という言葉を引用したと考えられる。つまり武家社会と百姓・町人との厳然たる差別を表した言葉ということだろう。

その昔、祇園会で倡瞽が淫楽を奏でた坪井川・一駄橋付近(宗禅寺より)
「淫楽」とされた「古浄瑠璃」の一つ「外記節」は江戸後期に廃れていたが、十代杵屋六左衛門が「外記節」を長唄に取り入れ、「外記猿」などの新しい長唄を創った。
この「歳序雑話」については以前僕もブログに取り上げたことがあるが、祇園社の下を流れる坪井川には遊舟が浮かべられ、舟上では酒食とともに音曲を楽しむ風景が描かれている。その中で気になったのが「倡瞽ハ淫楽ノ器ヲ鳴シ、淫風ノ歌ヲ謳ウ」という一節。これは「盲人の音楽家がみだらな楽器を演奏し、みだらな歌を唄う」という意味に解釈できるが、「みだらな音楽:淫楽」という表現が気になった。山崎半彌という藩士は陽明学にも明るかった識者と伝えられるので、江戸前期の儒者熊沢蕃山の著書「集義和書」(1676年頃)を読んでいたと考えられる。その「集義和書」の中に「天下の人心、正楽なき時は、必ず淫楽(インガク)をこるものなり」という一節がある。ここでいう「正楽」とは雅楽や武家の式楽である「謡曲」などを指し、「淫楽」とはいわゆる民俗楽を指したものらしい。山崎はこの「淫楽」という言葉を引用したと考えられる。つまり武家社会と百姓・町人との厳然たる差別を表した言葉ということだろう。

その昔、祇園会で倡瞽が淫楽を奏でた坪井川・一駄橋付近(宗禅寺より)
「淫楽」とされた「古浄瑠璃」の一つ「外記節」は江戸後期に廃れていたが、十代杵屋六左衛門が「外記節」を長唄に取り入れ、「外記猿」などの新しい長唄を創った。
2015.12.23 花童あやの卒業公演より















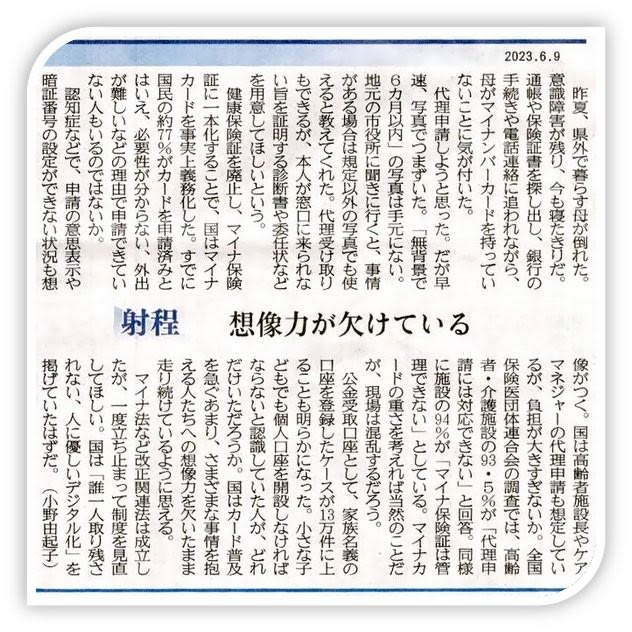









 (英語版)
(英語版) 僕がこれまで中村花誠先生からお聞きしたことも含め、知り得る限りのことをお答えすると、基本的に日本舞踊は無表情であること。所作や動きなど一つ一つに意味があり、体全体で表現するものであり、「顔で踊ってはいけない」ともいわれているそうです。日本舞踊とは狭義には歌舞伎舞踊のことで、元をたどれば四百年前に出雲阿国が始めた「かぶき踊り」が起源といわれますが、阿国の「かぶき踊り」は能をもとにしているから無表情だという説もあるそうです。
僕がこれまで中村花誠先生からお聞きしたことも含め、知り得る限りのことをお答えすると、基本的に日本舞踊は無表情であること。所作や動きなど一つ一つに意味があり、体全体で表現するものであり、「顔で踊ってはいけない」ともいわれているそうです。日本舞踊とは狭義には歌舞伎舞踊のことで、元をたどれば四百年前に出雲阿国が始めた「かぶき踊り」が起源といわれますが、阿国の「かぶき踊り」は能をもとにしているから無表情だという説もあるそうです。