「大阪でビバった旅行記 #2-3」のつづきです。
「#2-3」で京都鉄道博物館の特徴を以下の3点に整理しました。
 SLが煙と蒸気を吐きながら
SLが煙と蒸気を吐きながら レールの上を走る
レールの上を走る 車両だけでなく、システムとしての鉄道の仕組みと歴史を観られる
車両だけでなく、システムとしての鉄道の仕組みと歴史を観られる 旧国鉄 & JR西日本だけでなく、私鉄にも敬意が払われている
旧国鉄 & JR西日本だけでなく、私鉄にも敬意が払われている
せっかくですので、この観点から京都鉄道博物館をふり返ってみます。

前身の梅小路蒸気機関車館の保存車両(SL)に、交通科学博物館の保存車両(SL)も加わって、扇形車庫は満車 状態
状態
20両の保存車両(SL)のうち、8両が動態保存 されていて、SLが煙と蒸気を吐き、熱を発散しながら目の前を走る、あるいは、SLが牽引する車両に乗れるという、貴重な体験ができます。
されていて、SLが煙と蒸気を吐き、熱を発散しながら目の前を走る、あるいは、SLが牽引する車両に乗れるという、貴重な体験ができます。
近づくと、注意書き が結構しつこい…
が結構しつこい…
煙が衣服につくと汚れる、とか、
煙や水しぶき が飛ぶ、とか、大きな汽笛
が飛ぶ、とか、大きな汽笛 が鳴る、とか、
が鳴る、とか、
機関車に触るとやけど 等の危険
等の危険 があるとか、煙・スス、熱
があるとか、煙・スス、熱 、蒸気
、蒸気 、超やかましい汽笛
、超やかましい汽笛 といったものは、SLには付きものなのですが、SLが全然一般的でなくなってしまった現代では、こうした注意
といったものは、SLには付きものなのですが、SLが全然一般的でなくなってしまった現代では、こうした注意 をしておかないとトラブルの元
をしておかないとトラブルの元 になってしまうんでしょうなぁ…
になってしまうんでしょうなぁ…
私が幼少のみぎり、私の故郷ではまだSLが走っていまして 、あの煤煙の臭いとか、発する熱気といったものを漠然と覚えています。
、あの煤煙の臭いとか、発する熱気といったものを漠然と覚えています。
2011年3月に梅小路蒸気機関車館にやってきたとき、その臭いを超久しぶりに嗅いだんでしたっけねぇ…
んでもって、私がずっと不思議に思っていたことがあります。
それは、SLの煙突の一番上がグルグル回っていた ということ。
ということ。
仕組みも判らなければ、そもそも、何のために回っていたのかも判らない… 、でも判らなくても生活に支障は生じない…なんて状況で、記憶の中に埋もれていたこの疑問が、京都鉄道博物館の扇形倉庫で突如掘り起こされ
、でも判らなくても生活に支障は生じない…なんて状況で、記憶の中に埋もれていたこの疑問が、京都鉄道博物館の扇形倉庫で突如掘り起こされ 、解決に至りました
、解決に至りました
説明板 によれば、「回転火の粉止め(Spark arrester)」という、元も子もない名前
によれば、「回転火の粉止め(Spark arrester)」という、元も子もない名前 の装置だそうで、
の装置だそうで、
煙突の上部に取り付けられる部品で、煙突からの排気の勢いで羽(ファン)が回転し、煙とともに発生した火の粉を粉砕し、火の粉による沿線火災を防止します。
という仕組みと機能なのだそうな。
うん十年の時を超えて、疑問が解決するとは、幸せ でございました。
でございました。
ところで、SLが動くためには、石炭と水 が必要です。
が必要です。
というか、石炭(熱源)と水があれば動くわけで、自動車やディーゼル車、電車などに比べれば、かなりシンプルな機関です。
水蒸気 の圧力をピストン&シリンダーで往復運動に変えて、それをクランクで回転運動に変える仕組みは、水蒸気
の圧力をピストン&シリンダーで往復運動に変えて、それをクランクで回転運動に変える仕組みは、水蒸気 の圧力をガソリンや軽油の爆破力
の圧力をガソリンや軽油の爆破力 に置き換えれば、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンと同じですな。
に置き換えれば、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンと同じですな。
んでもって、SLのピストンと、
シリンダーも拝見いたしました。
んん~~ん、楽しい
 つづき:2017/05/22 大阪でビバった旅行記 #2-5
つづき:2017/05/22 大阪でビバった旅行記 #2-5














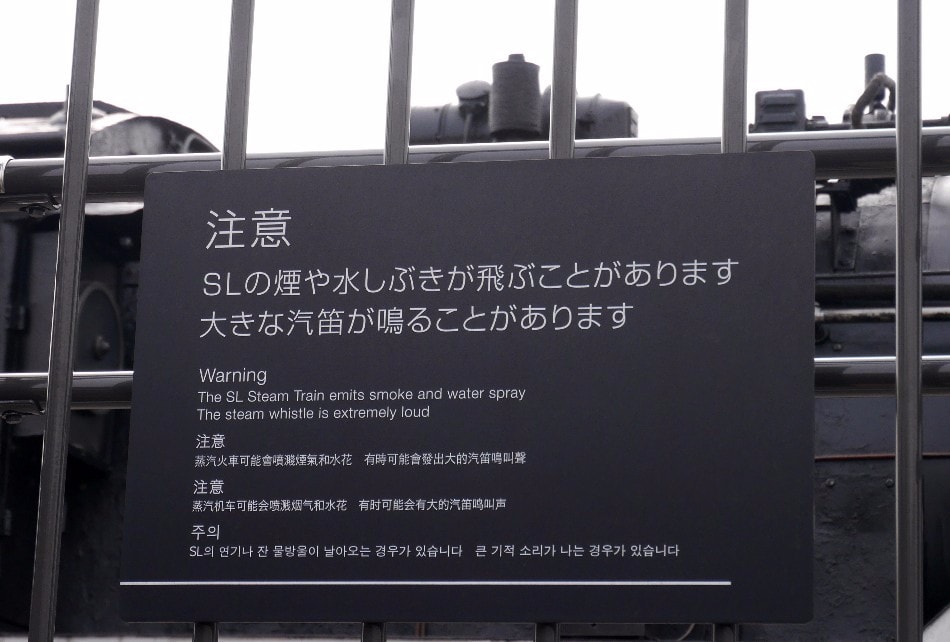
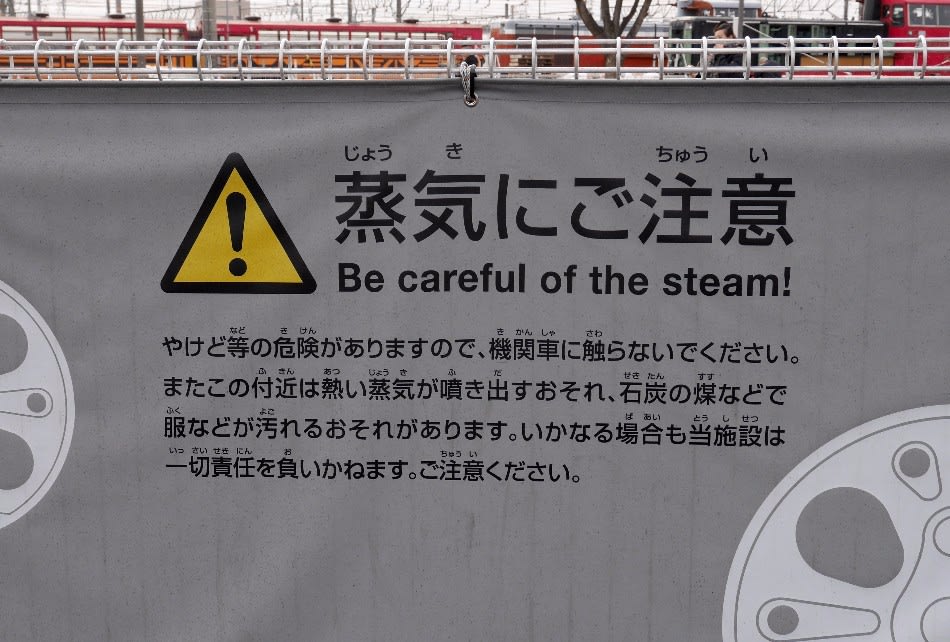



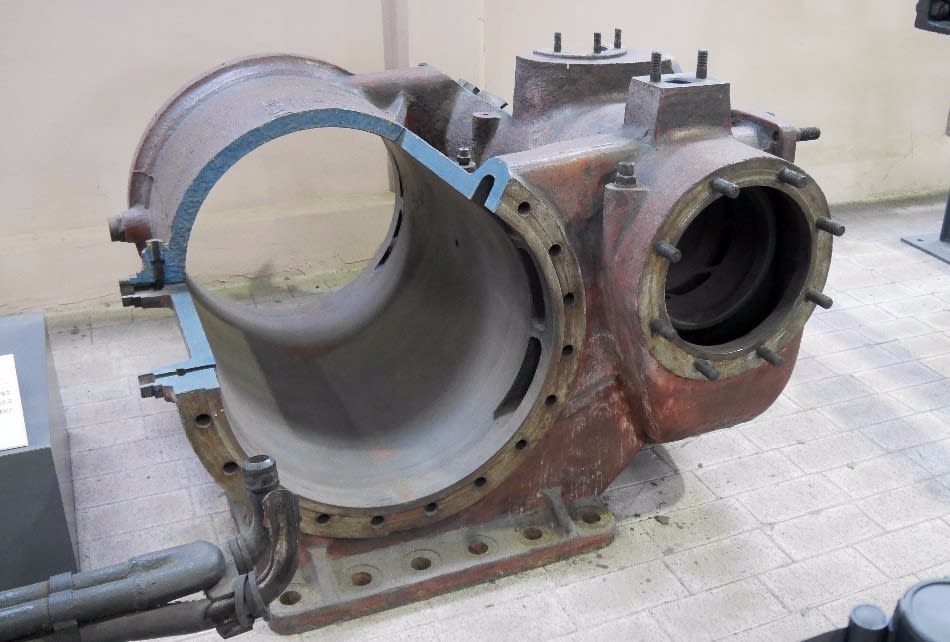






 、ずいぶんと
、ずいぶんと



 によれば、
によれば、 を確保するには、あまりにも
を確保するには、あまりにも 、
、 と考えています。
と考えています。 化
化






