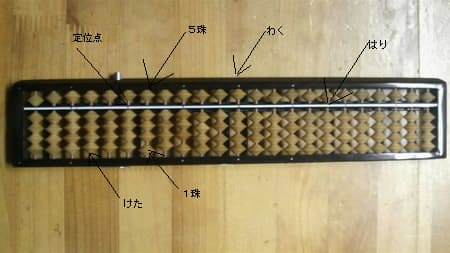さて今日は「集中力」です。
たとえば、入学後およそ1年前後で到達するレベル「検定7級」では。かけ算を例にしますと、2桁×2桁の問題を計算する過程において、9回前後の指先操作を要求されます。計算中は、かけ算九九を4回唱え、4桁の答えを記入します。その間、一度のミスも許されません。この問題を20回繰り返すと規定問題数を計算し終えたことになります。指先の動きは、約200回程度になります。小学校で九九を学習していない1年生でも、この程度は楽にこなしてしまいます。計算間違えの原因のほとんどが「途中で目を離す」ことに起因します。学習している本人の「できるようになりたい」と思う心が育った時点で、集中力も育ちます。
さらに、進んで1級まで到達しますと、6桁×5桁の問題を計算する過程において、100回以上の指先操作を要求されます。計算中は、かけ算九九を30回唱え、11桁の答えの記入が求められます。指先の動きは、約2000回程度になります。
このかけ算20問。制限時間は10分間なんですよ。ちょうど今はやりの学習時間を区切って、複数の中身を一つの授業時間で行う「モジュール授業」の1モジュールがおおよそ15分ですから、昔からそろばんの1種目は子供たちの集中力の持続時間を経験的に把握していたんでしょうね。
このことから「指先は外に出た脳」と言われていますように、ソロバン学習が指先トレーニングによって集中力を育てていることがおわかりいただけると思います。
そろばん学習でステップアップしていく過程で、訓練するレベルもステップアップし、集中力もステップアップする。という好循環を生み出すことになります。
指導時に子供たちを見ていますと、小学3年生以下の場合はそろばん6級、4年生~6年生で4級、に合格すると集中力が「ついてきたな!」と感じます。
たとえば、入学後およそ1年前後で到達するレベル「検定7級」では。かけ算を例にしますと、2桁×2桁の問題を計算する過程において、9回前後の指先操作を要求されます。計算中は、かけ算九九を4回唱え、4桁の答えを記入します。その間、一度のミスも許されません。この問題を20回繰り返すと規定問題数を計算し終えたことになります。指先の動きは、約200回程度になります。小学校で九九を学習していない1年生でも、この程度は楽にこなしてしまいます。計算間違えの原因のほとんどが「途中で目を離す」ことに起因します。学習している本人の「できるようになりたい」と思う心が育った時点で、集中力も育ちます。
さらに、進んで1級まで到達しますと、6桁×5桁の問題を計算する過程において、100回以上の指先操作を要求されます。計算中は、かけ算九九を30回唱え、11桁の答えの記入が求められます。指先の動きは、約2000回程度になります。
このかけ算20問。制限時間は10分間なんですよ。ちょうど今はやりの学習時間を区切って、複数の中身を一つの授業時間で行う「モジュール授業」の1モジュールがおおよそ15分ですから、昔からそろばんの1種目は子供たちの集中力の持続時間を経験的に把握していたんでしょうね。
このことから「指先は外に出た脳」と言われていますように、ソロバン学習が指先トレーニングによって集中力を育てていることがおわかりいただけると思います。
そろばん学習でステップアップしていく過程で、訓練するレベルもステップアップし、集中力もステップアップする。という好循環を生み出すことになります。
指導時に子供たちを見ていますと、小学3年生以下の場合はそろばん6級、4年生~6年生で4級、に合格すると集中力が「ついてきたな!」と感じます。