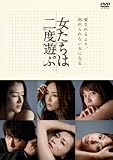あと、実際に記述してみて書きにくいと感じたのは、個別の指導計画の具体的な取組のねらいについては、どの項でもあらかじめ5つの力の区分の枠か記載されていること。
5つに分けて考えてみるのはいいと思います。とりわけ、短期的あるいは長期的な視点で「社会(家庭・地域)で豊かに暮らす力 」について、考えてみることは意味があり、必要でもあると思いました。
しかし、これ、あらかじめ5つの枠が全部にいりますか。枠があった方がいいでしょうか。私はこの枠はない方がいいと思います。視点として5つの力ということで考えてみるのはいいのだけれど、文書としてあらかじめその枠があると、記述する時にそれにとらわれがちになることがあります。また、並列的にあらかじめ項目の枠が設定されていると、つまり、その授業なり教育活動でのもっとも重要なポイントはなんなの?、というのがパッと見てわかりにくい。
だから、例えば、その授業での中心的なねらいは太字にして最初に上の方に書く。で、それが5つの力のどれに関わっているかというのは、ねらいの文末に、例えば<健康>とかいうように記入すればいい、それでわかるから。
こうすると、その教育活動での中心的なねらいと副次的なねらい、こういう面もあるし、大事にはしたいねといったことの位置づけが見てわかりやすいです。
今だと、あてはまらないねらいのところは「*」のマークを記入したりしていますが、こういうことをする必要もないということになります。
全体の文書の量もこうすれば幾分かはコンパクトになるかもしれません。
それから、やはりポイントになるのは「評価」。
「評価」とは何かということはやはり考え共通理解しておく必要がある。
で、最近、よく言われる、指摘されたりするのが、授業なり取り組みの中での子どもの様子の記述、これは評価ではありませんよと。そうなのかな?。
様子を記述するということは、無数にある子どものいろんな状況の中から意味がある、大事だと思う、そういう事実を、その評価をする人、書く人が抽出してくる、選択して整理して記述するわけで、それはもう評価の一部というか根本というか基礎というか、評価そのものというか、だと思います。
だって、そういうことがあって、それがいいのか悪いのか、できてるのか、できてないのか、どうできてるのか、どういうところが難しいのか、それはなんで?、課題そのものが合わない?、目標の設定そのものが適切でないのかなぁ、あるいは、手立てですか。目標は合ってる、それをどう子どもに合った形で具体的に提示できているのか、そういうこっちの手立ての問題ですか、とか、そういうことに発展していくわけでね。
だから、まあ、あまり冗長にならない範囲で、重要だと思う様子はきちんと記述した上で、それがどうだったのかという評価的なことを書く、記録的な意味でもそういうことが必要かと思います。
区別するのであれば、そうした子ども自身の評価と、こちら、指導者側の手立てなり教育方法とか配慮点とか、そういうことはこれはなるべくごっちゃにしないで記述した方がいいのではないかなと。
なので、全体としては目標を記述する欄はなるべくコンパクトに、で、評価とか手立てを記述する欄を枠としてなるべく広く設定した方がいいのではないか、
とか、前期の個別の指導計画の評価のところを書いていて思ったのでした。
というのは、私の個人としての感想なり意見ですが、まあ、こうしたいろんな意見をうまく集約しつつ一定の改善の方向性なり具体案を検討していく、2学期はいろいろあるでしょうけど、3学期から次年度に向けては、そういうことが大切になってくるのではないかと思った次第です。
5つに分けて考えてみるのはいいと思います。とりわけ、短期的あるいは長期的な視点で「社会(家庭・地域)で豊かに暮らす力 」について、考えてみることは意味があり、必要でもあると思いました。
しかし、これ、あらかじめ5つの枠が全部にいりますか。枠があった方がいいでしょうか。私はこの枠はない方がいいと思います。視点として5つの力ということで考えてみるのはいいのだけれど、文書としてあらかじめその枠があると、記述する時にそれにとらわれがちになることがあります。また、並列的にあらかじめ項目の枠が設定されていると、つまり、その授業なり教育活動でのもっとも重要なポイントはなんなの?、というのがパッと見てわかりにくい。
だから、例えば、その授業での中心的なねらいは太字にして最初に上の方に書く。で、それが5つの力のどれに関わっているかというのは、ねらいの文末に、例えば<健康>とかいうように記入すればいい、それでわかるから。
こうすると、その教育活動での中心的なねらいと副次的なねらい、こういう面もあるし、大事にはしたいねといったことの位置づけが見てわかりやすいです。
今だと、あてはまらないねらいのところは「*」のマークを記入したりしていますが、こういうことをする必要もないということになります。
全体の文書の量もこうすれば幾分かはコンパクトになるかもしれません。
それから、やはりポイントになるのは「評価」。
「評価」とは何かということはやはり考え共通理解しておく必要がある。
で、最近、よく言われる、指摘されたりするのが、授業なり取り組みの中での子どもの様子の記述、これは評価ではありませんよと。そうなのかな?。
様子を記述するということは、無数にある子どものいろんな状況の中から意味がある、大事だと思う、そういう事実を、その評価をする人、書く人が抽出してくる、選択して整理して記述するわけで、それはもう評価の一部というか根本というか基礎というか、評価そのものというか、だと思います。
だって、そういうことがあって、それがいいのか悪いのか、できてるのか、できてないのか、どうできてるのか、どういうところが難しいのか、それはなんで?、課題そのものが合わない?、目標の設定そのものが適切でないのかなぁ、あるいは、手立てですか。目標は合ってる、それをどう子どもに合った形で具体的に提示できているのか、そういうこっちの手立ての問題ですか、とか、そういうことに発展していくわけでね。
だから、まあ、あまり冗長にならない範囲で、重要だと思う様子はきちんと記述した上で、それがどうだったのかという評価的なことを書く、記録的な意味でもそういうことが必要かと思います。
区別するのであれば、そうした子ども自身の評価と、こちら、指導者側の手立てなり教育方法とか配慮点とか、そういうことはこれはなるべくごっちゃにしないで記述した方がいいのではないかなと。
なので、全体としては目標を記述する欄はなるべくコンパクトに、で、評価とか手立てを記述する欄を枠としてなるべく広く設定した方がいいのではないか、
とか、前期の個別の指導計画の評価のところを書いていて思ったのでした。
というのは、私の個人としての感想なり意見ですが、まあ、こうしたいろんな意見をうまく集約しつつ一定の改善の方向性なり具体案を検討していく、2学期はいろいろあるでしょうけど、3学期から次年度に向けては、そういうことが大切になってくるのではないかと思った次第です。