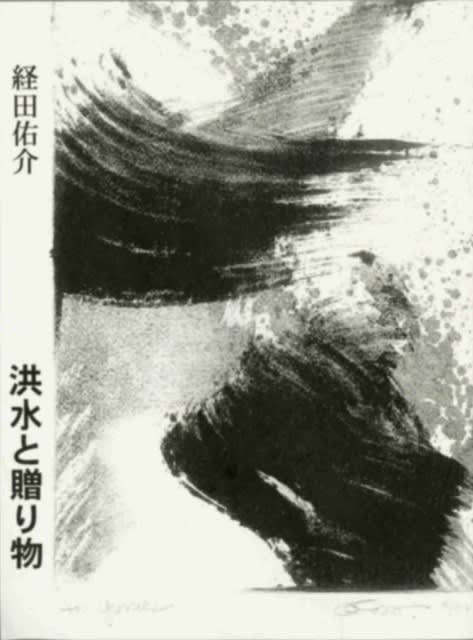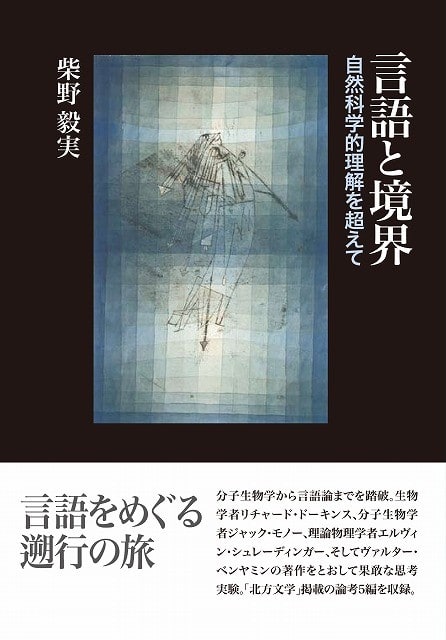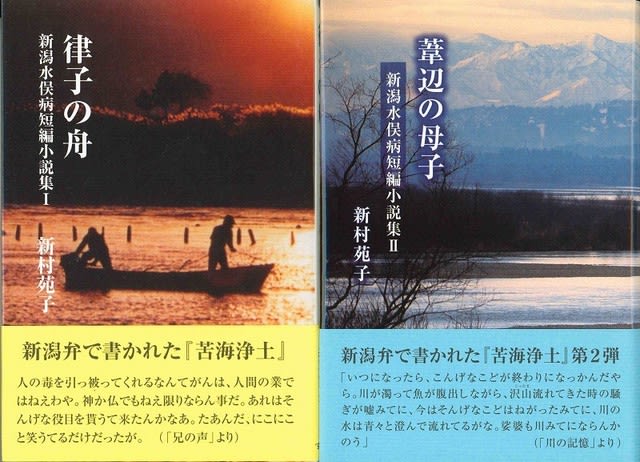中村龍介はわたしと同じ1951年生まれで、1973年に処女詩集『世界の片隅で』を出版し、1978年12月26日、経田さんが「師走、信濃川/歩いて歩いてあんたは入ってった」と書いているようにして自殺した。
中村は分裂病者であった。彼の存在と言葉は私には重荷であった。彼が死んだ後に私は、死者というものは甦るものであるということを初めて知った。死者はキリストの復活のように甦る。ただし、肉体としてではなく、言葉として。私の胸の内に。
そんなわけで中村の死の二年半後、私は彼の残した詩編をまとめて『中村龍介詩集』を編集し、出版した。
経田さんはこの『中村龍介詩集』を読んで、作品を書いたのであろう。「死者をあがめてはならない」という言葉は、中村の「火の祭」という作品の冒頭の一行である。そして経田さんもまた、中村の甦りについて書くのである。
「生誕の夜、
死者は
水底から還ってきた、
ことばのために」
しかし、そんなことばもむなしく消えていくものであることを、経田さんは残酷にも指摘する。
「雪に刻んだ、あんた、最後のことばも
もう消えてしまったよ。
それっきりさ。」
もはやここに、経田さんの皮肉や底意地の悪さを見ることは出来ない。自分もまた死ねば、「最後のことばも消えてしまって、それっきり」だという認識を読み取るべきである。そこにはだから経田さん流の深いペシミズムがある。ペシミズムは他者に向かい、自己にも向けられる。37人のさまざまな死に方をした死者たちがいる。しかし、自分自身もまた未然の死を生きているのにすぎない。
だから「死者をあがめてはならない」のだ。経田さんの37人の死者に対するスタンスは一貫しているが、そこに軽重があるのもまた事実である。
3頁以上の長い作品を挙げれば、経田さんが深く傾倒している対象が分かるだろう。ジャック・ケルアック(アッケル・クヮジャ)、パウル・ツェラン(ウル・パツェンラ)、田端あきら子(コアラ・キタタバ)、シモーヌ・ヴェイユ(シモーヴェ・ユイヌ)、ヴィンセント・ゴッホ(セント・ヴィ・ゴホンツ)、アルチュール・ランボー(チューラン・アルルボー)、ジャニス・ジョプリン(ニジャ・J・プリンス)、ガルシア・ロルカ(ルルシカ・ガロア)の8人である。
1970年パリのセーヌ川に死体の上がった、パウル・ツェランについての詩は、重厚で沈鬱、いささかも皮肉は感じられない。ナチスによるユダヤ人虐殺をテーマに詩を書いたツェランへの陰鬱なオマージュである。
「耳は夜の受話器にかしいでいる
声を待つ
骨つぼからばらばら砂が落ちる
声を待つ
焼死した
声を」
さらにスペイン内乱で銃殺されたガルシア・ロルカについての詩は、手放しの讃辞に近い。最終連を引く。
「ルルシカよ
あなたの死は
何百万という無名の死の
一つにすぎない
しかし あなたの詩は
わたしたちにとり
稀有な 高潔な
大きな謎なのだ」
ヘロイン中毒のため27歳で死んだブルース歌手、ジャニス・ジョプリンをテーマにした作品が入っているのも経田さんらしい。ジャニスは我々日本人にとっても真実のスターだった。ロック・ミュージシャンの死の中で、彼女の死ほど惜しまれたものはない。
ミュージシャンでは他に、ジミ・ヘンドリックスやチャーリー・パーカー、ジョン・コルトレーンなどが取り上げられている。いずれも麻薬や癌で夭逝した人たちである。
『洪水と贈り物』の紹介はこれで終わりにするが、この詩集がたった限定200部しか発行されていないということが信じがたい。なんということだ。
(この項おわり)