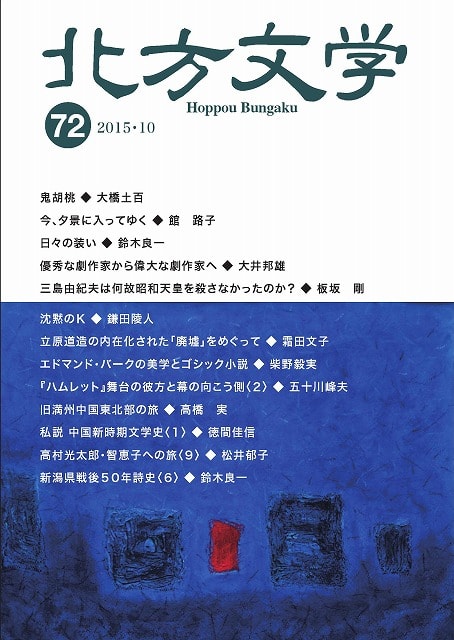ジェフリーさんの『わたしの日付変更線』は、言語論的なアポリアだけで成立していると私は書いた。そのことはジェフリーさんが故国を離れて、日本にいるときに強調されてくる。そのような位置をよく示しているのが「無縁という場」という1編である。
生まれ育った国へ
帰れなくなると
どの国でもないここに
わたしたちは 辿り着く
家族のいないわたしたち
愛されていないわたしたち
闇の境目を彷徨うわたしたち
狼に追いかけられたわたしたち
ここでは日本という国が「どの国でもないここ」と表現され、自身の帰属の不可能性が語られていくのだが、では日本語を使って喋ったり、書いたりしたらどうなるのだろう。不思議なことに彼の不可能な帰属意識が変容を始めるのである。つまり……。
その言葉を使い
お互いの存在を初めて知る
言葉の力で屋根の曲線のように
空中に持ち上げられる
その無国籍の言葉を聞き
追いかけてきた孤独の狼は
門外の闇に消えていく
『わたしの日付変更線』は「西へ」「東へ」「過去へ」「現在へ」「未来へ」の5つの章で構成されているが、「東へ」は日本での体験に基づいているだけに、最も言語論的である。タイトルからして「翻訳について」「文法のいない朝」「センテンスの前」などとあり、それらが言語論的体験を背景にしていることを明瞭に語っている。日本語体験は「センテンスの前」で次のように語られている。
ここでは何が起こったのか
有刺鉄線が地面に落ちている
言葉と ランゲージを隔てていた
国境は完全に崩れている
日本語というものが本来の出自を失って、かつては漢字の体系を受け入れ、現在では英語をも自在に受け入れる「バベルの塔以前の楽園(エデン)」であるというのである。確かにバベルの塔の崩壊によって言語の混乱を混乱として認識するキリスト教世界の住人と、日本人との決定的な違いはそこにある。もっと意地の悪い見方をジェフリーさんは次のような詩句で示している。
しかし アダムもエバもいない
言葉(ランゲージ)は奔放に交じり合うだけ
始まりも終わりもない乱交
知恵の身は 試食されないまま
木から重くぶら下がっている
言語論を通した日本人論をここに読み取ることが出来るが、それでもジェフリーさんは日本人が、あるいは日本が好きでたまらないのだ。だから文法を乗り越えた場所、あるいは翻訳の可能性の達成の中に、彼は至福の時間を見出すだろう。
ジェフリーさんは、二人の〝わたし〟が翻訳を通して同衾する可能性を、「翻訳について」という作品の中で夢想しているではないか。
二人のわたしはため息を漏らし
部屋は沈黙に戻ってしまう
シーツの下でおどおどして
お互いの手を取り
そしてしばらく天井を仰ぐ
やがて 抱きあい
赤の他人のように愛撫しあう
一個の完全な人格になれるように
この同衾の夢を高橋睦郎のように〝エロティック〟と呼ぶことも出来るだろう。禁じられた不可能事を犯すことをエロティックと呼ぶことができるならば……。
初出一覧に「停電の前の感想」と「地震後の帰国」の2編が「現代詩手帖」とあるが、2011年6月の「北方文学」現代詩特集のはずなのだが……。
(この項おわり)