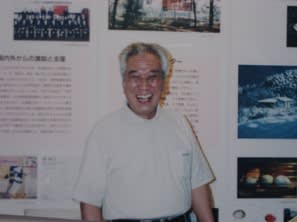※ お写真は横綱の曙と大関の小錦が体調が悪く癒しを受ける為に浄心庵を訪問した時の恩師とのスナップ写真です。
癒しを受け体調がよくなった曙はこの場所に優勝しました。
~ 恩師の「心行の解説」より ~
「日々の生活のなかにおいて己の魂を修行すべし」
日々の生活の中でしか、魂の修行をすることはできません。
寝ている間に魂の修行はできないのですから、よく夢のことばかり言う人があり、
「夢の中に高橋信次先生が出てきました」
「お大師様が夢の中に出て来てこんなことを言いました」とおしゃいますが、
これはあくまでも寝ていた時のことです。
「心行」の中に、夢の中で日々の生活の修行をすべしとは書いてありません。
私たちは起きている日々の生活の中で魂の修行をしております。
日々の生活の中で愛の実践をしていただきたいと思います。
正法という名を騙る小集団がありますが、その今月号に、
私のことが書かれています。
それによると「長尾というマッサージ師は大勢の方を騙して歩いている」のだそうです。
私は皆さんを騙すかもしれないから、騙されないように、しっかり疑問追求して下さい。
昨夜九時ごろ、アメリカンフットボールをして、鎖骨を骨折された大学生の方が、
大きな三角巾で腕を吊り下げてお見えになりました。
皆さんとお話していましたが、ちょっと待ってもらって、
「骨はくっつきなさい、あなたは折れてはいけません、元の位置に帰りなさい」と、
光を入れて祈りますと、腕を吊っていた三角巾を取っても、
「あれ、もう痛いことありません」と言って、治ってしまったのです。
その後レントゲンで見ると完全に元通りになっていたそうです。
あれはマッサージとは違います。
手も触れずに治る愛の祈りです。治るまで二、三分もかかっていないですね。
あっと言う間の出来事です。
これは神様の癒しであり、愛の祈りによって、神が働き給うた出来事です。
来られた時は痛くて痛くて片手で支えなくてはいられないし、服を着るどころではありません。
上からジャンパーをかけて来られたのですが、帰りには知らない間に服を着て帰られたのです。
昨夜はたくさんの皆さんと一緒に神の癒しを見せていただきました。
熊本か見えた方たちは帰る時、「あれはヤラセのサクラを使っていたのだ」と
言っていたと後で聞きました。
複雑骨折を今、完全に元通りの正常な骨に戻っているという方もおれます。
また三つに折れてバラバラになった仙骨が、たちまちにしてくっついて、
レントゲンを撮ると、何の傷もないという方もありました。
それは全部神の御業です。
肉体を戴いた私たちが、愛を実践しました時に、神がその御業をなし給います。
愛の実践ほど強いものはありません。
日々の生活の中で魂の修行をし、愛の実践をしていただきたいと思います。
~ 感謝・合掌 ~