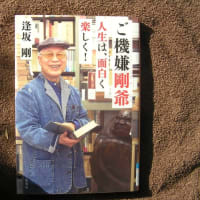と き 2009年6月8日(月) 晴れ 海上ときおり強風
と こ ろ S市O島S地区
釣り時間 9時30分~15時10分
汐 大汐(満潮13時前後)
釣 果 クロ(メジナ)550g1匹、足の裏~手の平サイズ20匹、海タナゴ9匹






「おい、明日の月曜日に釣りに行くぞ」と言ったら、家内がちょっと首を傾(かし)げる。あまりいい顔をしないのである。最たる理由は釣ってきた魚の調理を一手に引き受けているから。
釣り歴40年近くなるが生来の”ぶきっちょ”で釣ってきた魚をさばくことはまずない。もちろん内臓とウロコを取って焼き魚ぐらいは出来るが、肝心の「三枚おろし」ができないのがつらい。不精なので覚えようという気がないのも困る。
したがって、釣行前にいつも家内の了解(?)を必要とする。いつも言い出すタイミングを適当に狙っているが、今回は家内が大好きな「潮干狩り」(日曜日の単独行)に行くときを見計らって宣言したのだがそれでも不承不承(ふしょうぶしょう)にOKという感じ。
「お前だってしょっちゅう貝掘りに行ってるじゃないか」「私は自分できちんと後始末をやってます」とやり返されると、こちらの方がやや分が悪い。しかし、当日はしっかり早起きして朝食の支度と昼食の海苔巻きオニギリ2個をつくってくれた。
前回の釣行が5月31日(日)だったので約1週間後となる今回の釣行はこういう状況下での決行と相成った。
やっぱり年令と体力とを考え合わせると二週間に一度くらいの釣行が”いいのかも”という気もするが、一方では世の中に”こんな面白い遊びはない”ので体力があるうちにできるだけ沢山経験しておこうという焦りにも似た気持ちがある。
「音楽&オーディオ」は高周波に対する聴覚が加齢とともに低下していくものの死ぬ間際までどうにか楽しめるが、釣りはそういうわけにはいかない。せいぜい(体力が)もったとしてもあと10年あるかないかといったところだろう。
当日の出発は早朝の6時40分となった。当初は10時発の”渡し船”の時間に合わせて7時半出発の予定だったが「逸(はや)る気持ち」のせいか5時頃に目が覚めてしまい時間の余裕が出来たので6時40分発に急遽変更。これなら9時発の”渡し船”にどうにか間に合う。
「逸る気持ち」 → 実を言うと今回の釣行はつい先日購入した「リールと竿」の初試しをしたくて”ウズウズしていた”というのが真相である。もちろん家内には内緒。ゴルフ好きの方がクラブを新調して早くコースに出たくてウズウズする心境とおそらく同じだろう。



最近、長竿を1日中振り回していると右手首に負担がかかってコリがひどくなりなかなか回復しない。したがって出来るだけ軽いリール、出来るだけ持ち重りのしない竿を求めて購入したのが上記の写真。当然のごとく「もっと短い竿を使えばいいのに」と言われそうだが、自分独特の釣り方のためには7m前後の竿が是非必要なのである。
リールのほうは「(有)黒鯛工房」がこの5月に発売した新製品「THEヘチLIMITED88W」で自重が115gと物凄く軽量でスピニングリールの中の一番軽いものと比べても重さが約1/2程度のスグレもの。
竿のほうは「がまチヌ」ヘチ専用竿の7.2mで付着の(道糸を通す)ガイドが物凄く小さいのでこれまた非常に軽い。こちらの方はオークションで入手。
「ヘチ」という言葉がしきりに出てくるがこの意味は防波堤やテトラポッドの際(きわ)を意味し、このあたりで居食いをするチヌ(黒鯛)を釣るための用語。したがってひときわ繊細なつくりになっている。
さて、港に予定どおり8時40分頃に到着し早速、渡し船に荷物を積み込む。写真でご覧のとおり通常の1.5倍はあるでっかいクーラー、予備の竿3本が入った竿袋、荷車、仕掛け入りバッグなど小荷物が多い。
船長さんとも顔なじみになって”やあやあ”という感じ。前回と同じ防波堤に着けてもらったが相変わらず人っ子ひとりいない、どこで釣ってもいいがあえて同じ箇所を選択。釣れているうちはしつこく同一箇所に固執するのが自分のセオリーである。
今日は新しいリールと竿の「お披露目」なので”あまり釣れなくてもいいや”と踏んでいたのだがいざ海に臨んでみると狩猟本能が芽生えてきてそうもいってられなくなる。
汐は大潮で満潮が13時前後なので引き込みと満ち込みが両方狙える理想的な釣行だが結果的にはそううまくは問屋がおろさなかった。
午前中の引き潮では始めからクロ(メジナ)がドンドン海面近くまで浮いてきて、これはいただきという感じ。立て続けに足の裏クラスがヒットする。そのうち大物が食いついてグ~ンと海底深くまで潜られたが軽くて新しい長竿の威力が見事に発揮され竿をグットためて一気に海面まで浮かせた。
さすがに「がまかつ」の竿はしなやかで力強い。取り込みが随分と楽でバランスのよさに感激した。帰宅して計ってみると550gあった(写真不鮮明!)ので前回の510gよりも大きいのだが竿のせいで逆に小さく感じてしまう。やはり竿の威力は大きい。しかし、大物はこれ1匹だけに終わった。
午前中があまりにも良かったので、午後もこの調子だとクーラーが満タンになってオーバーするかもと心配したのだがこれが見事に「取らぬ狸の皮算用」。13時過ぎからの満ち込みに変わったとたん、パタリと喰いが止った。マキエを追いかけはするのだが肝心の釣り針のエサに見向きもしないし咥えてもすぐ放す感じ。すっかり手の内を読まれているようだ。
とうとう、しびれをきらして別の竿を引っ張り出してウキ下3m近くの深仕掛けにしてみたりいろいろ試みるが一向にアタリがない。結局午後は1匹も釣果がなくてガックリ。
釣りにはこういう極端なことがままある。原因がよく分からないがどうやらこの場所は基本的に引き潮向きになっていると考えていいが、釣り人側の工夫も必要なんだろう。
釣れなかったときの分析は極めて大切でこれも「釣り」のうち、帰宅後にじっくりと考えてみた結果、次回はやや細かくなるが次のようなチャレンジをしてみよう。
1 「オキアミ」は魚が満腹になりやすいので一切使わずにマキエの配合を大幅に見直す。とりわけ業務用(飲食店)の柔らかくて香りのいいパン粉を購入して混ぜる。
2 釣り針の小型化、ウキとオモリの変更、ハリスの長さの検討
3 マキエ杓の変更とエサ盗りのかわし方など
以上、チャレンジというほどのこともないがやはり「釣り」にもちょっとした変化とか工夫が常に求められる。とにかく移ろう自然が相手なのでこれでいいという正解がないところに奥の深いものがある。
結局、納竿は15時10分と早めで1/3ほど残ったマキエはいさぎよく海中に棄てた。
最後にヘチ用「リール」の使い勝手だが一言でいえば一長一短だがプラス面のほうが多いと感じた。何よりもスピニングリールのように道糸に「撚(よ)り」がかからずモツレないのが最大のメリット。しかし、うまく使いこなそうと思えば若干の時間が必要で、独自の改造(ハンドル部分)も必須のように思った。