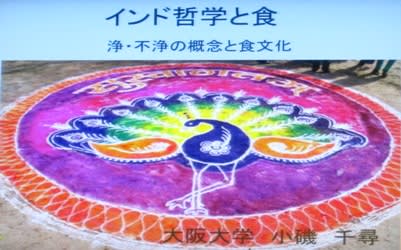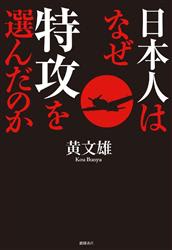【奈良町遺跡から出土した平安~江戸時代の遺物を展示】
奈良市埋蔵文化財調査センターで「平成25年度春季発掘調査速報展」(28日まで)が開かれている。平安~江戸時代の陶磁器や犬形土製品などが出土した奈良町遺跡(今小路町)の出土品に加え、24年度に実施した東大寺旧境内食堂院地区の出土品も併せて展示している。


奈良町遺跡の場所は転害門の南西約70m。平安時代の緑釉陶器や灰釉陶器をはじめ、鎌倉時代の井戸から鹿の角、室町時代の井戸からは小さな犬形の土製品や石製のサイコロなどが見つかった。このほか15世紀前半の地層からは瀬戸産のおろし皿や体を温かめる温石(おんじゃく)なども出土しており、都が平安京に移って以降の土地利用の変遷や人々の暮らしぶりが垣間見える。
江戸時代終わり頃の土坑からは信楽や瀬戸、肥前などの陶磁器や木製品が大量に出土した。この地は江戸時代の絵図などから4大茶会記の1つ「松屋会記」(1534~1650年)で有名な漆問屋松屋・土門家の邸宅があったことが分かっており、同センターではこれらの出土品も土門家に関わるものではないかと推測している。


東大寺食堂院地区は僧侶の食事をつくる「大炊殿(おおいどの)」と呼ばれる建物があったとみられる所。現在駐車場になっている場所を発掘したところ、大量の奈良時代の瓦や奈良三彩、須恵器横瓶などの土器類が見つかった(上の写真)。瓦の中には「真依」「六人」「長」「東」「東大」という文字が刻印されたものが合計10点あった。
「真依」は「まより」、「六人」は「むと」という瓦工人の名前とみられる。こうした人名を刻印した瓦はこれまでに東大寺の法華堂(三月堂)や恭仁宮跡、平城宮跡などからも出土している。「東」と「東大」は東大寺を意味し東大寺造営時の瓦とみられる。