きのこ検定を受験してきた!
「きのこ検定」は、ありとあらゆる検定試験を企画している日版が、ホクトなどの協賛をえて催した資格試験。資格って言っても、ほとんど役に立つとは思えないが、マニアを自認する者としては挑戦とも受けとれるこの企画、受けざるをえない。あざといわ…。
全国4会場で試験が行われて、自分が受けた名古屋会場は100人ちょっとが集まった。
今回は3級と2級が同日開催だったので、自分は併願してみた。
それぞれマークシート式の四択問題が100問、持ち時間は1時間。7割正解で合格のようだ。
「きのこ検定公式テキスト」というのが市販されていて、そこから出題されるんだけど、私はマニアの意地を見せるため、テキストなしのハンデ戦で挑んだ。いやいや、まだそれだけでも足りないと思って、消しゴムを使わない追加ハンデも!(すいません、忘れただけです)
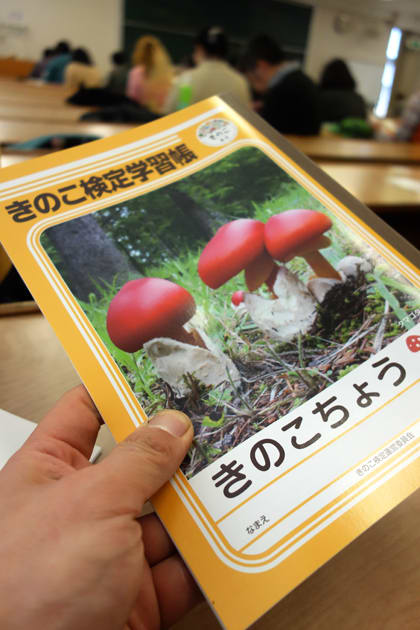
参加賞のきのこ学習帳(笑)
試験開始。楽勝だと思ってた3級が予想以上に難しくてあせった。キノコ栽培の歴史とか、研究者の名前とか、生産量や消費量の統計なんて、ぜんぜんわからん……!でも、なんとか合格ラインには到達した。80点くらいかな。
午後。こりゃ2級はまずムリだろうなと諦めてたんだけど、ふたを開けてみればラッキー、意外にできる!2級は3級と比べてたしかに難しかったけど、そんなに差がなかったような……キノコの種類とか特徴とかの問題が多かったので、そちら方面ならさばけるってことだったかも。70点ちょっといったか?ギリギリ大丈夫だと思う・・・たぶん!
はー、テストなんて何年ぶりだったろ。おもしろかったけどちょっと疲れた1日だった(^_^;)
3
2
「きのこ検定」は、ありとあらゆる検定試験を企画している日版が、ホクトなどの協賛をえて催した資格試験。資格って言っても、ほとんど役に立つとは思えないが、マニアを自認する者としては挑戦とも受けとれるこの企画、受けざるをえない。あざといわ…。
全国4会場で試験が行われて、自分が受けた名古屋会場は100人ちょっとが集まった。
今回は3級と2級が同日開催だったので、自分は併願してみた。
それぞれマークシート式の四択問題が100問、持ち時間は1時間。7割正解で合格のようだ。
「きのこ検定公式テキスト」というのが市販されていて、そこから出題されるんだけど、私はマニアの意地を見せるため、テキストなしのハンデ戦で挑んだ。いやいや、まだそれだけでも足りないと思って、消しゴムを使わない追加ハンデも!(すいません、忘れただけです)
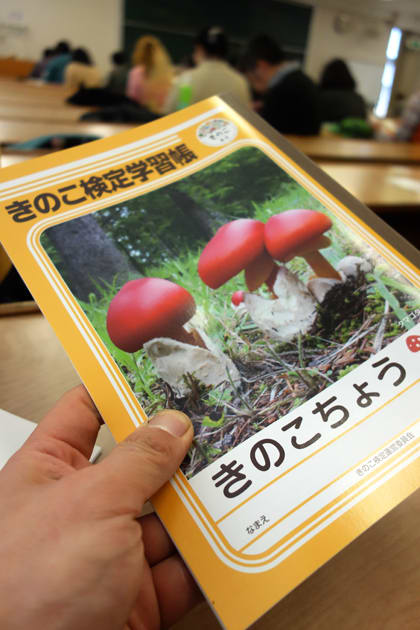
参加賞のきのこ学習帳(笑)
試験開始。楽勝だと思ってた3級が予想以上に難しくてあせった。キノコ栽培の歴史とか、研究者の名前とか、生産量や消費量の統計なんて、ぜんぜんわからん……!でも、なんとか合格ラインには到達した。80点くらいかな。
午後。こりゃ2級はまずムリだろうなと諦めてたんだけど、ふたを開けてみればラッキー、意外にできる!2級は3級と比べてたしかに難しかったけど、そんなに差がなかったような……キノコの種類とか特徴とかの問題が多かったので、そちら方面ならさばけるってことだったかも。70点ちょっといったか?ギリギリ大丈夫だと思う・・・たぶん!
はー、テストなんて何年ぶりだったろ。おもしろかったけどちょっと疲れた1日だった(^_^;)
3
2
「きのこ検定」は2月23日だ!ほとんど勉強してないぜ!三級は受かる自信あるけど、二級は落ちる確率がかなり高い!テキスト一回でいいから通し読みすれば、合格率大アップするけど!テキスト使わないルールでチャレンジしてるから!
解説:なぜわざわざそんなことをするかと言えば、それは合否ぎりぎりラインに身を置くことで、テストをワクワクドキドキ受けたいからである。
ということで、日曜日、試験会場の名古屋にまいります。
急所
キノコの栄養成分・薬用成分の固有名詞やなんか
テキストにはきのこ年表が付いているらしいが、年号とか
写真のキノコ、ムラサキヤマドリだと思うんだけど、なんか変だな……
解説:なぜわざわざそんなことをするかと言えば、それは合否ぎりぎりラインに身を置くことで、テストをワクワクドキドキ受けたいからである。
ということで、日曜日、試験会場の名古屋にまいります。
急所
キノコの栄養成分・薬用成分の固有名詞やなんか
テキストにはきのこ年表が付いているらしいが、年号とか
写真のキノコ、ムラサキヤマドリだと思うんだけど、なんか変だな……
イグチ目
イグチ科
ヌメリイグチ属をはじめとしたいくつかのグループが離脱するも、オニイグチ科を吸収して大勢力を保つ。属が増え、配置替えあり。
キヒダタケ属、アワタケ属、タマノリイグチ属、コショウイグチ属、キイロイグチ属、ヌメリコウジタケ属、ウツロイイグチ属、ヤマドリタケ属、キアミアシイグチ属、ニガイグチ属、クロイグチ属、ヤマイグチ属、オニイグチ属、ヤシャイグチ属、キクバナイグチ属、ベニイグチ属
主な変更
クロアワタケ、キアミアシイグチ ヤマドリタケ属→キアミアシイグチ属
モエギアミアシイグチ ニガイグチ属→キアミアシイグチ属
ウラグロニガイグチ ニガイグチ属→ヤマイグチ属
アイゾメクロイグチ ニガイグチ属→クロイグチ属
クリイロイグチ科
独立。微小勢力。
ミダレアミイグチ科
独立。微小勢力。
ヌメリイグチ科
イグチ科から独立。ハナイグチ、アミタケなど。
転出 ハンノキイグチ→ヒダハタケ科ハンノキイグチ属
イグチ系腹菌類
ディプロシスチジア科…ツチグリ属
ニセショウロ科…ニセショウロ属 コツブタケ属
クチベニタケ科…クチベニタケ属
ショウロ科…ショウロ属
ジャガイモタケはジャガイモタケ科からイグチ科へ転属
ベニタケ目
ベニタケ科 ベニタケ属一属で占める大グループ。変更なし
チチタケ科 チチタケ属一属で占める大グループ。変更なし
ベニタケ系ヒダナシタケ類
マツカサタケ科…フサヒメホウキタケ属、マツカサタケ属
カワタケ科…カワタケ属
ウロコタケ科…アカコウヤクタケ属、キウロコタケ属、カタウロコタケ属
サンゴハリタケ科…サンゴハリタケ属(ヤマブシタケなど)
ニンギョウタケモドキ科…ニンギョウタケモドキ属
ミヤマトンビマイ科…マツノネクチタケ属、ミヤマトンビマイ属
イグチ科
ヌメリイグチ属をはじめとしたいくつかのグループが離脱するも、オニイグチ科を吸収して大勢力を保つ。属が増え、配置替えあり。
キヒダタケ属、アワタケ属、タマノリイグチ属、コショウイグチ属、キイロイグチ属、ヌメリコウジタケ属、ウツロイイグチ属、ヤマドリタケ属、キアミアシイグチ属、ニガイグチ属、クロイグチ属、ヤマイグチ属、オニイグチ属、ヤシャイグチ属、キクバナイグチ属、ベニイグチ属
主な変更
クロアワタケ、キアミアシイグチ ヤマドリタケ属→キアミアシイグチ属
モエギアミアシイグチ ニガイグチ属→キアミアシイグチ属
ウラグロニガイグチ ニガイグチ属→ヤマイグチ属
アイゾメクロイグチ ニガイグチ属→クロイグチ属
クリイロイグチ科
独立。微小勢力。
ミダレアミイグチ科
独立。微小勢力。
ヌメリイグチ科
イグチ科から独立。ハナイグチ、アミタケなど。
転出 ハンノキイグチ→ヒダハタケ科ハンノキイグチ属
イグチ系腹菌類
ディプロシスチジア科…ツチグリ属
ニセショウロ科…ニセショウロ属 コツブタケ属
クチベニタケ科…クチベニタケ属
ショウロ科…ショウロ属
ジャガイモタケはジャガイモタケ科からイグチ科へ転属
ベニタケ目
ベニタケ科 ベニタケ属一属で占める大グループ。変更なし
チチタケ科 チチタケ属一属で占める大グループ。変更なし
ベニタケ系ヒダナシタケ類
マツカサタケ科…フサヒメホウキタケ属、マツカサタケ属
カワタケ科…カワタケ属
ウロコタケ科…アカコウヤクタケ属、キウロコタケ属、カタウロコタケ属
サンゴハリタケ科…サンゴハリタケ属(ヤマブシタケなど)
ニンギョウタケモドキ科…ニンギョウタケモドキ属
ミヤマトンビマイ科…マツノネクチタケ属、ミヤマトンビマイ属
テングタケ科
旧分類と変わらず。テングタケ属は屈指の大グループ。テングタケ属、ヌメリカラカサタケ属。
ウラベニガサ科
旧分類からわずかに変更。
フクロタケ属、オオフクロタケ属、ウラベニガサ属
ハラタケ科
コガネタケやカブラマツタケなどが独立するも、ササクレヒトヨタケ属が合流、さらに腹菌類から大量流入をうけて勢力拡大。
オオシロカラカサタケ属、カラカサタケ属、シロカラカサタケ属(ツブカラカサタケなど)、キヌカラカサタケ属(キツネノハナガサなど)、ハラタケ属(マッシュルーム、ウスキモリノカサなど)、オニタケ属、キツネノカラカサ属、ササクレヒトヨタケ属、ケシボウズタケ属、オニノケヤリタケ属、チャダイゴケ系、ノウタケ属(オニフスベなど)、ホコリタケ属
カブラマツタケ科
ハラタケ科から分離独立した小グループ。シワカラカサタケ、コガネタケなど。
ナヨタケ科
中堅勢力だった旧ヒトヨタケ科はワライタケ属・ジンガサタケ属に離反され、さらにササクレヒトヨタケ属と内部分裂を起こした上に、ナヨタケ属のクーデターにより乗っ取られた。劇的な没落ぶり。
ヒメヒトヨタケ属(ヒトヨタケなど)、キララタケ属(イヌセンボンタケなど)、ヒメヒガサヒトヨタケ属、ナヨタケ属(イタチタケなど)、クロヒメオニタケ属
オキナタケ科
小勢力。フミヅキタケ属が離反するも、ワライタケ属、ジンガサタケ属、キショウゲンジ属が合流。
ワライタケ属、ジンガサタケ属(ツヤマグソタケなど)、オキナタケ属、コガサタケ属
モエギタケ科
食用キノコのナメコやチャナメツムタケを擁する中堅グループ。フミヅキタケ属が合流、ヒメスギタケが離反。クリタケの属名が混乱気味。
フミヅキタケ属(ツチナメコ、ヤナギマツタケなど)、モエギタケ属(サケツバタケなど)、ニガクリタケ属(クリタケなど)、クリタケ属、ミヤマツバタケ属、シビレタケ属、スギタケ属(ナメコ、ヌメリスギタケモドキ、チャナメツムタケなど)、センボンイチメガサ属
チャムクエタケ科
ヒメスギタケ属
アセタケ科
フウセンタケ科から独立したグループ。小型で種類が多く、判別が難しい。旧チャヒラタケ科は降格してここに吸収された。
アセタケ属、チャヒラタケ属
ヒメノガステル科
フウセンタケ科から独立。
ワカフサタケ属(ナガエノスギタケなど)、ケコガサタケ属(コレラタケなど)
フウセンタケ科
アセタケ属、ワカフサタケ属、チャツムタケ属、ケコガサタケ属の離反を許し弱体化したが、結果、フウセンタケ一属でほぼ統一、結束力は高まった。
フウセンタケ属(ショウゲンジ、ニセアブラシメジ、ヌメリササタケなど)
所属科未定
チャツムタケ属(オオワライタケ、ミドリスギタケなど)
転出 キショウゲンジ フウセンタケ科→オキナタケ科キショウゲンジ属
イッポンシメジ科
旧分類から変更はあまりない。
ヒカゲウラベニタケ属、イッポンシメジ属
イチョウタケ科
ヒダハタケ科から独立。微小勢力。イグチ目。
イチョウタケ属(ニワタケなど)、サケバタケ属。
ヒダハタケ科
微小勢力。イグチ目。ハンノキイグチが加入。
ヒロハアンズタケ科
微小勢力。イグチ目。
オウギタケ科
少数。旧分類から変更なし。イグチ目。
クギタケ属、オウギタケ属
旧分類と変わらず。テングタケ属は屈指の大グループ。テングタケ属、ヌメリカラカサタケ属。
ウラベニガサ科
旧分類からわずかに変更。
フクロタケ属、オオフクロタケ属、ウラベニガサ属
ハラタケ科
コガネタケやカブラマツタケなどが独立するも、ササクレヒトヨタケ属が合流、さらに腹菌類から大量流入をうけて勢力拡大。
オオシロカラカサタケ属、カラカサタケ属、シロカラカサタケ属(ツブカラカサタケなど)、キヌカラカサタケ属(キツネノハナガサなど)、ハラタケ属(マッシュルーム、ウスキモリノカサなど)、オニタケ属、キツネノカラカサ属、ササクレヒトヨタケ属、ケシボウズタケ属、オニノケヤリタケ属、チャダイゴケ系、ノウタケ属(オニフスベなど)、ホコリタケ属
カブラマツタケ科
ハラタケ科から分離独立した小グループ。シワカラカサタケ、コガネタケなど。
ナヨタケ科
中堅勢力だった旧ヒトヨタケ科はワライタケ属・ジンガサタケ属に離反され、さらにササクレヒトヨタケ属と内部分裂を起こした上に、ナヨタケ属のクーデターにより乗っ取られた。劇的な没落ぶり。
ヒメヒトヨタケ属(ヒトヨタケなど)、キララタケ属(イヌセンボンタケなど)、ヒメヒガサヒトヨタケ属、ナヨタケ属(イタチタケなど)、クロヒメオニタケ属
オキナタケ科
小勢力。フミヅキタケ属が離反するも、ワライタケ属、ジンガサタケ属、キショウゲンジ属が合流。
ワライタケ属、ジンガサタケ属(ツヤマグソタケなど)、オキナタケ属、コガサタケ属
モエギタケ科
食用キノコのナメコやチャナメツムタケを擁する中堅グループ。フミヅキタケ属が合流、ヒメスギタケが離反。クリタケの属名が混乱気味。
フミヅキタケ属(ツチナメコ、ヤナギマツタケなど)、モエギタケ属(サケツバタケなど)、ニガクリタケ属(クリタケなど)、クリタケ属、ミヤマツバタケ属、シビレタケ属、スギタケ属(ナメコ、ヌメリスギタケモドキ、チャナメツムタケなど)、センボンイチメガサ属
チャムクエタケ科
ヒメスギタケ属
アセタケ科
フウセンタケ科から独立したグループ。小型で種類が多く、判別が難しい。旧チャヒラタケ科は降格してここに吸収された。
アセタケ属、チャヒラタケ属
ヒメノガステル科
フウセンタケ科から独立。
ワカフサタケ属(ナガエノスギタケなど)、ケコガサタケ属(コレラタケなど)
フウセンタケ科
アセタケ属、ワカフサタケ属、チャツムタケ属、ケコガサタケ属の離反を許し弱体化したが、結果、フウセンタケ一属でほぼ統一、結束力は高まった。
フウセンタケ属(ショウゲンジ、ニセアブラシメジ、ヌメリササタケなど)
所属科未定
チャツムタケ属(オオワライタケ、ミドリスギタケなど)
転出 キショウゲンジ フウセンタケ科→オキナタケ科キショウゲンジ属
イッポンシメジ科
旧分類から変更はあまりない。
ヒカゲウラベニタケ属、イッポンシメジ属
イチョウタケ科
ヒダハタケ科から独立。微小勢力。イグチ目。
イチョウタケ属(ニワタケなど)、サケバタケ属。
ヒダハタケ科
微小勢力。イグチ目。ハンノキイグチが加入。
ヒロハアンズタケ科
微小勢力。イグチ目。
オウギタケ科
少数。旧分類から変更なし。イグチ目。
クギタケ属、オウギタケ属
前回の続き。もっと細かく見てみる。有力グループは太字にしてある。基本的に山渓の「改訂版日本のきのこ」をまとめただけなので、洩れは多いと思う。
ヒラタケ科
もともと少数勢力だったが、さらに流出して超弱小グループに。
ヒラタケ属(ヒラタケ、タモギタケなど)
転出
キヒラタケ→フサタケ科キヒラタケ属
アラゲカワキタケ→タマチョレイタケ科カワキタケ属
マツオウジ→キカイガラタケ科マツオウジ属
ヌメリガサ科
変更は少ない。ホテイシメジが加入。
ヌメリガサ属、オトメノカサ属、アカヤマタケ属、ワカクサタケ属、ホテイシメジ属
旧キシメジ科
寄せ集めだった旧キシメジ科はほぼ解体された。ていうか何だこの混迷ぶり・・・なんとかしてくれ。
シメジ科
シメジ属(ハタケシメジ、シャカシメジ、ホンシメジ、カクミノシメジなど)にシロタモギタケ属(ブナシメジなど)、ヤグラタケ属、ヤケノシメジ属、オオシロアリタケ属を加えたグループ。
ヒドナンギウム科
キツネタケ属。
ツキヨタケ科
中堅グループ。メンツを見ても正直、統一性というものが感じられん(汗)
シイタケ属、ツキヨタケ属、モリノカレバタケ属(アマタケ、ワサビカレバタケなど)、アカアザタケ属(エセオリミキなど)、シロホウライタケ属
(新)キシメジ科
旧勢力の大半を失ったとはいえ、なお大きい勢力を持つ。特にキシメジ属は美味な食用菌を擁する有力グループ。
カヤタケ属、ハイイロシメジ属(オシロイシメジ、ドクササコなど)、ムラサキシメジ属、サマツモドキ属、ニオウシメジ属、キシメジ属(シモコシ、シモフリシメジ、マツタケ、カキシメジなど)、オオイチョウタケ属
タマバリタケ科
中堅グループ。枯れ木に生えるものが多い。
ナラタケ属、ビロードツエタケ属、ヌメリツバタケ属、ツエタケ属、マツカサキノコ属(スギエダタケなど)、ダイダイガサ属、エノキタケ属
ガマノホタケ科
ムキタケ属 、ヒメカバイロタケ属。旧ヒダナシタケ目からガマノホタケ属、ホソヤリタケ属が合流。
ポロテレウム科
ゲロネマ属(オリーブサカズキタケなど)、ヒロヒダタケ属(ヒロヒダタケ)
オオモミタケ科
シジミタケ科
ホウライタケ科
アミヒダタケ属、ホウライタケ属(ウマノケタケ、スジオチバタケ、オオホウライタケなど)、ニセホウライタケ属、パイプタケ属
ラッシタケ科
中堅グループ。クヌギタケ属を中核とした小型菌中心。ワサビタケ属、ラッシタケ属、クヌギタケ属(ヤコウタケ、アシナガタケ、チシオタケ、サクラタケなど)、ヌナワタケ属、ホシアンズタケ属
フウリンタケ科
ニセマツカサシメジ属
所属科未定 ザラミノシメジ属 スギヒラタケ属
転出
ホテイシメジ→ヌメリガサ科ホテイシメジ属
ヒナノヒガサ→タバコウロコタケ目ヒナノヒガサ科ヒナノヒガサ属
ヒラタケ科
もともと少数勢力だったが、さらに流出して超弱小グループに。
ヒラタケ属(ヒラタケ、タモギタケなど)
転出
キヒラタケ→フサタケ科キヒラタケ属
アラゲカワキタケ→タマチョレイタケ科カワキタケ属
マツオウジ→キカイガラタケ科マツオウジ属
ヌメリガサ科
変更は少ない。ホテイシメジが加入。
ヌメリガサ属、オトメノカサ属、アカヤマタケ属、ワカクサタケ属、ホテイシメジ属
旧キシメジ科
寄せ集めだった旧キシメジ科はほぼ解体された。ていうか何だこの混迷ぶり・・・なんとかしてくれ。
シメジ科
シメジ属(ハタケシメジ、シャカシメジ、ホンシメジ、カクミノシメジなど)にシロタモギタケ属(ブナシメジなど)、ヤグラタケ属、ヤケノシメジ属、オオシロアリタケ属を加えたグループ。
ヒドナンギウム科
キツネタケ属。
ツキヨタケ科
中堅グループ。メンツを見ても正直、統一性というものが感じられん(汗)
シイタケ属、ツキヨタケ属、モリノカレバタケ属(アマタケ、ワサビカレバタケなど)、アカアザタケ属(エセオリミキなど)、シロホウライタケ属
(新)キシメジ科
旧勢力の大半を失ったとはいえ、なお大きい勢力を持つ。特にキシメジ属は美味な食用菌を擁する有力グループ。
カヤタケ属、ハイイロシメジ属(オシロイシメジ、ドクササコなど)、ムラサキシメジ属、サマツモドキ属、ニオウシメジ属、キシメジ属(シモコシ、シモフリシメジ、マツタケ、カキシメジなど)、オオイチョウタケ属
タマバリタケ科
中堅グループ。枯れ木に生えるものが多い。
ナラタケ属、ビロードツエタケ属、ヌメリツバタケ属、ツエタケ属、マツカサキノコ属(スギエダタケなど)、ダイダイガサ属、エノキタケ属
ガマノホタケ科
ムキタケ属 、ヒメカバイロタケ属。旧ヒダナシタケ目からガマノホタケ属、ホソヤリタケ属が合流。
ポロテレウム科
ゲロネマ属(オリーブサカズキタケなど)、ヒロヒダタケ属(ヒロヒダタケ)
オオモミタケ科
シジミタケ科
ホウライタケ科
アミヒダタケ属、ホウライタケ属(ウマノケタケ、スジオチバタケ、オオホウライタケなど)、ニセホウライタケ属、パイプタケ属
ラッシタケ科
中堅グループ。クヌギタケ属を中核とした小型菌中心。ワサビタケ属、ラッシタケ属、クヌギタケ属(ヤコウタケ、アシナガタケ、チシオタケ、サクラタケなど)、ヌナワタケ属、ホシアンズタケ属
フウリンタケ科
ニセマツカサシメジ属
所属科未定 ザラミノシメジ属 スギヒラタケ属
転出
ホテイシメジ→ヌメリガサ科ホテイシメジ属
ヒナノヒガサ→タバコウロコタケ目ヒナノヒガサ科ヒナノヒガサ属
きのこ検定の勉強のついでに新分類の変更点をおおまかに整理してみた。ただの覚え書きなうえ、専門的すぎて記事としては面白くないのであしからず。
旧ハラタケ目
ハラタケ目
以前は傘に柄のあるタイプのキノコの大半がハラタケ目だったが、新分類ではイグチ目とベニタケ目が独立した。それとは別に、少数ながらイグチ目への離反(オウギタケ科など)あり。さらにごく一部のキノコでヒダナシタケ系に転出した者がいる(アラゲカワキタケ、マツオウジ、ヒナノヒガサなど)逆に、ヒダナシタケ系からハラタケ目に移った者がかなり多い(スエヒロタケ、カンゾウタケ、フサタケ、ナギナタタケ、ムラサキホウキタケ、チャダイゴケ類、ホコリタケ、ノウタケなど)
イグチ目
イグチ科から昇格。ニワタケ、サケバタケ、オウギタケ、クギタケなどが加入。さらに腹菌系から加入あり(ツチグリ、ニセショウロ、コツブタケ、クチベニタケ、ショウロなど)
ベニタケ目
ベニタケ科から昇格。旧ヒダナシタケ目から加入が多い(フサヒメホウキタケ、チウロコタケ、サンゴハリタケ、ヤマブシタケ、マツカサタケ、ニンギョウタケなど)
旧ヒダナシタケ目
タマチョレイタケ目
かつてのヒダナシタケ目の主力、サルノコシカケ系。分裂や流出で勢力を大幅に減らした。ハナビラタケ、アミスギタケ、ヒトクチタケ、マイタケ、カワラタケ、ヒイロタケ、マンネンタケ、コフキサルノコシカケなど。
ラッパタケ目
旧ヒダナシタケ目から分離独立。少数勢力。ウスタケ、スリコギタケ、ホウキタケなど。
アンズタケ目
旧ヒダナシタケ目から分離独立。アンズタケ、カノシタ、カレエダタケ、シラウオタケなど。
イボタケ目
旧ヒダナシタケ目から分離独立。ボタンイボタケ、モミジタケ、クロカワ、コウタケなど。
タバコウロコタケ目
有象無象勢力。ハカワラタケ、アズマタケ、ワヒダタケ、ニッケイタケなど。ムラサキナギナタタケとヒナノヒガサがなぜかココ。
キカイガラタケ目
超微小勢力。マツオウジがココ。
コウヤクタケ目
超微小勢力。コウヤクタケと名につくものは、見た目が似てても出自が多様で、多くはここに所属していない。
旧腹菌類
スッポンタケ目
腹菌類にはホコリタケ目、ニセショウロ目、チャダイゴケ目など多くの目があったが、大半が解体・離散の憂き目に会い、唯一スッポンタケ目だけが残った。スッポンタケ、キヌガサタケ、サンコタケなど
ヒメツチグリ目
旧ホコリタケ目から独立。少数勢力。エリマキツチグリ、ヒナツチガキなど。ツチグリはイグチ目なのでここには入らない。
キクラゲ類
キクラゲ類は旧分類から変更なしの3グループ。
シロキクラゲ目
シロキクラゲ、ハナビラニカワタケなど。
キクラゲ目
キクラゲ類の主力。アラゲキクラゲ、ニカワハリタケ、ムカシオオミダレタケなど。
アカキクラゲ目
少数。黄色いキクラゲ類が多い。ツノマタタケ、ハナビラダクリオキンなど。
子のう菌類
チャワンタケ目
子のう菌類の主力。旧分類からほぼ変更なしだが、新加入が少し。オオチャワンタケ、オオゴムタケ、ノボリリュウタケ、アミガサタケなど。意外にもイボセイヨウショウロ(トリュフ)がここに転属された。
ビョウタケ目
ズキンタケ、ビョウタケ、ムラサキゴムタケなど。
エウロチウム目
弱小勢力だが個性派ぞろい。コウボウフデ、マユハキタケ、ツチダンゴなど。
ボタンタケ目
かつてバッカクキン目だった冬虫夏草類が今はここに分類される。
あとは省略。
旧ハラタケ目
ハラタケ目
以前は傘に柄のあるタイプのキノコの大半がハラタケ目だったが、新分類ではイグチ目とベニタケ目が独立した。それとは別に、少数ながらイグチ目への離反(オウギタケ科など)あり。さらにごく一部のキノコでヒダナシタケ系に転出した者がいる(アラゲカワキタケ、マツオウジ、ヒナノヒガサなど)逆に、ヒダナシタケ系からハラタケ目に移った者がかなり多い(スエヒロタケ、カンゾウタケ、フサタケ、ナギナタタケ、ムラサキホウキタケ、チャダイゴケ類、ホコリタケ、ノウタケなど)
イグチ目
イグチ科から昇格。ニワタケ、サケバタケ、オウギタケ、クギタケなどが加入。さらに腹菌系から加入あり(ツチグリ、ニセショウロ、コツブタケ、クチベニタケ、ショウロなど)
ベニタケ目
ベニタケ科から昇格。旧ヒダナシタケ目から加入が多い(フサヒメホウキタケ、チウロコタケ、サンゴハリタケ、ヤマブシタケ、マツカサタケ、ニンギョウタケなど)
旧ヒダナシタケ目
タマチョレイタケ目
かつてのヒダナシタケ目の主力、サルノコシカケ系。分裂や流出で勢力を大幅に減らした。ハナビラタケ、アミスギタケ、ヒトクチタケ、マイタケ、カワラタケ、ヒイロタケ、マンネンタケ、コフキサルノコシカケなど。
ラッパタケ目
旧ヒダナシタケ目から分離独立。少数勢力。ウスタケ、スリコギタケ、ホウキタケなど。
アンズタケ目
旧ヒダナシタケ目から分離独立。アンズタケ、カノシタ、カレエダタケ、シラウオタケなど。
イボタケ目
旧ヒダナシタケ目から分離独立。ボタンイボタケ、モミジタケ、クロカワ、コウタケなど。
タバコウロコタケ目
有象無象勢力。ハカワラタケ、アズマタケ、ワヒダタケ、ニッケイタケなど。ムラサキナギナタタケとヒナノヒガサがなぜかココ。
キカイガラタケ目
超微小勢力。マツオウジがココ。
コウヤクタケ目
超微小勢力。コウヤクタケと名につくものは、見た目が似てても出自が多様で、多くはここに所属していない。
旧腹菌類
スッポンタケ目
腹菌類にはホコリタケ目、ニセショウロ目、チャダイゴケ目など多くの目があったが、大半が解体・離散の憂き目に会い、唯一スッポンタケ目だけが残った。スッポンタケ、キヌガサタケ、サンコタケなど
ヒメツチグリ目
旧ホコリタケ目から独立。少数勢力。エリマキツチグリ、ヒナツチガキなど。ツチグリはイグチ目なのでここには入らない。
キクラゲ類
キクラゲ類は旧分類から変更なしの3グループ。
シロキクラゲ目
シロキクラゲ、ハナビラニカワタケなど。
キクラゲ目
キクラゲ類の主力。アラゲキクラゲ、ニカワハリタケ、ムカシオオミダレタケなど。
アカキクラゲ目
少数。黄色いキクラゲ類が多い。ツノマタタケ、ハナビラダクリオキンなど。
子のう菌類
チャワンタケ目
子のう菌類の主力。旧分類からほぼ変更なしだが、新加入が少し。オオチャワンタケ、オオゴムタケ、ノボリリュウタケ、アミガサタケなど。意外にもイボセイヨウショウロ(トリュフ)がここに転属された。
ビョウタケ目
ズキンタケ、ビョウタケ、ムラサキゴムタケなど。
エウロチウム目
弱小勢力だが個性派ぞろい。コウボウフデ、マユハキタケ、ツチダンゴなど。
ボタンタケ目
かつてバッカクキン目だった冬虫夏草類が今はここに分類される。
あとは省略。
栽培キノコ生産量
一位 エノキタケ
二位 ブナシメジ
三位 シイタケ
四位 マイタケ
五位 エリンギ
こんなかで、実はシイタケだけオートメーション化に成功していないんだよね。せいぜい半自動。それで三位なんだから立派立派・・・?
ただ素朴な疑問なんだけど、この統計って合ってるんだろうか……うちの会社で出荷するシイタケ、パック単位だから、重量を申告するようなこともしてないし、出荷先もまちまち。いったいどこでどうカウントしてるんだろうかと。
え?自己申告制?まさかなー。
一位 エノキタケ
二位 ブナシメジ
三位 シイタケ
四位 マイタケ
五位 エリンギ
こんなかで、実はシイタケだけオートメーション化に成功していないんだよね。せいぜい半自動。それで三位なんだから立派立派・・・?
ただ素朴な疑問なんだけど、この統計って合ってるんだろうか……うちの会社で出荷するシイタケ、パック単位だから、重量を申告するようなこともしてないし、出荷先もまちまち。いったいどこでどうカウントしてるんだろうかと。
え?自己申告制?まさかなー。
3つのヒントから、キノコの名前を当ててください。基本的な種類にしぼったつもりだけど、できるかなー?
問1
1.名前に生き物の名前が含まれています
2.イタリア語でポルチーニと呼ばれ、美味です
3.寒冷地の針葉樹の下に生えるため、日本の平暖地では見られません
問2
1.Lactariusというグループに属しています
2.傘にわっか状の模様(環紋)が見られます
3.カレー粉のにおいがします
問3
1.モエギタケ科フミヅキタケ属に属しています
2.食用になり、栽培キノコとして市販もされています
3.街路樹のプラタナスやカエデなどにも生える身近なキノコです
問4
1.DNAを元にした新しい分類でイグチの仲間に変更されました
2.柄も傘もありません
3.海岸の松林を好みますが、マツの衰退で発生が減少しています
問5
1.枯れたばかりのマツの幹に生えます
2.栗褐色でつやつやした丸っこいキノコです
3.成熟すると、傘の裏側に大きな穴が一つあきます
問6
1.秋、他のキノコに先駆けて生えるのでこの名があります
2.主にマツと共生する菌根菌です
3.傷つけると緑色に変色します
問7
1.ひだの裏は、成熟すると淡紅色に染まります
2.メジャーな毒キノコで、食中毒の常連です
3.判別が難しく「名人泣かせ」の別名があります
問8
1.朽ち木に群生します。
2.木材を分解する力が強く、時に生きている木を枯らすため、林業上の害菌とされています
3.おりみき、あまだれ、さわもたし、ぼりぼり など、さまざまな地方名があります
問9
1.その姿を大黒様になぞらえることがあります
2.菌根菌で栽培は不可能と言われてきましたが、品種改良の結果、栽培が可能になりました
3.マツタケと並び、古来から称賛されてきた美味なキノコです
問10
1.学名はAmanita rubescensです
2.柄の根元はふくらみますが、袋状のつぼはありません
3.傷つけると赤茶色に変色します
正解はここ
問1
1.名前に生き物の名前が含まれています
2.イタリア語でポルチーニと呼ばれ、美味です
3.寒冷地の針葉樹の下に生えるため、日本の平暖地では見られません
問2
1.Lactariusというグループに属しています
2.傘にわっか状の模様(環紋)が見られます
3.カレー粉のにおいがします
問3
1.モエギタケ科フミヅキタケ属に属しています
2.食用になり、栽培キノコとして市販もされています
3.街路樹のプラタナスやカエデなどにも生える身近なキノコです
問4
1.DNAを元にした新しい分類でイグチの仲間に変更されました
2.柄も傘もありません
3.海岸の松林を好みますが、マツの衰退で発生が減少しています
問5
1.枯れたばかりのマツの幹に生えます
2.栗褐色でつやつやした丸っこいキノコです
3.成熟すると、傘の裏側に大きな穴が一つあきます
問6
1.秋、他のキノコに先駆けて生えるのでこの名があります
2.主にマツと共生する菌根菌です
3.傷つけると緑色に変色します
問7
1.ひだの裏は、成熟すると淡紅色に染まります
2.メジャーな毒キノコで、食中毒の常連です
3.判別が難しく「名人泣かせ」の別名があります
問8
1.朽ち木に群生します。
2.木材を分解する力が強く、時に生きている木を枯らすため、林業上の害菌とされています
3.おりみき、あまだれ、さわもたし、ぼりぼり など、さまざまな地方名があります
問9
1.その姿を大黒様になぞらえることがあります
2.菌根菌で栽培は不可能と言われてきましたが、品種改良の結果、栽培が可能になりました
3.マツタケと並び、古来から称賛されてきた美味なキノコです
問10
1.学名はAmanita rubescensです
2.柄の根元はふくらみますが、袋状のつぼはありません
3.傷つけると赤茶色に変色します
正解はここ
キノコの分類ってややこしい!
と思っているアナタのために、キノコ分類(ハラタケ系)をざっくり整理してみた!
DNAをもとにした新分類が科学的には正しいんだけど、アマチュアには優しくないんだよね。キノコを系統だてて覚えるのなら、キノコの形をもとにした旧分類の方が向いてるので、今回はそっちでまとめてみた。
字、ヘタクソなくせに手書き(しかも筆ペン)なので、とこどどころ読めない場所があると思うけど、そこは想像力でカバーしてね(オイ)
注意事項
・各グループの特徴として書いてあることは、そのグループ全部に当てはまるわけじゃない。たとえばイグチの仲間で、コショウイグチは腐生菌だったり、キヒダタケは管孔を持ってなかったりするけど、少数派なので、あえて無視している。
・そのグループ独特の特徴だなー、と思ったものに特マークをつけておいた。たとえばヒトヨタケ科の「傘の液化」なんか。ただし、そのグループ全部ではなく、ごく一部にしか当てはまらない場合もある(ヒトヨタケ科の液化は、まさにそう)。
ハラタケ科とモエギタケ科の「ツバ」ってのは独特ってわけじゃないので微妙かもなー。あとフウセンタケ科に「クモの巣膜」をつけたかったんだけど、書くスペースがなかった(/_;)
・ここでいう「胞子の色」は、≒成熟したヒダの色、って解釈でいいと思う。ただ、イグチなんかは管孔と胞子の色ってかなり違うけどねー。
初心者がキノコの分類をまず覚えるといいのは、テングタケ・イグチ・ベニタケの三つのグループだ。この3つは独立性が高くて特徴もはっきりしているので、分類しやすい。特に夏はこの3つで過半を占めるので、これを分別するだけで一気にすっきりする。
次に覚えるのがハラタケ・ヒトヨタケ系列。基本的に地上生で、白黒のモノトーンか、せいぜい茶色系の単色。地味だけど、形は独特なので慣れてくれば覚えられる。ただし、ハラタケ科にはハラタケ属・カラカサタケ属・キツネノカラカサ属などがあって、それぞれ形がけっこう違うので、別々に覚える必要がある。
でもって、残ったグループがやっかい。ここは胞子の色でわけてみた。
白は キシメジ科
ピンクは イッポンシメジ科(地上)・ウラベニガサ科(樹上)
茶色は フウセンタケ科(地上)・モエギタケ科(樹上・地上)
超ざっくりである。例外がめちゃくちゃ多い。あとはとにかく図鑑めくって覚えるしかないのよねー。
胞子の色がわかる図鑑として家の光協会の『カラー版 きのこ図鑑』を推しておく。
にしてもキシメジ科、寄せ集めにもほどがある(笑)
と思っているアナタのために、キノコ分類(ハラタケ系)をざっくり整理してみた!
DNAをもとにした新分類が科学的には正しいんだけど、アマチュアには優しくないんだよね。キノコを系統だてて覚えるのなら、キノコの形をもとにした旧分類の方が向いてるので、今回はそっちでまとめてみた。
字、ヘタクソなくせに手書き(しかも筆ペン)なので、とこどどころ読めない場所があると思うけど、そこは想像力でカバーしてね(オイ)
注意事項
・各グループの特徴として書いてあることは、そのグループ全部に当てはまるわけじゃない。たとえばイグチの仲間で、コショウイグチは腐生菌だったり、キヒダタケは管孔を持ってなかったりするけど、少数派なので、あえて無視している。
・そのグループ独特の特徴だなー、と思ったものに特マークをつけておいた。たとえばヒトヨタケ科の「傘の液化」なんか。ただし、そのグループ全部ではなく、ごく一部にしか当てはまらない場合もある(ヒトヨタケ科の液化は、まさにそう)。
ハラタケ科とモエギタケ科の「ツバ」ってのは独特ってわけじゃないので微妙かもなー。あとフウセンタケ科に「クモの巣膜」をつけたかったんだけど、書くスペースがなかった(/_;)
・ここでいう「胞子の色」は、≒成熟したヒダの色、って解釈でいいと思う。ただ、イグチなんかは管孔と胞子の色ってかなり違うけどねー。
初心者がキノコの分類をまず覚えるといいのは、テングタケ・イグチ・ベニタケの三つのグループだ。この3つは独立性が高くて特徴もはっきりしているので、分類しやすい。特に夏はこの3つで過半を占めるので、これを分別するだけで一気にすっきりする。
次に覚えるのがハラタケ・ヒトヨタケ系列。基本的に地上生で、白黒のモノトーンか、せいぜい茶色系の単色。地味だけど、形は独特なので慣れてくれば覚えられる。ただし、ハラタケ科にはハラタケ属・カラカサタケ属・キツネノカラカサ属などがあって、それぞれ形がけっこう違うので、別々に覚える必要がある。
でもって、残ったグループがやっかい。ここは胞子の色でわけてみた。
白は キシメジ科
ピンクは イッポンシメジ科(地上)・ウラベニガサ科(樹上)
茶色は フウセンタケ科(地上)・モエギタケ科(樹上・地上)
超ざっくりである。例外がめちゃくちゃ多い。あとはとにかく図鑑めくって覚えるしかないのよねー。
胞子の色がわかる図鑑として家の光協会の『カラー版 きのこ図鑑』を推しておく。
にしてもキシメジ科、寄せ集めにもほどがある(笑)
きのこ検定模試・最後の分野だ!
問1ベニタケの仲間に寄生する、無葉緑植物(葉緑素をもたない植物)はどれ?
1.ナンバンギセル
2.ギンリョウソウ
3.ウマノアシガタ
4.シュンラン
問2
ナガエノスギタケはある動物の巣穴に生えることで有名。その動物とはどれ?
1.アナグマ
2.ノウサギ
3.キリン
4.モグラ
問3
マツタケの発生が激減した原因としてもっとも適当なものはどれ?
1.雨により土砂が流出した
2.自然破壊により発生環境が損なわれた
3.山の手入れをしなくなったため、松林から広葉樹林への遷移がすすんだ
4.乱獲したため、山の神様が怒った
問4
「ナラ枯れ病」を媒介することで知られる昆虫はどれ?
1.カシノナガキクイムシ
2.ヒメマルカツオブシムシ
3.マツノマダラカミキリ
4.ダイオウグソクムシ
問5
ナラ枯れ病の拡大と歩調を合わせるように発生が増え注目されているキノコはどれ?
1.コテングタケモドキ
2.カキシメジ
3.カエンタケ
4.ヒカゲシビレタケ
問6
「きのこの記念日」は何月何日?
1.1月11日
2.9月19日
3.10月15日
4.11月5日
問7
松林の地中にできる菌糸のかたまり(菌核)が漢方薬として用いられるキノコはどれ?
1.カバノアナタケ
2.ショウロ
3.ブクリョウ
4.マンネンタケ
問8
5000年前にアルプスで死亡したとみられる男性・通称「アイスマン」が身に着けていたキノコで、火を起こす火口(ほくち)として利用していたと言われる、英名で「ひづめ茸」の名をもつキノコはどれか?
1.ツリガネタケ
2.シロカイメンタケ
3.ヒトクチタケ
4.カエンタケ
問9
英語圏では「食用でないキノコ、あるいは毒キノコ」のことを、ある動物の名前を用いて「~~stool」(~~の椅子)と呼ぶ。その動物とは何か?
1.リス
2.ヒキガエル
3.子犬
4.コマドリ
問10
「妖精の煙突」、俗に“キノコ岩”とも言われる奇岩を含む特異な地形や遺跡が世界遺産にも指定されている、トルコの地名はどれ?
1.モヘンジョダロ
2.サグラダ・ファミリア
3.クスコ
4.カッパドキア
正解はココ
問1ベニタケの仲間に寄生する、無葉緑植物(葉緑素をもたない植物)はどれ?
1.ナンバンギセル
2.ギンリョウソウ
3.ウマノアシガタ
4.シュンラン
問2
ナガエノスギタケはある動物の巣穴に生えることで有名。その動物とはどれ?
1.アナグマ
2.ノウサギ
3.キリン
4.モグラ
問3
マツタケの発生が激減した原因としてもっとも適当なものはどれ?
1.雨により土砂が流出した
2.自然破壊により発生環境が損なわれた
3.山の手入れをしなくなったため、松林から広葉樹林への遷移がすすんだ
4.乱獲したため、山の神様が怒った
問4
「ナラ枯れ病」を媒介することで知られる昆虫はどれ?
1.カシノナガキクイムシ
2.ヒメマルカツオブシムシ
3.マツノマダラカミキリ
4.ダイオウグソクムシ
問5
ナラ枯れ病の拡大と歩調を合わせるように発生が増え注目されているキノコはどれ?
1.コテングタケモドキ
2.カキシメジ
3.カエンタケ
4.ヒカゲシビレタケ
問6
「きのこの記念日」は何月何日?
1.1月11日
2.9月19日
3.10月15日
4.11月5日
問7
松林の地中にできる菌糸のかたまり(菌核)が漢方薬として用いられるキノコはどれ?
1.カバノアナタケ
2.ショウロ
3.ブクリョウ
4.マンネンタケ
問8
5000年前にアルプスで死亡したとみられる男性・通称「アイスマン」が身に着けていたキノコで、火を起こす火口(ほくち)として利用していたと言われる、英名で「ひづめ茸」の名をもつキノコはどれか?
1.ツリガネタケ
2.シロカイメンタケ
3.ヒトクチタケ
4.カエンタケ
問9
英語圏では「食用でないキノコ、あるいは毒キノコ」のことを、ある動物の名前を用いて「~~stool」(~~の椅子)と呼ぶ。その動物とは何か?
1.リス
2.ヒキガエル
3.子犬
4.コマドリ
問10
「妖精の煙突」、俗に“キノコ岩”とも言われる奇岩を含む特異な地形や遺跡が世界遺産にも指定されている、トルコの地名はどれ?
1.モヘンジョダロ
2.サグラダ・ファミリア
3.クスコ
4.カッパドキア
正解はココ
















