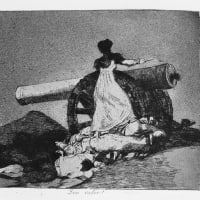サウジアラビアとイランが国交断絶した。すなわち、両国が互いに戦争を厭わないという状態に入ったのである。
三、四日ほど前に佐藤優と山内昌之が出演した「プライムニュース」(BSフジ)をみた。二人とも国際関係の知識と分析にかけては群を抜いているが、なんと「第3次世界大戦」にいたる不安要素があり、想定を超える新たな戦争の視座を解説してみせたのである。
特に佐藤は、今回の一触即発ともいえる情勢を「ポストモダン・モダン・プレモダン」の三つの位相にわけて、中東のパワーバランスを的確に分析していたのは印象的だった。
ポストモダンは脱現代であり、今後をみすえた未来戦を・・。宇宙やサイバー空間での戦争を想定し、ITや無人兵器、或いは核使用までも見据えたもの、と私は深読みした。モダンは近代、つまり国家間の戦争であり、従来型の力と力のぶつかりあいといっていい。三番目がプレモダンつまり前近代的なファクターが関与したもの。イスラーム社会ならではの宗教・宗派、部族間での軋轢、伝統的な慣習、民族的ネットワークによって、ノマド的というか分散・拡散型の戦争形態が現れるだろうということだ。(現在の中東諸国は、かつての西洋帝国主義によって都合よく線引きされた国境をもつ国家群だ。現在のイスラームの人々が抱いている国家イメージとは、部族とか宗派に属する想像上の共同体であろう。さらに、それは地域に固定されていないし、移動する場合もある。これこそがノマド=遊牧民の漂流するコミューンだ)
要は、イスラーム社会そのものが、プレモダン=前近代に深く根ざしていること。それは、今日的な科学合理主義を拒絶することで、イスラームという独自な社会が形成されたともいえる。
そして、私のなかで、なぜか小室直樹がよみがえった。「世紀末・戦争の構造」という徳間書店の文庫本を引っ張り出した。副題が「国際法知らずの日本人へ」となっていて、日本国憲法のみならず国際法にも精通した小室の慧眼が随所にいきた評論である。その第二章が「なぜイスラム教は近代をつくらなかったのか」である。(ちなみに第一章は「近代の基礎をつくったキリスト教」)
そのエッセンスを書く。
神は唯一神であり。イスラム教は、その他の如何なる神も絶対に認めない。キリスト教では、イエスが神か人かをめぐって大論争があり、三位一体説が生まれた。イスラム教はいかなる曖昧さを断乎として拒否している。
預言者マホメットは、神と契約を結んだ。神との契約=命令は則(そく)であり、法律であり、規範であり、戒律である。マホメットは、最終預言者でありその契約も最終的であるから新たな預言者がでてきて、契約を更改することはありえない。これがイスラム世界を、途方もなく保守的にした。第一法源は「コーラン」であり、第二法源は「スンナ」(マホメット言行録)であり、これらは不動、絶対である。
「よいことをせよ、わるいことをするな」とは、コーランが繰り返し力説する。(この点、福音書には、命令・禁止が一言もない。)さらに、イスラム教において勤行を明確に特定している。
信仰告白、礼拝、断食、喜捨、巡礼 この五行が宗教的義務でありイスラム教徒は必ず行わなければならない。これらは人間の外面的行動に関する命令(戒律=規範=法律)が多い。・・一方キリスト教徒であるための条件は、内面における信仰だけである。外面的行動はなんであってもよい。
イスラームにおける一日に五度の礼拝、一か月近くの断食などは、それだけで近代化を拒絶するものであり、経済活動にも支障をきたしている。
以上は抜粋で、要約もしている。この「なぜイスラム教は近代をつくらなかったのか」という章立てではあるが、実のところ大半がキリスト教についてである。しかし、イスラム教の本質を端的に語り、かつキリスト教と比較しつつイスラーム社会の後進性や硬直さを手際よくまとめている。次章の「国際法の成立の背景」、第四章「湾岸戦争で戦争の概念が変わった」へとつながる重要なパートになっている。
このブログを書くきっかけは、 昨日、友人とネット上で経済評論家の池田信夫の話題から、故小室直樹の話に及んだからだ。彼がいかに知の巨人であったかを確認する意味もある。
フランスの社会学者エマニュエル・トッドは乳幼児の出生率データからソ連崩壊を導きだしたが、それ以前に小室直樹は底知れない知力によって、ソ連瓦解を見事に予測していた。(※)私が二十代の頃は、カッパブックスといえば小室直樹の本であった。いま、橋爪大三郎や宮台真司らによって再び脚光浴びつつあり、かつての著作も続々復刊され始めた。
さて、件のサウジアラビアとイランの話。単なる宗派対立、スンニ派とシーア派の盟主同士の戦争ではなく、イスラーム世界全体をまきこむ内ゲバ的様相をみせ、それが従来とは違う形態の第3次世界大戦に発展すると懸念されているのである。また、ペルシャ湾を挟んで対峙する両国の動きよりも、背後に控える大国・米ソの関与でいかようにも深刻度合が変わるとのこと。プレモダンからポストモダンという三つのフェーズが複雑にからみあって、人智に及ばない錯綜とした紛争に発展しそうである。
不安視されるロシア経済の今後、トルコの煮詰まり(統治の脆弱)、ISの行く末、オバマ以降のアメリカ、難民で揺れるEU、カタールやイエメンなど周辺国の動向、鳴りを潜めているイスラエル、イラン高原付近のチェチェン人・クルド系の少数民族らの軍事組織・・、これらは私たち素人が考えてもどうなるものではない。
ただただ、平和な国際社会を祈るしかない年頭になってしまった。
※佐藤優、山内昌之が出演したプライムニュース。もう、ユーチューブにアップされていた。約1時間半なので、お暇な方向きです。下記アドレスをコピペしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=z3bSCXyXMDo (非公開になりました。深謝いたします)
※(追記/1・13) 北朝鮮の核実験について何もふれていない。これには深い意味はない。今回のマスコミの調査では、北朝鮮の核について脅威を感じる人は大半であった。なんの脅威も感じない人は4%いた。私もそこに含まれる。このブログをはじめて1,2年して「北朝鮮の核」について書いたが、そのときの考え方に変更はない。北朝鮮の対外戦略パラダイムおよび幼児的戦術アクティビティは、アメリカによってほとんど既定されているといっていいぐらいだ。北朝鮮の核を買い求める国はどこもいない。サウジアラビアでも買わない。北朝鮮がみずから使う? そこまで馬鹿ではない。
※(追記・2016 3/28)小室直樹の「ソビエト帝国の崩壊」の出版は1980年。エマニュエル・トッドの「最後の転落」の出版年は1976年でした。小室直樹の著作より4年前に先行して出版されていました。ここに訂正して深くお詫び申し上げます。トッドの著作は未読です。それにしても、彼が25歳のときの著作ですから驚愕いたしました。「シャルリとは誰か?」を読んでいて、その違いに思い至り、確認したところです。猛省しています。