上から目線という言葉がある。使われだしたのは、十年前ぐらいも前だろうか。人が他人をあからさまに「見下す」のではなく、自分では気づかずに権威的、優位的なものの見方や表現をしている時のことを言う。
あるとき、若いカップルのこんな会話を耳にしたことがある。
「そういう話し方ってウザイ。上から目線だよ。人を傷つけるかもしれない。気をつけた方がいいよ」と、女性がやんわりと彼氏をさとしていた。若い人たちの他者への配慮は意外にもきめ細かいのである。
いまはもう、「上から目線」はもっと強い意味をもち、他人を配慮しない横柄な人、傲慢な人を揶揄する場合にも使われている。
さて、上からものを見ることは人を見下すという面もあるが、鳥のように俯瞰する、高い視点から広い視野でものをみることができるというポジティブな面もある。
また、絵画や映画における「俯瞰する」像は、対象を的確に客観的にとらえるだけでなく、日常では感じることのできない安心感や癒し効果をもたらすのではないか。
誰しもが見晴らしの良い高い所に立って眼下を見渡したことがあるだろう。その高い塔やビルに登った時の、街の情景を見下ろしたときの感覚を呼び覚ましてほしい。
高みから人々を見守る、或いは睥睨する感覚。それは神や天使のまなざしといえないか。
先週の土曜日に「安野光雅展 旅の風景・ヨーロッパ周遊旅行」に行った。いまだ現役の日本を代表する絵本作家であり、柔らかな光と色彩が交錯するような美しい作品群は多くの人がみとめるアート作品だ。
初期の西欧旅行のスケッチから「旅の絵本」の原画など、まさに安野光雅ワールドにときめいた。
ただ不思議なことに気がついた。どのシリーズの作品も視点が同じなのである。ぶれがない、安定しているともいえる。これほどの作品群を一堂に集めて鑑賞できることは、ファンならずとも僥倖といえよう。特に、「旅の絵本」シリーズでは、一定の角度で風景を見下ろしている。これはルーチンであり、凡庸さにもつながりかねない。




どういう場所から描いているのか? 近くの高台か塔などにのぼって見下ろしながら描いたのであろうか。どの作品も同じシチュエーションなので、その疑問が強くなってきた。もしかしたら想像力で描いたかもしれない。
その一定した見下ろす角度は、いわゆる黄金比率みたいなものと関係していないだろうか。
最も安定した美感を与える長方形、その縦と横との関係が黄金比(1:1.618、約5:8)の割合となっている。キューブリックの名画「2001年宇宙の旅」に出てくるモノリスがそうだ。
パルテノン神殿、ピラミッドといった歴史的建造物やレオナルド・ダヴィンチ、コルビジェなどのアート、自然界では植物の葉脈や巻き貝の断面における螺旋模様など、この黄金比(1:1.618、約5:8)は都市伝説のように語られている。
同じように、人が見下ろす角度にも、その黄金比率のようなものが関係してはいないか・・。
ちなみに、飛行機が安定して着陸する角度はどんなものか調べてみた。

あるのだ。飛行機はどんな機体でも30度の角度を保って降下するらしい。ちなみに着陸しようとする航空機に適正な進入降下角度を示すために、滑走路に設置された表示灯をPAPI(パピ、Precision Approach Path Indicator)という。PAPIは、パイロットへ適正な進入降下角度°3を可視光で伝える役割をもつ。(ウィキペディアでは°3という表記。これは30度を示すものか分からない)
もし安野光雅の「旅の絵本」で表されている見下ろす視線の角度が30度であったら、これは面白くなる話になるであろう。
どなたか、この素人仮説を証明して下さる方はいないだろうか。



















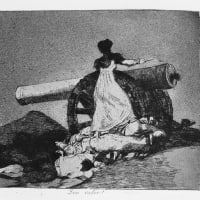

30度で降りられるのはVTOLかヘリかオスプレイかというところで、普通の機体なら30度での進入降下は着陸ではなく、墜落と呼ばれます。
安野画伯の旅の絵本シリーズは、一定の角度で見下ろしている、すなわちアクソノメトリックで描かれてはいません。
明らかにパースペクティブで描かれており、近くは急な深い角度で、遠くは浅い角度で見下ろされています。
画伯には角度について子供向けに絵解きした作品もあったかと存じます。
今からでも、初歩から勉強されてみては。
余りにも目に余る内容だったので、「鳥の目」から一言申し上げました。