刑法の論文対策をやってます。
さてさて、下記の場合の解決が分かりません。
行為無価値論者です。
過去問の類似事案です。
#別に乙は不要です。
「甲がAを殺害するために、Aを熟睡させる目的で乙に睡眠薬を渡した。
そして、乙は気づかずAに睡眠薬を投与した場合。」
#「甲がAを殺害するために、Aを熟睡させる目的で睡眠薬を飲ませた。」
#というのでもOKです。
甲はAに対して、殺人予備罪が成立。
#ここでスタ100は殺人の実行行為としているが、
#犯罪結果発生の具体的・現実的危険性はないというべき。
#∵睡眠薬を飲ます行為が全て殺人罪の実行行為になる
#構成要件的実行行為を検討するなら、客観面に即して判断すべき。
しかし、睡眠薬を用いた場合は傷害罪だから、傷害罪の間接正犯。
この場合、殺人予備罪の認識で傷害罪の間接正犯の結果発生ww!?
錯誤じゃないし。認識意思通りの結果発生。
でも、法定刑が2年以下と15年以下ですから、だいぶん違う。
殺人予備の認識なのに、傷害罪の間接正犯の認識も包含??
法条競合??
はて??
さてさて、下記の場合の解決が分かりません。
行為無価値論者です。
過去問の類似事案です。
#別に乙は不要です。
「甲がAを殺害するために、Aを熟睡させる目的で乙に睡眠薬を渡した。
そして、乙は気づかずAに睡眠薬を投与した場合。」
#「甲がAを殺害するために、Aを熟睡させる目的で睡眠薬を飲ませた。」
#というのでもOKです。
甲はAに対して、殺人予備罪が成立。
#ここでスタ100は殺人の実行行為としているが、
#犯罪結果発生の具体的・現実的危険性はないというべき。
#∵睡眠薬を飲ます行為が全て殺人罪の実行行為になる
#構成要件的実行行為を検討するなら、客観面に即して判断すべき。
しかし、睡眠薬を用いた場合は傷害罪だから、傷害罪の間接正犯。
この場合、殺人予備罪の認識で傷害罪の間接正犯の結果発生ww!?
錯誤じゃないし。認識意思通りの結果発生。
でも、法定刑が2年以下と15年以下ですから、だいぶん違う。
殺人予備の認識なのに、傷害罪の間接正犯の認識も包含??
法条競合??
はて??












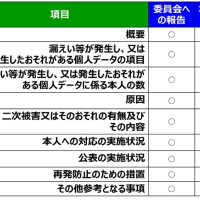
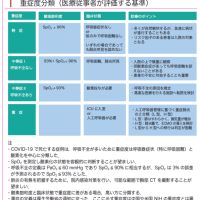
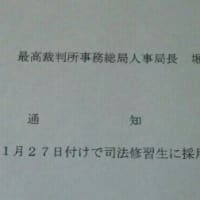











元の問題を知らないのですが、
「殺害するために」
→殺人の故意
(傷害の故意を包含)
「熟睡させる目的で」
→殺人予備罪の故意
なのではないでしょうか。
「殺害するために(=殺人の故意で)」睡眠薬を飲ませたのか、
それとも「殺人の準備として(=殺人予備の認識で)」睡眠薬を飲ませたのか…が、ポイントなんじゃないかと思いました。
コメントありがとうございます。
すいません。元の問題は、平成10年第1問で、
「甲は愛人と一緒になるために、病気で療養中の夫Aを、病気を苦にした首吊り自殺を装って殺害する計画を立てた。
そこで甲は、まず、Aに睡眠薬を飲ませ熟睡させることにし、Aが服用する薬を睡眠薬と密かにすり替え、自宅で日中Aの身の回りの世話の補助を頼んでいる乙に対し、Aに渡して帰宅するように指示した。
略」
です。
睡眠薬を飲ませることは、熟睡させるためであり殺害するための準備行為としての予備罪の認識だと考えます。
とすると、認識が殺人予備罪、発生事実が傷害罪の間接正犯(本来の問題とは異なりますが)になるのだろうか??
ということです。
錯誤ではないはずなのにいいのかなぁ?という疑問です。
スリの場合のポケットを触る点が実行行為かどうかの例題に似ているのかもしれません。
こちらこそ!
丁寧にありがとうございます(*^_^*)
H10問題では、Aは睡眠薬の服用によって死亡していますね。
ばぶちさんの応用問題(#にします)では、Aは昏睡状態になった、くらいでしょうか。
どちらの事例でも殺人予備罪が成立するのは、間違いなさそうですね。
ただ、ばぶちさんのおっしゃるように、殺人予備罪では、罪が軽すぎる。
そこで、
次に、傷害罪にあたらないか検討。
そうすると、甲または乙の行為により障害の結果(Aが昏睡状態になった)が発生するものの、殺人準備の故意しか存在しない。
つまり、ゆくゆくは殺人を犯す目的があったものの、殺人(傷害)そのものの故意がないわけで…
殺人準備の故意で、傷害の結果が発生した。
これは、行為者が認識した犯罪事実と現に発生した客観的な犯罪事実とが一致しない場合にあたります。
事実の錯誤にあたるのではないでしょうか?
H10は、Aが死亡しているので認識事実と発生結果は一致します。ただ、行為者の予見しない因果関係の経路をたどって発生結果が生じたので、因果関係の錯誤や「早すぎた結果発生」が論じられるのでしょうね。
以上のように感じました。
ご意見ありがとうございます!!
やはり認識事実と発生事実が異なる構成要件となるので、抽象的事実の錯誤としたほうが良い気がしますね。
H10年の問題なんですが、甲について、私は認識事実と発生事実が一致しないと考えているんです。
なぜなら、認識事実はやはり、殺人予備で、発生事実は殺人だと思います。
問題文は
「まず、Aに睡眠薬を飲ませ熟睡させること」
であり、
首吊り自殺を装って殺害するための予備段階だと思うのです。
睡眠薬を飲ませ熟睡させるだけであれば、認識においても発生事実においても、死亡結果の具体的・現実的危険が発生したといえない気がするのです。
というわけで、甲には殺人予備罪が成立するが、傷害罪も成立か??という思考過程に至ったのです。
この問題は、殺人の実行行為ありとする見解とないとする見解の両方があり得ますから、どちらも正解なんでしょう。
H10問題について、
ばぶちさんは、
1.発生事実
(これは殺人でなくAの死亡ですよね?)
①死亡結果の具体的・現実的危険が発生するほどではなかったが、②傷害罪には該当するものだった。
2.甲の罪責
①殺人予備罪の既遂と
②傷害致死罪の既遂が成立し、両罪は観念競になる。
と考えていらっしゃるんですね。
ところで、ばぶちさんの使っていらっしゃる本では、甲乙の罪責や経過はどうなっていますか?
私はWセミナーの過去問集を参照していますが、殺人予備罪について言及していないんです。
出版元ごとに解答の内容にどのくらい差があるのか、ちょっと気になりました。
因みに、早稲田の解答内容はこんな感じです。
↓行為無価値(大谷説)
乙:殺人既遂。
甲:殺人未遂。
→早すぎた構成要件発生の事例として、殺人既遂の具体的危険を客観的に発生させたから。
↓結果無価値(前田説)
乙:殺人既遂。
甲:傷害罪
早すぎた構成要件発生の事例とするものの、第一行為と第二行為が接着し密接に関係していないため、殺人の故意が認められない。
傷害罪の既遂にとどまる。
こんばんは~。
色々考えてみましたが、やはりH10年は殺人予備罪だと思います。
Aを昏睡させたのが甲であれば、傷害罪既遂です。
ごちゃごちゃしてきたので新たに本記事にまとめておきます。
過去問は私もスタ100(行為無価値)です。
H10年の私の見解は
1.甲の実行行為
Aへの傷害(昏睡目的)の間接正犯の実行の着手あり
あるいは殺人予備の間接正犯実行行為終了
(ここでスタ100は殺人の実行行為ありとするのに疑問なんです。)
2.発生事実
A死亡
3.因果関係
乙の介在により遮断
よって、死亡結果の責任を問えない
4.故意
殺人予備の故意
5.甲の罪責
殺人予備罪
早すぎた構成要件の実現というのは、
第一行為と結果の因果関係があることが前提ですよね。
すると、実行行為ありの場合に「早すぎ」が問題になって、なしだと問題にならないんでしょうか?
ちなみに、私の持ってる答案は、第一行為が予期せぬ殺人教唆の結果を発生させたと、検討してます。(辰巳と柴田です)
確かにそれなら、実行→結果、早すぎ問題になるかな??認めるかどうか別として。
楽しくなってきましたね(*^^*)昼にでも、新しい記事の方にコメントに伺います♪
早すぎた構成要件の事例について、
mameさんへ
早すぎ~の事例では、故意の有無が問題になります。
すなわち、
mameさんのおっしゃる通り、行為と結果の間には因果関係が存在します。
しかし、犯人は、あくまで第二行為で被害者を殺すつもりでした。
なので、第一行為には殺人の故意が(直ちには)認められません。
殺人の故意がなければ、構成要件を満たさないので殺人罪には当たりません。
でも、それだとおかしくないか?刑が軽すぎないか?
というわけで考えられたのが「早すぎ~」になるわけです。
これで答えになったでしょうか(;^_^A
H10について、教唆という考えもあるんですね!出版元ごとに違うなんて驚きました。
未熟者ですんで、勘違いしてたらすいません。
「早すぎ~」って、
第一行為①から第二②で予定された結果が生じた場合に、
①での故意を認められるか?の問題ですよね。
①と結果の因果関係がなければ(危険なし=実行行為でないなら)、
「早すぎ」で故意を検討するに至らないのはないかと。
①から教唆の結果発生とする(殺人の故意は教唆の故意を含むとする)なら、
②のつもりが①で殺人(教唆)が結果発生しちゃったということで、
①での故意を検討する必要があるように思います。
ただ、Wの過去問(私のはちょっと古いです)は、
①と死亡の因果関係を否定してすぐ、「早すぎ」で①での故意を検討してました。
途中、①から死亡の危険までは発生させたことを認定(①の実行行為性)がないので、
①での実行は認めたくない私には、なんか変な感じがしたのです…。
第一行為と結果発生の因果関係を否定するんですね。
確かに、そうであれば早すぎ~の問題は発生しません。妥当な解決だと思います。
(そうして見返すと、確かに早稲田の解答は「…?」ですね;)
ただ、2つ気になることがあったので、補足として↓に挙げておきます。
1.教唆について
(1)まず、甲の罪責を教唆で検討してありますね。
殺人の教唆でしょうか?
だとすれば、
教唆とは、人を殺すようそそのかすことですね。本事例で甲は、「(自分が)Aを殺すために」乙に睡眠薬を渡しています。
このことから、私は甲に教唆の故意は無いと考えます。
よって、
あえて殺人の教唆を取り入れるとすれば、
『甲はA傷害(かA殺人準備)の目的で乙に睡眠薬を渡した。しかし、発生した結果はAの死亡であり、一見して殺人教唆のような外観を備えていた。』
という感じになるでしょうか。
(2)一方、
傷害の教唆であれば、成立するかもしれません。
その場合は、単に乙が甲の意図を見破って利用しただけなのか、それとも、甲が乙の殺意を高めた(殺人を決心させた)まで言えるのかがポイントになると思います。
2.故意について
なお、mameさんは殺人の故意に殺人?教唆の故意が包括されるとしてありますね。
一概にはそう言えないと考えます。
なぜなら、「自分が殺す」ことと「人に殺させる」はイコールでないし、一方が他方を包括する関係にも無いと考えるからです。
以上です~