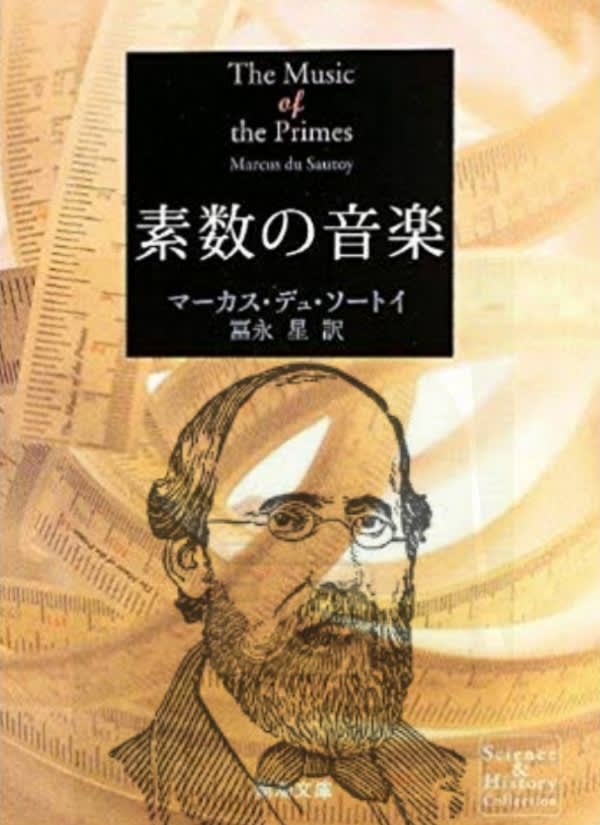
”その5”を更新するうちに長くなりすぎたので、2つに分けます。
故に、この後半部は”その6”になりますが、前半部の”その5”では、リーマンの第4論文の大まかな概略とリーマンが独自に定義した主要公式(解析公式)J(x)の説明でした。
そこで今日は、主要公式J(x)が誤差項を含む明示公式π(x)に展開され、リーマン予想に結びつく過程を紹介します。
解析公式と素数定理の誤差項と
この主要公式J(x)は、後のフォン•マンゴルドにより、新たな明示式に置き換えられ、主要公式の導出を証明します。そして最後には、リーマンの明示公式π(x)の導出にも成功します(1895年)。
リーマンが独自に定義した主要公式は、J(x)=π(x)+π(√x)/2+π(³√x)/3+π(⁴√x)/4+π(⁵√x)/5・・・ときれいな形で表され、”メビウス反転”を使えば、π(x)=J(x)−J(√x)/2−J(³√x)/3−J(⁵√x)/5+J(⁶√x)/6−J(⁷√x)/7+J(¹⁰√x)/10・・・=Σₙμ(n)J(ⁿ√x)/nと、π(x)をJ(x)で表せ、π(x)をJ(x)同様に4つの項に展開します。
但し、μ(n)はメビウスのμ関数と呼ばれ、nの条件により、0、1、−1との値をとります。
因みに、このπ(x)の解析公式は、”Σₙμ(n)/n*Li(ⁿ√x)+ΣₙΣᵨLi(ⁿ√(x^ρ))+(より小さな項)”と、大きく3種の項に分けられます。
つまり、第3のより小さな項とxの大きさに比例して一定の割合で大きくなる項(第1項=主項)を無視すれば、リーマンの明示公式とは数論的関数π(x)をメビウス関数μ(n)という周期関数に置き換えたものとも言えますね。
このリーマンの明示公式(素数公式)は、最初の主項(第1項)だけで見ても、ガウスの近似”π(x)~Li(x)”に比べても、ずっと精度が高い。
更に、リーマンが示唆した近似の拡張”π(x)~Li(x)+Σₙ[2,∞]μ(n)/n*Li(ⁿ√x)”で言えば、レーマーの近似(1913)よりも驚くべき程よい。
故に、リーマンの明示公式は”誤差項を含んだ素数定理”と呼ばれます。
つまり、リーマンは自ら生み出した離散関数J(x)を数論的関数π(x)に置き換えたと言える。
しかし、この明示公式が完全なものである為には、J(x)の解析公式の第2項”周期項”(ΣᵨLi(x^ρ))に登場する”リーマン予想”(ゼータの虚根のRe(ρ)=1/2)の完全決着が必要だったんです。
因みに、J(x)の主要公式もπ(x)の明示公式もフォン•マンゴルドが証明したんですが、その本当の困難さは、J(x)の周期項(第2項)のゼータの零点(根)ρに関する和(ΣᵨLi(x^ρ))が”項別積分可能”という事にあった。
しかしリーマンは、項別成分可能を主張しただけで、証明はしなかった。一方で、後にマンゴルドは項別積分の可能性を直接扱わず、異なる方法で主要公式を証明した(1895)。
お陰で、リーマンの”項別積分可能”の主張が正しかった事が証明されたんです。
因みに、この項目積分可能性を証明したのは、後のランダウ(1908)である。
主要公式J(x)の悲劇と
リーマンは主要公式J(x)の理由付けとして、数論的関数π(x)と経験的導出の近似Li(x)との解析的明示公式を示す為としてました。
そこには、ガウスの観察に基づいた素数定理の近似である”π(x)~Li(x)”の存在があった。これは、チェビシェフが考察した(階段)関数Ψ(x)を使えば、素数定理はΨ(x)~xと同義でした。
つまりチェビシェフのΨ(x)は、リーマンが生み出したJ(x)よりもずっと簡単でした。それに、J(x)にはマンゴルドが新たに導いたΨ(x)の公式と同じ情報を含み、一般化するにも証明するにも大きな困難さが付き纏う。
そこでマンゴルドはJ(x)ではなく、Ψ(x)を使って、リーマンの明示公式を導き出した。
故に、リーマンの第4の論文の主題である”主要公式J(x)”が忘れ去られてしまったという悲劇と真実。
リーマンは論文中でも注記してる様に、”リーマン予想は直接の対象には必要ない”。つまり、単にπ(x)の明示公式を得る為には必要なかったのだ。
しかし、この式によって導かれる結果の性質だけが、リーマン予想の正しさに左右される。
リーマン予想の本当の目的は、π(x)の形をとる素数の分布とゼータ関数の非自明な零点との密接な関係を示す事である。
つまりこの零点は、素数定理における誤差項の大きな、そして主要な成分をなしてるのだから(リトルウッド)。
しかし上述した様に、アダマールがクシー関数の積表示を証明し、マンゴルドやランダウが主要公式J(x)の積分可能性を証明した事は、リーマン予想にとっても後に、大きな意味を持つ事となる。
但し、ガウスの素数定理”π(x)~Li(x)”が正しいかという基本的な問題は、リーマンの論文では未解決なままだった。しかし、アダマールとプサンが証明した素数定理(1896)により初めて証明されました。
つまり、リーマン予想ばかりが未解決だと大きく騒がれるが、Re(s)=1/2上の零点分布の評価とJ(x)の主要項の項目積分可能性やクシー関数の積公式は、リーマンの死後に証明されたものである(「ゼータ関数とリーマン予想」)。
リーマン予想のその後
オイラーは、ゼータ関数ζ(s)をsが整数の時について考えたが、ディリクレはこれを実数へと、そしてリーマンが、複素数の範囲へと拡張した。
複素解析の威力が明らかになり、ゼータ関数の解析が進むと、そこから素数定理の証明が期待される様になった。当然、複素解析のスペシャルであったリーマンが必然的に関わる事になる。
実は1848年、チェビシェフがゼータ関数を使って素数定理の証明を試み、その可能性を示唆してはいた。
そして1859年にリーマンは、簡潔だが洞察に富む論文の中で、ゼータ関数の役割を明らかにし、素数の統計的性質がゼータ関数の零点と密接な関係にある事を示したのだ。
この論文の山場は、「与えられた値xより小さい素数の正確な個数」を、ゼータ関数の零点に渡り、足し合わせた無限級数として与える公式である。
その中に、自明な零点(根)を除いた全ての零点が全て、s=1/2+itという臨界線(Critical Line)上にあるという”リーマン予想”を含んでいた。
しかし当のリーマンは、”厳密な証明がほしい所だが、調べている直接の対象には必要がない”と述べるに留まってる。
この予想が正しければ、幾つもの重要な結論が導かれる。特に素数に関する様々な近似式がより精確(明確)になるが、証明も反証も見つかってはいない。
故に、Critical Line上の零点分布研究の発展に大きく繋がった。
1914年、ハーディーとリトルウッド(共に英国)は、”臨界線上に無限個の零点がある”事を証明した。これでリーマン予想に決着が付いたかに見えたが、”零点が一直線以外にも存在する可能性”を拭いきれず、結局は挫折した。
この研究は1942年のアトレ•セルバーグにより、クライマックスに達する。ハーディとリトルウッドの先駆的な研究を受けたセルバーグは、この直線上の零点数の増大度がKT(logT)以上(Kは正の定数)である事を示した。
ここにゼータ関数の零点は”ある定比率でこの直線上に乗ってる”事が、初めて確定した。
因みに、ハーディとリトルウッドは”KT以上”である事を証明していた(1921年)。
リーマン予想の反例とは?
”人工知能の父”と名高いアラン•チューリング(英)はリーマン予想の反証を試みた。1937年にコンピュータを開発し、1000個を超える零点を見つけたが、リーマン予想の反例を見つける事は出来なかった。
反例で言えば、”レーマー現象”が有名である。D•H•レーマーは、2万5千個の零点までリーマン予想が正しい事を、ジーゲルの公式(リーマン-ジーゲル公式=1932)とチューリングの方法で計算した。
しかし、有限体上のゼータ関数であるZ(t)の不規則な振舞いをも明らかにし、リーマン予想の反例の僅かな可能性を見出した。
2002年、ヴェデニフスキーは”ZetaGrid”プログラムにより、最初の1000億個の零点を確認した。しかし、コンピュータによる大量計算をした所で全ての零点を発見できる筈もない。
現在では、10兆個(2004)までの零点がリーマン予想を満たす事が計算され、反例は未だ知られていない。しかし無限にある零点からみれば、有限に過ぎない10兆個程度の零点は、零点分布の真の姿を反映するには至らないとして、この計算結果に対して慎重な数学者もいる(ウィキ)。
事実、「ゼータ関数とリーマン予想」の著者であるハロルド•M•エドワーズは、”レーマーの現象及びZ(t)が有界でない事実の発見は、リーマン-ジーゲル公式に基づく如何なる主張の発見をも無効とするものであり、・・・直線上以外にも根ρが現れる可能性は全く否定できない。リーマンの洞察は驚くべきものではあったが、人知を超えた予知能力とまでは言えない。1859年に、<恐らく>正しいと考えた主張が否定される可能性も、今日では出てきてるのである”と述べてはいる。
最後に〜素数の音楽家としてのリーマン
1972年には、ヒュー•モンゴメリーと物理学者のフリーマン•ダイソンがゼータの零点の分布を表す数式が原子核のエネルギー間隔と一致する事を発見し、リーマン予想と原子物理学が関連してる事が判り、更なる研究を促す事になる。
一方でリーマンは、素数に関する明示公式を導出する際、フーリエ解析(反転)を利用する事で、ゼータ関数の零点(解)が素数の不規則性を支配してる事に気付いた。
つまり、ゼータ関数の零点におけるフーリエ変換が、素数の累乗の集まりに幾つかの基本的因数を加えたものだったのだ。
複雑な音波(関数)を”フーリエ解析”すると基本的な正弦成分(周波数)に分解される。それと同じ様に、素数の壮麗で不規則な狂想曲も、ゼータの1つ1つの零点が奏でる個々の”音程”(周期成分)に分解される。それぞれの音程の大きさは、それに対応する零点の実部の大きさによって決まるのだ。
つまりリーマン予想とは、”全ての零点が同じ大きさ(1/2)の音を出す”と主張してる事になる。故にリーマンは、ゼータ関数に関する深い洞察を行った故に、”素数の音楽家”と見なされてるのだ(「素数の音楽」)。
かなり長くややこしくなりましたが。次回の”その7”では、リーマンの晩年の生涯について述べたいと思います。










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます