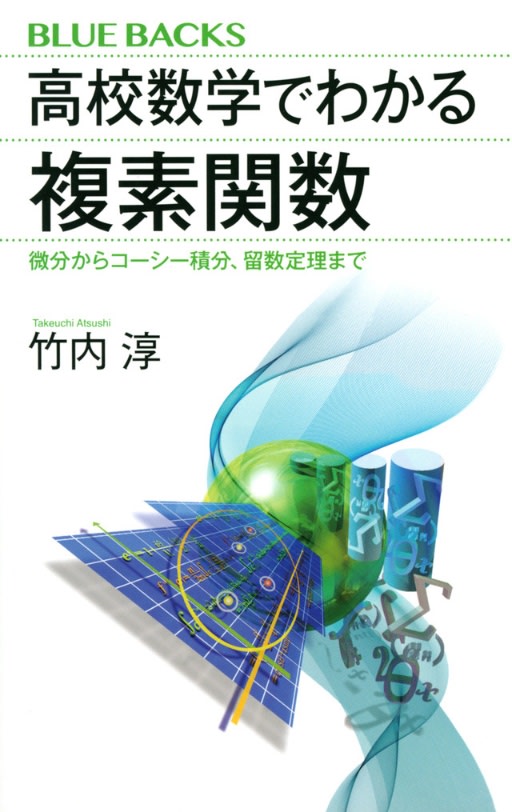
”3の8”でも少し述べた様に、リーマンの明示公式(素数公式)の導出には、ゼータ関数の解析接続を用います。この解析接続には、複素関数の積分が不可欠です。
そして、この複素積分の肝となるのが”留数定理”です。この留数定理は”複素解析の為にある”と言っても過言ではありません。
リーマンが求めた明示公式にも、留数定理がしばし登場します。故に、リーマンの論文(1859)の中に、この2πiを含む周回積分が数多く登場します。
例えば、ある複素関数fの極s=aにて留数Aが存在する時、その留数Aさえ判れば、極aの周りを周回する積分”∫f(s)=2πiA”が導き出せます。
つまり、f(s)の周回積分の答えが、”2πiA”になるという見事なトリックです。
このトリックを使う為には、まずテイラー展開とローラン展開を理解する必要があります。
そこで2回に渡り、複素関数の級数展開と留数定理について述べたいと思います。
テイラー展開と複素関数展開
先ずテイラー展開ですが、単にある点の周りの複素関数の展開の事です。
一般に、複素関数f(z)の点aの周りのテイラー展開は、f(z)=f(a)+f’(a)(z−a)+f’’(a)(z−a)²/2!+f’’’(a)(z−a)³/3!+・・・、(z∈C)―①と複素関数を単純な多項式の和で表せる”魔法の展開公式”です。
因みに、この概念はのジェームズ・グレゴリー(スコットランド)により定式化され、1715年にブルック・テイラー(英)により導入された。また、a=0として原点周りのテイラー展開をマクロリン展開とも呼び、f(z)=f(0)+f’(0)z+f’’(0)z²/2!+f’’’(0)z³/3!+・・・で表します。
仮に①式をf(z)=k₀+k₁(z−a)+k₂(z−a)²+・・・、a,k₀,k₁,k₂…定数とおき、まずf(z)にz=aを代入すれば、k₀=f(a)を得る。次にf(z)をzで微分しz=aとすれば、k₁=f’(a)を得て、更に微分すれば、k₂=f’’(a)/2を得る。これをn回繰り返せば、kₙ=f⁽ⁿ⁾(a)/n!となり、①式のテイラー展開を得る(証明終)。但し、厳密には以下で述べる”テイラーの定理”を使って証明すべきですが・・・
しかし、このテイラー展開にも制約がある。丁度、マジックには種と仕掛けがある様に。
先ずは、zとaが離れすぎてはいけない事。
aから僅かに離れたzにおいて成り立つのが一般的ですが、zがaを離れる程に展開項の数を増やせば、ズレが補正されて正確な値に近付く訳だが、勿論限界がある。
この限界を収束半径といい。収束半径の値は、どんな関数をどこの周りに展開するかにより異なる。関数によっては収束半径が無限大になるものも存在する。
便利なものほど厄介なんですね、現実も同じです。
もう1つの注意(制約)が、このテイラー展開の右辺(無限和)が必ずしも収束する訳でもない事です。
故に、剰余項”f⁽ⁿ⁾(c)”を展開式の最後に加え、収束させておきます。
故にテイラー展開は正確には、f(z)=f(a)+f’(a)(z−a)+f’’(a)(z−a)²/2!+・・・+f⁽ⁿ⁾(c)(z−a)ⁿ/n!となり、これはこの等式を満たすcがzとaの間に必ずある事を示してます。そして、これを”テイラーの定理”と呼びます。
つまり剰余項とは、テイラー展開の左辺の”関数f(z)の値”と右辺の”n−1次の項までの和”との”誤差”を表す。
cの値は具体的に分からない事が多いが、誤差の推論はできる。故に、右辺が収束するかの判断材料として使えます。
そして3つ目の制約だが、当前の事だが関数が微分可能(⇒正則)という事。しかし関数には、微分を繰り返すうちに滑らかでなくなったり、不連続になったりするのがある。つまり正則でなくなる場合があり、そういうのは展開できないのだ。
そこでテイラー展開の例を幾つか挙げる。指数関数や三角関数を0の周りで展開すると、
eˣ=1+x+x²/2!+x³/3!+・・・、
sinx=x−x³/3!+x⁵/5!+・・・、
cosx=1−x²/2!+x⁴/4!+・・・、
tanx=x−x³/3+2x⁵/13+17x⁷/315+・・・、などがあります。
特に、sinxの展開はオイラーの”バーゼル問題”で有名ですね。tanxの展開は結構ややこしいですが、ベルヌイ数Bₙで表せる事が知られてます。
これらの(初等的)超越関数が単純な和で展開でき、これらの収束半径は∞で、xの値に拘らず常に成り立ちます。
一方で対数関数の展開は、log(x+1)=x−x²/2+x³/3−x⁴/4+x⁵/5−・・・、(−1<x<1)と条件が付く。勿論、logxは0の周りではテイラー展開出来ないが、xを1ズラせば何て事はない。証明は少しややこしいですが。
tanxの逆関数であるtan⁻¹xのテイラー展開も、少しトリックが必要です。
(tan⁻¹x)’=1/(1+x²)ですが、この微分を繰り返すと当然手に負えなくなる。そこで、等比級数の公式を使い、1/(1+x²)=1−x²+x⁴−x⁶+・・・、(−1<x<1)。
故に、tan⁻¹x=∫[0,x]dt/(1+x²)=∫[0,x](1−t²+t⁴−t⁶+・・・)dt=x−x³/3+x⁵/5−x⁷/7+・・・と、テイラー展開できます。
テイラー展開からローラン展開へ
複素平面でもテイラー展開ができますが、このテイラー展開は正則(微分可能)な領域でしか使えませんでしたが、特異点(正則でない点)を中心にして表す方法がある事を1843年、ピエール・アルフォンス・ローラン(仏)が発表した。
因みに、このローラン級数の概念自体は先の1841年、カール・ワイエルシュトラス(独)により発見されてたが、公表されなかった(Wiki)。
先のテイラー展開は、極を持たない微分可能な正則関数(複素関数を含む)でのみ通用しますが、ここでは正則関数でなくともべき乗を掛ければ正則になる有理型関数を考えます。
但し、正則に出来るのは”孤立特異点”の事で、孤立特異点は”除去可能・極・真性特異点”との3つに分類されます。また、極でも可除特異点にも属さない特異点を真性特異点と呼ぶ。
故に、有理型関数とは正則関数を適当なべき乗で割り、テイラー展開の次元を一斉に下げ、”負のべき乗”を含んだ式に展開できます。これを”ローラン展開”と呼びます。
一言で言えば、テイラー展開は正則な点周りで展開し、ローラン展開は特異点周りで展開すると。
一般に、複素関数f(z)の点aの周りのローラン展開(級数aₙ)は、f(z)=Σₙ[−∞,∞]aₙ(z−a)ⁿで示されます。
先ず、テイラー展開(級数aₙ)のf(z)=a₀+a₁(z−a)+a₂(z−a)²+・・・を考えます。両辺をz−aで割り、以下のローラン級数を作る。
f(z)/(z−a)=a₀/(z−a)+a₁+a₂(z−a)+・・・=a₋₁/(z−a)+a₀+a₁(z−a)+・・・=g(z)と、次元を1つ下げます。
これは、”1位の極”aのローラン展開になってますね。そして、g(z)の両辺にz−aを掛けると、
(z−a)g(z)=a₋₁+a₀(z−a)+a₁(z−a)²+・・・=f(z)。
ここでzをaに近づければ残るのはa₋₁だけですね。この時、右辺の最初の項a₋₁を”留数”(residue=残余カス、残留物)と呼び、Res(a,f)で表します。つまり、複素関数f(z)は極z=aにて留数a₋₁を持つ。
一般に、特異点aが1位の極である時、留数a₋₁を求める公式は、Res(a,f)=lim[z→a](z−a)f(z)で表されます。つまり、f(z)をローラン展開した時の1/(z−a)の係数が留数になるんですね。特に、この1位の極の留数公式は頻繁に出てくるので、覚えておく必要がありますね。
因みに、”1位の極”という聞き慣れない言葉ですが。f(z)=g(z)/(z−a)ⁿが成立する時、aをfの”極”といい、極とはその絶対値が無限大になる特異点の一種で、その様な最小のnを極の位数といいます。n位の極が無限に続く時は”真性特異点”と呼ぶ。また、ローラン展開の分母の次数は極の位数となります。
次に、特異点が2位の極である場合、ローラン展開は以下の様になる。
f(z)=a₋₂/(z−a)²+a₋₁/(z−a)+a₀+a₁(z−a)+・・・、
ここで両辺にz−aを掛けても、右辺の第2項は留数になるが、第1項が邪魔になる。故に、(z−a)²を掛ければ、(z−a)²f(z)=a₋₂+a₋₁(z−a)+a₀(z−a)²+a₁(z−a)³+・・・となり、新たに第1項のa₋₂が留数になる。
しかし、この両辺をzで微分すれば、{(z−a)²f(z)}’=a₋₁+2a₀(z−a)+3a₁(z−a)²+・・・となり、a₋₂が消え、第2項のa₋₁が留数になる。
故に特異点aが2位の極の時、留数の公式は、”Res(a,f)=lim[z→a]d{(z−a)²f(z)}/dz”となります。
n位の極も同様にできますが、微分する度に係数が増えるので、それを消す必要があるから、公式を一般化すると以下の様になる。
”Res(a,f)=1/(n−1)!*lim[z→a]dⁿ⁻¹{(z−a)²f(z)}/dzⁿ⁻¹”。
因みに、ローラン展開の”妖艶さ”(Laurent)を意味するとありますが。テイラー級数(正則関数)をべき乗で割り、特異点(1位の極)周りのローラン級数を作り、留数をつまみだす。この流れが実に妖艶なんですかね。
次回は、ローラン展開から留数定理への説明です。ローラン展開を理解できれば、後は何とかですかね。










「ゼータ関数とリーマン予想」の著者であるHMエドワーズですが、レーマーの現象とZ(t)が有界でないという事実の発見こそがリーマン予想を無効とすると主張しています。
リーマンが”おそらく正しい”とした予想が否定される可能性も今日では出てきてるとも主張してますね。
つまりリーマンの驚くべき洞察が人知を超えた予知能力に勝るものだろうか?と語ってます。
レーマーの現象に関しても理解が追いつけば記事にしたいんですが・・・
レーマーの考察ですが、「ゼータ関数とリーマン予想」(H・M・エドワーズ著)の中から引用したんですが、今は記憶が曖昧なので詳しい事は後で紹介したいと思います。
ただ、リーマン予想の解決以上に、素数と素粒子の類似の方がずっと注目を浴びてますよね。
何だか考えるほどに分からなくなってきますが、詳しいアドバイスどうも有り難うです。
しかし特殊な形をした素数に対しては、より高速なアルゴリズムが存在する。例えば、メルセンヌ数(2ⁿ−1)が素数かどうかを調べ
る判定法として、エドゥアール・リュカの判定法をデリック・ヘンリー・レーマーが改
良したリュカ=レーマー・テストがある。
2013年の時点で知られてる最大の素数は、2013年1月に発見されたメルセンヌ素数の
1つの2^⁵⁷⁸⁸⁵¹⁶¹−1がある。十進法で表記すれば、その桁数は何と17,425,170桁。
しかし無限にある素数の分布の規則性については解明されていない。つまり、ある素数と次の素数の間隔を一般的に計算する事はできない。リーマン予想の証明はこの解決をめざしてるが、実部が1/2上の非自明零点が無限に存在する事は1914年にハーディにより証明されてる。しかし、実部が1/2上以外に非自明な零点が存在しない事は証明されてはいない。
転んだ君はレーマーの考察に拘ってるけど、レーマーの考察とは、実部が1/2上の非自明零点(リーマン予想)の虚部の値の分布をコンピュータを使い、可視化し調べたものだろうか。
ただ判ってるのは、虚部が大きくなる程に零点の密度が増してる事だけで、この零点の分布にどのような規則性があるのかは詳しくはわかっていない。