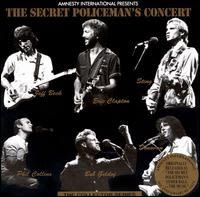2001年9月15日(土)

クリーム「ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・クリーム」(ポリドール)
60年後半活躍したロックバンド、クリームには、数多くのコンピレーション、ベスト盤が出ているが、今日のは「決定版」とでもいうべき一枚だ。95年のリリース。
全20曲が年代順に収められており、現在では入手の難しい、シングルのみでリリースされた曲も含まれているので、なかなかお買い得感が高い。
まずはデビュー・シングル「包装紙」。熱心なクリームファン以外には余り知られていない、レア・トラックだが、これがクリーム!?という感じのポップス。ビリー・ヴォーンあたりをほうふつとさせるサウンドだ。
もちろん、これはアメリカ市場に向けての戦略。いきなりギンギンのハードロックではなく、ソフトなヴォーカル、ポップな曲調でまずはアメリカ人を惹きつけようということか。
続いてはセカンド・シングル「アイ・フィール・フリー」。クラプトンのギターもサイケデリック色を前面に打ち出すようになる。もち、フィードバック・プレイもバシバシ聴かれる。
ヴォーカル&コーラスは、どこかウォーカー・ブラザーズのごとし。これも戦略か。
続く「エヌ・エス・ユー」は前の曲同様、デビュー・アルバム「フレッシュ・クリーム」に収録されたナンバー。
ライヴ・アルバムでもおなじみ、パワフルなコーラスとハードなコード・カッティングが印象的な曲だ。
次の「スウィート・ワイン」は、メロディ的にはブルースっぽくなく、コーラスがフィーチュアされているチューン。
でも、間奏では、もろブルーズィなギターが聴ける。
この曲まではすべてオリジナルだが、「アイム・ソー・グラッド」「スプーンフル」はブルース曲のカバー・ヴァージョン。
「アイム~」はスキップ・ジェイムズのいなたいカントリー・ブルースを見事に換骨奪胎、フィードバック・ギターがんがんのへヴィー・サウンドに仕上げている。最後には三声コーラスも。
一般にクリームは演奏主体のグループだということになっているが、スタジオ録音においては、この曲のように三人全員が歌いかつハモるなど、意外にヴォーカルに力を入れているのだ。
「スプーンフル」はもちろん、ハウリン・ウルフの十八番のカバー。ライヴ・テイクもあるが、ここでは「フレッシュ・クリーム」からのスタジオ・テイク版。
ワン・コードを執拗に繰り返す、重たいブルース・ギターは、まさに圧巻。
「ストレンジ・ブルー」はセカンド・アルバム「カラフル・クリーム(DISRAELI GEARS)」からカットされたシングル曲。
アルバート・キングに強く影響を受けた、スクウィーズ・ギターが聴ける。
この曲はベースを、ギターの低音パートとみなしたようなアレンジがなされていて、当時最先端のアンサンブルを<聴くことが出来、非常に面白い。
実際に大きめの音量で聴いて、確かめてほしい。
これは、セカンド・アルバムからプロデュースに携わったフェリックス・パパラルディのアイデアとも聞く。
「サンシャイン・ラヴ」は皆さんもご存知の代表的ヒット曲。
ブルースに若干のアレンジを加えた進行ながら、その重量感あふれるリズムは、もう完全にハードロックの域に達している。
「英雄ユリシーズ」は「ストレンジ~」のB面に収められた曲。初めてワウ・ペダルを導入、循環コードによる構成など、後出の「ホワイト・ルーム」のプロトタイプとも言える。
「スーラバー」は、いわゆるウーマン・トーン(高音をトーン・コントロールでカットした、どこかくぐもったようなギター音)が多出するナンバー。いかにもギブソン製ハムバッカーって音だ。
「間違いそうだ」はブルースのファルセット・ヴォーカル主体の、アンニュイなムードを持った、ちょっとユニークな作品。ベイカーのタム・プレイにも注目。
ここまでの5曲は「カラフル・クリーム」から。
2枚組の大作「クリームの素晴らしき世界」からカットされたシングル「ホワイト・ルーム」は「サンシャイン・ラヴ」とならぶ大ヒット。
ワウ、エコー、フィードバックなど、サウンド・エフェクトを駆使し、このうえなくサイケデリックなサウンドに仕上がっている。
担当プロデューサー、フェリックス・パパラルディの実力がいかんなく発揮された作品。
「トップ・オブ・ザ・ワールド」は、これまたハウリン・ウルフの代表曲を、クリーム流にヘヴィーにアレンジ。三人の鬼気せまるサウンド・バトルが繰り広げられる。
粘っこいファンクなリズムは、次の「政治家」でも聴かれる。
ギターのしつこいまでのオーバー・ダビングによる「音の洪水」に溺れそうな一曲だ。
「ゾーズ・ワー・ザ・デイズ」は、珍しくベイカーとジャズ畑のマイク・テイラーの共作によるアップ・テンポのナンバー。
ロックを少しはみ出して、前衛ジャズ的な音作りに挑戦した実験的ナンバー。
「悪い星の下に」はアルバート・キングの大ヒット曲のカバー。
ご本家に負けず劣らずの強烈なファンクネスを感じさせる演奏。クラプトンのギターも、アルバートを相当意識した、チョーキング全開のスタイル。
「荒れ果てた街」は、どこか作者(ブルース=ブラウンのコンビ)の心象風景を感じさせる、ザラついた感触のロック。そのスピード感あふれるグルーヴは、スゴいの一言。
そして極めつけはなんといっても、ライヴ録音の「クロスロード」。
わずか4分15秒という時間の中に、クラプトンのギターフレーズの「粋(すい)」が凝縮された、最高の演奏。
サイケにペイントされたギブソンSGから繰り出される音は、あまりに官能的だ。
これを聴いて、彼の才能に嫉妬しないギタリストは、ひとりもいないだろう。
極論すれば、クラプトンがもしこの一曲しか録音を残さなかったとしても、彼の名は永久に残り続けるであろう、それくらいの出来である。
映画「サヴェージ・セヴン」の主題曲として作られた「エニイワン・フォー・テニス」は他とは全く趣きの異なった、ポップ・チューン。のほほんとした曲調、ストリングもまじえたアコースティックなアレンジが実に新鮮に聴こえる。
ラストは「グッバイ・クリーム」(文字通りのラスト・オリジナル・アルバム)から、ジョージ・ハリスンと共演した名曲「バッジ」。
その後も何度かライヴでも演奏しているので、皆さんおなじみであろう。
レスリー・スピーカーを使ったという、ギター・アルペジオ(BY G・ハリスン)の美しい響きが余りに印象的なナンバー。
クラプトンのヴォーカルも、いつになく余裕にあふれ、説得力がある。彼のウタものとしてはベストのひとつだろう。
CD用に初めてリマスターされたという本盤、特にジンジャー・ベイカーのドラムス・プレイが、従来以上に鮮明に浮かび上がり、その大胆にして細心、メロディさえも感じさせるスケールの広い演奏に、改めて驚かされる。
そしてグループの持つ「引き出し」の多さにも、いまさらながらウナらされる。
とにかく、クリームをこれから聴いてみようかなという方は勿論、すでに全アルバム聴いているよという方にもおススメ。
全20トラック、すべて花マルという充実ぶり、おなかイッパイになれます。