位置天文衛星“ガイア”による観測で、地球から1560光年の距離にブラックホールが見つかりました。
現在知られているブラックホールの中で、最も私たちに近いものになるようです。
それは、すでに知られているブラックホールの中で地球に最も近いブラックホールでした。
このブラックホールは、これまでと異なる新しい手法を用いて発見されもの。
へびつかい座の方向約1560光年の距離に位置しています。
これまでで、最も近いとされていたブラックホールは約3000光年先なので、その距離を半分程度縮めたことになります。
地球に近いブラックホールの発見としては、2020年に発表のあった約1000光年先のブラックホールがありましたが、その後に否定されています。
このために、位置天文衛星“ガイア”のデータを調べています。
“ガイア”はヨーロッパ宇宙機関が運用する衛星で、天体の位置や運動について調査する位置天文学に特化した宇宙望遠鏡です。
天の川銀河に属する莫大な数の恒星の位置と速度を、きわめて精密に測定・記録しています。
このようなブレは連星が回ることで生じている可能性があるんですねー
この約17万件の事例から、恒星が見えざる天体に振り回されているように見える事例を探します。
すると、該当する候補が6つ残りました。
次に6つの候補に対して、他の観測データも合わせて分析。
“ガイアBH1”と名付けた天体だけは、ブラックホール連星の可能性が高いと判断しています。
さらに、地上の大型望遠鏡を動員して追観測を実施し、最終的にブラックホール抜きでは観測結果が説明できないとの結論に達したそうです。
天の川銀河には、恒星質量ブラックホールが、およそ1億個も存在すると推定されていますが、現在まで発見された数はそれに比べ極わずかです。
“ガイアBH1”のように、周囲の天体を振り回す以外の活動を示さないブラックホールは、数多く潜んでいるのかもしれません。
今回の観測結果によれば、“ガイアBH1”の質量は太陽の10倍で、その周りを太陽に似た伴星が185.6日周期で公転しています。
ブラックホールになる前の恒星は、少なくとも太陽の20倍以上の質量を持っていたとされ、その寿命は数百万年しかなかったはずです。
仮に現在見えている伴星も同時に生まれていたのだとすれば、太陽のように一人前の恒星に成長する前に、すぐ近くで超巨星になった主星に飲み込まれていたことでしょう。
生き残ったとしても、現状よりずっとブラックホールに近い軌道へ引きずり込まれていたはずです。
この謎を説明するために、“ガイアBH1”系の進化についてはかなり特殊なシナリオが提案されています。
例えば、2つの星の距離はもともとずっと遠かったが、別の星との遭遇によって軌道が変わったという可能性があります。
また、実はブラックホールが2つあり、伴星の軌道に比べはるかに近い距離で互いの周りを回っているとも考えられます。
大質量星が2つあれば、お互いが超巨星になるのを抑制しつつブラックホールに進化することができるからです。
将来のさらなる観測によって、これらのシナリオの可否を検討できればいいですね。
こちらの記事もどうぞ
現在知られているブラックホールの中で、最も私たちに近いものになるようです。
約1560光年先にあるブラックホール
アメリカ・ハーバード・スミソニアン天体物理学センター及びドイツ・マックス・プランク天文学研究所の研究チームが見つけたもの。それは、すでに知られているブラックホールの中で地球に最も近いブラックホールでした。
このブラックホールは、これまでと異なる新しい手法を用いて発見されもの。
へびつかい座の方向約1560光年の距離に位置しています。
これまでで、最も近いとされていたブラックホールは約3000光年先なので、その距離を半分程度縮めたことになります。
地球に近いブラックホールの発見としては、2020年に発表のあった約1000光年先のブラックホールがありましたが、その後に否定されています。
 |
| 今回見つかったブラックホール“ガイアBH1”のイメージ図。重力レンズ効果で周囲の光を歪めているが、地球から観測できるような光は発していない。(Credit: T. Müller (MPIA), PanSTARRS DR1 (K. C. Chambers et al. 2016), ESA/Gaia/DPAC(CC BY-SA 3.0 IGO) |
恒星とブラックホールの連星を探してみる
今回、研究チームが探したのは、太陽のような恒星とブラックホールが互いの周りを回る連星系。このために、位置天文衛星“ガイア”のデータを調べています。
“ガイア”はヨーロッパ宇宙機関が運用する衛星で、天体の位置や運動について調査する位置天文学に特化した宇宙望遠鏡です。
天の川銀河に属する莫大な数の恒星の位置と速度を、きわめて精密に測定・記録しています。
“ガイア”は、ヨーロッパ宇宙機関が2013年12月に打ち上げ運用する位置天文衛星。可視光線の波長帯で観測を行い、10憶個以上の天の川銀河の恒星の位置と速度を三角測量の原理に基づいて測定する位置天文学に特化した宇宙望遠鏡。測定精度は10マイクロ秒角(1度の1/60の1/60の1/10マンの角度)であり、これは地球から月面の1円玉を数えられる精度。
その“ガイア”のデータを調べてみると、時間とともに星の位置がブレている事例が約17万件ありました。このようなブレは連星が回ることで生じている可能性があるんですねー
この約17万件の事例から、恒星が見えざる天体に振り回されているように見える事例を探します。
すると、該当する候補が6つ残りました。
次に6つの候補に対して、他の観測データも合わせて分析。
“ガイアBH1”と名付けた天体だけは、ブラックホール連星の可能性が高いと判断しています。
さらに、地上の大型望遠鏡を動員して追観測を実施し、最終的にブラックホール抜きでは観測結果が説明できないとの結論に達したそうです。
天の川銀河には、恒星質量ブラックホールが、およそ1億個も存在すると推定されていますが、現在まで発見された数はそれに比べ極わずかです。
恒星質量ブラックホールは、大質量星が超新星爆発を起こした後に誕生する、太陽の数倍~数十倍程度の質量を持つブラックホール。宇宙に多数存在している。
すでに知られているブラックホールのほとんどは、近くにある天体からガスを大量に取り込み、そのガスが高温になって発するX線などをとらえることで見つかってきました。“ガイアBH1”のように、周囲の天体を振り回す以外の活動を示さないブラックホールは、数多く潜んでいるのかもしれません。
ブラックホール連星はどうやって進化したのか
今回発見したブラックホールとともに新たな謎も見つかっています。今回の観測結果によれば、“ガイアBH1”の質量は太陽の10倍で、その周りを太陽に似た伴星が185.6日周期で公転しています。
ブラックホールになる前の恒星は、少なくとも太陽の20倍以上の質量を持っていたとされ、その寿命は数百万年しかなかったはずです。
仮に現在見えている伴星も同時に生まれていたのだとすれば、太陽のように一人前の恒星に成長する前に、すぐ近くで超巨星になった主星に飲み込まれていたことでしょう。
生き残ったとしても、現状よりずっとブラックホールに近い軌道へ引きずり込まれていたはずです。
この謎を説明するために、“ガイアBH1”系の進化についてはかなり特殊なシナリオが提案されています。
例えば、2つの星の距離はもともとずっと遠かったが、別の星との遭遇によって軌道が変わったという可能性があります。
また、実はブラックホールが2つあり、伴星の軌道に比べはるかに近い距離で互いの周りを回っているとも考えられます。
大質量星が2つあれば、お互いが超巨星になるのを抑制しつつブラックホールに進化することができるからです。
将来のさらなる観測によって、これらのシナリオの可否を検討できればいいですね。
こちらの記事もどうぞ











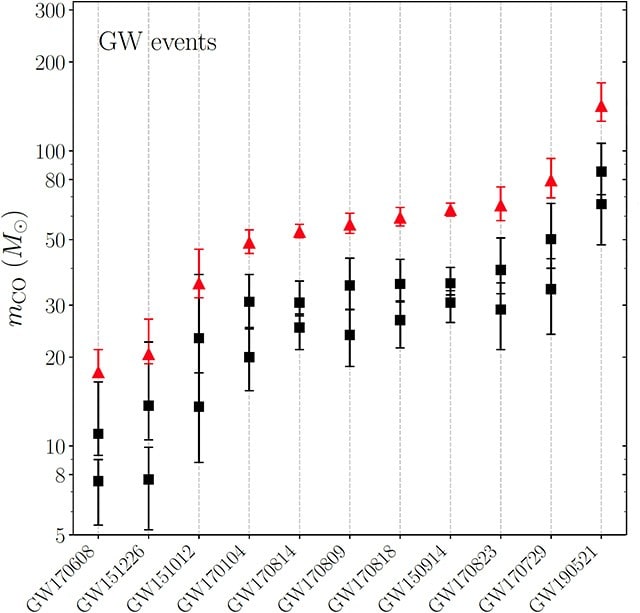










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます