
多分、
雅歌(1)の続き。
あの方は私を酒宴(しゅえん)の席に伴(ともな)われました。
私の上に翻(ひるがえ)る あの方の旗(はた)じるしは 愛(あい)でした。
 干しぶどうの菓子で私を力づけ、
干しぶどうの菓子で私を力づけ、
りんごで私を元気づけてください。
私は愛に病(や)んでいるのです。
(旧約聖書・雅歌2章4~5節)
雅歌は、主に、ソロモン(平和の王)とシェラムの女との対話が中心となって進められる。
たとえば、1章2節から7節は、王を慕(した)うシェラムの女。
(

ここで「エルサレムの娘たち」は誰を指すのかは、略。
ちなみに、「ケダルの天幕 1)のように」→「黒い」
「ソロモンの幕 2)のように」→「美しい」)
1章8節から11節は、王が。
1章12節から14節は、娘が。
(

ちなみに、もし、エン・ゲディがどこを指すのかを知ったら・・・、興味深い、と思う人もいるだろう。)
1章15節は、男性が。
1章16節から17節は、女性が。
♥。・゜♡゜・。♥。・゜♡゜・。♥。・゜♡゜・。♥。・゜♡゜・。゜♥。゜♡゜・。♥。・゜♡゜・。♥。
2章1節「私は、(単なる)シャロンのサフラン 3)、または谷にあるゆりの花のようなものです」と言っているのは、娘っこ。

谷にある、人の目にも留められず、ひっそりと咲いている花のようなものでもあり、そこらへんにある普通の野の花のことでもある。

2章2節で「僕の愛している者は・・・いばらの中の百合の花のよう」とは、王が娘を表して言っている。同じ「ゆりの花」と言っているのだが、…扱われ方は違うらしい。
また、どうして、ここで「いばら」が出てくるのかも、味わい深い。
そして、3節から6節は、娘が言っていること。(一部上記)
6節は、その言葉のままビジュアル化すると、顔を赤らめてしまいそうになるので、ここでは省略す。
♥。・゜♡゜・。♥。・゜♡゜・。♥。・゜♡゜・。♥。・゜♡゜・。゜♥。゜♡゜・。♥。・゜♡゜・。♥。
それは昔のこと。
聖書を通読していたある若人(わこうど)、雅歌を開いて、ばたっと、すぐ閉じた。

(え、ちょっと、・・・これは・・・。
こんなのが、聖書にあっていいのか!!?)
(そもそも、伝道者の書で
空(くう)の空(くう)。
すべては空(くう)
(1章2節、12章8節)
だとか、
むなしい つかのまの人生 (伝道者の書 6章12節)
と言っている、その次に、どうして、
 あの方が私に・・・
あの方が私に・・・
というものが続くんだ!?)
という、気持ち悪さ、というか、違和感のようなもの、いや、嫌悪感さえ抱いたのだ。
********************
(…一つつけ加えて言うならば、
まだこの当時、この若人、申命記27章22節の、

「父の娘であれ、母の娘であれ、自分の姉妹と寝る者はのろわれる」…
という箇所から
「どうしよう。
この前、お布団を干したら、
『○○兄/姉の布団、ふっかふか~~

』
って皆が来て、兄弟4人、一つの布団で寝てしまったではないか。(筆頭小学6年)
『狭い、狭い、どいてよ。』
『じゃあ、自分のところの布団で眠れよ』
『いやだ~』
etcって、ぎゃ~ぎゃ~騒ぎながら。
あれはいけないことだったのか・・・

どうしよう・・・」
と、
マジメに数ヶ月悩んでいるような
-つまり、「寝る」ということばに一つの意味しか知らないような-輩(やから)だった故、なおさらだったのだろうと思われる。

)
**********************
そんな若人の嘆きに、年配者
(母方の祖父)はこう教えた。
「いやいや、伝道者の書の次に、この雅歌の書があるのも意味があるんだよ」
そのことを、分からないなりに、一応、心には留めることにした。
とはいえ、その後しばらく、その箇所だけは避けていたが
【注】
1)ケダルの天幕:砂漠のアラビア人が住む黒い天幕(テント)。
ここでは、シェラムの娘っこの「生まれつきの容貌(ようぼう)」を示している。ただし、黒人、という意味ではない。
2)ソロモンの幕:細かい美しい亜麻糸(あまいと)で作られていたらしい。
3)サフラン:アヤメ科の秋咲きの植物。香り高い花らしい。
このサフランから作られるサフロンという香辛料?は、1g作るのに、サフランの柱頭150本分は必要なので高くなる。
【引用】
・聖書 新改訳,日本聖書刊行会,第2版,1987年
【参考】
・ウォッチマン・ニー著:歌の中の歌,牧草社,1982年
・廣部千恵子著:新聖書植物図鑑,教文館,1999年
 Γεια σασ.(ヤァサス;現代ギリシャ語で「こんにちは」。最後のシグマの小文字について、もう一つのが出てこなかった...
Γεια σασ.(ヤァサス;現代ギリシャ語で「こんにちは」。最後のシグマの小文字について、もう一つのが出てこなかった... )
)

 May God's blessing and love be with you today and forever.
May God's blessing and love be with you today and forever.










 ここ数日、雷雨(らいう)の日々が続きます。
ここ数日、雷雨(らいう)の日々が続きます。 判定基準は、「可愛(かわい)い」「美人」「点滴を刺すのが上手い」「恐い」「親切」・・・等だろか?
判定基準は、「可愛(かわい)い」「美人」「点滴を刺すのが上手い」「恐い」「親切」・・・等だろか?
 ええ、浮腫(むく)みます、クマできます。加えて、
ええ、浮腫(むく)みます、クマできます。加えて、 虚(むな)しさを感じる一場面。
虚(むな)しさを感じる一場面。 あります、あります。
あります、あります。

 はい、ガンバリマス。
はい、ガンバリマス。 



 彼の人しかいない。
彼の人しかいない。 脱力感が押し寄せ、ため息つきたくなるのも分かる。そして、それを一人で片付けるツラさも。
脱力感が押し寄せ、ため息つきたくなるのも分かる。そして、それを一人で片付けるツラさも。 やはり、少々、めんどくさい。
やはり、少々、めんどくさい。

 そして、ちゃぶ台返しをする人(犯人)は、片付けをしない。
そして、ちゃぶ台返しをする人(犯人)は、片付けをしない。 イギリスが最高と誇れること
イギリスが最高と誇れること アメリカが最高と誇れること
アメリカが最高と誇れること

 多分、
多分、 干しぶどうの菓子で私を力づけ、
干しぶどうの菓子で私を力づけ、 ここで「エルサレムの娘たち」は誰を指すのかは、略。
ここで「エルサレムの娘たち」は誰を指すのかは、略。 ちなみに、もし、エン・ゲディがどこを指すのかを知ったら・・・、興味深い、と思う人もいるだろう。)
ちなみに、もし、エン・ゲディがどこを指すのかを知ったら・・・、興味深い、と思う人もいるだろう。) (え、ちょっと、・・・これは・・・。こんなのが、聖書にあっていいのか!!?)
(え、ちょっと、・・・これは・・・。こんなのが、聖書にあっていいのか!!?)
 「父の娘であれ、母の娘であれ、自分の姉妹と寝る者はのろわれる」…
「父の娘であれ、母の娘であれ、自分の姉妹と寝る者はのろわれる」… どうしよう・・・」
どうしよう・・・」 今日、洗濯日和(びより)でした。
今日、洗濯日和(びより)でした。






 行きは雨雨、帰りは晴れ。
行きは雨雨、帰りは晴れ。 みんなで なんにん のったでしょうか。
みんなで なんにん のったでしょうか。



 昔、人が悪いことばかり行っていたため、神様が心を痛め、滅ぼそうと思った。
昔、人が悪いことばかり行っていたため、神様が心を痛め、滅ぼそうと思った。 をくわえて船に戻ってきた。さらに7日たってハトを放すと、ハトはもう戻ってこなかった。
をくわえて船に戻ってきた。さらに7日たってハトを放すと、ハトはもう戻ってこなかった。 ふむ。
ふむ。 )
)
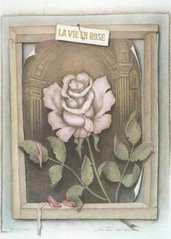
 受動喫煙:認知症の恐れ 長期に及ぶと血管に悪影響
受動喫煙:認知症の恐れ 長期に及ぶと血管に悪影響
 ここ最近、他国では使用禁止になっている農薬が使っていたというニュースもあちらこちらで流されるようになってきているが、数年前から、中国では農薬で年間数千人もの人が死んでいるというニュースもあったな...。急激な工業発展は、大抵環境汚染ももれなくセットですか
ここ最近、他国では使用禁止になっている農薬が使っていたというニュースもあちらこちらで流されるようになってきているが、数年前から、中国では農薬で年間数千人もの人が死んでいるというニュースもあったな...。急激な工業発展は、大抵環境汚染ももれなくセットですか






