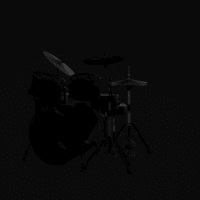今回は、映画記事です。
このカテゴリーでは、前回、ゴジラシリーズ記事の一環として『ゴジラ対ヘドラ』について書きました。
そこでも書いたように、映画評論家の町山智浩さんは、この映画に非常に大きな影響を受けています。
町山さんはWOWOWで映画の解説をされていて、YouTubeでその動画を見ることができるんですが、そのなかに『ゴジラ対ヘドラ』についてのものもあります。
今回は、前の記事の続編として、そこで町山さんが指摘している点について私なりの考えを書いてみようと思います。
町山さんは、『ゴジラ対ヘドラ』に強い衝撃を受けた理由として、「社会的メッセージ」を挙げています。
環境問題をテーマにしているという点がそうですね。
公害という当時のタイムリーな問題を取り扱い、そうすることによって、第一作ゴジラへの回帰を目指しているのです。
以前書いたように、ゴジラ作品は時代を映す鏡たることを宿命づけられていて、それがまさにこういうかたちであらわれているわけです。
そして、これは町山さんの指摘で気づかされたんですが……『ゴジラ対ヘドラ』に、もう一つまた別の観点から当時の日本の社会状況を映し出しているとみなせる場面がありました。
それは、“学生運動の挫折”と、そこからくる“シラケ”ムードです。
町山さんによれば、この映画には学生運動敗北の記憶が反映されてもいるのです。
物語のクライマックスとなる、富士の裾野の決闘にいたる場面。
ヘドラの硫酸ミストによる被害が広がる中、なぜだかここで100万人ゴーゴーをやろうという話になります。
ところが、実際当日になってみると、100人ぐらいしか人が集まらないのです。
100万人といっていたけれど、実際には100人しか集まらない……ここに、学生運動の挫折の残響があると町山さんは読み解きます。
それは、俗に「政治の季節」から「経済の季節」へと呼ばれる変化でしょう。
1960年代は、世界的に学生を中心とした学生運動が活発化しており、68年~69年ごろは、まさにそのクライマックスの時期でした。
たとえばローゼズの記事で言及したパリの5月革命があり、日本では各地で大学闘争がありました。
しかしそれらの運動は、大局的に見て、失敗に終わった。
日本でいえば、安田講堂をクライマックスにして学生運動は終焉した。過激派は暴走してよど号ハイジャック事件を起こし、非常に後味の悪いものになってしまった。ゆえに、運動に参加していた学生たちも、その過去を切り捨てなければならなかった……
藤子F不二雄先生が漫画で書いた言葉を借りれば「青春時代のはしかのようなもの」として否定しなければならなくなってしまったということでしょう。
これが、70年代の「シラケ」ムードと呼ばれる空気を醸成していたようです。その時代を体感していない自分には想像するよりほかありませんが……アングラ酒場で酒を飲む行夫(主人公の兄)が妙にやさぐれているのも、そういうことなのかもしれません。
そうした変化は、程度の差はあれ、アメリカやヨーロッパでも同様で、このブログで何度か書いてきたロック界の変化もそれを背景にしているように思われます。
そうした時代を、このブログで何度か名前が出てきたジャクソン・ブラウンは、The Pretender という歌に歌いました。
pretender
というのは、「~のふりをする」という意味のpretend をする人ということですが、この歌は、社会運動が挫折に終わった後、抜け殻のようになって生きていく人の姿を描いたものと一般的に解釈されます。
社会運動などなかったかのような「ふりをして」、毎朝起きて仕事にいく……そんな生活です。
そんな苦い挫折が、『ゴジラ対ヘドラ』にも反映されていると町山さんはいうのです。
たしかに、そうかもしれません。
そういう視点でみれば、ヘドラに立ち向かっていく若者たちがバタバタと倒れる姿は、強大な力の前に押しつぶされて学生運動が瓦解していくさまと重ね合わせることもできるのかもしれません。ヘドラにたいまつを投げるのは、機動隊に火炎瓶を投げるようなものともいえるでしょう。巨大な化け物に対してそんなことをしても、勝負になるわけがない。いちご白書的な話です。
しかし……私は、ここに描かれているのは挫折だけではないとも思います。
実際ゴーゴーが行われる前に、「100万人運動」というスローガンが書いてあったのを「100万人ゴーゴー」に書き換えるというくだりがあるんですが……私はここに、60年代から70年代への変化を見ます。
それはすなわち、正面から権力に抗するのではなく、権力が規定する「正当」から逸脱することで抵抗するパンクへの変化です。
60年代ロックの表舞台において思想的にも音楽的にもパンクに最も近かったのはフーだと思いますが、彼らのクレバーな抵抗のスタイルが、70年代につながっていくのです。
「100万人運動」を「100万人ゴーゴー」に書き換えるというのは、ウッドストックのピート・タウンゼントがアビー・ホフマンをギターでぶん殴ったというエピソードに通ずるものがあるんじゃないでしょうか。
そうすると、ここでも『ゴジラ対ヘドラ』は時代を鋭く切り取っているといえるのかもしれません。
それにしても……『ゴジラ対ヘドラ』は東宝チャンピオン祭りという子供向け企画で上映された映画の一つなんですが、よく子供向け映画でこんなのを作ったなと思わされます。
もっとも、その点に関しては、むしろ子供向け映画だからこそできたという側面もあるといわれます。
逆説的ですが……
正面から公害問題を扱う映画だったら、ここまではやれなかったはず。その当時のゴジラの感覚からすると、どのみちそんなに注目されることはないだろうという読みがあったからこそ、ここまで大胆にやれたというわけです。もっといえば、「所詮は子ども向けの怪獣映画」みたいな意識があったがために、内なる検閲とでも呼ぶべき作用が働かなかったというか……
ともかくも、当時の社会状況や映画を取り巻く環境、落ち目の特撮怪獣映画という状況の中で、エアポケットというか、亀裂のようなものができて、その諸々の偶然が重なりあってできた隙間からこのカルトムービーが出てきたといえるかもしれません。
斬新な作品というのは、しばしばそういうところから出てくるんですね。
その来歴からも、『ゴジラ対ヘドラ』は――肯定的に評価するかどうかは別としても――“奇跡の一作”としてゴジラ史上他に例をみない異様な光彩をはなっているのです。