司馬遼太郎の『城塞』を読みました。
シバリョウさんは、今年で生誕100周年を迎えます。
音楽関係の話では50周年という話をしていて、クイーンが50周年、エアロスミスが50周年ということなんですが、司馬遼太郎は100周年。そこで、ひさしぶりに読んでみようかと。しかしなんだかんだいって主要作品は結構読んでいるので、未読の作品のなかでまあ、それなりにメジャーであろうという作品を選ぶと、この『城塞』となりました。
ここでいう城塞とは、大坂城のこと。
いわゆる「大坂の陣」を描く作品です。
徳川VS豊臣、戦国の世を名実ともに終わらせる最後の大合戦……今年の大河ドラマは徳川家康ということでやってますが、そのあたりともからんできます。
その『どうする家康』ですが、だいぶ視聴率が伸び悩んでいるとも聞きました。
脚本がどうとか、美術がどうとか、史実と違いすぎるとか、いろいろ理由は考えられるでしょうが、もっと根本転機なところで、徳川家康という人物の不人気に負う部分が大きいのではないかと個人的には思います。
『城塞』を読んでいると、とにかく家康という人物は非常にイメージが悪いです。
手練手管を弄して大名たちを服従させ、圧倒的な数で大坂をつぶそうとする。そうして、数にまかせて力押ししているにもかかわらず、真田幸村らの猛反撃に遭い、一時は本陣にまで斬りこまれ、命からがらで逃走する……カッコ悪すぎでしょう。まあ、司馬遼太郎一流の脚色もあるでしょうが、それにしても無様なのです。
そうすると、策謀を尽くす古狸に立ち向う大坂城の将たちのほうが断然かっこいいという話になってきます。
家康の率いる大軍を迎え撃つのは、真田幸村をはじめとする“大坂城七将星”とも呼ばれる武将たち。「七将星」なんていう呼び方からして、もうかっこいいでしょう。(ただし、『城塞』に「大坂城七将星」という言葉は出てきません)
彼らには、それぞれドラマがあります。
秀頼の乳母子で義兄弟ともいうべき関係にあるイケメン武将・木村重成、父子にわたる豊臣家への恩義のためにすべてを捨てて馳せ参じた毛利勝永、切支丹復興のために戦う明石掃部など……家康への忖度に終始し、お家大事と強い者にひたすらこびへつらう東軍方の大名らに比べれば、彼らのほうに肩入れしたくなるのが人情というものでしょう。
しかし、やはりこれは“敗北の美学”なのです。
老獪で卑劣な権力を相手に筋を通してよく戦った、結果として負けたけど……という例のあれです。
それはそれで余韻を残しはしますが、やはりそれだけで終わってはいかんとも思うのです。敗北の美学をこじらせると、「清廉潔白なものは勝つことができない」から「勝者は勝利している以上清廉潔白ではない」となりかねず、実際日本の社会運動はそのレベルにまでこじらせてしまっているケースがあるように私には思われます。こうなってしまうと、はなから敗北を前提とした戦いを延々と続け、うっかり勝ちそうになると慌てて後退するというような……日本の左派運動はそういうところがあるんじゃないでしょうか。
そういうふうにみると、ここに描かれる敗北の美学は、日本における権力のあり方と、それに抗する抵抗運動のあり方を象徴しているようにも感じられます。
いっぽう“敗北の美学”と対になるのが、“カッコ悪い勝者”としての徳川家康ということになります。
一応家康を弁護しておくと……彼にしてみれば、強い者が戦に勝ち天下をとって何が悪い、ということでしょう。大名らが家を維持するために強い者の傘下に入るのは戦国の世では当たり前のことであり、そこに旧主への忠義などという価値観は入り込む余地がない、といわれればそれまでです。現実問題として、徳川家が完全勝利することで平和な世が到来するわけであり、一般庶民としてみればこれは歓迎すべきことで、武家の論理で乱世が続くのはたまったものじゃないということになるかもしれません。
徳川家のほうも、秀頼が一切復権可能性がない状態で隠居すれば矛をおさめるという一応の譲歩はしています。それ自体無茶な要求ではありますが、江戸時代の終わりに徳川家が同じ立場に立たされたときには、実際にそうすることで大戦争を回避しているわけで……まあ、徳川家として筋はとおっているともいえるでしょう。
と、そんなふうに考えれば、家康を非難するのは筋違いかもしれません。
しかし、そうはいってもやはり、この小説に出てくる家康を好きにはなれないんですが……











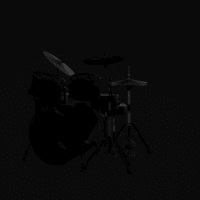









文庫でいうと上中下ある長編ですが、それを何度も読まれているとは……やはりそれだけの魅力がある傑作ということなんですね。