今年は、家の梅は不作だし、よそからもらえそうにない、とあきらめていた梅ですが、友人から「もらってくれる?」と声がかかりました。

ずっと昔、新聞記事で見つけて一度だけ作ったことがある梅漬けがあります。とてもおいしかったのですが、かなり面倒だったという記憶があります。最近になって、あの梅漬けをもう一度食べてみたいとおもったのですが、名前すら忘れていたので、探しようがありませんでした。
梅をもらってから、ふと思いついて、昔のスクラップブックをめくってみたら、すぐに見つかりました! それで作ったのが、梅びしおです。紫錦梅(しきんばい)ともいう、水戸に古くから伝わる梅漬けだそうです。
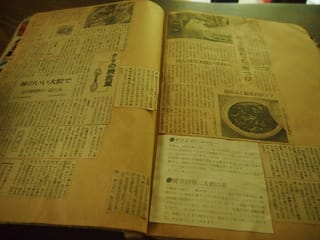
つくり方は単純です。梅の実と塩と赤紫蘇を漬けるだけ。普通の梅干しと同じなのですが、最初が違います。梅の実をすべて割って、種をのぞくのです。
この工程が昔はやたらめんどうだったのです。でも、いま、わたしは梅の実割り、という道具を手に入れているので、簡単でした。この道具は、草木染めでクルミの青い実や渋柿を割るために買ったのですが、本来の役割を果たしたのは今回が初めて。けっこう楽しい作業です。

この梅漬けは、落ち梅や完熟しすぎの、梅干しにならないような梅を処理するための加工食品。でも、私が友人からもらったのは、表面こそそばかすが出ていますが、まだりっぱに青い状態の梅です。完熟を待とうかとおもいましたが、熟さずに傷んでしまいそうだったので、青いまま、漬けることにしました。
種をのぞいた梅2300gに、塩を、その2割の460g容器に入れ、混ぜます。その後、様子を見てはかきまわしました。新聞の切抜きには、「ガラス瓶に入れてよくまざるように振る」とありましたが、たくさん作ったので振るのは不可能。それで、手でかきまぜたのですが、これでは酵素ジュースを作るときと同じなので、酵素が出てしまってよくないかな、と途中で気がつき、しゃもじを使うようにしました。
全体がなじみ、カビの心配がなくなった頃、赤紫蘇を梅の重量の1割用意します。よく洗ってから、紫蘇の量の1割の塩でよくもみ、固く絞ってから、梅漬けの上に広げます。そして、全体をかきまわします。そうしておいて一晩経ったのがこちら。

まだ、赤いところと青いところがありますが、いずれ梅干し色になるはずです。ただし、昨夜紫蘇を入れた段階で、水気が少ないのが気になり、梅酢を足してやりました。
完熟梅を使っていないので、じゅくじゅくした感じが少なくて、前に作ったときとは様子が違います。でも、そのうち、多分なじむのでしょう。この梅漬け、干す手間もないし、出来上がった梅の種をとる必要もないので、楽。和え物に使うときとかにも、すぐに利用できそうです。
ところで、新聞の切抜きには、取り除いた種を煮出して漉せば、ふきんなどの消毒用に使える、と書いてありました。それで、何回も煮出して1リットルのペットボトル分1本半ほど液を作りました。ときどき、洗い物が終わったあと、流しに振り掛けたり、ふきんをつけておいたりして使っています。

ずっと昔、新聞記事で見つけて一度だけ作ったことがある梅漬けがあります。とてもおいしかったのですが、かなり面倒だったという記憶があります。最近になって、あの梅漬けをもう一度食べてみたいとおもったのですが、名前すら忘れていたので、探しようがありませんでした。
梅をもらってから、ふと思いついて、昔のスクラップブックをめくってみたら、すぐに見つかりました! それで作ったのが、梅びしおです。紫錦梅(しきんばい)ともいう、水戸に古くから伝わる梅漬けだそうです。
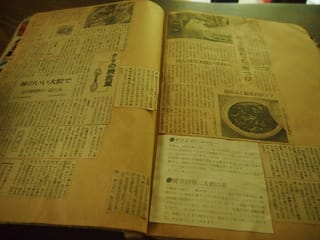
つくり方は単純です。梅の実と塩と赤紫蘇を漬けるだけ。普通の梅干しと同じなのですが、最初が違います。梅の実をすべて割って、種をのぞくのです。
この工程が昔はやたらめんどうだったのです。でも、いま、わたしは梅の実割り、という道具を手に入れているので、簡単でした。この道具は、草木染めでクルミの青い実や渋柿を割るために買ったのですが、本来の役割を果たしたのは今回が初めて。けっこう楽しい作業です。

この梅漬けは、落ち梅や完熟しすぎの、梅干しにならないような梅を処理するための加工食品。でも、私が友人からもらったのは、表面こそそばかすが出ていますが、まだりっぱに青い状態の梅です。完熟を待とうかとおもいましたが、熟さずに傷んでしまいそうだったので、青いまま、漬けることにしました。
種をのぞいた梅2300gに、塩を、その2割の460g容器に入れ、混ぜます。その後、様子を見てはかきまわしました。新聞の切抜きには、「ガラス瓶に入れてよくまざるように振る」とありましたが、たくさん作ったので振るのは不可能。それで、手でかきまぜたのですが、これでは酵素ジュースを作るときと同じなので、酵素が出てしまってよくないかな、と途中で気がつき、しゃもじを使うようにしました。
全体がなじみ、カビの心配がなくなった頃、赤紫蘇を梅の重量の1割用意します。よく洗ってから、紫蘇の量の1割の塩でよくもみ、固く絞ってから、梅漬けの上に広げます。そして、全体をかきまわします。そうしておいて一晩経ったのがこちら。

まだ、赤いところと青いところがありますが、いずれ梅干し色になるはずです。ただし、昨夜紫蘇を入れた段階で、水気が少ないのが気になり、梅酢を足してやりました。
完熟梅を使っていないので、じゅくじゅくした感じが少なくて、前に作ったときとは様子が違います。でも、そのうち、多分なじむのでしょう。この梅漬け、干す手間もないし、出来上がった梅の種をとる必要もないので、楽。和え物に使うときとかにも、すぐに利用できそうです。
ところで、新聞の切抜きには、取り除いた種を煮出して漉せば、ふきんなどの消毒用に使える、と書いてありました。それで、何回も煮出して1リットルのペットボトル分1本半ほど液を作りました。ときどき、洗い物が終わったあと、流しに振り掛けたり、ふきんをつけておいたりして使っています。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます