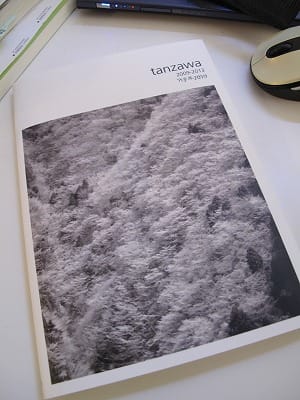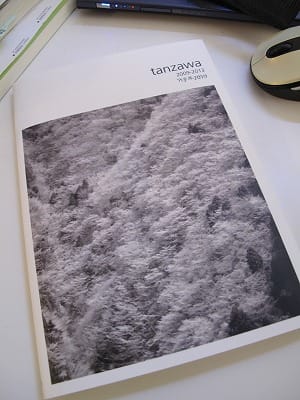いつも、葉山のダイビングショップ「NANA」さんの
「
NANA 今日の海日誌」というブログを楽しんでいます。
わたしはダイビングはしないのですが、このブログを見ると、
たとえ海に行けなくても、海の生きものたちのことを、
陸上の季節とは異なる海の変化を日々知ることができ、
とても……有り体に言うと癒やされるというか、海への気持ちが膨らみます。
また、潮だまり派の僕らと、海中派の彼らとは、同じ海を見ていても、
当然ですが見ているものがずいぶんとちがっていて、そこもおもしろいところです。
これまでも「ダンゴウオ」を通じて、スタッフの方々と夜の磯にご一緒したり、
昼間の海でごあいさつしたりと、ゆるやかな交流を続けています。
で、
1月9日のブログです。
すばらしい!!!!!
なにがって明け方の海で3時間ダンゴを追って、
明るくなったらどこにいくかを観察されたんですよ!
(まだ抱卵中の個体は発見されていません)
*
この時期、夜はふつうにダンゴが観察できるのに、昼間はいっさい見ることができません。
春になれば、水深のあるところで、稚魚とあわせて成魚が昼間のダイビングで観察できるそうですが、
繁殖期を迎える今は、夜だけが行動時間というか、われわれの目に付くところで活動しているのです。
単純に聞こえますが、このことも潮だまり派の僕らと、海中派のNANAさんたちが
交流することによってわかってきた事実です。
で、NANAさんは、じゃあ明るくなったらダンゴはどこに行くかを
確認するために明け方の海に潜ったのです!
そして!!!!
少なくとも昼間にいる具体的な場所が見えてきたのです!
当然、そういう場所で抱卵する可能性は大!?
…というかほぼそんな感じ!!!???
わたしの気持ちとしては…
1 すばらしい!
2 うらやましい!
3 やられた!
…の3つが入り交じっております。
このブログでも何度か書きましたが、
わたしは、夕暮れ時や明け方の森でじっとして
野生動物を観察する…というか動物が出てくるのを待つ
…という不毛で、博打のような手法に凝っていた時期がありました。
称して“夜待ち”。
これはほんとうに楽しい手法です。
NANAさんは、それを海でやったのです。
すごいですよね! 3時間も冬の明け方の海に潜るんですよ!
海中で夜明けを迎えるってどんな感じなんでしょう?
そして、その3時間はどんな時間だったんでしょう?
寒くて、じれったくて、どきどきして。最高ですよね!?
*
昔の記録を引っ張り出すと、
はじめてこの海でダンゴウオを発見したのは
2004年12月25日のことでした。


(昔のデータを引っ張り出しました…)
あれから8年が過ぎ、仲間ができ、知見が増え、
夜の磯でダンゴを発見することそのものは簡単になりました。
この冬、いよいよ抱卵が観察できる可能性が高くなってきました。
潮だまり派の僕らが観察できる場所なのかどうかはわかりません。
いずれにせよ、こいつの真価が問われるな…。

今年こそ自分の目でダンゴウオの抱卵を見たい…そう強く思うと同時に、
その発見が(まだ発見してないけど)、この海、この磯の大切さと豊かさを伝える貴重なものとして、
ダイバーだけではなく、潮だまりを観察をするナチュラリストに対しても、
重要なメッセージなるんじゃないか…という気がしています(おおげさかなあ…)。
そして、そのメッセージが負の結果を招くことも、可能性としては否定できません。
先日も、深夜の磯でダンゴウオを採集している人を見かけました。
抱卵期は、勝手に2月、3月と想定しています。
小さな不安を抱えつつも、大きな期待で今からドキドキしています。