桐紋
(きりもん)
朝廷から下賜された名紋
五七の桐 中輪に五三の桐 五七の桐に笹
桐車 五三鬼桐
五三の桐 は ≪家紋4≫で呉服屋さんの陰謀かも知れないという
記事を書いたが、桐自体を書いていないようなので補足しておこう。
リンク(主な使用家)
~HP:KAMON WORLD様より~
いつもお世話になりありがとうございます。

皇室の副紋とされる桐紋は格式の高い紋章
後醍醐天皇が足利尊氏に下賜された史実は、
朝廷の御紋章として鎌倉末期に確立していた証拠でもある。
尊氏は、拝領したこの桐紋を、一門の吉良、細川、新田、
今川、山名、一色、斯波、畠山 などの諸氏に分け与えた。
豊臣秀吉も同様に、下賜された桐紋を多くの将士に与え、
いに普及させた。が、菊に継いで最も名誉ある紋章は、
武将の憧れの的であった。地方豪族の中には、いろいろな
理由をでっち上げて、この紋を使った者もあった。
〔『応仁後記 』には大河内備前守が遠江と三河の武士を集め、
菊一揆と称し十六葉の菊を用いたとある。これは皇室から下賜
されたものではなかった。こうした不逞のやからが増え出すと
あわてた皇室では、禁令をただちに発布した。天正十九年、
『多門院日記』 6月7日の記述には 、菊や桐の紋はつけては
いけないと、 奈良じゅうに御触れ書きが出た、とある。〕
これが天正十九年の「菊桐禁止令」である。
ついに秀吉も”禁令”を発して、その無断使用を厳禁した。
*****************************************************
文禄三年(1594年)八月三日
『豊臣氏大老連署掟(おきて)追加』
一、衣裳紋御赦免以外、菊・桐つけるべからず、御服拝領者
においては、その御服所持の間は、これを着るべし、
染替、別の衣裳に御紋を付けるべからずの事、
この掟によると、限られた人々の衣裳の紋所には菊花紋と桐紋を
特に許可され、免許された特殊の人々以外は一切の使用禁止。
特許を蒙った本人のみで、当然、その家族・一族には及ばない。
また免許にも厳しい制約が設けられていて、「御服拝領者」とは
紋付の御服であるから、拝領の一着限りということになる。
免許は生涯着用の資格までには至っていないのである。
この法令は、菊花紋取締りに仮托した豊臣家の太閤桐を擁護
することによる太閤秀吉の権威の確立政策の一環であった。
*****************************************************
豊臣家滅亡後も
桐紋は天下の大紋として栄え、現在でもベスト5 に入る。
また、秀吉の養子となった結城秀康(家康の次男)系の
越前家一門は、姓は松平氏であっても葵を用いず、桐紋を使用し、
”豊臣朝臣(とよとみのあそん)”のシンボルを受け継いでいる。
桐紋は、花の数によって ”五三の桐” ”五七の桐” に分類する。
桐はゴマノハグサ科の落葉高木、スミレ色の花は下むきに咲く。
中国の伝説では、鳳凰の住む聖樹 とされている。
 「見る知る楽しむ 家紋の辞典」 真藤 建志郎著より
「見る知る楽しむ 家紋の辞典」 真藤 建志郎著より
2008-07-06 20:40:20 記.

〔 〕内を追記致しました。ーー「家紋総攬図鑑」よりーー
2008-07-26 18:07:00 追記

******** から********までを追記致しました。
「日本紋章総覧」(歴史読本歴史百科シリーズ臨時増刊'74-12)より
椿紋
(つばきもん)
縁起の悪い「椿紋」
ツバキは、春を飾るまことにあでやかな植物。
なので昔からも着物や帯、調度品などに良く見かける
文様であるが、いざ家紋となれば見当たらない。
椿の花は、突然「バッサリ!」と落ちる。
これが、人間の首が落ちるに似て武士には嫌われる。
家紋にも採用されないゆえんなのだそうだ。
ところが、
山脇東洋という幕末の医者がこれを用いている。
この人は、日本で最初に人体解剖をした有名な人。
今の京都市中京区六角大宮西の六角獄舎で、
14人(男10人、女4人)の首の無い刑死体を腑わけした。
宝暦4年(1754)、彼が五十歳の時であるが、
西洋人の解剖図によく一致しているので、深く感動した。
五年後にあらわした『蔵志』には、その感想が載っている。
昭和45年発行 歴史読本臨時増刊
歴史百科シリーズ『日本紋章総覧』
「家紋採集の旅」 丹羽基二:記 (特別読み物)
~~~ より以下引用 ~~~
山脇家は代々医者であるが、家紋は千葉椿(八重椿)紋である。
ところが、この千葉椿の実形が未だにわからない。いわば幻の
紋だ。ところがあるとき、教え子の結婚式で、一席をやって着席
すると、隣席の山脇さんという人が、心安く話しかけてきた。
いろいろ伺ってみると、この人が山脇東洋の末孫。
いま、芸大の教授をしていらっしゃる山脇洋二先生だ。
「お宅の千葉椿紋は、カタチがわかりますか。」
「確か、古いつづらか何かあったはず。探してみましょう。」
ということで、頂いたのが下図の「千葉椿」。
千葉椿紋
花弁を見ると十四枚、首を切られた十四人の数と同じ。
この十四人の戒名の刻まれた墓は今、京都の誓願寺に
あるが、その一つに「利剣夢覚信士」とある。首を切られた
人たちが自分の迷いを覚ましてくれたという意味か。
千葉椿は、
東洋の人体解剖を記念した創作紋ではなかろうか。
~~~引用終わり~~~

椿紋で検索すると、
【椿紋の由来水天宮】と出てきた。
第八十代天皇の高倉天皇と建礼門院の皇子として、
治承2(1178)年にお生まれになり、生後まもなく立太子となり、
数え三歳にして第八十一代天皇に即位された安徳天皇。
歴史には安徳天皇は、御年わずか五歳の生涯を閉じたと
記述されているが、言い伝えとして、官女の按察使局に
守られて筑後に潜幸されたと久留米に残っているらしい。
その安徳天皇と玉江姫の恋物語の由縁から、
椿の花が神紋になったとされる。
画像は「水天宮」のHPを参考にしてください。→ 「椿紋の由来」
≪なぜ菊紋は天皇紋になったのか?≫
それは不老長寿の薬草として、
中国から伝えられたことによるといえる。
『万葉集』には菊を詠んだ歌が一首もない。
但し百代草(ももよぐさ)として、小輪の花が
歌われているのが野菊とみられている。
もともと日本にも野菊は自生していた。
天皇紋の菊紋は小菊ではなく大輪の菊である。
日本にもたされたのは桓武天皇の時代とされる。
延暦十六年(797)十月の歌会に、
天皇はこの花を諸侯に鑑賞させている。
『日本紀略』(平安末期の史書)
「曲宴。酒を楽しむ。皇帝(桓武天皇のこと)歌っていわく。
『この頃のしぐれの雨に菊の花 散りぞしぬべきあたらその香』」
と記す。
中国から来たこの大輪の菊は、酒に浮かべて飲むと、
不老長寿の薬になると信じられた。
菊は翁草・千代見草・齢草(よわいぐさ)とも呼ばれ、
桓武天皇に始まり、多くの天皇家がこの花を愛した。

翁草(おきなぐさ)は長寿をもたらす花という
「菊慈童(きくじどう)」の伝承が、
中国から美しい大輪の花と共にもたされた。
≪菊慈童伝承≫
甘谷(かんこく)の菊水(咲き競う菊花の露が落ちた水)
を飲んで菊慈童は七百歳までも生きたというもの。
| |
大輪の菊は長生きの妙薬とされ、菊の花を酒に浮かべて
飲む菊花酒は、桓武以降の天皇が好むところとなった。
桓武の子、嵯峨天皇も菊花を仙薬として重視
「神仙の霊薬をめで喜び、俗世間の世情を忘る」
と漢詩にも詠んでいる。
≪最も菊の魅力に取り付かれたのが後鳥羽上皇≫
衣服・牛車・けんのはばき(刀身が抜けないように締める金具)
から懐紙にまで菊の文様を用い、菊帝と呼ばれた。
後鳥羽上皇が「承久の変」(1221)で敗れ、
隠岐にに流され不遇な死を遂げた半世紀後、
後深草、亀山、後宇多の三天皇によって、
菊は天皇紋となったのである。
十六ヵ弁菊花の紋は
不老不死の精神を根本として誕生したのである。

『紫式部日記』
紫式部が九月九日の重陽の節供にちなみ、
自分が仕える中宮の母、つまり藤原の道真の妻である
倫子(りんし)から「菊の綿」をもらったことが出てくる。
≪菊の綿≫
重陽の節供から当日にかけ、菊の花の露と香りを綿に
移し、その綿で体を拭くと、老いないとされた。これを
「着せ綿」といったが、紫式部はこれをもらって歌を詠んだ。
「菊の露わかゆばかりに袖ふれて 花のあるじに千代はゆづらむ」
≪意味≫
菊の露に染みた綿に、私はほんのちょっと若返るほどに
袖を触らせていただくだけにして、千年の寿命は、花の
持ち主でいらっしゃる倫子様にお譲りいたします。
道長の屋敷の庭には、大輪の菊が咲き競い、
宴ではその菊を酒に浮かべて飲んだ。
貴族は美しく見た目も良い長寿の花と信じられた菊を
こぞって栽培した。
その究極にいた西園寺(さいおんじ)家の庶流が今出川家で、
今出川兼季(かねすえ)は、庭一面を菊で埋め尽くし、
以後、子孫は家名を菊亭とするのである。

≪徳川幕府≫
幕府は重陽の節供を五節供の一つに定めて
武家の祝日として重視し、
大名は江戸城に総登城して祝った。
大名は大奥にも紅白の丸餅に
菊花一枝を添えて献上するのが慣例だった。
 『あなたのルーツがわかる 日本人と家紋』 楠戸義昭:参照
『あなたのルーツがわかる 日本人と家紋』 楠戸義昭:参照
久留子紋
(くるすもん)
もともとは十字架の形からデザイン化されたもの
キリスト教のシンボル
久留子はポルトガル語のクロウズスで十字架のこと。
キリスト教が我が国に伝来したのは、天文18年(1549)。
ポルトガル人フランシスコ・サヴィエルが鹿児島に上陸して以来
わずかの間に信者は数十万に及んだ。上は大名から下は百姓
町人に至るまで、当時やたらに胸で十字をきったらしい。
坊主の横暴を憎んだ織田信長の腹いせもあるらしいが、
当時京都の南蛮寺をはじめ、近江安土、周防山口、豊後府内
などにはキリスト教の寺院、会堂、学校等が建ち並び、大いに
この新興宗教が流行した。これらの寺院の屋根瓦や鐘、墓碑
などには十字架が据えられ、高々とキリスト教が宣布された。
また、彼らは武器、馬標、旗印、陣幕にも日本の家紋と同じ
ように使い、自分達の信仰を誇示した。しかし、それはほんの
わずかの間で、やがて厳しい弾圧の時代に転じた。
「日本西教史」によれば、慶長15年大坂籠白の兵士に
十字架の旗を用いたものがいる。これは、切支丹の兵士
が禁令を解いてもらう約束で大坂方に味方したものである。
計画は豊臣氏の敗北で水泡に帰したが、それから23年後の
寛永15年(1638)島原・天草島に再び十字架の旗が翻った。
徳川氏が徹底した鎖国主義をとったのはこの後であるが、
それでも秘密に信仰した隠れキリシタンもいた。
マリヤを観音様に、十字架を轡紋十の字紋と偽ったり
して密かに信仰していた。
【 形 】
原形・・・十字
マルスター形(十字の先に切り込みがある)・・・切り竹久留子
アンドリウス形(※直〈筋〉違(すじかい))・・・丸に直違
花形(先が錨のように三分されているもの)・・・花久留子
※桛(かせ)形や丸で囲ったもの・・・丸桛木、丸に桛木(=中川久留子)
祇園守のように十字架の一部を取り入れた
ものや、島津氏の「丸に十文字」と
外見はなんら変わらないものも存在した。

花久留子 四つ子持ち久留子


切り竹久留子 中川久留子 変り花久留子菱
(丸に桛木)
≪ ※ 直違(すじかい) ≫
筋違ともかく。二本の線を斜めに交差させたいわゆる×印で、
違棒ともいう。普通は建造物の柱の間に入れた材木をさすが、
江戸時代領地や財産の没収刑の目印に用いられた。
交差する線の面白さが紋章の起こりとされている。
≪ ※ 桛木(かせぎ)≫
かせぎとは、つむいだ糸を巻き取る「エ」字形糸巻きのこと。
桛木紋は、簡略化したカセギを縦横に重ねたもので
キリスト教信仰をカムフラージュする目的でも用いられた。
馬の轡に煮ているので轡紋とも言う。
いつもお世話になっている↑↑家紋ワールドさんです。
いつもありがとうございます。

戦国時代、摂津地方の豪族
池田、高山、中川、伊丹、能勢、枚岡
の諸氏が教徒として十字架紋を用いた。
その他、備前、因幡の両池田氏
筑後の立花、有馬氏など。
 『家紋大図鑑』(秋田書店):参照
『家紋大図鑑』(秋田書店):参照
 『見る知る楽しむ 家紋の辞典』 真藤建志郎著:参照
『見る知る楽しむ 家紋の辞典』 真藤建志郎著:参照
轡紋
(くつわもん)
馬具の轡をデザインした紋章
尚武的意義
【 読み方説 】
① 口喰(くちば)み説 → 馬の口に含ませる鉄の口金から
② 口輪(くちわ)説 → 口にかませた輪から
銜(はみ)と呼ぶ棒状の金具を馬の口にかませ
面繋(おもがい)で頭に止め、銜の両端にある
引手鉄(がね)に手綱をつけて馬を操縦する。
引手鉄には輪(轡の鏡板)がついている。
紋章となったのはこの轡の鏡板である。
武家の轡にはたいてい丸形の中に十文形
がつけられているが、変化形もあった。
S字形・・・・・唐鞍轡
杏葉形・・・・・掛け轡
菱形・・・・・菱轡


陰轡菱 待ち合い轡



月輪に豆轡 轡 卍轡


三つ重ね轡 花轡
いつもお世話になっている↑↑家紋ワールドさんです。
いつもありがとうございます。

江戸時代、キリスト教信者の疑惑を避けるため
十字架や十文字を使っていた武将は
「轡」と幕府に届けたり紋帳に記したりしたが、
紋章学上は、発生が違うので正しい分類ではない。
島津氏・・・「丸に十文字」
平氏維将流 島崎氏・・・花クルス紋(花轡紋)
豊後中川氏(清和源氏頼光流)・・・クルス紋(十字架紋)
を、『寛政重修諸家譜』に「轡紋」として届けている。
【 轡紋を用いている諸氏 】
『見聞諸家紋』・・・小笠原氏流の大草氏「掛轡紋」
祖先の三郎左衛門公経「三階菱の掛轡」
『寛政重修諸家譜』における大草氏は八家に及ぶ。
その他、島崎、後藤、浅井、島、久保田、下田の諸氏。
(「仏教の話 ☆ 11≪江戸宗教政策≫」私のブログ参照→こちら) 『家紋大図鑑』(秋田書店):参照
『家紋大図鑑』(秋田書店):参照
 『日本家紋総覧コンパクト版』編集 能坂利雄:参照
『日本家紋総覧コンパクト版』編集 能坂利雄:参照
(ちょうもん)
艶麗優美な姿態の千変万化
蝶紋は、桓武平氏の代表紋
昆虫の蝶をデザインとして紋章として用いたもの。
胡蝶の場合は、胡(=西湖)から異郷の蝶を意味する
らしいが、小蝶を胡蝶に置換えたぐらいにしか見えない。
平清盛の父貞盛が「天慶の乱」を討伐した功
により、朝廷から鎧を頂戴した。
この鎧に向い蝶(対い蝶)の文様があったので、
これをとって平氏の紋にした、と伝えられる。
平家は、壇ノ浦で滅んだが、残党もいた。
平頼盛は、母池禅尼(いけのぜんに)が源頼朝の命を救った
関係から、六波羅に居を構え、朝廷に仕えることができた。
この一族を“六波羅党”という。



変り向い揚羽蝶 剣片喰揚羽 伊豆蝶


揚羽蝶 中陰蔦飛び蝶



熨斗胡蝶 備前蝶 三つ反り胡蝶
いつもお世話になっている↑↑家紋ワールドさんです。
いつもありがとうございます。

『餝(かざり)抄』・・・蝶紋が文様から転じたと見られる資料
「加茂祭り使用車」には「透かし蝶の円」と記があり、
平維盛(重盛の子)が治承の頃用いていたとある。
『大要抄』・・・・・「蝶円は六波羅党 」と記がある。
『雲上明覧』・・・・・西洞院、松平、長谷、交野、石井の五公家
武家では、六波羅党の平氏が蝶の丸を用いている。
戦国期になって関氏、一門の亀山、神戸、峯氏らが使用。
桓武平氏では伊勢氏、つづいて織田信長。
江戸期になって大名、旗本など約三百家が用いた。
蝶紋は、その描き方のスタイルで五つに大別できる。
① 飛び蝶
② 揚羽蝶(とまったポーズで羽を揚げる)
③ 蝶丸(輪蝶)
④ 胡蝶(真向きのもの)
⑤ 浮線蝶、などの変形
 『見る知る楽しむ 家紋の辞典』 真藤建志郎著:参照
『見る知る楽しむ 家紋の辞典』 真藤建志郎著:参照
 『日本家紋総覧コンパクト版』編集 能坂利雄:参照
『日本家紋総覧コンパクト版』編集 能坂利雄:参照
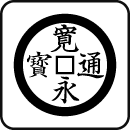
2.寛永通宝紋
寛永通宝は徳川初期の寛永年間に鋳造された通貨。
幕府は最初、江戸浅草・江戸芝・近江坂本の3箇所で
「寛永通宝」の生産を開始。その後、佐渡、京都、石ノ巻、
足尾、仙台、大坂、長崎など全国数十箇所で鋳造された。
詳しくはこちらのサイト様へ
↓↓↓
様の「寛永通宝」
使用家は
「寛政重修諸家譜」によれば、藤原氏流の福島氏。
伝に福島氏の祖・正勝が、東照宮に参拝し、
社殿にぬかずいた時、偶然 寛永通宝が
懐中より転がり出、広げた扇の上にとまった。
そこで、「これはおめでたい」とばかり、
以後、この形を家紋にしたという。
 『家紋大図鑑』:参照
『家紋大図鑑』:参照 
家紋 25 ≪銭紋≫へ戻る。
ちょっと気になるリンク集
そうそう、そういや~寛永通宝って
見たことあると思っていたのよね~。
で思い出したのがこれ!
小学生の時からずーっとみてたっけ!
「あの投銭は回収するのだろうか?」
「紐が付いてて引き戻すねん。」
とかいうお笑いもあったような…?
ほんと、懐かしい~♪
 様より「変な寛永通宝」
様より「変な寛永通宝」
「貨幣一覧」
資料出典:日本銀行金融研究所 貨幣博物館等
銭形平次 主題歌
http://www.youtube.com/watch?v=4M3UjvDLp7g&feature=related
(2011.11.8 動画を変更致しました)
大川橋蔵さんが銭形平次をはじめたとき、
それまで一番人気だった長谷川一夫さんの
強烈な印象があったようですが、
私はこの大川橋蔵さんからしか知りません。
1966年5月4日~1984年4月4日
までの18年間ついついみてましたね。

1.永楽通宝紋
中国において、明の成祖の永楽年間(1403~23)に造られた
永楽通宝銭を紋章化したもの。これが日本に輸入されたのは
足利時代で、当時我が国では久しく貨幣の鋳造がなかったから、
便宜上用いているうちに紋章に採用された。
初めて文献にあらわれたのは「羽継原合戦記」。
≪永楽の銭は三河国水野の紋≫とある。
戦国時代に織田信長が旗紋にこの「永楽」の文字を用いている。
部下の将士にも大いに分け与えた(仙石氏、荒尾氏、黒田氏)。
水野氏(徳川家康の母・於大の方の実家)もやはり信長に賜った
(信長より古くから使っているとの説も有)が、その子孫の代に
徳川家康に見つかり、「(永楽通宝)の文字を除くべし」と言われ、
仕方なく水野氏はそれに従った。
信長の用いた「永楽」の文字が家康にはよほど気になったらしい。
今、水野氏の紋を見ると「永楽通宝」の替紋として
「裏永楽銭」を用いているのがそれである。
その他「永楽銭紋」使用の諸氏
源氏系・・・・・松平氏、奥村氏、本郷氏
小野氏流・・・永見氏
丹治氏流・・・中山氏
 『家紋大図鑑』:参照
『家紋大図鑑』:参照 
家紋 25 ≪銭紋≫へ戻る。
ご訪問の記念に、1クリック募金を!
↓↓↓
押してくれたら嬉しいな~♪
銭紋
(ぜにもん)
銭は訓では「ゼン」というが、これは音の
「セン」が「セヌ」になり、「ゼン」に転じたもの。
銭紋が初めて文献に現れるのは、
「蒙古襲来絵詞」の『連銭』。



寛永銭 天保銭 六つ念じ銭


青山銭 六連銭(六文銭)
真田六文銭は地蔵信仰による六道銭!
真田氏は、三途の川の渡川料として
六文銭をいつも所持するという秘話からくる、
先陣の旗などで決死を表したものという。
≪六道=地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天井≫
【有文銭紋】・・・文字が書かれているもの
「永楽」などの瑞祥的理由から。
① 政和通宝(中国製)
② 永楽通宝(日本製)
③ 寛永通宝(日本製)
④ 康熙通宝(中国製)
【無文銭紋】・・・文字が書かれていないもの
信仰的理由、文字の省略。
① 裏銭
② 三文銭
③ 六連銭
④ 八連銭
⑤ 銭九曜
いつもお世話になっている↑↑家紋ワールドさんです。
いつもありがとうございます。

≪ 銭 ≫
古代には稲米、布帛、、家畜、勾玉、鏡、剣
などの現物が用いられることが多く、稲米と布帛は
法定鋳貨の出る鎌倉期まで一般に使用された。
天武天皇の頃、銅銭が使用されたとか、
朱鳥八年(694)鋳銭司の置かれた伝承はあるが、
最初の鋳貨は和銅元年(708)の「和銅開宝」といわれる。
その後、平安末まで十二種の鋳銭を「皇朝十二銭」と呼ぶ。
銭は唐制にならって、1文を単位とし、千文を一貫。
しかし、日本の銭は人気が無く、十世紀にやむなく廃絶。
十二世紀に、中国の銅銭(鎌倉期の宋銭、室町期の明銭)
が輸入され、これに諸国の私鋳銭が加わり、
十五世紀辺りまで続いた。
天正、文禄、慶長のころには、ようやく国家権力が統一
されて諸通宝が鋳造され、金・銀の半金が登場した。
江戸期には、金座、銀座、銭座の貨幣発行機関が
開かれ、貨幣の統一を実現。
 『家紋大図鑑』:参照
『家紋大図鑑』:参照 
 『日本家紋総覧コンパクト版』:参照
『日本家紋総覧コンパクト版』:参照 

ちょっと気になるリンク集
「音読・日本の絵巻」
by: 楊 暁捷 (X. Jie YANG)様 様より「永楽通宝の謎」
様より「永楽通宝の謎」
永楽銭は嫌われたり好まれたり、大小いろいろな
サイズのものが唯一残っている銭とのことです。
戦国武将 家紋ロータリーキーホルダー
真田幸村六文銭紋
(もちもん)
石高加増の縁起かつぎ!
餅を紋章としたのは、
古くから餅が、神祭や祝儀の際に用いられた
めでたいものとされてきたからである。
特に「黒餅」は〈こくもち〉とも読め、
先陣ではよく出したから≪石持(こくもち)≫に通じ、
石高加増の幸先よしと縁起をかついだものである。
「白餅」「枡に餅」「水に餅(一名月水)」など。
餅の中に他の紋も組み込んだ紋もある。
いつの間にか、黒餅・白餅・月の区別も混乱した。
だから、餅を月と呼んでいるところもある。
もっとも、かなり古くから黒・白に関わらず、
「餅紋」を「石持」と呼ぶようになっていたらしい。
基本は、白あるいは黒の円形だが、
他の図形をこの中に入れたものもあり、
二つ重ねた「重ね餅」、「菱餅」もある。

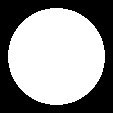

菱餅 白餅 黒餅
「白餅紋」
「城持ち」を表すといわれている。
① 近江西大路藩主市橋氏
「三つ盛り菱」「柊に打ち豆紋」と併用。
② 備後福山藩主阿部氏(⑤)の分家、上総佐貫藩主阿部氏
「丸に左重ね鷹の羽」と「白餅」を併用。
③ 同じく(=⑤の分家)磐城棚倉藩主阿部氏
「白餅に違い鷹の羽」に「中輪」を併用。
「黒餅紋」
「石持ち(こくもち)」として多くの土地を持つ
ことを意味する。
④ 福岡藩主黒田氏
「藤巴紋」に「黒餅」を併用。
⑤ 藤原北家八田氏の後の備後福山藩主阿部氏
「丸に右重ね鷹の羽」と「黒餅」を併用。
⑥ 武蔵七党丹治党加治氏の末の上総久留里藩主黒田氏
「黒餅の内に木瓜」と「枡に月」を併用。
⑦ 羽前ノ山藩主松平氏
「黒餅の上に酢漿草」「五三の桐」「山桜」を併用。
旗本では、浅野・島田・竹中・谷・黒田・
五十嵐・筑紫・市橋・阿部の諸氏が用いた。
いつもお世話になっている↑↑家紋ワールドさんです。
いつもありがとうございます。

【 追記 】
餅は、①黐(もち)のようにねばる、
②もとは丸形のもちが多いので望(もち)の意、
③腹もちがいい、④持ち運ぶに便利な飯(いい)
などの諸説がある。
また、餅紋は、ふつう外郭として用いられ代表家紋はない。
 『家紋大図鑑』;参照
『家紋大図鑑』;参照 

「石持紋」は、
留袖の既製品を作るためのものと思っていました。
着付け関連の本家紋の本には、
そのような説明しか載ってませんでした。
今の時代は、普段の家紋で「白餅紋」「黒餅紋」を
使っている人を見たことがありませんでしたし、
自分が持ってる家紋の本にも載ってるのがありませんでした。
今勉強してる古文書がらみで、「石高」がよく出てきます。
なので、「石持紋」が気になっていました。
本当に由来は「石高」からだろうか、と思っていました。
しかし、食料の餅からとは思いませんでした。
そういや、腹が減っては戦は出来ぬといわれるし、
祭りや正月などお祝いの時に良く供えられるもの。
考えてみれば、納得でした。
 『家紋の由来と美』丹羽基二著:参照
『家紋の由来と美』丹羽基二著:参照 
 『苗字・名前・家紋の基礎知識』監修・編者:渡辺三男
『苗字・名前・家紋の基礎知識』監修・編者:渡辺三男 
































